いつの間にかガムに代わってコンビニの棚をにぎわせているグミ。その大ヒットの背景にはZ世代の情報発信力と、それを見る他の世代の購買力があった。
『グミがわかればヒットの法則がわかる』から一部を抜粋・再編集してお届けする。
Z世代とグミ
1990年代半ば以降から2010年代前半に生まれたZ世代。消費のパイとしては小さいが、デジタルネイティブである彼ら・彼女らの価値観や消費スタイルに着目したマーケティングは、新たなニーズを掘り起こすヒントになり、幅広い世代への波及効果も期待できる。
多様性を重視し、個性を認め合う世代
Z世代は多様性を重視し、個性を認め合う傾向が強いとされる。失敗談も含めてネットで何でも調べられるからこそ、Z世代は製品の購入に対して慎重な面もある。そして、生産や流通、 決定に至るプロセスの透明性を求め、企業の広告色の強い発信を好まない。
「SHIBUYA109lab.」所長の長田麻衣さんは「Z世代はSNSでトレンドを追いかけていて、あまり豊かではないが好きなものにはお金をかける。そういう人たちが今後、消費の中心になっていく。企業側から見ると『一緒に商品を盛り上げていくパートナー』として、きちんと動向を見ていくべき対象だ」と指摘する。
参考にするのはインスタグラムの情報
コミュニケーションの仕方もほかの世代とは異なる傾向がある。
Z世代は画像や動画を介したビジュアルコミュニケーションを重視する。視覚的な共通認識のもとで交流し、SNSで得られる身近な人のお薦めを購入の判断材料にする傾向が強いと見られる。
「地球グミ」のヒットはSNS発
2021年後半から2022年に話題を集めた「地球グミ」のヒットも、こうしたZ世代から生まれた。地球グミは、大陸の模様が描かれた透明のプラスチックケースに1個ずつ包装され、 地球儀のような見た目。グミの中にはマグマをイメージした真っ赤な「ラズベリー」のソースが入っている。
この地球グミは、正式名称は「Trolli Planet Gummi」。ドイツの老舗メーカーMEDERER社のブランド「Trolli」がスペインの工場で製造している。2020年秋から日本に輸入が始まり、PLAZAなどの店頭に並び始めた。
販売価格は1袋(グラム、4個入り)で500円以上と、グミにしては高価だが、店舗や正規のオンラインショップでは軒並み品切れ。通販サイト「アマゾン」ではプレミア価格がついた。
希少性がさらなる話題・人気に拍車
今回のケースでは、大規模なマーケティングを行った形跡はない。SNSを通じて、一部の若者や子どもの間で盛り上がったのが特徴だ。
2018年ごろ、韓国のユーチューバーがSNSで紹介したのが、そもそものきっかけ。それに日本の「原宿系」と呼ばれるユーチューバーが飛びつき、「地球グミ」を団子のように串に刺したり、「地球グミ」を琥珀糖(こはくとう)にして食べる動画を投稿したり、「地球グミ」の〝もきゅもきゅっ〟とした咀嚼音を撮影したASMR動画の投稿が相次いだりしていった。
TikTokでは、「口で地球グミのパッケージを割る」動画がバズり、それを真似したいと思ったZ世代が追随した。
韓国のSNSで流行し始めた当初は、「地球グミ」は日本にはまだ輸入されておらず、希少性が高かったこともさらなる人気を呼んだ。輸入されてからも販売数が少なく、品薄や品切れもネタになった。
「国境」を意識しない世代
デジタル時代の消費者、特にZ世代は「国境」をさほど意識しない。
グミ市場は、国産だけでなく、「ハリボー」や「地球グミ」といったヨーロッパ産、さらに最近では韓国産が同じ棚に並び、 それぞれが好みのグミを手にしている。
元々、グミの持ち味は多様性かもしれない。〝元祖〟「ハリボー」の「ゴールドベア」は、長さ約2センチのクマの形。弾力感ある歯ごたえで、かむうちにフルーツの香りが広がる。イギリスでは定番のクマの形にはあきたらず、7色のミミズやへそ型といったユニークなグミの受けが良い。
一方、韓国では動物をかたどった食品は好まれない。イスラム教国では、原料に豚ゼラチンを使うことは許されず、牛のゼラチンでグミをつくる。
ネット時代は、情報が拡散される。その情報は世代間で断絶されているわけではなく、誰でもSNSを開けば情報を目にすることができる。
例えば、SNSではAI(人工知能)がアルゴリズムによって、好みに合ったものや情報を薦めてくれる。若くなくても、Xでトレンドを追っているうちに流行に関する情報がたくさん届く。Z世代は年長の世代と比べると人口が少なく、現状は購買力も高いわけではないが、購買力がある上の世代にZ世代の発信力が影響を与えるサイクルは無視できない。
今後の社会を担う世代
また、Z世代は今後の社会や消費を担う存在となっていくため、Z世代を意識した製品・サービス開発の取り組みが相次いでいる。
グミではないが、カンロは2022年2月、Z世代を主要顧客に想定した飴「エモーショナルキャンディ」を期間限定で発売した。若年層の飴離れに危機感を持つ同社が、PLAZAを展開するスタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーと組んだ。
3種類の味があり、それぞれ「風」「恋」「夜」というテーマを設定した。パッケージ裏面には製品コンセプトに沿った詩を書き込んだ。「風」と「恋」は詩の内容に合わせて味が変化し、飴をなめている時間を楽しめるようにした。Z世代にとっては「味が変わらない」などの飴に対するイメージがあり、コンセプトを明確にした商品で新たな価値を提供しようとした。
Z世代のニーズを捉えた製品開発は、新たな視点を持つことにもつながる。カンロでは、こうした取り組みにより、製品のアイデアを練る際に柔軟性が生まれると期待する。
「好き嫌い」より「共感したい」
「SHIBUYA109lab.」所長の長田さんは「Z世代は『好き嫌い』よりも『共感したい』のほうが強い気がする。すごく好きな『推し』がいるとか、自分の主観がしっかり作用している部分もあるが、そうではない部分のほうが多い。自分の主観が強烈に働かないところに関しては、みんなが『いい』って言っているものに『わかる、わかる』と共感したい。そういう感じではないか」と、Z世代への価値観や嗜好を分析する。
毎週のように新商品が発売されるグミの市場は、企業と消費者が、まさに一緒に盛り上げていくパートナー同士という関係性が構築されている。「いかに『好き』を捉えて、それに応える商品を提供するか」ではなく、「いかに『共感』の空気を生むか」が、これからの生活者の消費意欲をくすぐるポイントになっている。
文/白鳥和生 画像/shutterstock
『グミがわかればヒットの法則がわかる』(プレジデント社)
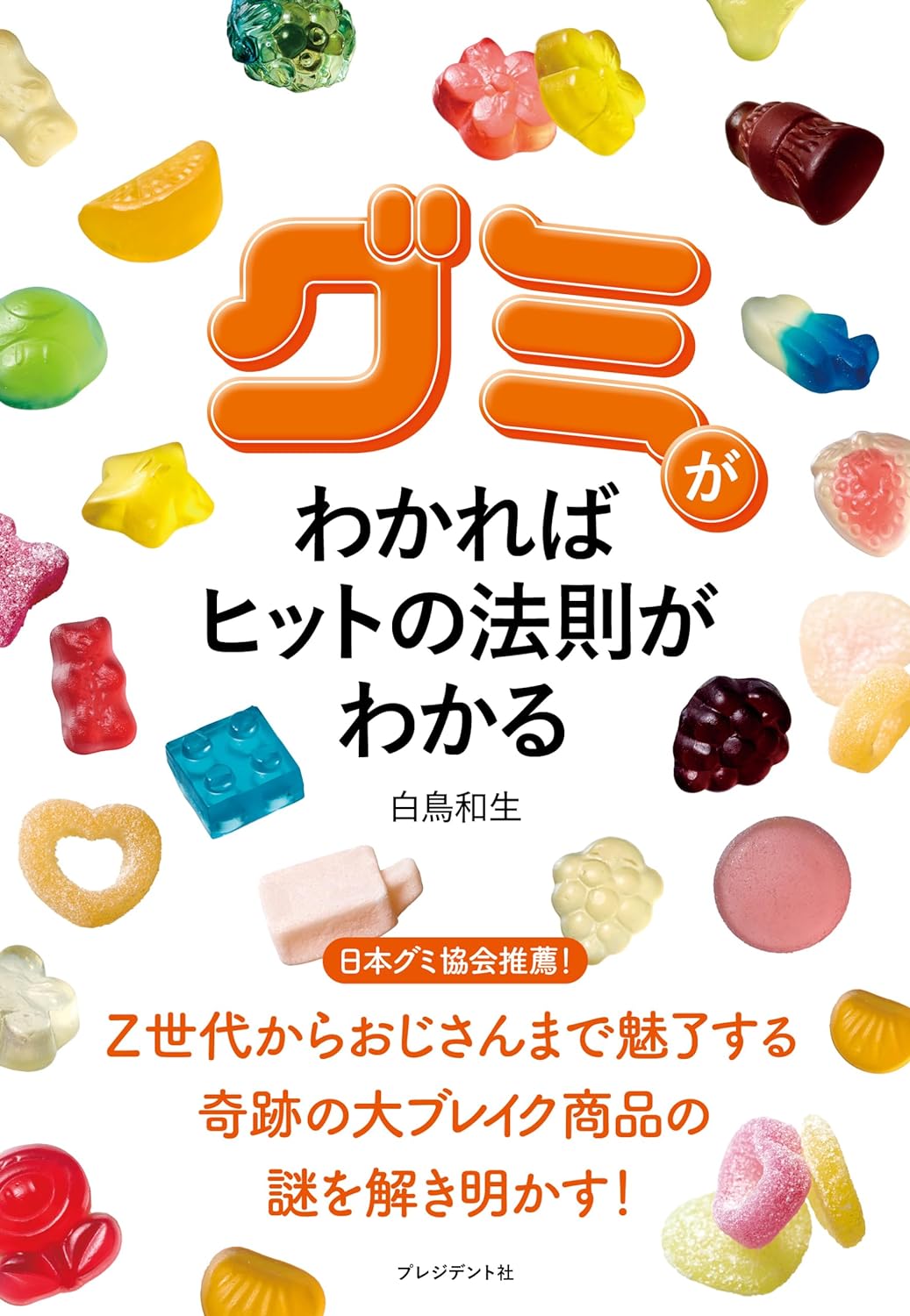
飲食料品の世界で起きた、四半世紀ぶりの〝大逆転劇〟。 2021年、グミがチューインガムの市場規模を上回った。 グミは日本で発売されて40年ほどの歴史しかないが、いまや老若男女問わず愛されるお菓子に成長した。
グミとは何者なのか。グミには5つの顔がある。
① 「幸せ感」につながる小腹満たし・気分転換ニーズを満たす
② 「コスパやタイパ」につながる代替ニーズを満たす
③「楽しさ」につながるバラエティーの豊かさ
④「期待感」が高まる相次ぐ新商品の登場
⑤「つながっていることを実感」できるコミュニケーションツール
様々な顔を持つグミの魅力に惹きつけられたファンたちが集う「日本グミ協会」という団体が生まれたり、「グミ文化祭」というイベントが開催されたりしていることにも注目だ。
人口減少が進む日本で、グミがヒットしたひみつとは? 元・日経新聞記者で、あらゆる小売業の動向を長年追いかけてきた著者が、マーケティングの観点からわかりやすくひもとく。
【目次】
はじめに
◆第1章 グミの歴史と人気 ・グミの起源はドイツ ・日本は「明治」が先陣切る ・2021年にグミ市場がガム市場を逆転! ・コロナ禍が後押しした市場拡大 ・小売り側の反応 ・物価高騰のなかでも支持を集めるグミ ・コラム かむことと健康の関係
◆第2章 消費者の声から読み取る「グミ」とは ・グミは誰が食べているか? ・人口が減少するニッポンで、なぜグミは成長しているのか ・「タイパ」と「代替需要」 ・Z世代とグミ ・消費者が持つ「グミ」のイメージ ・情緒的価値が大切なベネフィット ・コンセプトが商品の命 ・グループインタビューから見えてきた消費者インサイト ・グミを形づくる5つの要素 ・コラム マーケティングコンセプトハウスの山口博史社長の分析
◆第3章 メーカー各社の戦略 ・グミの持つ多様性と技術 ・明治 ・カンロ ・UHA味覚糖 ・ハリボージャパン(ハリボー日本法人) ・コラム グミ市場を支える地方メーカーと菓子卸
◆第4章 企業と生活者による「共創」 ・ヒットの法則とグミ人気 ・ファンがブランドを育てる ・ファンマーケティング ・勝手連がグミを応援 ・オタクとは違う「推し活」 ・コラム 「グミ文化」を目指す(日本グミ協会の武者慶佑名誉会長の寄稿)
おわりに
参考文献














































































































































