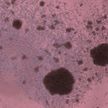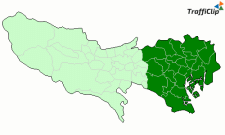【竹下陽二記者コラム】
先日、東京都内で行われた名球会主催の野球教室「ベースボールアカデミー」の取材をした。1回目は、投手編で西武、ダイエー、巨人、横浜で活躍した、224勝投手、工藤公康さんとのことだった。コーチ役の名前を聞いて、正直、私は、ちょっぴり、ユウウツになった。
なぜなら、工藤さんとは因縁があったからだ。今から36年前。私は入社2年目で26歳になろうとしていた。今はすっかり丸くなったが、しょっちゅうデスクに逆らい、血気盛んでイケイケであった。私より一つ下の工藤さんは西武のエースとして君臨し、生意気盛りであった。そして、その事件は、今はもうない、阪急ブレーブスが本拠地としていた西宮球場の三塁ベンチ裏の試合前に起きた。
ちょっとした取材上の言葉の行き違いから激しい口論となった。突然、ベンチ裏で起きた乱闘寸前のののしり合いにロッカールームから渡辺久信や高山郁夫らが飛び出してきて、仲裁に入った。以来、頑固な私は工藤から遠ざかるようになり、のちに、西武担当を外れても、不思議と取材する機会もなかった。工藤さんがソフトバンクの監督時代、楽天の仙台の本拠地ですれ違い、少し言葉を交わす機会があったが、わだかまりは残ったままだった。私も定年を迎え、今さら、それはそれでもう、仕方ないと諦めていた。
だから、ベースボールアカデミーの取材が回ってきても、一切、無視という選択肢もあった。あるいは、昔のことは知らんぷりして、さくっとインタビューしようかとも思った。しかし、それでは、面白くないと思った。こちらから、36年ぶりのボールの投げることで生まれる小さなドラマもあるだろう。よくよく、考えれば、あの時、何げない言葉のやりとりのあと、最初に声を荒げて、口論を仕掛けたのは私であったことに、今さらながらに気づいた。振り返ると、記者になりたてで、思うに任せない取材活動や原稿執筆のイライラを爆発させたような気がしないでもない。長い年月は流れたが、そのことを素直にわびようと思った。
工藤さんは、根っからの野球人であった。29人の小学生高学年と中学生相手に、一人ずつ約3時間半、ノンストップで熱血指導をした。汗だくの工藤さんに「すごいスタミナですね。まさに、コーチングハイになってるようでした」と声をかけ、さりげなく、例の事件をことを持ち出した。
「覚えてますか?あの日のこと?」
すると、白い無精ひげを生やした私を見て、工藤さんはこう言った。
「もちろん。忘れてません。覚えてますよ、それにしても、年食いましたねえ」
オイオイ、36年目でいきなり、これかい(笑)。予測もしない突然の胸元へのブラッシュボールにムッとした。しかし、私も経験を重ね、曲がりなりにも、大人になっていた。一瞬、のけぞった私だが、即「ま、それは、お互いさまでしょ?」と返すと、工藤は「そうだねえ。もう、61になっちゃったよー。うへえ」とおどけてみせた。
なんとなく、うち解けたところで、グッドアイデアがひらめいた。「その節は、大変、失礼しました。記念に写真撮りましょう」と頭をペコリと下げ、提案すると「あ、良いですよ」と工藤さんは快諾。さらに、ここぞとばかりに「せっかくだから、握手しましょう」とたたみかける私。一瞬、拒否されるかと思ったが、工藤さんは右手で私の右手を快く握りしめてくれた。ごつごつした分厚い手のひらだった。私は和解のつもりだったが、工藤さんはどういうつもりで私の右手を握りしめてくれたんだろう。私に突然、カメラを手渡され、ツーショット写真を撮らされた関係者も、そこに小さなドラマあったとは思いもしなかったろう。
あの事件の時、僕らは20代で独身だった。それから、工藤さんは結婚し、家庭を持った。西武から数球団を当たり歩き、一時代を築き上げ、のちにソフトバンクの監督としても成功をおさめた。私も結婚し、家庭を持ち、今や、愛犬を溺愛する、間もなく62になる定年オヤジである。あの頃と同一人物であることは違いないが、36年という歳月が流れ、お互いを別人にしてしまったのかもしれなかった。ゴメンと言うのに36年という年月を要するとは、我ながら頑固にもほどがあるとは思う。でも、覚悟を決めて、歩み寄ったことで、わだかまりが消えた。
「工藤さん、また、どこかで」とサヨナラすると、工藤さんも「うん」と右手を挙げた。あの事件は、この再会、和解のドラマの書くために仕組まれたものかもしれない。そんな勝手な解釈もしてみた。今度は、酒でも飲みながら、人生を語りたい。それが、私のささやかな夢の一つになった。私が何をしなくても、また、人生の神様が、どこかで思いもよらぬ演出をしてくれるに違いない。