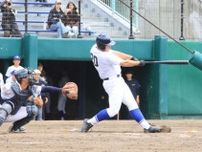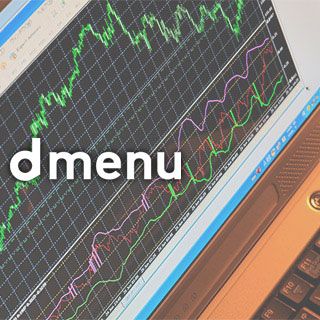前編【甲子園優勝校の4番打者は日ハム入団後、鳴かず飛ばず…心に沁みた同期入団・ダルビッシュの気遣いとは】のつづき
ノンフィクションライター・長谷川晶一氏が、異業種の世界に飛び込み、新たな人生をスタートさせた元プロ野球選手の現在の姿を描く連載「異業種で生きる元プロ野球選手たち」。第9回は愛媛・済美高校からプロ入りした鵜久森淳志さん(37)。前編では北海道日本ハムファイターズに入団し、東京ヤクルトスワローズで現役引退するまでを伺いました。鵜久森さんが第二の人生に選んだのはライフプランナー。それを目指したきっかけや、現在の仕事への取り組みはどのようなものかを聞きました。(前後編の後編)。
「今度は自分が、支え、応援する側になりたい」
2015(平成27)年オフ、北海道日本ハムファイターズから戦力外通告を受けた。そして、18年には東京ヤクルトスワローズから再び自由契約を告げられた。二度目のトライアウト会場で出会ったのは、かつて千葉ロッテマリーンズに在籍していた青松慶侑だった。現役引退後、彼はソニー生命の社員となっていた。鵜久森淳志と青松は同学年であり、ともに05年に高卒でプロの世界に飛び込んでいた。
「最初のトライアウトのときにも、ソニー生命の方から名刺や資料を頂いていました。そして、二度目の時、青松や彼の上司も一緒に会場にいました。この時点では、“ソニー生命にお世話になろう”とは考えていなかったけど、いろいろと考えているうちに、“この会社で働きたいな”という気持ちになっていったんです」
二度のトライアウトを経て、「もう、野球人生に別れを告げよう」と腹は固まった。新たな道を踏み出すにあたって、「自分に何ができるのか?」「自分は何をしたいのか?」と自問自答を繰り返した。その結果、鵜久森は一つの方向性を見定める。
「自分の過去の経験を振り返ってみたときに、“自分はこれまで、本当に多くの人に支えられ、応援されてきたのだな”と気づきました。最初に日本ハムから戦力外通告を受けたときに、改めて人の大切さを知り、次にヤクルトをクビになったときには、“今度は自分が支え、応援する側になりたい”という気持ちが強くなっていました。“恩返しをしたい”、そんな気持ちになったんです」
スワローズ時代の鵜久森は、「報恩謝徳」をモットーに全力でプレーしていた。自分が受けた恩に対して、最大限の努力をして報いたい。そんな感謝の思いを込めた言葉である。そして今度は、「また新たな形で報恩謝徳を実践しよう」と考えたのである。
「過去の自分を振り返っているうちに、多くの人々の人生に寄り添うことのできるライフプランナーという仕事に魅力を感じるようになりました。いろいろな保険会社があるけれど、“ソニー生命なら、自分がやりたいことができるのでは”と考えて、入社試験を受けることを決めました」
冒頭で述べたように、「元プロ野球選手」の肩書きを持つ同い年の青松がすでにソニー生命で働いていた。青松にも相談し、鵜久森は入社試験に挑むことを決めた。
「青松からいろいろアドバイスをもらって対策を講じて臨みました。最終面接は、現役時代のサヨナラホームランを放った時の打席と同じくらい緊張しましたね。面接は2時間半ほど続いたけど、ここまできたら自分ではどうにもならないのだから、“とにかく自分の思いをきちんと伝えよう”と臨んだら、何とか採用となりました(笑)」
「8年かけてプロ野球選手になれたから、8年で再びプロになる」
2019年、鵜久森にとって、右も左もわからぬ保険業界での新しい生活が始まった。ソニー生命では、ライフプランナーを育成するための研修・教育プログラムが充実しており、入社時に保険や金融の知識がなくてもライフプランナーとしての専門性を身につけ、成長していくことが可能となる。「一から学びたい」と考えていた鵜久森にとって、それは理想的な環境だった。
「入社は19年の1月で、仕事内容は生命保険の販売に関することでした。ライフプランを通じて、お客様に保険を考えて頂くのが主でしたけれど、資格をとらないと生命保険商品を扱うことができないので、まずはその勉強をしました」
資格取得のための勉強と並行して、パソコンの使い方を学び、ビジネスマナーの習得に励んだ。初めて知ることばかりだったが、やりがいは大きかった。この間、鵜久森には「一つの信念」があった。
「僕は野球を始めてから8年かけてプロ入りを実現しました。ならば、必死な思いで同じ時間をかければ、次の人生でもまたプロになることができるんじゃないか。それは決して、確信ではないです。でも、8年間、懸命に頑張ってプロ野球選手になれたのだから、同じぐらい死ぬ気で頑張れば、またプロになることができるはず。もちろん、どんな仕事をしていても、何年かけても終わりはないし、満足することはないのかもしれないけど、やる以上はもう一度プロを目指す。そんな思いで、あの頃は勉強していました」
初めての契約が取れたのは19年3月だった。これが、ライフプランナーとしての第一歩となった。前年までのチームメイトたちが、シーズン開幕に向けて意気込んでいた頃に、鵜久森の第二の人生が本格的に始まったのだ。
「初めてご契約をいただいて、“やっと始まった、これが第一歩だ”と思いました。ずっと不安だったし、周りもどんどん仕事をしていたので焦りもありました。最初の頃は誤った説明をしてはいけないので、上司と一緒にお客さまの元へ行きました。横で見ていてもらって、訂正してもらったり、助言をもらったりして、少しずつ学んでいきました。青松にもたくさん相談に乗ってもらいましたね」
公称189センチメートルの体躯をスーツに包み、東へ西へと駆け回る日々に、鵜久森もまた少しずつ手応えと充実感を覚えていた。
「プロ野球時代よりも、責任は重い」
ライフプランナーとなって2年目の20年は新型コロナウイルス禍に見舞われ、自宅待機、リモートワークの日々も経験した。
「あの頃は、電話での現状確認がメインの仕事でした。契約者さまに電話をかけて“体調はいかがですか? コロナは大丈夫ですか? マスクはありますか? 私たち保険会社といたしましては、今こういうことができます”といったことを説明させていただきました」
コロナ禍が落ち着き、現在では新たな契約と、既存の契約者のフォローを両立させる日々が続いている。ライフプランナーとなってすでに5年が経過し、6年目に突入している。改めて鵜久森に、この仕事の楽しいところ、やりがいを尋ねてみた。
「お客様と会話することがいちばん楽しいです。とても責任のある重たい仕事でもあるので、“楽しい”というとちょっと語弊があるんですけど、“鵜久森さんが担当でよかった”と言われることがとても嬉しいです。お客様に何かが起きたときこそ、僕らが評価されるところなので、苦しんでいるときに“助かりました、ありがとうございます”というひと言をもらえるために、僕らはライフプランニングしていますから。責任は野球選手より重いですからね」
プロ野球選手時代よりも、責任は重い――。この言葉にこそ、現役ライフプランナーとしての自負がある。
「みなさんそれぞれの事情があり、家庭環境も違います。その一つひとつに丁寧に取り組んでいかなければいけない仕事ですから、やっぱり責任は重大です。プロ野球時代も、1年1年一生懸命頑張ってきましたけど、今はさらにもっと必死に取り組まなければいけない。その思いは強くなっています」
現役時代、まさか自分がライフプランナーになるとは微塵も考えていなかった。二度の戦力外通告を経て、現在は顧客の幸せを何よりも願うようになった。ひと足早く新たな世界に飛び出した鵜久森から、現役選手たちへのアドバイスをもらった。
「僕の個人的な考えですけど、野球だけをやっていても決して上手にならないと思います。絶対に野球以外の多くの人の意見を聞いた方がいい。野球界という小さな輪の中にいるのではなく、積極的にいろいろな人に会って、いろいろな考え方に触れた方がいい。それが結果的に野球のためになることも多いし、引退後にも役立つことになると思います」
高校時代には「期待のスラッガー」として注目されてプロ入りした。けれども、14年間のプロ生活では結果を残すことができなかった。改めて反省の弁がこぼれる。
「僕の場合は、変に真面目過ぎて、練習のし過ぎだったのかもしれないですね(苦笑)。僕が失敗したのは、10回打席に立ったら10本のヒットを打ちたかったこと。もっと柔軟な考え方をしていたら、また違った結果になったのかもしれません」
一拍の間をおいて、鵜久森は笑顔で言った。
「野球に関しては、いろいろ反省点はあるけど、ライフプランナーの仕事は絶対に失敗が許されないから、常にアップデートを怠らずに頑張っていきたいと思います」
すでにスーツ姿が板についている。パソコン操作もスムーズに行っている。保険販売に必要な資格も取得し、保険や金融の知識も増えた。数百人を超える契約者の一人ひとりをフォローしながら、「保険のプロフェッショナル」としての日々を、鵜久森は今、懸命に生きている――。
(文中敬称略・前編【甲子園優勝校の4番打者は日ハム入団後、鳴かず飛ばず…心に沁みた同期入団・ダルビッシュの気遣いとは】のつづき)
長谷川 晶一
1970年5月13日生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務を経て2003年にノンフィクションライターに。05年よりプロ野球12球団すべてのファンクラブに入会し続ける、世界でただひとりの「12球団ファンクラブ評論家(R)」。著書に『いつも、気づけば神宮に東京ヤクルトスワローズ「9つの系譜」』(集英社)、『詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村・ヤクルトの2年間』(双葉文庫)、『基本は、真っ直ぐ――石川雅規42歳の肖像』(ベースボール・マガジン社)ほか多数。
デイリー新潮編集部