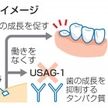TOKYO FMのラジオマン・延江浩さんが音楽や映画、演劇とともに社会を語る連載「RADIO PAPA」。今回は寺山修司の戯曲を稲葉賀恵が演出する音楽劇「不思議な国のエロス」について。

* * *
音楽劇「不思議な国のエロス」で「セックス・ストライキ」という言葉を知った。戦争にかまけている男たちに愛想がつき、「セックスしない」と女たちが立ち上がるストーリー。アリストパネスの『女の平和』を下敷きにした寺山修司の戯曲である。執筆は1965年、ベトナム戦争の時期だが、半世紀経った今でもロシアのウクライナ軍事侵攻、パレスチナ・イスラエル戦争と戦火が止むことはない。
しかし、ボブ・ディランが歌ったように「時代は変る(ザ・タイムス・ゼイ・アー・ア・チェンジン)」。
セックスできないことが、果たして今、男の好戦性を薄めることになるのだろうか。そもそも兵士の中には女性もいる。そんなモヤモヤを抱えながら観、演出を担った稲葉賀恵に会った。
「アリストパネスの古代ギリシャはシンプルだった。人間の原始というか、(マッチョな)欲望があった。寺山の時代はベトナムがあって、(反戦の)カウンターカルチャーもあった」
現代はそこにジェンダーが加わる。
「YESかNOか、男か女か、戦争か平和か。そんな分かりやすい対立軸に『今』をどう盛り込むのかで悩んだ。企画書みたいにわかりやすい答えはないし」と言う。

左から松岡依都美、まりゑ(撮影:友澤綾乃)
「観た後のモヤモヤがよかった。あなたのモヤモヤが伝染して考えさせられた」と告げると、「でもそのモヤモヤを稽古で見せられないのが演出家。演者がビビるから。家で悩みました」と苦笑する。考えてみれば、人生に答えなどあるはずもない。ヒントがあるとしたらグレイゾーンにこそなのだろう。
「突拍子もないものを観てしまったと思って欲しい。観客の心に種を蒔くというか。それがわかりやすいエンタメに対する私なりのせめてもの抵抗です。売れたい。でも、観たくないのなら観なくてもいい。そこで葛藤する日々です。経済的に売れることは戦争に加担していることにも繋がる。であればそんな私が戦争反対というのはどうなんだろう? って」
性差の問題は稲葉の世界に現存しているという。
「女性の地位は低い。例えば“女性”演出家という呼称とかね。舞台を作る時も女性は力がない。そういう肉体的なことも。一方でそもそも『男らしさ』を演じてくれる人もいない」
悩むのが趣味という稲葉は演劇の力をこう語る。
「演劇でしかできないことをやっていきたい。丸くならずに尖っていたい。小劇場の舞台ならできる。演劇は閉じていてもいい。特別な経験ができれば。観客を監禁して、強制的に観てもらう」

内海啓貴(撮影:友澤綾乃)
考え続けることが問題解決になる。演出家として、当事者として絶えず答えを探している稲葉の姿勢をこの演目で感じた。
(文・延江 浩)
※AERAオンライン限定記事