
農家に嫁いで20年。代々の伝統を引き継ぎ、行われてきた年中行事に「続ける意味があるのか」と疑問を持つ48歳女性。多くの年中行事を淡々とこなす「仕事」を伝統として伝える意味が分からなくなっているという。そんな女性に、鴻上尚史が贈った「伝統は、変わってもいい」というアドバイスの真意とは。
【相談224】
農家に嫁ぎましたが、いまだに残る年中行事に疑問を感じます。(48歳 女性 お豆さん)
東京郊外で農業を営んでいる40代女性です。農家に嫁いで20年になります。畑仕事自体はわりと好きで東京にいながら自然を満喫できて楽しく仕事をしております。
今回ご相談したいことは家に伝わる年中行事のことです。大晦日に年越しそば( うどん) を食べたり、お正月におせち料理やお雑煮を食べ、仏壇や神棚(5つもある) にお供えするのはわかるのですが、その他にも七草、鏡開き、蔵開き、えびす講、節分、初午と続くとなると、一体何のためにやっているのか、やる必要があるのか自分でもよくわからなくなります。
お姑さんがそういう行事をきちんとやらないと気が済まない人で、手伝っているうちに今日にいたり、今では私が主に行うようになってきました。でも、お姑さんに小言を言われる前に、淡々と仕事としてこなす感じです。
現代においてこのような行事を続けることに意味はあるのでしょうか。私自身が疑問に思っているのに、さらに次の世代に繋いでいくことは難しいようにも感じます。
鴻上さんはどのようにお考えになりますか。
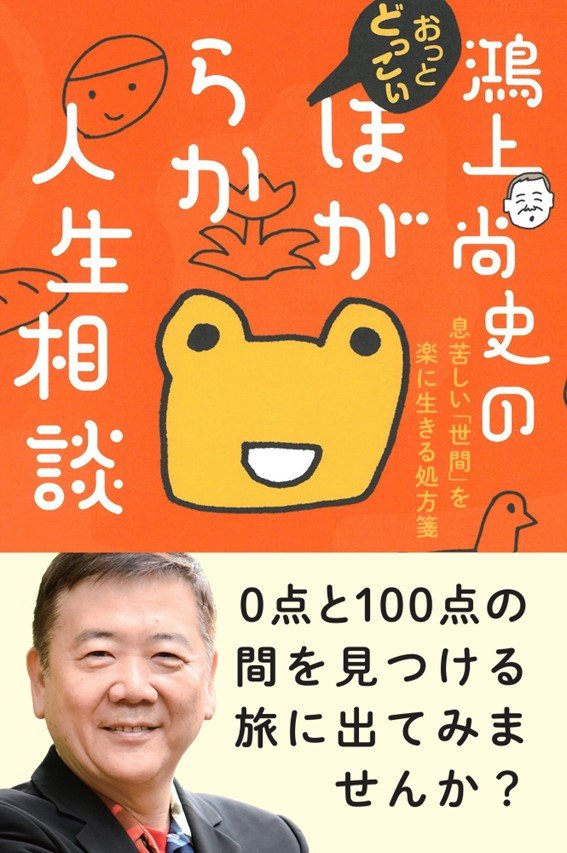
【鴻上さんの答え】
お豆さん。大変ですね。そんなにたくさんの行事があるんですね。
びっくりしました。
さて、僕の考えは、「お豆さんが家を仕切るようになれば、お豆さんの考えるやり方でいい」ということです。
お姑さんは、伝統を大切に守った。それは素敵なことです。伝統は、誰かが強引に作ったものではなく、理由があって自然に生まれたものだと思います。
昔、大晦日や正月だけではなく、七草、鏡開き、蔵開き、えびす講、節分、初午があったのは、それぞれに理由があったのでしょう。
今のように長期・短期の正確な天気予報があるわけではなく、自然に囲まれ、時間と自然が一体になった時代の必要から生まれたものが、これらの「伝統」だったと思います。

ですから、「伝統」は変わります。必然を感じられなくなったら、「伝統」を続ける意味がなくなるからです。
時々、「どうしてそれを続けているの?」と聞いて「それが伝統だから」と答えるだけの人がいます。でも、それが「伝統」になったのには、理由があるはずです。そして、今も残っている理由が「伝統を守ろう」ということだけではなく、「こういう理由で残した方がいい」という明確な理由があれば、それは素敵な「伝統」だと思います。
もちろん、「理由は分からないんだけど、『伝統』だから残そう」と主張することは、悪いことではないと思います。今の私には想像もつきませんが、次世代がこの伝統の意味を見つけてくれる、なんて可能性もあると思います。
ただし、それは、みんなが「伝統」を残すことを納得し、「伝統」の維持に関して、みんなが積極的に努力することをためらわない場合だと思います。
一部の人達の犠牲と努力のみに支えられた「伝統」は、残念ながら長くは続かないと思います。
お姑さんがご存命の間は、「伝統」を続けたいと思われるでしょう。でも、お豆さんの代になり、「これとこれはもういいんじゃないでしょうか」という思いを実行することは、とても当たり前のことだと思います。お豆さんの夫がどう考えるかは問題ですが、「自分は何もしないけど、すべての伝統を残してほしい」と言われたら、話し合う余地があると思います。
お豆さん。
伝統に関しては、僕はこんなふうに考えています。








































































































































