
小学生の家庭学習は毎日少しずつでも取り組んで習慣化させることが大切です。保護者の中では子どもの学習面で不安があったり、サポートの仕方が分からないという人も多いのでは。今回は、小学生の家庭学習について、目的やおすすめのやり方、各学年別に躓くポイントなどをママライターが伝授!
わが家で実際に行っている家庭学習やおすすめの教材も合わせてご紹介します。
小学生における家庭学習の目的・目安の時間

学校からのお知らせや保護者懇談会などでも、家庭学習をしっかりと行うように言われたことがある保護者も多いでしょう。学校毎日宿題が出ていますが、そもそも家庭学習はどんな目的があるのでしょうか。
家庭学習の目的
家庭学習には以下のような目的があると考えられます。
学習習慣の定着
家庭学習は毎日勉強する習慣を小学生のうちから定着させることが大きな目的の一つです。短時間でも集中して勉強することを続けていくと、家庭学習は生活のルーティーンになり、勉強することが特別なことではなく当たり前のように感じられるように。
特に小学校1年生から学習習慣を身につけられると高学年や中学生以降も家庭学習に抵抗がなくなります。
授業の復習・補足
学校の宿題や家庭学習は学校の授業だけでは補えない分の補足や復習が目的。特に漢字や計算は繰り返し学習することで知識として身についていきます。
ドイツの心理学者であるエビングハウスによると人間の脳は覚えたことを24時間以内に70%忘れてしまうとも言われています。そのため、学習したことをきちんと記憶し、理解するには次の日やその次の日にも繰り返し復習をしたり学習していくことが大切になります。
自発的に行動する力を養う
学校の授業は先生が主導になり子ども達にとっては受動的な学習が多くなります。“先生に言われたからやる”という考えしかできないと、自ら学ぶ姿勢が身に付きません。その反面、家庭学習は自発的に学習する力を養えるチャンスでもあります。
最初は親がやることを提示していったとしても、子どもに家庭学習で何をすべきか何をやりたいかなどを聞きながら自主的に勉強できるような働きかけをしていきたいところです。
家庭学習時間の目安
家庭学習の時間は学校からの宿題や塾で勉強する時間も含まれると考えてよいでしょう。目安としては学年×10〜15分とされています。例えば、1年生なら10〜15分、6年生なら60〜90分が目安になります。これは年齢によって集中できる時間が異なること・学習の難易度が年々上がることも関係しています。
家庭学習の目安時間は子どもが集中して取り組んでいる時間です。片づけや準備などを含めると予定よりも長くなることもありますね。
家庭学習を定着化させる方法

家庭学習は子どもが自発的に勉強できればよいのですが、最初はそう簡単にはいきません。すぐに集中力がきれてしまいいつのまにか遊びだしたり、なぜか兄弟喧嘩に発展したりと親もイライラモヤモヤしてしまいますよね。できれば1年生のうちから家庭内でルールを作って親も家庭学習の応援をしていく必要があります。
毎日決まった時間に家庭学習を行う
遊びや習い事などで忙しい令和の小学生たち。子ども達が無理なく家庭学習できるように子どもが動きやすい時間をみつけて毎日決まった時刻に勉強を行えるようにしていくのもよいでしょう。
例えば、学校から帰ってきたらまず宿題をする。そのあと遊びや習い事へ行き、帰ってきてから夕飯までの間にそのほかのドリルや教材を進めるなどやることを分割して決めていくのもおすすめです。一気に全部やらなけらばならないと思うと、子どものやる気も半減し、集中力も低下します。特に学年が上がり学習時間が長くなってきたら休憩を挟んであげるとよいでしょう。
朝勉は家庭学習習慣の効果大!
放課後は忙しくて家庭学習の時間が足りない場合には、朝学校へ行く前のちょっとした時間を家庭学習時間に隔てるのがおすすめです。実際に、わが家では朝勉を習慣づけており1年生の頃から朝食を食べて、学校へ行く前に20分ほど学習することを続けています。
朝ごはんを食べた後は目を覚めて集中力も高くなります。このちょっとした時間でできる量を親が調整してあげると無理なく続けられます。例えば、漢字の書き取りや計算ドリルを1ページ、通信教育の内容などが取り組みやすいですよ。
子どもと一緒に教材を選んだりルールを決める
市販のドリルや問題集を家庭学習で使用する場合は、今のお子さんの学習力にあった難易度のものを使うとよいでしょう。あまりに難しいものは毎日つづけるのが嫌になってしまいます。少しずつレベルを上げていけるようにしていけばOK。
お子さんが興味を持てるようなイラスト入り・オールカラーのものなどは比較的取り組みやすいです。一緒に本屋さんへ行って子どもに選んでもらうのもおすすめです。
また、家庭学習のルールは親が一方的に定めるのではなく、親子で話し合って決めるのがよいでしょう。勉強の目標から、どうやったら頑張れるか、時間やルールを子どもと一緒に相談してきめてください。子ども自身で目標や方法を考えることで自主性や責任感も養えるようになります。
集中できる環境づくり
子どもが家庭学習を定着できるようになるには、集中できる環境づくりやサポートが大切になっていきます。子どもが勉強している間はTVをつけない、いつでも親に質問できるようにそばにいてあげるなどの配慮をしていきましょう。
時間があるときには、親子で問題を出し合うなどクイズ形式で勉強するのもあり。
【学年別】つまづきやすい学習ポイント

学校や家庭学習を進めていく中で、つまづきやすいポイントがでてきます。各学年ごとに気をつけてみてあげたい単元やサポート法をご紹介します。
1年生:漢字の読み書き
入学したばかりの1年生にとって、学習するすべてのことが初めてのことばかり。特にひらがなの読み書きから始まる国語は、2学期以降の漢字の学習でつまづく子が多いです。漢字は正しい書き順で、トメ・ハネ・はらいに気を付けて書くことが大切です。自分なりの書き方が定着する前の1年生の時期に、しっかりと書き順に意識を向けられるように促していきましょう。
家庭学習では、書き終わった字をチェックするだけでなく、書き順や鉛筆の持ち方など書いている途中の様子をよくみてあげるのがポイントです。
2年生:かけ算
2年生になると算数はかけ算の学習が始まります。かけ算は、ただ九九を覚えるだけでなく意味を理解することが大切です。文章問題で九九を利用して計算できるようになることで学習した内容をいかせるようになります。
九九を覚えることが苦手なお子さんには、ドリルなどで書くことに加えて繰り返し九九を唱えることも大切。×1〜×9まで順に覚えた後は、×9〜さかのぼって言えるようにするなど工夫して学習を進めていきましょう。
また、国語の漢字は、1年生では80字覚えたものが2年生になると160字と倍の数を学習していきます。定期的に漢字ドリルを使用して覚えているか復習していくことも重要。
3年生:割り算や単位
3年生では、あまりのある割り算を学習するようになり、より複雑な計算に取り組みます。商とあまりの関係をきちんと理解して、ひっ算の仕方をマスターできるのが目標。また、長さや重さの単位も学びますが、ここでこんがらがってしまう子も多いです。
家庭学習では、家にある身近なものの長さや重さなどを実際に計測するなどして理解の定着を図りましょう。割り算の学習はひっ算を綺麗に書けているか(縦がそろっているか)、確かめ算ができるかをチェックしてあげましょう。
4年生:小数や図形
4年生でも算数でつまづく子が多いです。この学年になると小数の計算が課題に。小数点の移動を忘れてしまうなどのケアレスミスも増えてくるため、家庭学習でも繰り返しドリルなどで学習していきましょう。
また、垂直と並行を理解し、ひし形や平行四辺形などの図形も学びます。平面・立体の図形を学習する上での基礎となるため家庭でも作図をするなどして理解を深めていきたいですね。
5年生:英語
2020年から学習指導要領に則り小学校での英語教育が完全実施されるように。それにともない5年生からは英語が教科として成績もつくようになります。英語教室へ通っている子と今まで英語に触れてこなかった子ではスタートからかなりの差がついており、家庭学習でもサポートをしていく必要があります。
学習内容としてまだ難しいものではありませんが、苦手意識がつかないようにまずは楽しむことからスタート。ドリルなどではなく、アプリやゲーム感覚で英語を学べるような学習法をとりいれるのもありです。
6年生:算数の速さや社会の歴史
小学校生活の集大成である6年生は、算数は四則計算をマスターすることに加え、速さの計算などより複雑な学習が始まります。また、以前は中学で学んでいたxやyをつかった計算式も6年生で学ぶように。中学生になってからスムーズに学習できるよう、苦手な単元は今のうちに復習しておく必要があります。
社会では歴史や政治を学んでいきます。これらは興味を持てるとスムーズに学習できるのですが、興味がない子は頭になかなか入りません。家庭学習では歴史の学習漫画やニュースや新聞などを親子でみて一緒に勉強するのがおすすめです。
家庭学習で使える教材の選び方
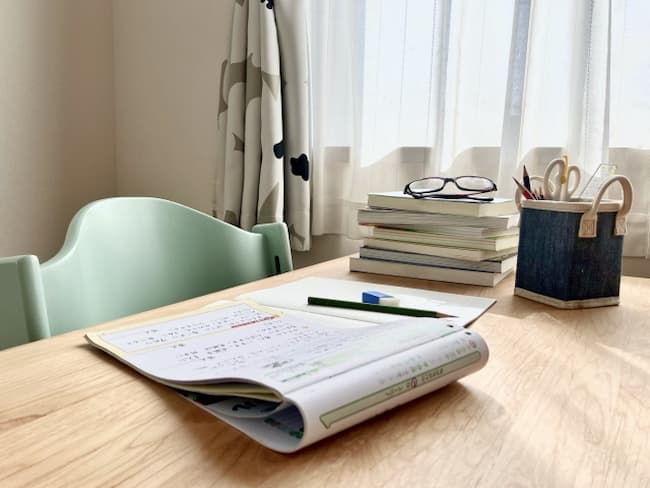
家庭学習では、子ども達が興味をもってわかりやすく学べるようなドリル・教材を用意するとより学習効果が期待できます。それぞれのお子さんにあった教材を選んで少しずつでも毎日の家庭学習に役立ててみてくださいね。
通信教材
親が丸付けしたり学習をつきっきりでみるのが大変という場合もありますね。そのような時には子どもが一人でも学習しやすい通信教材を取り入れるのがおすすめ。
小学校低学年なら毎日取り組みやすい「進研ゼミ」や「スマイルゼミ」などが人気です。たくさん学習するとご褒美がもらえたりポイントを集めてゲームができるなど、お楽しみがあるのもポイント。
高学年では「Z会」「スタディサプリ」などで動画授業をみたり学習の先取り・復習が自由に行えるようなもものおすすめです。
ドリルや問題集
学校の宿題だけでは不足する部分は市販のドリルや問題集で補いましょう。授業についていけるか心配な場合は授業内容に沿った問題集を使ったり、計算力・漢字力を高めたいという場合は繰り返し使えるドリルがおすすめ。
低学年ならイラストが可愛いものを選ぶと家庭学習が取り組みやすいかもしれません。
ライターおすすめドリル
・「学研 毎日のドリル」出版・編集/学研プラス
1日1枚短時間で取り組める学習ドリル。朝勉にもぴったり。専用アプリもあり得点を入力するとキャラクターが育つなど子どもが楽しめる工夫も。
・「グレードアップ問題集」出版・編集/Z会指導部
基礎から発展して応用問題にチャレンジさせたい時に活躍する問題集。良問が多く、思考力も高まります。カラーで見やすく挿絵があり飽きがこないのもポイント。
・「陰山メソッド 徹底反復 百ます計算」著者/影山英男 出版社/小学館
とにかく計算力を付けたい、速度を上げたいというときにはこちらのドリルがピッタリ。毎日同じ問題を2週間続けることにより正確性・速度UPが期待できます。陰山メソッドの基本実践を家庭でも行えるようたし算、ひき算、かけ算、わり算の百ますプリントが2週間分セットになっています。
学校導入の学習ソフト
各自治体や小学校ごとに学習指導要領に基づいてPCやタブレットを使って学べる学習ソフトを導入している場合も。ライターの住む自治体では「小学校向け学習・授業支援ソフトジャストスマイル」というソフトでの家庭学習を推奨されています。こちらのソフトは、学校での自習タイムや、家庭学習の支援として国語、算数、理科、社会、英語と学年ごとに単元がまとめられており、好きな単元を選んで問題にチャレンジできます。
教科書レベルのものなので、学校の予習復習や苦手教科の克服にも活躍。知っていても活用していなかったという家庭も多いので、お子さんの学校でもこのような学習ソフトが導入されているか一度確認しておくとよいでしょう。
テストの間違い直し
学校のテストの振り返りも家庭学習にピッタリ。テストを実施した後すぐに間違い直しをする子は多いのですが、一度したらもう終わりでテストをそのまま破棄してしまっていませんか?
わが家では1年間分のテストを100点だったものとそうでないものを分けて保管しています。学期末や年度末などの長いお休みの間に今まで間違えたところをもう一度解き直しして、苦手な単元は教科書を使って復習しています。特に漢字テストや単元ごとのまとめのテストは解き直してみると忘れてしまっている部分が分かりやすいですよ。
スマホのアプリなどでは、記入したテスト用紙をスキャンすると解答部分だけ空欄にできるものもあります。このようなアプリを利用して印刷しておくと復習がしやすくおすすめです。
【参考文献】
・小学校学習指導要領解説:文部科学省 (mext.go.jp)
・小学生におすすめの家庭学習教材11選!勉強を定着させるには? | わんぱく教育カンパニー (meigakukan.co.jp)
・家で勉強しよう。学研のドリル・参考書 (gakken.jp)
















































































































































