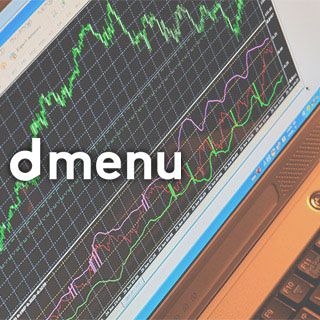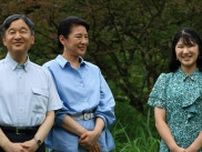やけにうるさい心臓の鼓動が、白菜を切る音と重なった。
香世は使い慣れない義実家の台所で、この上なく神経を尖(とが)らせていた。
ただし目の前の料理に、ではない。香世が気にしているのは隣りですき焼きに入れる割り下を調合している義母の隆子だ。
香世たちは現在、義実家に帰省をしている。義実家とわが家がさほど距離が離れているわけでもないので、いつでも来られる距離なのだが、ゴールデンウィークやお盆のような大型連休は必ず顔を出す。31歳で結婚してから12年、1度も欠かしたことはなかった。
白菜を切っていると、白滝を入れていた鍋が煮立つ。ここからはスピードが大事になってくる。しかしまだ材料の下ごしらえが終わっていなかった。香世は1度台所から外し、居間のソファに座っている息子の勇太に声をかける。
「勇太、こっちきて料理を手伝って」
「ああ」
生返事が戻ってくるが、勇太は手元のゲーム機から視線を外さない。
「ねえ、勇太、おばあちゃん家に来たらゲームはしないって約束だったよね?」
「いまいいとこ」
声を強めたが、勇太は香世のほうを見もしなかった。香世はため息を吐いた。
今年で11歳になる勇太は、最近はゲームばかりをしていて家でもあまり口をきいてくれない。学校の様子を聞いても答えてくれるはずもなく、勇太が何を考えているのか分からなくなることがある。
いわゆる反抗期というやつで、時間が解決してくれることなのかもしれないが、それでも心配になるのが親心だろう。
「香世さん? 何してるのさ!」
台所から隆子の声が響く。声からしていら立っているのは明白で、香世は駆け足で台所へと戻る。
「まったく、すぐ油を売るね」
隆子の鋭い視線が突き刺さり、香世の肩には自然と力がこもる。
「ほら、ぼーっと突っ立ってないで動きな。香世さんがいると通れないんだから」
隆子は香世を押しのけ、冷蔵庫から肉を取り出す。適度に脂が乗っている肉には”山形牛”と黒地に金文字のシールが張ってある。
「まだ5月だっていうのに見てるだけで暑苦しいね。充人や勇太はすらっとしてるのに、どうして香世さんはこうなんだかね」
隆子は吐き捨てて、居間へ向かっていった。
呆気(あっけ)にとられて何も言えなかった香世は、台所でひとりため息を吐く。
また始まったと思った。
隆子はことあるごとに、香世の体形をばかにしてくる。たしかに”ぽっちゃり”と呼ぶのでは足りない体形をしているが。
だから毎年、隆子と会わないといけないこの時期が嫌だった。
だが、このままここでふさぎ込んでいては、またのろまだなんだと言われるだろう。香世は深く吸いこんだ酸素で気持ちを切り替え、夕食の準備を再開した。
自分にだけ肉を取り分けてくれない義母
テーブルにはすき焼きだけではなく、出前で取ったすしも並んでいた。
「勇太が好きだって聞いたからね、すしもすき焼きも両方準備したのよ」
隆子の言葉に、勇太はうれしそうに笑った。
「あ、ありがとう、おばあちゃん」
「気にしないでいいんだよ。たくさん食べてね」
隆子は菜箸を持って、すき焼き鍋の前に陣取ると、肉や野菜を盛り付けた小皿を勇太へと渡した。勇太は小皿が渡されるや、溶いた卵に絡めた肉を口に放り込んだ。思わず笑みがこぼれる。
「こら、勇太。まだいただきますしてないでしょ。すいません、お義母(かあ)さん」
「香世さんはまたそんなちっちゃいこと気にして。でかいのは身体だけかい?」
隆子は笑いながら言って、充人にもすき焼きを取り分けた小皿を渡す。充人だって聞こえていたはずなのに、知らん顔でビールを片手に締めさばを頰張っていた。
「ああ、香世さんも好きなだけ食べてね」
隆子は最後に香世にも小皿を渡してくれたが、香世の小鉢にはネギや白滝のみで、肉が入っていなかった。
たまたまかな、と思ったがそれから高そうなお肉は全て勇太と充人の元に向かい、香世のところに来ることはなかった。
これは明らかにわざとだ。
「どう、香世さん、おいしい?」
アルコールのせいで少し赤くなった顔で嫌みったらしいほほ笑みを向ける隆子に、香世は笑顔で応える。
「あ、は、はい。ありがとうございます……」
別に肉を楽しみにしていたわけではなかったし、食い意地を張りたいわけでもない。
けれど、たとえ血はつながっていないとはいえ、ここは家族の食卓のはずだ。それなのに香世だけが、村八分にされている。太っているのはそんなに罪なんだろうか。きれいでないことはそんなに悪なんだろうか。ただ家族で普通に、食事を楽しむことすらも許されないほどのことなのだろうか。
「それにしても、勇太はきれいな顔だよ。目なんかは若いころのあたしそっくりだ」
「母さん似ってことは、俺似だろ?」
「何言ってんだい、あんたの目はわたしがつけてやったんじゃないか」
ゆらゆらと立ち上るすき焼きの湯気の向こうで、隆子の笑い声が響いている。しかし香世はその温度から切り離されている。
耐えればいい。いつも通りだ。
香世は自分にそう言い聞かせ続け、いまいち味のしみていないネギを口に運ぶ。視線を落とした小皿のなかに、横から大きな肉が突っ込まれた。
思わず顔を上げる。隣りではそっぽを向いた勇太がサーモンを食べていた。
「俺、もういらないから、お母さんにあげる」
「え……」
あまりに唐突のことで、香世はなんと返すのが正しいのか分からなかった。どこかに答えはないかと視線をさまよわせた。鍋の湯気越し、隆子と目が合った。
隆子は目を眇(すが)め、香世のことをにらんでいた。
●優しい息子の行動に喜びたいところだが、義母の厳しい目が……。香世は義母の時代遅れなイビリに耐えるしかないのだろうか? 後編にて、詳細をお届けします。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。