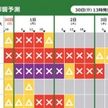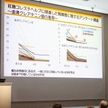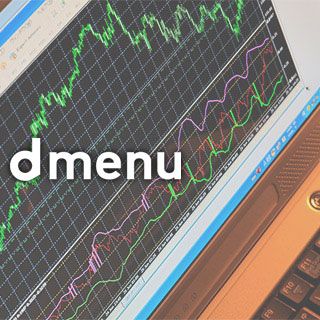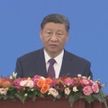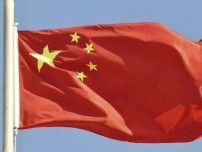アルバムをめくるたび、匂いや景色や夫の声がよみがえった。先月、夫の秀樹が老衰で亡くなった。無事に葬儀を終えた妙子は重い腰をあげ、ようやく遺品整理を始めた。
秀樹は写真が趣味で、書斎にはたくさんのアルバムが敷き詰められている。背表紙にマジックで書かれた日付の、きちょうめんな筆跡すらもいとおしかった。けれど肝心の写真は、日常の風景や動物園の動物、妙子を写したものがほとんどで、秀樹が写っている写真は少なかった。
「これなら、私もあの人の写真をもっと撮っておくんだったよ」
妙子はぼやきながら、アルバムをめくっていく。寂しい気持ちはあるが、悲しみはあまりなかった。もうしばらくしたら、また会える。そう思っていた。一度見始めてしまうと遺品整理ははかどらず、けっきょくただ思い出に浸るだけでその日は終わった。
妙子は独りぼっちの居間で食事を取った。秀樹はいつも妙子が作る料理をおいしそうに食べてくれた。そんな秀樹がいない食卓は、一カ月がたっても慣れなかった。気持ちを紛らわすようにテレビをつける。内容はちっとも入って来ず、にぎやかな笑い声だけが耳元を滑って消えていく。部屋が寒く感じるのは、単に今が冬だからというわけではなかった。
明日は何をしようか。秀樹が亡くなってから、妙子はよく考え込んでいた。秀樹が亡くなるまでの2年間、妙子の生活の中心は介護だった。脳梗塞を発症した秀樹は下半身不随になり、ずっと妙子が秀樹の生活を支え続けていた。亡くなる3カ月前からは寝たきりの状態になり、ヘルパーも頼んでいたが、それ以外の日常の世話を妙子がやっていた。
近所の友人には、大変だったね、偉いねと同情のような言葉をかけられることも少なくない。もちろん大変だったと言われたら、そうだ。だがつらいとは思わなかった。生前の秀樹にたくさんの幸せをもらった妙子にとって、介護は恩返しの機会だったのだ。自分が秀樹を支えているということに使命感もあったし、周りが言うほど、つらい日々ではなかった。何より、今思えば、秀樹がそばにいてくれたことが幸せだった。
しかし秀樹がいなくなった今、のこされた妙子には何もやることがなかった。自由と言われれば聞こえはいいが、心は何ひとつとして躍らなかった。
「明日、何をしようかね……」
妙子は声に出してみた。
しかしにぎやかなテレビの音に紛れるだけで、答えは永遠に返ってこなかった。
か細い鳴き声の正体
翌朝、妙子が散歩に出掛けたのは単なる習慣だった。秀樹がまだ元気だった頃、2人でよく近所にある自然公園を散歩していた。家にいて面と向かって話せないようなことも、並んで歩いていると話せたから、夫婦で散歩することが習慣になっていった。
とはいえ、秀樹が寝たきりになってからも妙子は1人で散歩を続けた。理由は特になかったが、今思えばいつかまた元気になった秀樹と散歩することを願っていたからなのかもしれない。しかし秀樹は一足先に旅立った。このまま緩やかに、何もない毎日だけがひたすらに続いていくのだろう。そのことにどんな意味があるのか、妙子には分からなかった。
みー、みー。
ぐるりと公園を1周し終え、今日の献立を考えながら帰ろうとしたとき、妙子の耳に弱弱しい鳴き声が聞こえた。
みー。
妙子はあたりを見回したが、声の正体は見つからない。普段ならば気にも留めずに歩き出していただろう。しかしどことなく寂しげで頼りない声音が気になって、妙子は耳を澄ませ、鳴き声のあるじを探した。
近くの茂みを順繰りにのぞいてみる。すると横たわっている三毛猫が見つかった。妙子に気づいた三毛猫は、だるそうに体を起こし移動しようとする。しかし前足をけがしているのか歩き方がおぼつかない。

「どうしたんだい、お前さん。痛そうだね」
放っておけなかった。妙子は茂みに入り、猫を抱きかかえた。軽く抵抗して身をねじった猫だったが、元気がないのかすぐに妙子の腕の中でおとなしくなった。
妙子は三毛猫を大事に抱きかかえ、家に連れて帰って手当てをしてやることにした。
夫は動物園の職員だった
猫を保護して家に帰り、傷口を消毒しようとしたが、暴れてうまくいかなかった。明日、獣医さんに診てもらわなくては。段ボールにタオルを敷いて簡易の寝床をこしらえ、皿に水を入れておいた。段ボールに飛び込んだ猫は水に気付き、しばらくすると警戒をしながらもおそるおそる水に舌を付けた。
妙子はその様子に、ひとまず胸をなでおろした。見たところ首輪はついていないから、飼い猫というわけでもないのだろう。どうせ妙子にはやることがない。ならば、この猫の気が済むまで休める場所くらいにはなってもいいだろうと思った。
「しばらく休んでいくといいさ」
妙子は猫をなでようと手を伸ばすが、警戒した猫は段ボールの隅に移動して威嚇するようにシャーと牙をむいた。
「なんだい。つれない子だねぇ」
そう言いながらも、猫を放り出すようなつもりはない。きっと秀樹なら、猫のけがが完治するまで家で面倒を見てやるに違いないからだ。
秀樹は定年まで動物園の職員として働いていた。普段からずっと動物園にいるはずなのに、休みの日までよく動物園に連れまわされたものだ。家で動物を飼おうという話が持ちあがることこそなかったが、動物園で担当している生き物の話をする秀樹は少年のように楽し気だったことを思い出す。
「あたしはね、妙子って言うんだ。妙子だよ」
妙子は猫に話しかける。人間のことを警戒している動物には辛抱強く話しかけて信頼関係を築いていくのが大事なんだと、秀樹が言っていた。
「そうだ。一緒に暮らすんだからあんたにも名前が必要だね。……ミーミーって鳴いてたからミーちゃんなんてどうだい? 安直かね」
みー。
三毛猫はあくび混じりに鳴く。
まあ、名前なんて何でもいいだろう。お互いに呼び合う名前があることが大事なんだ。
こうして、妙子とミーの共同生活が始まった。
●突然やってきたミーに癒やされていく妙子。1人と1匹の距離は縮まるのだろうか。 後編にて、詳細をお届けします。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。