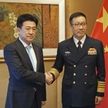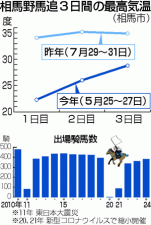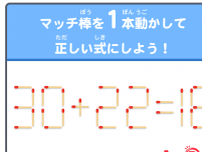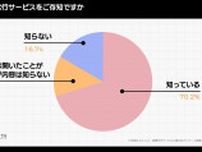「教育のまち」を掲げて英語の無料公営塾を運営するなど、 子育て世帯からの評価も高い岡山県南東部の和気町。その取り組みに ひかれて東京と奈良から移住した2人は、結婚して住まい探しを始め、 愛犬たちも気持ちよく過ごせる平屋の古民家を見つけた。
掲載:田舎暮らしの本 2024年4月・5月合併号

吉備高原から連なる山々に囲まれ、岡山県三大河川の1つの吉井川が貫流する和気町。瀬戸内の穏やかな気候に恵まれ、地理的に台風や地震などの災害が少ない。山陽自動車道を経由して大阪から約2時間。
段差が少なく広い庭付き 建物の歴史も気に入った

平屋の古民家で快適に暮らす中村さんファミリー。愛犬は左から温厚なこつぶちゃん、やんちゃなおちょぼくん。
東京で学習塾の講師をしていた中村和馬(なかむらかずま)さん(33歳)は、教育分野でのまちづくりに取り組む和気町に興味を抱き、公営塾担当の地域おこし協力隊として2016年に移住。奈良県で学芸員として働いていた暁子(あきこ)さん(36歳)は、美術講師や海外生活の経験が生かせると考え、19年に同協力隊に着任した。活動を通して出会った2人は結婚し、新居探しを始めることに。その際に気遣ったのが2匹の愛犬のことだったと暁子さんは話す。
「結婚前は2階建ての賃貸住宅に住んでいましたが、わんちゃんが遊べるほどの庭はなく、老犬になるにつれて階段が上りづらそう。次に住むなら老犬にも負担の少ない平屋がいいなと思っていました」
タイミングよく知人から紹介されたのが、改修済みの5LDKの平屋。和室の続き間になっている昔ながらの日本家屋で、室内の段差が少なく、広い庭があることにもひかれた。
「築100年以上の建物には、ペリー来航時などの古文書が残され、幕末から明治時代にかけて寺子屋として使われていたという記録も。そんな歴史を感じながら住めるのもいいですね」
と、和馬さん。現在は私塾を営み、自宅でも地域の子どもたち向けに寺子屋のような場を設けているため、導かれたような縁を感じているそう。
引っ越し後の愛犬たちの様子について暁子さんはこう話す。
「元気なおちょぼは庭を走り回って楽しそう。今まで見たこともない姿でリラックスしていることもあります。室内にいる老犬のこつぶは、元気なときは日の当たる縁側と和室が定位置。筋力が落ちてきた近ごろはリビングから外を眺めたり、昼寝をしたり。それぞれマイペースで過ごしています」
幼い文野(ふみの)ちゃん(1歳)と愛犬を連れてのんびり散策できるのは、田舎の環境ならでは。里山の風景に囲まれながら、買い物や交通の適度な利便性を併せ持ち、親子3人と2匹でストレスなく暮らしている。
改修にかかった費用(概算)
キッチンの棚の材料費…約1万円
玄関ステップの材料費…約5000円
地域でかかる費用
自治会費…年5000円
移住後に参加している行事
年3回ほどの草刈りや掃除、新年の寄合など。
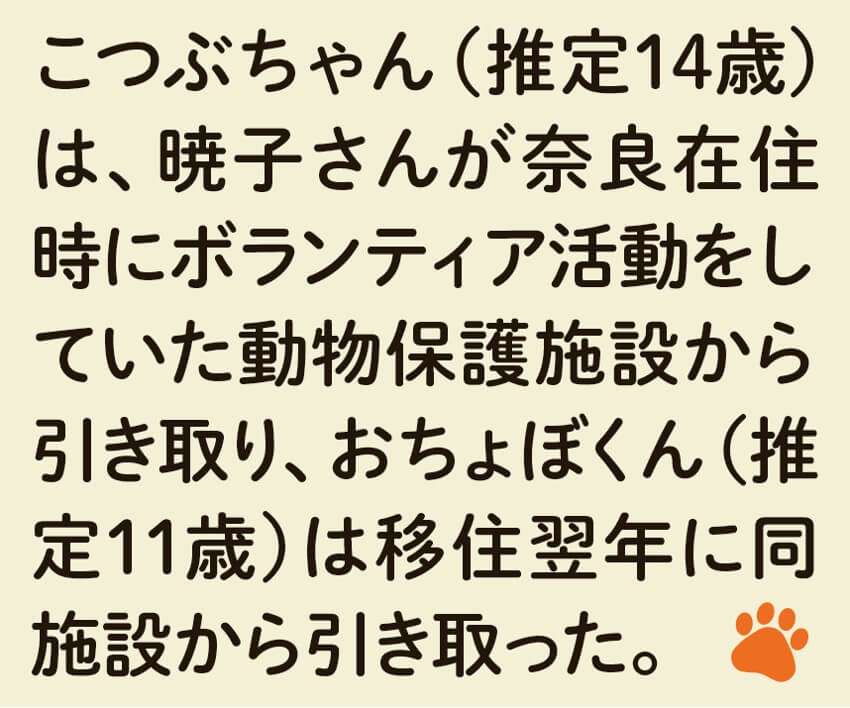

広い玄関土間は散歩帰りの愛犬の足拭きに重宝。老犬のために段差緩和のステップを設置。

キッチンの横にDIYで棚を設置。そのほかは現代的に改修されていたので即入居できた。

現在、暁子さんは和気町歴史民俗資料館の学芸員として、史料収集や埋蔵文化財の発掘などにあたる。「和気町は和気清麻呂など、深い歴史のあるまちです」。

和馬さんは協力隊卒業後、中・高生対象の私塾を立ち上げた。そのほか自宅で寺子屋的に学習や体験の場も設けている。

縁側にて愛犬たちとともに。走り回りたいおちょぼくんは基本的に庭で過ごしている。

ペットが暮らしやすい!
中村さん宅は庭がゆったりと広がり、愛犬に好環境。四季折々に変化する植栽も美しい。

老犬のこつぶちゃんは、粗相や視力の低下もあるので、LDK の一角をゲートで囲ったエリア内にいることも多い。

川沿いの散歩が日課。草や土の上を歩けるので真夏も愛犬の負担になりにくい。
先を見据えた物件選びを
「老犬になったときのことを考えると、段差がないか、バリアフリーにしやすいかなどは要チェック。広い庭が理想ですが、除草剤が使えないので手入れの手間との兼ね合いも。わんちゃんを飼うことに理解がある地域かもリサーチしておくとトラブルが避けられます」(中村さん)
中村さんオススメ! 本格的ドッグラン「キンデル・パーク」
日本警察犬協会公認訓練所
「山の起伏を利用したドッグラン施設で、豊かな自然に囲まれてわんちゃんが走り回れる環境が整えられています。日本警察犬協会公認の訓練士がいて、わんちゃんとのコミュニケーションの取り方やしつけの方法などについて相談に乗っていただけるのもありがたいですね。とてもすてきな場所です」(中村さん)

イヌと飼い主が自然のなかで学びながら遊べる「キンデル・パーク」。
https://www.kinderpark.jp
文・写真/笹木博幸