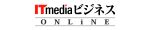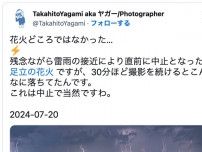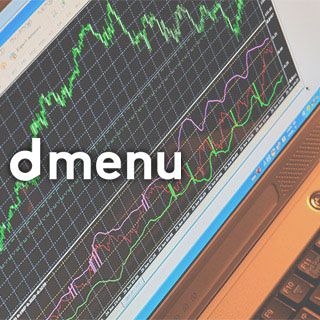さまざまなメディアで「2024年問題」が取り沙汰されている。2024年問題とは、これまで働き方改革関連法の「時間外労働の上限規制」が猶予されていた物流・運送業界、建設業界、医療業界にも上限規制が適用されるようになったことで起こる諸問題を指す。
長時間労働がはびこるこれらの業界において、労働時間の上限規制は労働環境改善につながるはずだ。
しかし一方で、一人当たりの労働者が合法的に働ける時間が減ってしまうことにより、事業者側はこれまで以上に多くの人員を確保しなければならなくなる。
影響は人手不足に苦しむ事業会社のみならず、物流の停滞や建設工期の遅れ、公共交通の路線網廃止、医療提供体制の弱体化など、社会構造自体にも及ぶため、社会全体で働き方を問い直すことが求められそうだ。規制の時間数や例外規定は業種により異なる。
この記事では特に建設業が直面する問題について解説する(物流・運送業については、記事前編「今さら聞けない「物流2024年問題」のウラ側 根本解決はできるのか?」にて解説した)。
●2024年問題のウラ側 「休めない、人手が足りない、若手がいない」
建設業では2024年4月以降、例外なく一般則である「労働時間は月45時間、年360時間まで」「特別な事情がある場合でも、残業は年720時間、複数月平均80時間、単月100時間未満が限度」という条件が適用される。ここは運送業とは異なるポイントだ。
ただし、災害時の復旧や復興事業に関しては例外規定に則るため、一部の規制は適用されず、「時間外労働は年720時間以内」「時間外労働が月45時間を超過するのは年6回まで」という2点のみの順守が求められることになっている。
長時間労働の常態化、人手不足、就業者の高齢化が三重苦のようにのしかかる建設業は、労働環境改善が特に求められている業種の一つである。
国土交通省調査によると、建設業の年間実労働時間は2021年度で1978時間。調査対象となったほかの全産業と比べても約350時間多く、労働時間が約2割も長いことが分かる。さらに建設工事全体では、技術者の約4割が「4週4休以下」で就業している状況だ。
年間実労働時間と休日数を見るだけでも、建設業における労働環境の課題は明確であるが、ほかにも就業者数はピーク時の685万人(1997年)に対して、485万人(2021年)と約3割減。また建設業就業者のうち55歳以上が35.5%と4割近くに上る一方、29歳以下の若手人材は全体のおよそ1割となる12.0%しかいないという危機的状況だ。
高齢人材はいずれ引退するため、次世代を担う若手人材を確保しやすい労働環境への改善が急務なのである。
●働き方改革を阻む、業界ならではの「2つの要因」
一方で、業界ならではの「働き方改革を阻害する要因」もまた存在する。
その一つは「週休2日制導入のハードルが高い」ことだ。先出の資料にもあった通り、現状週休2日制を実現している事業者は全体の約2割程度にとどまっている。その理由はさまざま存在するが、業界で広く採り入れられている「日給月給制」は原因の一つといえるだろう。
日給月給制は、1日を計算単位として給料が定められているため、労働日数が多い月は給料が増え、労働日数が少ない月は給料が減る。したがって日給月給制のまま週休2日制になると、稼働日が純減し、収入も大きく減ってしまうこととなり、現場から反対の声が挙がるケースが少なくない。
現場が動いている以上施工管理なども現場せざるを得ないため、実質的な休日出勤が常態化しているという構造だ。
もう一つの業界ならではの要因は「多重下請け構造」である。IT・システム業界などでも見られるが、多重下請けによって中間マージンが差し引かれると、利益が残らず十分な人員を配置することが困難となる。
結果的に一人当たりの負担が大きくなり、長時間残業・休日出勤の元凶となるうえ、指揮系統の複雑化、作業効率低下なども、労働環境の悪化につながってしまう。
●実際に、成果が出た取り組みは……
企業規模を問わず各社とも知恵をしぼって2024年問題に立ち向かおうとしている。実際に残業時間削減や採用定着に明確な成果が出た取り組みとしては、次のようなものが挙げられる。
・ウェアラブルカメラやドローン、設計支援システム等を活用したデジタル化・システム化推進により、作業の進捗管理や現場監視、事務作業の効率化を実施
・Web会議活用による移動時間削減
・マニュアルやスキルマップ、手順書作成による業務平準化と属人化解消
・ベテラン作業員の業務を動画共有することによる技術向上と生産性向上
・取引先への協力要請による無駄作業・残業削減
・下請け構造から脱却し、自らが元請けとなって、工期と利益をコントロール
ただしこれらの施策を実現するためにも、発注側である元請企業の協力は不可欠である点では運送業の構造とも同じである。
少なくとも適正な工期設定は必要となるし、残業でカバーできない分の人件費負担を施主に要求する必要も出てくるだろう。そうなると建築費用は現状より大幅増となることは明白であるが、業種そのものを持続可能にしていくためにも、社会全体で受け容れなければならないテーマであるといえる。
●どう事業を回していくか知恵をしぼる
帝国データバンクの2024年1月調査によると、正社員の人手不足企業の割合は52.6%と過去最高水準に肉薄しており、「2024年問題」に直面している建設、物流、医療業界では人手不足割合は約7割にまで達している。
少子化がさらなる進展をしている以上、この傾向は今後も変化しないどころか、人手不足はあらゆる業界で顕在化していくことだろう。
今後は「人手が足りないから採用する」という手法に頼ることはより困難となるため、「人手がいない中でどう事業を回していくか知恵をしぼる」という方向にいかにリソースを投入できるかがカギとなるだろう。
これまでの「働き方改革」の文脈では、個別企業の努力によってITやシステム、機械化を進めて、極力少ない人手で売上や利益を最大化することに注力してきた。今後は国を挙げて、人手不足という難関に立ち向かっていかねばならない。
●具体的な「2つの手段」
その手段の一つは過酷な条件を強要するあまり、結果的に劣悪な労働環境が生まれる元凶となってしまう発注者への「ペナルティ強化」だ。運送業でも建設業でも、発注者側が適切な納期や業務量を考慮せず、無理なスケジュール、無理な業務量を強要することで下請け企業がシワ寄せを受ける構造になっているケースが多い。
例えば運送業であれば、荷主が過積載となることを認識しながら運送を要求した場合、道路交通法に基づき罰則を受ける。これと同様に、運送業者に法定時間を上回る残業を強いるようなスケジュールを要求したり、時間短縮を要求するのに高速代を負担しなかったりする荷主に対してペナルティをつけることも一考に値しよう。
同じように、建設業の場合は、建築の確認申請の中に適正工期の審査を導入するなどの監視体制強化が必要ではないだろうか。
もう一つは「適正値上げ」を国民全体の合意として歓迎するムードを醸成することだ。法律改正によって各業界の労働環境が改善されることは望ましい反面、労働時間減少が収入源に直結することがネガティブ要因ともなり得る。「働きやすくなったが給料は少ない」となると業界自体の魅力もなくなり、さらなる人手不足へと負のスパイラルが発生することにもなりかねない。
さらには、残業が厳格に管理されている以上、稼ぎたい人は副業やかけ持ちを始め、結局長時間労働が温存されるばかりか、疲労や集中力低下によって事故の危険性も高まるリスクがある。そうなってはまさに本末転倒である。
長時間労働とされる業種の仕事は、好き好んで長時間労働しているわけではなく、そのとき求められている仕事をきちんとこなそうとした結果、長時間労働になってしまっているのだ。長時間労働抑制のためには、業務量を減らすか、人を増やすかしかない。
業務量自体は簡単に減らない以上、人を増やすためには人件費が必要であるから、その分が価格転嫁されてしかるべきなのだ。
残業規制とセットで、発注主には発注金額の底上げと、雇用主には賃上げ、そして全業界で一斉に賃上げと連動した値上げをするくらいの対策が必要だ。
そもそもわが国では、低価格店であっても高級店並みの接客サービスが当たり前のように行われているし、本来追加料金を徴収しておかしくない配達時間指定や再配達が無料で提供されている。
われわれは高品質低価格サービスにどっぷり浸かり、悪い意味で慣れきってしまっているのだ。また、シーズン真っ最中の観光地やアミューズメントパークで発生する大行列と大混雑で疲弊したり、人気の新商品に予約注文が殺到して入手できるのが数カ月〜数年待ちになり、転売商品に手を出さざるを得なかったりするのも同じような状況といえる。
単純に考えれば、いずれも「安すぎる」からこそ買い手が殺到するのだ。これらも需要に合わせて柔軟に値上げすれば、待ち時間のイライラ、在庫枯渇による機会損失、本来不要な転売ヤーの増加など、多くの問題を解消することができるはずだ。
これまではマスコミも、少々の値上げであってもまるで「悪いこと」かのように報道してきたし、われわれ消費者も「値上げするならもう買わない」とばかり、価格上昇に対して強い拒否感を抱いてきた。
しかし、それでは低価格が維持できるメリットがある反面、「誰かの給料が上がらないまま」「誰かの労働環境が悪いまま」で据え置かれることと同義でもある。
「『今だけ、自分だけが良ければよい』という考えはよくない」という風潮がようやく生まれ始めてきた今こそ、国と企業が連携し、適正な値上げを実施し、皆が働いた分だけの充分な給料を得られる社会にしていきたい。
(新田龍、働き方改革総合研究所株式会社 代表取締役)