クルマの前後に備わり、衝撃を守ってくれる「バンパー」。かつては独立した鉄製の部品として存在感を放っていましたが、近年はすっかり車体のデザインと一体化してしまいました。ここでバンパーの変遷について、あらためて振り返ってみます。
車体とは別に備わっているのが当たり前だった「バンパー」
クルマの前後に装着されるバンパー。現在では車体デザインの一部に組み込まれ、その存在感は薄くなっていますが、かつては「バンパーここにあり」という造形をしていました。
バンパーの変遷について、今回は「デザイン」の観点から追ってみます。
バンパーは、外部からの衝撃を和らげるためクルマの前後に装着される部品で、英語では「Bumper」と記します。
自動車用語では「バックミラー」「ウインカー」「クラクション」など「日本でしか通じない和製英語」が多いですが、バンパーはそのまま通用します。
なお「Bump」とは「〜にぶつかる、〜をぶつける」などの意味があります。
19世紀末に誕生したクルマですが、バンパーが装着されはじめたのは1930年代頃のことでした。
初期のバンパー形状は横一文字型を基本とし、素材はスチール、表面はメッキが基本でした。
そして車体とは明らかに別に取り付けられていました。
このような「バンパーは鉄製、車体とは別」というスタイルは、フロントフェンダーが次第に車体に取り込まれていった1940年代から1950年代を経て、ボディデザインに自由度が増した1960年代から1970年代に入っても、ほとんどのクルマがそのスタイルを堅持し続けました。
しかし同時にこの頃から、いわゆるメッキバンパー以外に、初代のルノー「5(サンク)」の樹脂製バンパーなど、様々な素材・デザイン解釈のバンパーが出現し始めたのです。
例えば3代目のシボレー「コルベット」では、1968年のデビュー時はボディ前端に細いメッキバンパーを備えていました。
しかし1973年には、バンパーが車体の先端デザインと完全にビルトインしています。
空力性能の高さをスムーズなフォルムで表現するデザイン思想は、こうしてまずスポーツカーを中心に拡がっていきました。
「大きなバンパー」=「頑丈で安全なクルマ」をイメージ!?
それではここからは、現代に至るまでのバンパーの変遷・歴史について、初代デビューから70年近く販売を続けてきたトヨタの高級車「クラウン」のデザインを通じて検証してみましょう。
初代クラウン(1955年〜1962年)、2代目クラウン(1962年〜1967年)では、バンパーは「見るからに頑丈で重そうな形状」でした。
続く3代目クラウン(1967年〜1971年)のバンパーで、ボディデザインの流れに逆らわないデザインに変化しました。
そして当時としては非常に革新的なデザイン「スピンドルシェイプ」を採用した4代目クラウン(1971年〜1974年)では、画期的な「ボディと一体化したバンパー」に挑戦。
しかし斬新すぎるデザインが保守的なクラウンユーザーに受け入れられず、マイナーチェンジでメッキの面積を増やして、バンパーの存在感を「復権」させています。
これを見ても、当時は「バンパー=メッキで頑丈なもの」というイメージが強かったことがうかがえます。
その反動を受けてか、5代目クラウン(1974年〜1979年)では、どっしりとした高級車らしいスタイルに回帰。
バンパーも、再び大柄なメッキバンパーに戻っています。
注目点としてはこの5代目から、バンパーのカドに、樹脂製のゴムブロックを貼り付けるようになったことが挙げられます。
6代目クラウン(1979年〜1983年)では、当時流行していたスクエアなイメージに変わりました。
バンパーは5ナンバー(小型自動車)車と3ナンバー(普通自動車)車で大きくデザイン・素材ともに異なっており、前者はメッキバンパーに黒い樹脂モールが巻かれ、後者ではこの頃登場しはじめた「樹脂製バンパー」「ボディ同色(カラード)バンパー」を採用したことが大きなトピックでした。
興味深いのは、長年にわたり君臨していたメッキバンパーと、新しい素材により自由な形状を可能にした樹脂バンパーが併用されていたことです(TOPページ画像参照)。
1970年代と80年代では、クルマのデザイン自体にも明らかに大きな進化がありますが、新旧2種のバンパーが用いられていたこの6代目クラウンは、まさにクルマのデザイン上の過渡期・転換点の象徴と言えます。
3ナンバー車がバンパーのデザインを「進化」させた!?
ところでこのころクラウンではなぜ、5ナンバー車と3ナンバー車で異なるバンパーを装備していたのでしょうか。
実は当時「贅沢品」扱いだった3ナンバー車(排気量2000cc以上、全長4.7m・全幅1.7m以上など)の自動車税が、非常に高額だったことが要因として挙げられます。
例えば1984年では、5ナンバー車の最大額が約4万円だったのに対し、3ナンバー車では(しかも3リッターまで)約8万円もしたのです。
そのため、日本車のほとんどは5ナンバー規格に収まるように造られていました。
そこで3ナンバー車は、5ナンバーサイズの車体のまま、バンパーやモールを大きくすることで外観を造り分けし、上級モデルとしての差別化を図っていたという訳です。
これまで続いたメッキバンパーがクラウンの一部車種(商用モデル)以外から消えたのは、7代目クラウン(1983年〜1987年)からでした。
5ナンバー車でも黒モール付きの樹脂製カラードバンパーになり、次第に車体との融合性が高まっていきました。
カドを落とした優美な曲面に身を包んだ8代目(1987年〜1991年・一部車種は1999年まで)では、5ナンバー規格を突破した「3ナンバー専用ボディ」が導入されています。
バンパーモールはまだ残っており、基本は黒ですが、グレードによってはボディ同色が用いられました。
なお8代目発売中の1989年には自動車税制が大きく変更され、3ナンバー車の税金が引き下げられました。
その結果、3リッター車の自動車税が約5万円になりました。
こうした税制改革に加え、時のバブル経済も手伝って、日産「シーマ」や三菱「ディアマンテ」などの3ナンバー専用ボディのモデルが飛ぶように売れるようになりました。
そして次第に5ナンバー車と3ナンバー車を造り分けることもなくなっていったのです。
21世紀に入り本来の「衝撃吸収」という目的が形骸化していった
9代目クラウン(1991年〜1995年)、10代目クラウン(1995年〜2001年)、11代目クラウン(1999年〜2007年)へとフルモデルチェンジを重ねるたびに、クラウンのバンパーは次第にボディと一体化していきます。
立派さや上質さが重視されてきた高級車のクラウンとはいえ、燃費や操縦安定性にも影響を及ぼす空力性能の向上も求められてきたのです。
そもそも本来の用途であった衝撃吸収ですが、実はバンパー単体だけでなく、クルマのフロント骨格部全体で衝撃を受け止めることで客室部を守るという安全設計思想は、既に1960年代には一般化していました。
サイドモールとともに、バンパーは依然として軽度の衝突から車体を守る役割を果たしているものの、それもフォルムとの一体化にともない、形状の意味合いすら形骸化していくのです。
21世紀に入り、12代目クラウン(2003年〜2008年:通称「ゼロクラウン」)からはグリルがバンパー側に付くように。
さらにボディとの連続性が持たされ、高級感とともにスポーティさや革新性も併せ持つスタイリングとなりました。
続く13代目クラウン(2008年〜2012年)では、フロントバンパー形状はもはや以前のように前方へ飛び出ることもなくなりスムーズ化。14代目クラウン(2012年〜2018年)以降では、グリルが上下に大幅拡大し、バンパー部分まで浸食しはじめます。
16代目となる現行型「クラウンクロスオーバー」(2022年〜)となると、「バンパーというパーツ」が視覚的に視認しづらくなるほどに、バンパーは車体のフォルムと完全に同一化するに至りました。
※ ※ ※
こうして歴代クラウンの変遷を眺めてみると、バンパーはデザインの進化に合わせて大きく姿を変えてきたことがわかります。
今後、エンジンを搭載しないEV(電気自動車)も増えていくなか、クルマのバンパーはどのような形になっていくのでしょうか。
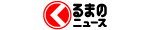



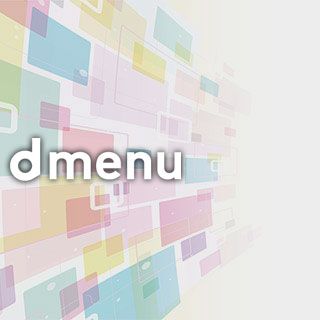

















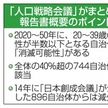




































































































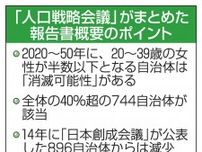








![[競馬ニュース]第1回福島開催の最終週! ほか - 今週末の競馬(2024年04月20日、21日)](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33011.jpeg)


