
日々忙しく生きる人々にとって、コンビニやデリバリー、外食などの食事は便利で手軽な手段の一つです。しかし、食事の選択肢が多様になったことが⾷べ過ぎや好き嫌いなど、逆に栄養を偏らせてしまう原因ともなります。
現在、厚生労働省でも⼼⾝の健康を⽀えるための⾷⽣活を促進する「⾷育⽉間」を毎年6月に設けるなど、健全な⾷⽣活の実現に向けた取り組みを国をあげて⾏っています。
そこで今回は、静岡県⽴総合病院リサーチサポートセンター臨床研究部⻑の⽥中清先⽣に、栄養の偏りによって起こる症状や普段の⾷事で気を付けるべきことを教えていただきました。
⾷⽣活の偏りによる低栄養素が引き起こす体の不調
体内の栄養が不⾜し、⾝体機能の維持に必要な栄養が⾜りない状態を「低栄養素」と言います。食事量の低下だけでなく偏った食生活でもなってしまう低栄養素ですが、これにより引き起こされる症状を⽥中先⽣に教えていただきました。
・集中⼒の低下
栄養不⾜の代表的な症状である集中⼒・思考⼒の低下。主な原因は炭⽔化物不⾜です。また、炭⽔化物をブドウ糖に変換する栄養素、ビタミン B 群の不⾜も脳の働きを低下させる原因です。
・体⼒の低下
⾷事量が減ったり偏ったりすると、必要な栄養素が摂取できないため体⼒が低下し、活動的な状態を維持できなくなります。体を動かすことがしんどくなり、体型の崩れや肥満といった悪影響が出てくる可能性もあります。
・免疫⼒の低下
「免疫⼒」とは⼈間の体に備わっている防御能⼒のことで、細菌やウイルスといった病原体の体内侵⼊を防ぐことができます。免疫⼒を損なわないためには運動や睡眠などのさまざまな要素が必要ですが、なかでも重要なのが⾷事です。たんぱく質不⾜やビタミン不⾜は、免疫⼒の低下を促します。
いま注目されている栄養素「ビタミン B1」
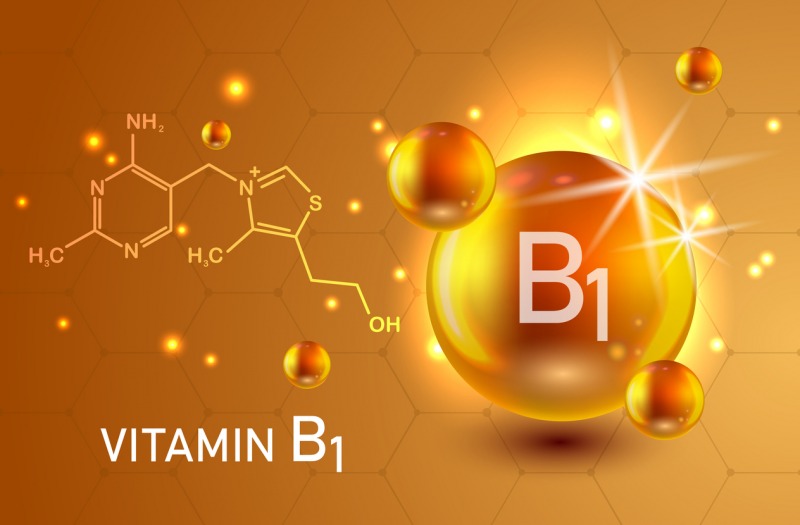
昨今世界で摂取不⾜が注⽬されている栄養素が「ビタミン B1」です。この栄養素は“疲労回復ビタミン”とも呼ばれ、⽣活するうえで重要な栄養素です。今回は「ビタミン B1」の効果や不⾜の原因、効率的な摂取⽅法を⽥中先⽣に教えていただきました。
・「ビタミン B1」の効果
「ビタミン B1」はチアミンとも呼ばれる⽔溶性のビタミンです。糖質を燃やしてエネルギーに変えるときに必要なビタミンのため、糖質やアルコールを多く摂取する⼈には不可欠な栄養素です。
不⾜するとブドウ糖から⼗分にエネルギーを産⽣できなくなり、⾷欲不振、疲労などの症状が現れます。脳はブドウ糖をエネルギー源としているため、「ビタミン B1」が不⾜すると脳や神経に障害を起こします。重症な場合は脚気(⾜の浮腫、しびれ、動悸・息切れ)やウェルニッケ・コルサコフ症候群(中枢神経が侵される障害)になり、重篤な場合は死亡することもあります。
・アルコールの飲みすぎに注意
「ビタミン B1」は⾁類、⿂類、⾖類、穀類、種実類などに多く含まれます。⽶や⼩⻨にも多く含まれますが、精製されると少なくなってしまいます。
⽋乏の原因としてあげられるのがアルコールの多量摂取です。アルコールを摂取すると代謝酵素によりアセトアルデヒドに分解され、さらに体内で分解されて酢酸に変化します。最終的にエネルギーを作り出すときに「ビタミン B1」が消費されますが、多量にお酒を飲んだ場合は、代謝酵素のみでは分解が追い付かず「ビタミン B1」 が必要となります。
・おすすめの食材
「ビタミン B1」は⽞⽶、胚芽⽶、全粒粉パンなど胚芽の部分に多く含まれているため、精製されていない⾷材を選ぶのがポイントです。⽔に溶けやすいので、汁ごと⾷べられる調理法もおすすめです。また、ニンニクや⽟ねぎに含まれる「アリシン」と⼀緒に摂ることで 吸収率がアップします。
ビタミン B1 が摂れる⾷材

その他の摂取したい栄養素
特定の栄養素ばかりを過剰に摂取してしまうと体に悪影響を及ぼす可能性もあるため、植物性⾷品、動物性⾷品ともにバランスよく摂取することが健康への近道です。「ビタミン B1」以外にも、カルシウムやリンの吸収を促進し、ウイルスや細菌などの感染を予防する「ビタミンD」や、エネルギー代謝の補酵素となり、免疫機能の正常な働きの維持、⽪膚の抵抗⼒の増進に必要な「ビタミン B6」もオススメの栄養素です。
気軽に好きなものが食べられる飽食の時代。偏った栄養の食事にならないよう、意識的に色々な種類の食品を食べるように心がけていきましょう。推奨量を摂取しにくい栄養素に関してはサプリメントで補うのも⼀つの⽅法です。

















































































































































