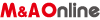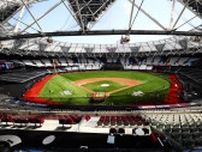前回のコラムでは、株式会社制度の骨格をなす基本原則である「株主有限責任制度」「資本充実原則」そして「株式譲渡自由原則」が、オランダ東インド会社(VOC)の「合併」プロセスを通じて生まれたのではないかという考えを述べた。では、スペインやポルトガル、そしてイスラム圏からオランダに移り住んだユダヤ教徒は、VOCの成立にどのように関わったのか。もしくは関わらなかったのか。今回はこれについて書いてみたい。
ユダヤ教徒がVOCの株主になれなかったのはなぜか
まず、事実関係を整理しよう。VOCの設立時点の株主にユダヤ人は2名しかいなかった(出所:「ユダヤ人〜世界と貨幣〜」)。その株主とはステファン・カルドーゾとエリザベス・ピント。
筆者はこの2名はユダヤ教徒ではなく、キリスト教徒に改宗した新キリスト教徒、またはコンベルソだったと理解している。(筆者注:このコラムにおける新キリスト教徒とコンベルソの定義については、第29回を参照)。なぜそう考えるのか、理由を説明しよう。
オランダ東インド会社の勅許状は、1602年3月20日にオランダ共和国議会が承認した。この勅許状には、株主になるための条件としてオランダ市民であることが明記されている。(出所:「1602年のオランダ東インド会社の勅許状について」田渕保雄著)
VOC勅許状第9条(投資者の権利)
「会社の事業計画が了解されていない場合、投資者は投資金を引き揚げることができる。外国人を除く連邦共和国のすべての市民に対して、金額の多寡に関係なく、一定額をもって、会社に関与することが認められる。」
「1国家1宗教」と市民権
勅許状には、VOCの株主になる要件として「オランダ市民」でなくてはならないと明記されている。では、ここでいうオランダ市民とはなにか。それは「キリスト教プロテスタント・カルヴァン派」の教徒を指すと考えてまず間違いない。それがオランダの国教となっていたからだ。
オランダがユダヤ教徒に対して宗教的寛容を示したのは間違いない。しかし、それはこの時代の大前提だった「1国家1宗教」の原則を超えるものではなかった。オランダ市民になるためには、キリスト教プロテスタント・カルヴァン派である必要があった。
オランダはユダヤ教徒を受け入れ、植民地獲得競争における共闘集団の一員に加えた。だが、これはユダヤ教徒がオランダ市民になれることを意味したわけではなかった。(参考:「物語 オランダの歴史」桜田 美津夫著)
ユダヤ教徒がVOCの株主として存在感を示すようになるのはもっと後だ。時代が進むにつれて市民権の縛りは徐々に弱まったと推察される。そして流通市場でVOCの株式を購入したり、増資を引き受けたりしたユダヤ教徒の投資家が増えていった。
17世紀後半には、VOCの株主の4分の1をユダヤ人が占めるに至ったとされる。ただ、これをもってユダヤ教徒が統治者(株主)の立場でVOCの設立や発展を主導したと捉えるのは、筆者の感覚では明らかに誤りだ。VOCの設立から100年近く経ってなお、ユダヤ教徒の株式保有シェアはせいぜい25%程度だったのだから。
カーメルの無機能投資家にユダヤ教徒が参加していた?
このようにユダヤ教徒は初期VOCの株主になれなかった。では、VOCの成立においてユダヤ教徒は全く関与しておらず、その影響もなかったのか。これはまた別の問題だろう。例えばVOCの成立母体となった6つの投資集団(カーメル)への出資者として、ユダヤ教徒あるいはコンベルソや新キリスト教徒が関与していた可能性はないだろうか。
前回のコラムで述べたように、6つのカーメルには複数の機能投資家(取締役)や無機能投資家がいた。特に無機能投資家は匿名性が高く、現在その名前や出資額を把握することは極めて困難だ。もし、この無機能投資家の中に離散ユダヤ教徒の人々がいたならば、彼らはVOC誕生における「合併トランザクション」において、どのように処遇されたのだろうか。
筆者はこう考える。すでに述べたように、オランダ市民ではない彼らはそのままVOCの株主になることはできない。だとしたら、彼らは合併の際「債権者(デットの人)」として整理された可能性はないか。筆者は、6つのカーメルの中心にあった「アムステルダムグループ」の無機能投資家の中には、少なくとも少数の離散ユダヤ教徒がいた可能性があると考えている。
アムステルダムグループに深く関与したと思われるユダヤ教徒の商人の名前も複数散見される。VOCを誕生させた6つのカーメルの合併。この合併トランサクションの中で、ユダヤ教徒の無機能投資家は株主になれず、代わりに債権者(デットの人)として整理されたのではないか。これが筆者の想像だ。
歴史に思いを巡らせながら、このように空想することは楽しい。が、残念ながら彼らが無機能投資家(あるいは機能投資家=取締役)だったことを裏付ける確たる情報はなさそうだ。この頃、ユダヤ教徒は、生命と財産をキリスト教徒に奪われる危険に常に晒されていた。
そうした中で彼らは、自らの信仰や出自に関する情報が漏洩しないよう慎重に行動しただろう。もし筆者の想像が正しかったとしても、それを裏付ける情報がないのは、ある意味必然なのかも知れない。
オランダ東インド会社の「成長戦略」とユダヤ教徒
このように筆者は合併を通じてユダヤ教徒はVOCの統治者(=株主)」ではなく、債権者にしかなれなかったのはないかと推察している。しかし、ユダヤ教徒がVOCの株主になれなかったからといって、VOCの成長(ビジネス)に、彼らの貢献が全然なかったということにはならない。そこで次はユダヤ教徒とVOCの関係を、事業成長の側面から「ビジネス・デューデリジェンス」してみよう。
植民地獲得競争において、スペインやポルトガルに後れを取ったオランダ。彼らが直面した最初の課題はなんだっただろうか。それは言うまでもなく、航路の確保である。
オランダ独自の航路が確保できなければ、植民地獲得競争に参戦するなど夢のまた夢だ。東インド航路(喜望峰を回ってインドに到達するルート)は、ポルトガルが開拓した超国家機密ルートだ。そしてコロンブスが道を開いた新大陸への大西洋航路は、スペインのものである。
そこで、オランダは新大陸への独自ルートを開拓すべく北進ルートを模索した。バルタザル・ド・ムーシュロンという豪商が中心となり、複数回に渡って北進ルートの開拓が試みられた。1585年から1595年のことだ(出所:「株式会社発生史論」大塚久雄著)
北進ルートとは大西洋を北上し、ノルウェーの北岸から東シベリア海、ベーリング海峡へと東進して現在のカナダ沿岸付近を目指すルートである。北欧のバイキングを描いた漫画「ヴィンランド・サガ」で、主人公のトルフィン*一行が航海したルートに近い。
*実在した中世アイスランド商人のソルフィン・カルルセヴニ・ソルザルソンがモデル
しかし、現代の視点から見れば、木造帆船で酷寒の海を航海し、貿易ルートとして確立しようというこの試みが、いかに無謀だったかは容易にわかる。凍てつく北限の海を帆船で航海することは困難を極めただろう。オランダの北進ルート開拓はあえなく挫折する。
喜望峰ルート開拓は、離散ユダヤ教徒との共闘の賜物
ここで大航海時代初期の歴史において、最も奇跡的な出来事のひとつが起こる。オランダは驚くべき短期間で、ポルトガルの独占ルートであったはずの喜望峰ルートを自ら攻略することに成功したのだ。
筆者は、オランダが喜望峰ルートを短期間で開拓することに成功した背景に、離散ユダヤ教徒の貿易商人たち(いわゆるポルトガル商人と呼ばれる人々の一部)の少なからぬ貢献があった可能性は非常に高いと考えている。
スペイン、ポルトガルを追放される前、ユダヤ教徒の人々はイベリア半島の商業・貿易における重要なキープレイヤーだった。長距離航海に欠かせない天文学、地図や測量の技術、長距離航海のノウハウ。ユダヤ教徒は豊饒の海・地中海と大西洋を舞台として、これらを発展させてきた主役の一人だった。オランダの喜望峰ルート開拓成功は、イベリア半島からのユダヤ教徒の追放がもたらした技術流失の帰結である。
もちろん、すべてをユダヤ教徒がもたらしたなどと拡大解釈するつもりはない。地中海が育んだギリシャ文化や南欧イスラム文化との交流。イベリア半島は古代からこうした文化の交差点であり、情報の交差点だった。創造性は交差点が育むのだ。この文化の結節点の中で花開いたもののひとつが、スファラディの知恵と能力だった。筆者はそう考えている。
オランダは、長期航海可能な船を建造することができるようになった。そして喜望峰ルートに関する様々な情報(寄港地や難所、航海に適した季節風など)を自分たちのものにした。そして、敵国(ポルトガルやスペイン)の庭先を突っ切って、喜望峰ルートで香辛諸島に到達したのだ。
ユダヤ教徒は、オランダ市民にはなれず、VOCの株主になれなかった。しかし、VOCの初期の成功と発展は、オランダのカルヴァン派キリスト教徒とユダヤ教徒の共闘なくして成し得なかった。筆者はそう考えている。
(この項つづく)
文:西澤 龍(イグナイトキャピタルパートナーズ 代表取締役)