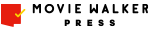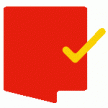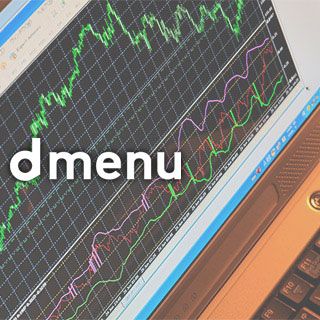是枝裕和監督と脚本家の坂元裕二が初タッグを組み、音楽を坂本龍一が手掛けた『怪物』(公開中)。第76回カンヌ国際映画祭で脚本賞と独立部門のクィア・パルム賞を受賞するなど、国内外で高い評価を得ている本作は、よくある子ども同士のケンカを巡り、母親、教師、そして子どもたちの意見が食い違い、次第にメディアを巻き込む大事に発展していく様を描いたヒューマンドラマだ。
MOVIE WALKER PRESSでは、かねてより是枝監督と坂元のファンである作家の凪良ゆうにインタビューを敢行。インタビュー前編では『怪物』を観た感想や是枝監督と坂元の共作について語ってくれたが、後編では、自身の作品群との共通点や、凪良が『怪物』で感じたメッセージや解釈などをお届けする。
※本記事は、ストーリーの核心に触れる記述を含みます。未見の方はご注意ください。
■「“怪物的”な多面性を書く意志が、坂元さんにあったのでしょうか」
『ドライブ・マイ・カー』(21)に続き、日本映画では2年ぶりとなった脚本賞を受賞した本作。是枝監督は「今回は自分の作品だからというよりも、物語がおもしろい、自分には書けない本でしたし、ストーリーテリングというものがとても無駄がなくて、とても面白かった」とインタビューに応えており、坂元の圧倒的な筆力が世界的にも評価されたことに喜びを噛み締めていた。坂元の丁寧に積み重ねられた描写から立ち上がってくる、生きづらさや怒りを抱えた不安定な登場人物たち。そのキャラクター描写の振り幅の広さは、「筆力がないとまとめきることができない」と凪良は語る。
「たとえば、田中裕子さんが演じる校長先生。スーパーで騒がしい子どもに足を引っ掛けたり、自分の保身のために動いたりするのに、同時に、子どもたちのために幸せを語ったりもする。確かに人間という生き物は多面的で、一人の人間が善悪どちらも持ち合わせていると、現実では理解できます。ですが、物語のなかで“複雑さ”を描くことは難しいんです。小説だったら、担当編集者さんに『人物像がブレています』って赤字を入れられかねない(笑)物語をうまく料理する自信がないと書ききれないと思いますし、タイトルにもつながってくる“怪物的”な多面性を書く意志が、坂元さんにあったのでしょうか」と、坂元の脚本力を称えた。
第20回本屋大賞を受賞した、凪良の小説「汝、星のごとく」。男女の恋愛物語というベーシックな設定ながら、緻密に重ねられた描写で世界に没入させてくれる本作でも、その筆力に圧倒される場面が多々ある。本作の執筆中の凪良に、迷えるときの「ひとつの方向性」を示してくれたのは、坂元が脚本を手掛けた映画『花束みたいな恋をした』(21)だったという。
「『汝、星のごとく』はあらすじだけ取り出してしまえば、男女が出会って、別れて、時間が経っていくという、なんの変哲もない恋愛物語です。どうやったら読者の皆さんに楽しく読んでいただけるか模索していた時、私はどんでん返しやミステリー的な仕掛けを入れるなど、奇をてらおうとしてしまっていました。ですが、当時たまたま『花束みたいな恋をした』を観て、真正面から『恋愛』を捉えながらも、こんなにも分厚い物語が描けるんだと衝撃を受けました。“仕掛け”を入れなくても、一つ一つのセリフやシーンを丁寧に積み上げていくことで、物語はこんなにもおもしろくなる」と、当時を振り返る。
■「複数視点で物語を書くことは、ミステリーを書いているのと近い感覚」
そうして生まれた『汝、星のごとく』や凪良の過去作と『怪物』は、たくさんの共通点が垣間見える。その一つが、複数視点で物語が描かれていること。視点がスイッチする物語を書くおもしろさを、凪良は「人の心こそがミステリーだから」と説明する。
「人間は、誰しも自分の見たいようにしか世界を見られない生き物なので、同じものを見ても自分と相手の捉え方がまったく違っていることはよくありますよね。そのわけのわからなさ、理解できなさという意味で、私は人の心が一番ミステリアスな存在だと感じています。なので、複数視点で物語を書くことは、私からするとミステリーを書いているのと感覚的に近いんです。書き進めながら、人の心に潜む謎を解いていく喜び、楽しさのようなものを感じます」。
自分自身が世界を恣意的に見ていると気づかされた時、ある種ホラーのような恐怖を感じるが、書き手としては「読み手の思惑を裏切る喜びは、作り手にある気がします。それは騙したいわけではなく、もっともっと、奥深いところに読者を引き込んでいきたい、という欲望なのかもしれません」と語る。そうした欲望は、『怪物』の作り手たちにも重ねられそうだ。
■「事実と真実が違うことは世の中にありふれている」
もう一つの共通点が、ある事件に対して渦中の人物の真実が知られることなくバッシングが起こってしまうという状況。凪良は「流浪の月」で、加害者と被害者が再会し、特別な絆を結んでいく様を書き、本作ではその渦中に立たされる保利先生(永山瑛太)を思う。
「最初は、とても許せない先生だと思わされます。ですが、視点が変わると彼の表情も違って見えてきました。無気力で、死んだ魚のような目にも、その表情になってしまうだけの理由がある。(永山本人は)あえて演じ分けていないというお話を伺って、世界はこんなにも個人のフィルターがかけられてしまっているんだと、自分自身の世界の見方に心が痛みました。かといって、彼が完璧な善人であり、すべての行動が認められるということでもない。作中で描かれたような何気ないひと言が、誰かを傷つけてしまう経験は誰しもあり、場合によっては大きなバッシングにつながっていきます。『自分はなにが悪かったのか』を丁寧に振り返っても拾いきれないけれど、加害してしまう可能性があることを認識しておくことは大切。事実と真実が違うことは世の中にありふれていることなのだとも改めて思いました」。
世の中は善人と悪人に二分されない、誰しもが加害者になりうる可能性があり、そうした「無自覚の悪意」というテーマは凪良の作品群からも受け取れる。「私は、登場人物の誰かに肩入れをしない、それぞれの立場でフェアに書くということを、とても意識しています。『汝、星のごとく』には、誰から見ても正しい人も悪人も出てきません。世間一般のものさしではなくて、自分の正しさを守って生きているんですよね。
たとえ、社会の正しさのレールから外れていても、自分をまっとうする。これだけ価値観が多様な時代に、なにか一つの基準に押し込めることは難しいので、結局自分なりの真意を持って、各々の意見を受け止めて、すり合わせて生きていくしかないと個人的にも思うからです。ですが、時として意図せずとも人を傷つけてしまうことがある。そうなった時に覚悟を持って挑むのか、引き下がるのか、どちらも正解で間違いかもしれない。結局、選ぶのは自分ですよね。この映画のなかでも、“それぞれの人生でしか生きられない”ということを痛烈に描いていたと思います」。
■「私たちはあの子たちに追いつかないと駄目ですね」
そうした意味で、子どもたちの選択を描いた「光に向かって走り出すシーン」は様々な解釈を生むのではないかと凪良は話す。「あまりにも美しい映像で、これまで歩いてきた世界と彼らの世界がもう“別物”になったんだなと思ったんです。その時『流浪の月』で、変わらない世界を見捨てて自由に生きる2人を書いたことを強烈に思い出しました。絶望感というか、私たちはあの子たちに置いてけぼりにされちゃったんだな、と思って」と持論を述べる。
この解釈については、インタビューに同席していた編集部員を交えて様々な議論に及んだ。そこから生まれたのは、「どんな状況でも、自分が思うままに生きていくことへの祝福」という視点だ。これだけ生きづらい世の中でも、世界は変われるのか。そのために大切な“自分の正しさを守っていく”ことは、子どもにも必要なはずだ。凪良は、「私たちはあの子たちに追いつかないと駄目ですね」と、柔らかな表情を浮かべていた。
それぞれの人生でしか生きられないけれど、人は人と関わることを避けられない。凪良の作品群に共通する「人と人はそもそもわかり合えない、だけどわかり合える奇跡のような瞬間がある」というテーマと本作の根底に流れるメッセージが重なる。「わかり合えたとしても、次の瞬間にすれ違いが訪れる。儚いけれど、関係をつむぐことを目指していくと、映画にもあったような希望が訪れる。一方で、コミュニケーションが取れていない親子の間には“怪物”がいましたよね。やっぱり感覚のアップデートというのはとても大切で、意見をふさぎこむディスコミュニケーションは怪物を生む背景になりうるのかもしれないと考えさせられました」。
取材・文/羽佐田瑶子
作家・凪良ゆうが『怪物』に見出した、“子どもたちの選択"への解釈。「私たちはあの子たちに追いつかないと」

関連記事
おすすめ情報
MOVIE WALKER PRESSの他の記事もみるあわせて読む
-

the GazettEベーシストREITAさん 最後の投稿にファン涙 15日に死去、当日までX更新
スポニチアネックス4/16(火)17:42
-

REITAさん死去 相次ぐバンドマンの訃報 最近では櫻井敦司さん、HEATHさん、チバユウスケさんら
スポニチアネックス4/16(火)17:55
-

前澤友作氏、メタ社の声明に怒り心頭「おいおい。まずは謝罪の一言は?」「日本なめんなよマジで」
スポニチアネックス4/16(火)21:39
-

「第2子ご懐妊中とはいえ…」橋本マナミ、最新姿にファン衝撃「だれこれ?」「ここまで変わる?」「別の方みたい」
中日スポーツ4/16(火)15:23
-

トヨタ自動車・豊田章男会長 マクドナルドおまけに大喜びの姿が大反響 「可愛いですね」「親近感わく」
スポニチアネックス4/16(火)15:52
-

フジ入社3年目24歳女子アナ“難病”告白しスタジオ騒然「カラオケ誘われても…」と笑顔で宣言
日刊スポーツ4/16(火)16:42
-

小泉孝太郎 まさか超大物が俳優師匠「俺が死ぬまで誰にも言うな」夜通し教え受けた関係告白 現場で「孝太郎をよろしく」と頭下げ
デイリースポーツ4/16(火)18:44
-

新熊本県知事 生まれつきの障がいに言及した動画が大反響 泣かせた母に謝罪 「泣いた」の声
スポニチアネックス4/16(火)21:01
-

「Destiny」次回予告に一瞬映った意外な人気女優 ネットざわつく「いたよね?」「何の役?」「奏のママなの?」
デイリースポーツ4/16(火)22:26
-

菊川怜が初告白「2リットル」大量出血の過去「とてもとても怖い」症状名も明かす
スポーツ報知4/16(火)20:14
-

「親いなくなって」武井壮の投稿に反響 松井珠理奈も生い立ち明かし「幸せそうな家族見ると…」
日刊スポーツ4/16(火)14:19
-

板野友美の妹&夫・高橋投手の妹 コネ活動「コネコネCLUB」ネタ逆手 美女2人でヤクルト応援「可愛い」「似合ってる」
デイリースポーツ4/16(火)23:52
-

人気ロックバンドのベーシストが死去…死去当日の投稿が「意味深すぎて」「悲しすぎる」とファン涙
女性自身4/16(火)17:31
-

野口健氏 水原一平容疑者への〝万死に値する〟発言を釈明「『比喩』としての言葉だと私なりに解釈し使いました」
東スポWEB4/16(火)20:42
-

中央大法学部を卒業した松田聖子(62)、「兄との和解」も果たしたワケ
文春オンライン4/16(火)17:00
-

内田也哉子さん 本木雅弘との結婚秘話 亡き母樹木希林さんに反対されると思ったら…「拍子抜けした」
スポニチアネックス4/16(火)15:40
-

片渕茜アナ「鑑定団」卒業 自ら“お宝”持参、まさかの結果に「お宝の世界は奥深い」
スポニチアネックス4/16(火)22:07
-

石原さとみ、開口一番で涙ぐむ「早い!」 渾身の主演映画完成で願う「誰も不祥事起こさないで」
ORICON NEWS4/16(火)19:25
エンタメ アクセスランキング
-
1

the GazettEベーシストREITAさん 最後の投稿にファン涙 15日に死去、当日までX更新
スポニチアネックス4/16(火)17:42
-
2

REITAさん死去 相次ぐバンドマンの訃報 最近では櫻井敦司さん、HEATHさん、チバユウスケさんら
スポニチアネックス4/16(火)17:55
-
3

前澤友作氏、メタ社の声明に怒り心頭「おいおい。まずは謝罪の一言は?」「日本なめんなよマジで」
スポニチアネックス4/16(火)21:39
-
4

「第2子ご懐妊中とはいえ…」橋本マナミ、最新姿にファン衝撃「だれこれ?」「ここまで変わる?」「別の方みたい」
中日スポーツ4/16(火)15:23
-
5

トヨタ自動車・豊田章男会長 マクドナルドおまけに大喜びの姿が大反響 「可愛いですね」「親近感わく」
スポニチアネックス4/16(火)15:52
-
6

フジ入社3年目24歳女子アナ“難病”告白しスタジオ騒然「カラオケ誘われても…」と笑顔で宣言
日刊スポーツ4/16(火)16:42
-
7

小泉孝太郎 まさか超大物が俳優師匠「俺が死ぬまで誰にも言うな」夜通し教え受けた関係告白 現場で「孝太郎をよろしく」と頭下げ
デイリースポーツ4/16(火)18:44
-
8

新熊本県知事 生まれつきの障がいに言及した動画が大反響 泣かせた母に謝罪 「泣いた」の声
スポニチアネックス4/16(火)21:01
-
9

「Destiny」次回予告に一瞬映った意外な人気女優 ネットざわつく「いたよね?」「何の役?」「奏のママなの?」
デイリースポーツ4/16(火)22:26
-
10

菊川怜が初告白「2リットル」大量出血の過去「とてもとても怖い」症状名も明かす
スポーツ報知4/16(火)20:14
エンタメ 新着ニュース
-

4月23日(火)「上田と女がDEEPに吠える夜」下着のお悩み
日テレTOPICS4/17(水)0:24
-

吉岡里帆 黒チューブ美肌でお口ぽかーん 美しすぎる白い肩「お肌が綺麗すぎ」「ぽかーん可愛い」「キュンキュン」
デイリースポーツ4/17(水)0:14
-

作家の宗田理さん死去、95歳…「ぼくらの七日間戦争」シリーズ51作
読売新聞4/17(水)0:10
-

Charisma.com、覆面ラップグループ・MIDICRONICAらを迎えた2024年第二弾シングル「変身」をリリース
SPICE4/17(水)0:00
-

日向坂46正源司陽子、春のピンクコーデで最強スマイル 17歳の新センター『マガジン』初ソロ表紙
ORICON NEWS4/17(水)0:00
-

『グリム童話』ホラー×ファンタジー視点で描く 新連載『グリム組曲』開始
ORICON NEWS4/17(水)0:00
-

元乃木坂46・相楽伊織1st写真集 「解放」テーマに“史上最大露出”にも挑戦
クランクイン!4/17(水)0:00
-

TOKIO・松岡昌宏と丸亀製麺が共同開発のうどん、期間限定で復活 新CM21日からオンエア
スポーツ報知4/17(水)0:00
-

【4月17日生まれの著名人】アルフィー高見沢俊彦、Kiroro玉城千春、ワンオクTakaら
日刊スポーツ4/17(水)0:00
-

内山田洋とクールファイブが77曲をストリーミング配信 前川清「当時の声をぜひ味わって!」
日刊スポーツ4/17(水)0:00
総合 アクセスランキング
-
1

the GazettEベーシストREITAさん 最後の投稿にファン涙 15日に死去、当日までX更新
スポニチアネックス4/16(火)17:42
-
2

REITAさん死去 相次ぐバンドマンの訃報 最近では櫻井敦司さん、HEATHさん、チバユウスケさんら
スポニチアネックス4/16(火)17:55
-
3

【速報】栃木・那須町の河川敷で2人の焼損遺体発見 1人は住居不詳の55歳男性と判明
TBS NEWS DIG4/16(火)22:06
-
4

【続報】タワーマンションで転落事故か 3歳女児が死亡 広島・中区
広島ホームテレビ4/16(火)21:19
-
5

東海道新幹線「車内に蛇いる」、6号車で体長40センチの蛇を捕獲…一部列車に遅れ
読売新聞4/16(火)20:37
-
6

前澤友作氏、メタ社の声明に怒り心頭「おいおい。まずは謝罪の一言は?」「日本なめんなよマジで」
スポニチアネックス4/16(火)21:39
-
7

「第2子ご懐妊中とはいえ…」橋本マナミ、最新姿にファン衝撃「だれこれ?」「ここまで変わる?」「別の方みたい」
中日スポーツ4/16(火)15:23
-
8

トヨタ自動車・豊田章男会長 マクドナルドおまけに大喜びの姿が大反響 「可愛いですね」「親近感わく」
スポニチアネックス4/16(火)15:52
-
9

フジ入社3年目24歳女子アナ“難病”告白しスタジオ騒然「カラオケ誘われても…」と笑顔で宣言
日刊スポーツ4/16(火)16:42
-
10

岸田政権の浮沈左右する衆院3補選告示、島根1区敗北なら退陣論も
産経新聞4/16(火)20:03
いまトピランキング

東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

カープダイアリー第8586話「ユニコーン夢物語とリアルな世界の境界線…大谷翔平に口裏合わせまで要請した水原一平容疑者、権力一極集中による“失踪”はカープ球団でも」(2024年4月15日)
ひろスポ!4/17(水)0:10
-

U-23日本代表、U23アジアカップは白星スタート!退場者を出すも松木玖生のゴールで中国に勝利
Qoly4/17(水)0:05
-

レヴァークーゼンで「細貝萌がともにプレーしたスゴい10選手」
Qoly4/17(水)0:00
-

U-23日本代表、U23アジアカップに招集できなかった「海外日本人」の逸材たち12名
Qoly4/16(火)21:00
-

編み上げが超レトロ!カリアリに「伝説のスクデット獲得」54周年記念の限定ユニフォームが登場
Qoly4/16(火)20:00
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) MOVIE WALKER Co., Ltd.