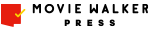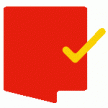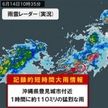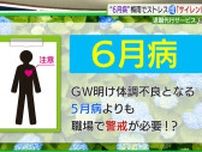北条司の大人気コミックを日本で初めて実写化した映画『シティーハンター』がNetflixにて世界独占配信中。主人公の冴羽獠を鈴木亮平、ヒロインの槇村香を森田望智、獠の相棒である槇村秀幸を安藤政信、獠とは腐れ縁の刑事・野上冴子を木村文乃が演じる本作は、配信直後から「日本の週間TOP10(映画)」で1位を獲得。「週間グローバルTOP10(非英語映画)」で初登場1位を記録し、フランス、韓国、香港、ブラジルなどを含む世界50の国と地域でも週間TOP10入りを果たしている。
東京の大都市、新宿の裏社会で起こる様々なトラブル処理を請け負う、超一流のスイーパー、冴羽獠の活躍を描く本作。原作では1980年代中盤が舞台となっていたが、映画版では舞台を現代の新宿に設定し、原作コミックスの序盤のエピソードをベースに現代的な設定、要素を取り入れ物語を再構築。人間を凶暴化させる麻薬“エンジェルダスト”をめぐる争いによって相棒の槇村を失った獠が、犯罪組織ユニオン・テオーペとの戦いのなかで、槇村の妹、香を新たなパートナーにするまでの物語が描かれる。
作品の舞台となる新宿は最もロケ撮影が難しい場所として知られているが、本作はこれまでにない大規模な新宿ロケが行われた。本作のプロデューサーを務めた株式会社オフィス・シロウズの押田興将は、映画やテレビドラマの撮影が可能なロケ地の情報を提供し、案内・調整を行う東京都の窓口となる組織「東京ロケーションボックス」の協力を得ながら、難しいはずの新宿ロケを敢行し、作品の世界観を見事に表現した。
■「『シティーハンター』を新宿で撮影せずにどこで撮影する」
公開中の映画『コットンテール』や李相日監督作『許されざる者』(13)など、数々の話題作を手掛けてきた押田。「新宿の街中では大規模な撮影許可が下りる可能性は極めて低い。歌舞伎町ではまず許可が下りない」が当たり前となっているなかで、どのようにロケを実現させたのか。
「例えば、撮影ができないと言われていた成田空港や、環境保護地区での撮影も時間はかかったけれど突破してきたので、今回の突破先は歌舞伎町だなって思っていました。撮影がダメな場所だから最初から諦める、大したシーンじゃないから(ほかの撮影方法で)逃げられるということはしたくない。映画をやっている人間の矜持として、『シティーハンター』を新宿で撮影せずにどこで撮影する、という気持ちがあったので、やるつもりではいました。ただ、気持ちだけではどうしてもうまくことが進まない。そこで、東京ロケーションボックスの遠藤肇さんに協力を仰ぎ、2人でいろいろなものを突破してきました」と振り返る。「シネシティ広場、ゴジラロード、歌舞伎町一番街、できればさくら通り。ここは絶対突破しようと思っていました」と気合い十分だったという。「この10年で歌舞伎町は相当変わりました。ほんの数年前にはゴジラはいなかったし、コマ(劇場)を再現しなきゃいけないとなったら、ものすごく大変だったはず。現代が舞台になったことは、逆にありがたかったですね」。
歌舞伎町の地元商店街、新宿行政関係者、警視庁新宿署など各関係者の全面協力を得て新宿ロケを実現。勝因は「進め方が非常に的確だったから」と説明する。
「どこから話をするのか、誰に話を通すのか。その道筋を間違えると実現への道は遠くなる。僕たちはどこに話を通すべきなのか、それを探るのに時間がかかるんです。僕が交渉の最前線に立ったのは、撮影の2か月ほど前のこと。時間が足りないなかで、“このやり方ならどうでしょう?”など相手の反応を見ながら、“仮”の形で提案をしていきます。結果、ありがたいことに全面協力のような形になりましたが、すごく得したなと思ったのは『シティーハンター』という作品だったこと。『シティーハンター』だから新宿で撮るしかない、という前提で向き合ってくださった方たちばかりでした。作品の力はとにかく大きい。(許可書に)ハンコを押す立場の方が原作世代、僕たちの許可書を上司に渡す、窓口の方はアニメ世代。非常に好意的に進めていただけたことも大きかったと思います」と充実感を漂わせる。
「警察の方たちも、単に“撮影させない”と言っているのではない。住民の方からの苦情が出なければいい。夜中の撮影で、住民の方に迷惑をかけることになったら、苦情の行き先は警察。夜中に苦情の電話は受けたくないですよね。だから逆に“地元の人がいいなら”という感じで許可が下りることが多かったです。加えて、内閣府の海外誘致の流れもあって、撮影の後押しをする空気もあったりして。ここで苦情が出ずにロケができれば、次につながる。ロケをやらせてもらえる場所もやれる内容も増えていく、と思いながら交渉していました」。
■「“諦めずにやってよかった”と思えたシーンの一つです」
許可をとってシネシティ広場、TOHOシネマズ新宿の前を走るロケを実現したことは「本当によかったです」と微笑む。「過去にあの場所の撮影で失敗してしまった事例がある。そういう経緯があるなかで、ロケをやりづらくなっていた場所なだけに、いい事例を作れたのは本当にうれしかったです。今後、できるようになる可能性を作れたかなと思っています」。このシーンでの工夫はエキストラの配置だった。
「歌舞伎町の目立つ場所での撮影。東京は撮影をひと目見ようという人集りは地方に比べればできにくいもの。とはいえ、やはりテストの時には撮影に興味を持った方が結構な数、集まってしまって。どうしたものかと思ったのですが、テストで撮影場所を走っていたのはスタッフだったので、映画の撮影とは思わなかったようで、見物をする人の数がいい感じで減っていってくれて。鈴木くんたちが実際に走る時には人はほとんどいなくなっていたし、なにより、エキストラをたくさん準備したので、ぶつかるのもすり抜けるのも全部エキストラの人。最初はエキストラの数が多いことに難色を示されたけれど、結果、エキストラがいたほうが安心。獠たちの追いかけっこの動線を埋めるくらいのエキストラを準備して、その周りの通行人を止めずにスムーズな撮影ができました。出来上がった映像を観た時に“諦めずにやってよかった”と思えたシーンの一つです」。
■「鈴木くんから出てくるアイデアは“ああ、本当に考えているんだな”と納得するものばかり」
美女に目がなく、「もっこり」と叫ぶような男だが、スイーパーとしての腕前は超一流。ハードボイルドとコミカルのブレンドが絶妙な冴羽獠を演じた鈴木の本作への思い入れは特別だ。「僕は鈴木くんを本当にリスペクトしています。佐藤(祐市)監督とも話し、鈴木くんがやりたいことをどう表現するかというのを大事にしました。作品への向き合い方はすばらしかったし、彼が思い描く世界観を形にするために、佐藤監督がどう演出していくか。そういうやり方にシフトしたのもすごくよかったと思います。『シティーハンター』ってコメディとシリアスの切り替えがすごく難しい。漫画ならデフォルメしたり、画のルック自体を変えられるけれど、実写では簡単にいかない。でも、鈴木くんから出てくるアイデアは“ああ、本当に考えているんだな”と納得するものばかりでした」。
作品への向き合い方として、一番印象に残っているのは鈴木が発するある言葉だったという。「今回鈴木くんは脚本にも参加しています。毎回コミックス全巻をゴロゴロ(カートに乗せて)持ってきて脚本打ちをするのですが、それぞれが意見を言う時に鈴木くんは必ず“僕らは”って言うんです。ファン代表として参加してるんですよね。それがちょっとおもしろくて(笑)」と思いだし笑いの押田は、鈴木の作品への思い入れの強さは並々ならぬものだったが、プレッシャーも大きかったと推測。
「作品がよかった時はいいけれど、悪かった時に一番ダメージを受けるのは彼。相当プレッシャーもあったと思います。しかもずっとやりたいと言い続けてきた役だから、“鈴木亮平がやりたかった冴羽獠はこれだったのか”って言われる可能性もあるわけで。そういう状況でファン代表として彼のような振る舞いで作品に向き合えるのは本当にすばらしいこと。よく頑張ったと思います。現代を舞台にすることで要素や設定を調整した脚本に関しては、いろいろな意見が出るかもしれません。でも、冴羽獠というキャラクターを実写でどう造形するか、ということに関してはこれしかないと思ってもらえるとはず。ファンの方も異論はないんじゃないかな」。
■「ロケ地にも天気にも、そして役者、スタッフにといろいろと恵まれた撮影」
作品愛が深すぎる鈴木が大好きなシーンとして挙げたのは、物語のラストで朝焼けの西新宿から歌舞伎町に向けて靖国通りをミニクーパーが走る場面だ。「あれは監督のアイデアで生まれたシーンです。車内からの実景なので、鈴木くんは映ってないけれど(笑)。監督の狙いどおりの朝日が撮影できました。朝日がビルに反射して見えるのをやりたいというので、とにかく何回もロケハンに行って。時間と角度によってガラスに映らないし、空撮の空の光も合わなきゃいけない。何度も夜明けのテストに行きました。撮影そのものは大掛かりなことないのだけれど、準備は本当に大変でした。まあ、出来上がったものを観たらやってよかったという気持ちにしかならないんですけれどね(笑)。僕もあのシーンは大好きです。あの情感たっぷりの場面から香とのドタバタという流れも絶妙だし、『シティーハンター』らしくていいですよね」としみじみ。
ガラスに映る朝日の撮影にもこだわり抜いた本作のロケは天気にも恵まれた。「忙しい役者さんばかりをキャスティングしたので、スケジューリングは大変でした。1月は2日雨が降ったら崩壊、みたいなスケジュール。撮影許可もピンポイントで取っているので、雨が降った時の段取り調整は本当に大変で。制作部の頑張りは言うまでもないのですが、40何年か振りに降水量の少ない1月というのも味方して、今回のMVPは天気だと言ってもいいくらい、ここで降ったら終わりというところでも降らなくて。ロケ地にも天気にも、そして役者、スタッフにといろいろと恵まれた撮影でした」。
取材・文/タナカシノブ
「『シティーハンター』だから新宿で撮るしかない」プロデューサーが明かす、作品愛あふれる鈴木亮平もこだわった新宿ロケ撮影の裏側

関連記事
おすすめ情報
MOVIE WALKER PRESSの他の記事もみるあわせて読む
-

『恋を知らない僕たちは』その視線の先には誰が…?齊藤なぎさ&莉子&志田彩良の場面写真が公開
ORICON NEWS6/14(金)12:00
-

シリーズ最新作公開記念『キングダム』第1作から第3作を「金ロー」で3週連続放送!山崎賢人のコメントも
MOVIE WALKER PRESS6/14(金)12:00
-

映画『キングダム』「金ロー」で3週連続放送に山崎賢人「うれしく思います」 『運命の炎』は本編ノーカット&地上波初
ORICON NEWS6/14(金)12:00
-

映画「キングダム」シリーズ 3週連続 金曜ロードショーで放送決定!山﨑賢人「どの作品も全てがものすごいクオリティになっています」
日テレTOPICS6/14(金)12:00
-

「キングダム 大将軍の帰還」公開記念 山﨑賢人主演映画「キングダム」シリーズを「金ロー」で3週連続放送
iza!6/14(金)12:00
-

AKB48×テレ東『星屑テレパス』60秒トレーラー&場面写真が公開 “おでこぱしー”やロケット打ち上げシーンも
ORICON NEWS6/14(金)11:00
-

山崎賢人、『キングダム 大将軍の帰還』大沢たかお演じる王騎将軍は「すさまじい!信の目線になって見て」と力説
MOVIE WALKER PRESS6/14(金)9:30
-

新木優子、美デコルテ際立つドレス姿で映画『キングダム大将軍の帰還』レッドカーペットに登場
DailyNewsOnline6/14(金)9:30
-

永野芽郁と佐藤健が「半分、青い。」以来の共演…他作品でも共演者が同じになるのはナゼ?識者に聞いた
日刊ゲンダイDIGITAL6/14(金)9:26
-
-

映画『ゴールデンカムイ』で好きな俳優ランキング! 2位「山田杏奈」、1位は?
All About NEWS6/14(金)8:05
-

美術講師も絶賛!『ブルーピリオド』キャストの絵画練習風景のメイキング写真
MOVIE WALKER PRESS6/14(金)8:00
-

眞栄田郷敦・高橋文哉・板垣李光人・桜田ひよりが本気で挑んだ、絵画練習の姿を捉えたメイキング写真公開
ORICON NEWS6/14(金)8:00
-

増田貴久“那月”が“殺意なき惨殺”の謎を追う 『ギフテッド Season2』第2話あらすじ公開
ORICON NEWS6/14(金)7:30
-

SUPER★DRAGON・田中洸希&多和田任益W主演! おうちごはん×BLドラマ『シュガードッグライフ』8月スタート
クランクイン!6/14(金)7:00
-

話題の癒し系BLコミック『シュガードッグライフ』、田中洸希(SUPER★DRAGON)×多和田任益W主演で今夏実写ドラマ化
ORICON NEWS6/14(金)7:00
-

『笑うマトリョーシカ』回想シーンの若手キャスト&相関図が公開 青木紬は櫻井翔の演技を研究
ORICON NEWS6/14(金)5:00
-

青木柚、『笑うマトリョーシカ』で“清家”櫻井翔の学生時代演じる! 西山潤、濱尾ノリタカも出演
クランクイン!6/14(金)5:00
-

映画『キングダム』最終章 キャストが「レべチ」な魅力を語り合う
クランクイン!6/13(木)21:30
-
エンタメ アクセスランキング
-
1

難病公表の米倉涼子「治療後に1ヶ月寝たきり」状態になっていた 一時は「引退も覚悟」
ORICON NEWS6/14(金)8:59
-
2

“金曜夜の顔”TBS上村彩子アナが結婚 お相手は「職場で出会った、仕事に対して真摯でとても誠実な人」
スポニチアネックス6/14(金)10:08
-
3

蓮舫にうんざり!で大炎上 眞鍋かをりが週刊文春だけに語った「ココだけの話」
文春オンライン6/14(金)6:00
-
4

いとうあさこ“この子はいい子”共演したアイドルの卵をかばうも…正体判明「余罪が13件」 周囲衝撃
スポニチアネックス6/14(金)8:07
-
5

フジ主演ドラマは絶好調ならずも… 山下智久〝争奪戦〟がテレビ界で勃発の「なぜ?」
東スポWEB6/14(金)5:00
-
6

“狂犬”と化した粗品に聞く耳なし? 宮迫博之との舌戦で悪評ふんぷん…干される可能性も
日刊ゲンダイDIGITAL6/14(金)9:26
-
7

「ジム友は超大物女性歌手」松本潤新社長の強すぎる“非ジャニ”人脈…起業でみえる確かな勝算
女性自身6/14(金)6:00
-
8

上沼恵美子 同居の義両親に対する悩みにキッパリ「姑やる価値なし。話にならんわ。別居された方がいい」
スポニチアネックス6/14(金)6:30
-
9

「虎に翼」次週予告 ついに寅子と再会も よねは拒絶?ネット心配「わだかまりが…早く和解してほしい」
スポニチアネックス6/14(金)8:15
-
10

BTS・JIN、除隊後初のSNS更新にファン感極まる「いろんな感情大渋滞」「現実なんだ」
スポーツ報知6/14(金)7:26
エンタメ 新着ニュース
-

「奇跡の52歳」取締役フリーアナ、顔&うなじドアップに騒然「前からも後ろからも綺麗」
日刊スポーツ6/14(金)12:14
-

宝塚急死に関わった団員を名指しの株主に「犯罪者みたいに言うのはどうか」疑問呈す株主も
日刊スポーツ6/14(金)12:13
-

窪塚洋介、妻&愛娘と“親子3ショット”「若くてお綺麗」「幸せな光景にうっとり」 家族で妻・PINKYの誕生日を祝う
ORICON NEWS6/14(金)12:12
-

『【推しの子】』越えも期待の続編夏アニメ およそ30年ぶりの新作も
マグミクス6/14(金)12:10
-

ナチス占領下のパリで生まれた女性歌手が死去、80歳 悪性リンパ腫で20年間の闘病 映画女優としても活躍
よろず~ニュース6/14(金)12:10
-

BTS・JIN、HYBEのパン・シヒョク氏が2ショ公開 「父と長男!」「BTSを守ってね」の声
スポーツ報知6/14(金)12:10
-

宝塚急死問題 「隠蔽体質」指摘 団員謝罪求める者、個人矢おもて反対…株主でも意見割れる
日刊スポーツ6/14(金)12:09
-

宝塚 劇団員急死で親会社は大荒れ株主総会 怒号も飛び交い株主同士もバトルの様相
デイリースポーツ6/14(金)12:08
-

Mrs. GREEN APPLE、TBS『CDTVライブ!ライブ!』の出演を見合わせ「またの機会の出演を楽しみに」
ORICON NEWS6/14(金)12:08
-

森香澄、“超ミニ”で太もも美脚全開「ミニスカ最強」「脚がとてもきれい」「ミニが眩しい」
ORICON NEWS6/14(金)12:07
総合 アクセスランキング
-
1

大逆転負けのバレー、二枚看板・石川真佑を交代させた理由「見ての通り…」 指揮官が明確回答【ネーションズリーグ】
THE ANSWER6/14(金)6:43
-
2

難病公表の米倉涼子「治療後に1ヶ月寝たきり」状態になっていた 一時は「引退も覚悟」
ORICON NEWS6/14(金)8:59
-
3

“金曜夜の顔”TBS上村彩子アナが結婚 お相手は「職場で出会った、仕事に対して真摯でとても誠実な人」
スポニチアネックス6/14(金)10:08
-
4

蓮舫にうんざり!で大炎上 眞鍋かをりが週刊文春だけに語った「ココだけの話」
文春オンライン6/14(金)6:00
-
5

麻生副総裁が岸田首相に激怒「事前相談なしで謝罪のみ。ナメてるのか」
デイリー新潮6/14(金)6:00
-
6

中国主席「ロシアに武器売却せず」、ウクライナ大統領との電話会談で
ロイター6/14(金)7:29
-
7

いとうあさこ“この子はいい子”共演したアイドルの卵をかばうも…正体判明「余罪が13件」 周囲衝撃
スポニチアネックス6/14(金)8:07
-
8

フジ主演ドラマは絶好調ならずも… 山下智久〝争奪戦〟がテレビ界で勃発の「なぜ?」
東スポWEB6/14(金)5:00
-
9
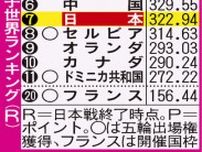
【バレー】女子代表カナダにフルセット負けも五輪へ依然有利 14日にカナダ−オランダ直接対決
日刊スポーツ6/14(金)5:00
-
10

【女子バレー】なぜ眞鍋監督は石川真佑を第2セット途中で外したのか?よもやの大逆転負けに「順調にいくとは初めから思っていない」【ネーションズリーグ】
THE DIGEST6/14(金)4:54
いまトピランキング

東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

鹿島アントラーズの知念慶、衝撃のボランチ転向はなぜ成功した?安田理大が明かす「彼はのほほんとしていて…」
Qoly6/14(金)12:00
-

EURO2024開幕戦、「超能力オランウータン」が結果を予言!開催国ドイツの勝利は確実か…
Qoly6/14(金)11:40
-

4歳息子「スカートが履きたい」 自分の好きに忠実な男の子の生き方について、母に聞いた
ほ・とせなNEWS6/14(金)11:30
-

「ダロット」ではなく「ダロ」!EURO2024に出場するプレミア選手の「本人による名前発音ビデオ」が話題
Qoly6/14(金)11:20
-

神楽坂に「囲炉裏焼肉 祇園」 神戸牛などのいろり焼きを古民家で
みんなの経済新聞ネットワーク6/14(金)11:00
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) MOVIE WALKER Co., Ltd.