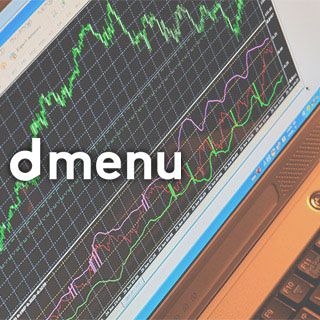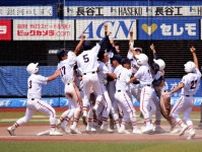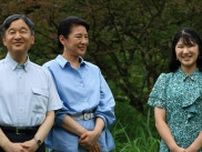「宜野湾組」に選出された意味
新天地に懸ける想い――。
昨年7月に東京ヤクルトスワローズから横浜DeNAベイスターズに移籍をした西浦直亨(なおみち)は球春到来の2月、キャンプ地の沖縄県宜野湾市で、日々汗を流している。プロ11年目。若手に交じって西浦は声を出し、溌剌とした動きを見せていた。
「じつは宜野湾の球場に来るのはプロになって初めてなんです。宿泊しているホテルからは海も見えるし、何かすごく新鮮な気持ちで一日一日を過ごしています。練習ではいい感じで動けていますし、やらなきゃなって」
浅黒く焼けた肌に引き締まった精悍な顔つき。西浦の表情からは充実している様子が窺われた。
この4月で33歳になるベテラン。実績のある同年代の選手たちは、一軍スタッフが指導する宜野湾(A班)ではなく、ある程度の自己調整が認められている奄美大島(B班)のキャンプに参加している。西浦は、首脳陣の目に止まりやすい宜野湾キャンプに選出された意味を十分に理解している。
「とにかくアピールすること。バッティングはもちろんですが、走塁、そして複数のポジションを守れるユーティリティー性を見せられるように毎日取り組んでいます」
張りのある声の中に、危機感が滲み出ていた。
電撃トレード
突然のトレードだった。シーズン中の移籍の期限が迫っていた昨年の7月26日、西浦と阪口皓亮のトレードが、ヤクルトとDeNAの両球団から発表された。DeNAとしては右打ちの内野手が補強ポイントであり、実績のある西浦に白羽の矢が立った。
トレードを西浦が悟ったのは、ファームの試合で遠征していた仙台でのことだった。
「試合を終えて宿舎に帰ったタイミングで、関係者から『明日、球団事務所に来て欲しい』と言われ、そのまま東京に戻ったんです。翌日、球団事務所に行くとベイスターズへのトレードを告げられました」
時期も時期であり、覚悟をしてその言葉を聞き入れた。
ベイスターズと聞いて…
「昨年だけじゃなく、その前の年から(トレードは)あるかもしれないと思っていたんです。たしかに少し驚いた部分はあったんですけど、ベイスターズと聞いて、知っている選手も多いですし、全然知らないところに行くよりもホッとしたのが正直なところでした」
同じセ・リーグでしのぎを削ってきた近隣都市の球団。DeNAには法政大学の1学年先輩である三嶋一輝や1学年後輩の石田健大らがいた。
ただ、やはり10年間プレーした愛着あるヤクルトから離れるのは寂しいものだった。
「本当、関係者の方々にはお世話になりましたし、ファンの方々からはいつも応援してもらい感謝しています。けど、寂しい思いがある一方で、すぐに次のことを考えている自分もいたんです。新しい場所で、新しい挑戦がしたいって」
焦りがあった
2013年のドラフト会議で2位指名されヤクルトに入団した西浦は、ショートを中心とした堅実な守備と、ここぞという場面でのパンチ力のある打撃で、入団5年目の2018年にレギュラーを獲得。以降、激しい競争により浮き沈みはあったが、2021年のリーグ優勝と日本一に貢献している。
しかし、一昨年の2022年は出場機会を失い、わずか6試合の出場でシーズンを終えると、昨年もトレードをされるまで一軍で力を発揮することはできなかった。この時期、西浦になにが起こっていたのだろうか。
「結果を出さなければいけないという思いばかりで、焦りがあったと思います。相手ではなく自分自身と戦ってしまって、どっしりとプレーできている感じではなかったですね……」
陥ったジレンマ
キャリアを重ねようとも立ちはだかる壁。危機感と焦燥感が、体の自由を奪っていく。西浦は、もがいていた。
「なにかを変えなければ同じ状況だと思ったし、変えるにしても果たしてそれが正解なのかもわからない。その繰り返しですよね」
アスリートならではのジレンマ。仮説を立てて試みるも、どのような結果になるかはわからない。“変えること”は勇気のいることだ。
とはいえ西浦は昨季、トレードとなる直前までファームで打率3割以上をマークしており、それがDeNA移籍へのひとつの要因になったと考えられる。バットのスイング軌道を変え、手応えを感じていた矢先のDeNA行きだった。
移籍と言っても多摩川を越えるぐらいだよ
移籍が発表された夜のこと、DeNA一軍内野守備走塁コーチの田中浩康から西浦に連絡があった。二人はかつてヤクルトでともに内野手としてプレーをした同じ釜の飯を食った仲だ。
田中コーチは、心中複雑とおぼしき西浦に次のように伝えたという。
「移籍と言っても多摩川を越えるぐらいだよ。ベイスターズは明るくて独特なノリがあるから、その波に乗っていけばいい」
ナオミチさーん!
のちに田中コーチに西浦の評価を尋ねると次のように答えた。
「若いとき一緒にやっていましたけど、非常に明るい性格だから、すぐチームに溶け込めると思っていました。ショートやサードを中心に内野手として経験のある選手ですし、小力(こぢから)があるというか、強いバッティングもできます。これまでいろいろな経験をしてきているので、ある意味シンプルに野球に打ち込めるように手助けしていけたらなって」
実際にDeNAの一員になると、瞬く間にチームに溶け込んでいった。若い選手たちから敬愛を込め「ナオミチさーん!」と、呼ばれている姿をよく見かける。西浦は30歳を超えて知った新たな環境について次のように語る。
全員が『野球を楽しもう』という意識がある
「先輩後輩関係なく誰からも事あるごとに声を掛けてもらって、すぐに馴染むことができました。チームが変われば戦い方も変わるので、そこもすごく勉強になっているし、刺激にもなっています。ベイスターズには前向きな雰囲気がありますよね。自然なのか、意図してのことなのかわからないけど、全員が『野球を楽しもう』って意識があって、プロとしていいなってすごく感じたんです」
元気でパワーあふれる新天地に身を置き、西浦の中にある思いが芽生えた。
「この数年『失敗したらどうしよう』といった思いが少なからずあったんですけど、ベイスターズに来てからは、今まで以上にトライしてみようって気持ちになれたんです。チーム全体に失敗を恐れずチャレンジしようっていう空気があって、僕自身あまりネガティブなことを考えないようになりました」
明るい表情で西浦はそう言った。昨季は途中加入の難しさもあり、DeNAではわずか13試合の出場だったが、今季こそ真価を発揮し、チームの勝利に貢献しなければならない。
自分のためというよりも…
「自分のためというよりも、ベイスターズがこの場を作ってくれたわけですし、期待していただいていることも伝わってくるので、とにかく結果を出してチームに恩返しをしたいという気持ちです」
DeNAファンにとって西浦と言えば、忘れられない思い出がある。2014年のヤクルトとの開幕戦(神宮)、ルーキーだった西浦は8番・ショートでスタメン出場し、初回に大学時代の先輩の三嶋一輝が投じた初球を叩き、3ラン本塁打を放っている。開幕戦における新人選手の初打席、初球本塁打は日本プロ野球史上初の出来事だった。
球史に残る“超”ビッグインパクト。初の開幕投手を任されながら西浦の3ランを含め2回で9失点を喫してしまった三嶋は、苦笑しながら当時を振り返る。
三嶋vs西浦
「いやまあ、あの時は調子が悪かったんですよ。周りの人はすごく印象に残っているって言うけど、僕はあんまり覚えてないんですよね。もう10年ぐらい前のことですし。西浦ともその話をしないし、それにあれ以来、あんまり打たれてないんじゃないですかね」
例によって負けず嫌いの顔をのぞかせる三嶋である。ただ実際に西浦も「あれ以来、あんまり三嶋さんから打った記憶ってないんですよねえ」と語っている。どこか楽しそうな表情で三嶋は続ける。
「こうやってまた同じチームでプレーできるのは嬉しいですよね。(石田)健大もそうだけど、縁があるって言うんですかね。大学時代は守備範囲が広くて何度も助けられたし、本当に巧い選手だなって。だからね、まだまだ力はあると思っているし、打てるようになっていけば、守備も良くなっていくはず。いい年齢ですけど、もうひと花もふた花も咲かせてもらいたいし、僕も負けないように頑張らないと」
西浦を一言でいうと、どんな人間?
では西浦を一言でいうと、どんな人間だろうか。
「天才肌……いや“不思議ちゃん”ですかね」
そう言うと三嶋は笑った。たしかに西浦にはスポーツ選手らしいキリッとした佇まいはありつつも、ふんわりとした柔和な空気をまとっているように見える。西浦にそのことを尋ねると、笑みを浮かべ、首をかしげながらぼやくのだ。
「ずっと言われているんで慣れているんですけど、なにをもって“不思議”なのか自分ではよくわからないんですよねえ」
そう言って静かに宙を睨む様子を見て、西浦が短期間でチームメイトから愛される存在になった理由がわかったような気がした。
辞めることになっても後悔がないように
さて、勝負の1年。残りのキャリアも若い選手のように長くはなく、一試合一試合、一打席一打席が重要になってくる。危機感の中、あらんかぎりの力を発揮し、チームに貢献するつもりだ。
「ユーティリティーとしてチームに求められる仕事を精一杯やりたい。あと、これまでの人生を振り返ると、“野球”が大半を占めているわけです。だから辞めることになっても後悔がないように、一日一日、野球に真剣に向き合っていきたいと思います」
競争が激しい内野陣で西浦は果たして存在感を示せるのか。今季に懸ける想いを胸に、ベテランならではの経験値の高さ、そして勝負強さをぜひ発揮してもらいたい。
文=石塚隆
photograph by Sankei Shimbun