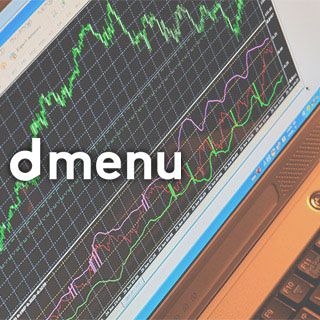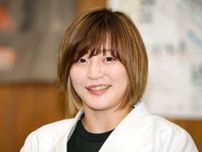40歳での鮮烈なFA宣言、巨人へ電撃移籍した落合博満……1993年12月のことだった。
あれから30年。巨人にとって落合博満がいた3年間とは何だったのか? 本連載でライター中溝康隆氏が明らかにしていく。
連載第14回(前編・後編)、41歳の落合は巨人2年目(1995年)を迎えた。しかし、まさかの最下位、そして“名球会拒否”と波乱のスタートとなる。【連載第14回の前編/後編も公開中】
◆◆◆
星野仙一に年賀状を出さなかった男
「怪我が幸いしたよね、じっくり治療に専念できたから。例年のように年明け1月、2月になってから野球を始めたのであれば、開幕に間に合っていないと思う。それに、これから先も長く野球を続けていこうと思ったら、ゆっくり休んでぼちぼち始めるのではなく、週に2〜3日でもいいから練習を続け、新しいシーズンに備えるのがいいのかもしれない」(激闘と挑戦/落合博満・鈴木洋史/小学館)
1995(平成7)年春、落合博満は巨人一軍がキャンプを打ち上げたあとの3月も宮崎にひとり居残り、独自調整を続けた。負傷した左脚の状態を確かめるようにウォーキングやランニングメニューを黙々とこなし、エア・テント内で納得のいくまでバットを振る。その打撃練習の様子を視察した、前年までの阪神のチーフ兼打撃コーチで解説者の石井晶氏は、背番号6の技術の高さに驚いたという。
「カーブ・マシンばかり170球くらい打つのを見とったんやが、一球一球きっちり考えながら打っとる。まったく軸がブレへんし、今年も要注意や。広沢とかマックと比べても一番イヤラしいし、開幕には当然、四番に入ってくるやろうな」(週刊ベースボール1995年3月13日号)
なにかと周囲に気を遣っているように見えた移籍初年度とは違い、巨人2年目は個人メニューでの練習を消化するため、ベテラン組ともほとんど顔を合わせないマイペースぶりだった。これまで多くの移籍選手が、「伝統の巨人軍」と同化しようと苦しんだが、この男には関係なかった。契約を交わしている以上は巨人のために戦うが、決して巨人に媚びることはない。中日時代、星野仙一監督に、チームで落合だけが年賀状を出さなかったという。それがオレ流の生き方だった。
巨人OB「落合に居場所はない」
そんな主砲の独自調整に長嶋茂雄監督は、左足首ねんざでスロー調整中の20歳の松井秀喜と比べて、「テントのおじさん(落合)のほうが元気ですよ」と笑ってみせたが、同時に総額33億円を費やした大型補強にも手応えを感じていた。
読売新聞社の渡邉恒雄社長の「カネに糸目はつけないから、大物選手を取れ」という大号令のもと、オフにシェーン・マックや広沢克己を獲得。指揮官は「去年は落合コケたら、みなコケてしまったからね」と、オレ流依存からの脱却を掲げた。キャンプ中、「戦略という意味では『どうやっても優勝できる』というだけのことはやった。あとは、実際にやるだけです」(週刊現代1995年2月25日号)なんて、長嶋監督は勝利宣言とも受け取れる絶対的な自信を口にするほどだった。
その一方で、年齢的に落合の故障からの完全復活には懐疑的な声も多く、巨人OBの青田昇は、「落合の痛めた内転筋は一発でダメになる部分。私も内転筋をやってダメになった」と自身の現役時代の経験を引き合いに出して、完治は困難と断言。同じく球団OBの元沢村賞投手・小林繁は、大型補強の理由を「今年は、落合が必ずしも『不動の4番』でない可能性を示唆している」と、自身の連載「小林繁の[野球は心理学]」の中で背番号6の追い込まれた立場を強調する。
「落合は6、7番に適したバッターではないのだ。脚力の面でもそうだし、落合に送りバントをさせるわけにもいかないだろうから。したがって、極めてシビアな見方をすれば、4番の座を外れた落合には、『もはや、居場所がない』と言っても過言ではないと思う。あえて言えば、『4億円の代打』しか。これは、落合の選手生命の終焉を意味すると言っていいだろう」(週刊宝石1995年3月2日号)
コーチも「落合が“無理”なら、はっきり言う」
新任の武上四郎打撃コーチも、就任早々「キャンプで落合を見て、もし『無理だ』と思えばはっきり監督にそう進言しますよ」と、まるで元三冠王に引導を渡すのが自分の仕事だと言わんばかりに週刊誌でアピールする。
「体力も、筋力も落ちているでしょうし、本人も自覚しているでしょう。(中略)今年は1年間4番を通すことは苦しいでしょう。去年は、長嶋監督も代えたい気持ちはあったが、それに代わる打者がいなかったということでしょう。しかし、今年は誰が4番を打ってもいいですから」(週刊現代1995年2月4日号)
数カ月前の10.8決戦でヒーローとなり、4番打者としてファンに優勝の立役者と絶賛されながら、それでもなおOBやコーチからは、まるでチームの世代交代の足枷のような言われ方をしてしまう。これがジャイアンツの外様選手の現実だ。ならば、オレはオレの好きなようにやらせてもらうさ――。50日間にも及ぶ、一軍本隊から離れての孤独な調整は、落合のそんな意思表示のようにも見えた。
落合「すぐ引退と書かれるからな」
宮崎での“ひとりキャンプ”を終え、ようやくオープン戦に出場したのが開幕を目前に控えた3月21日のダイエー戦。背番号6は「4番一塁」で東京ドームに登場すると、いきなり第1打席で工藤公康からセンター前ヒットを放ち、4打数2安打と結果を出してみせた。しかも、この試合で代名詞の胸の正面にバットのグリップを掲げる神主打法から、剣道の中段のような構えでバットを下げてスタンスを狭くとる新打法を試している。
「週刊ベースボール」1995年4月10日号では、落合自身が打撃改造の意図を「もともとバランスで打っていた選手が、ここ何年か崩されっぱなしだから」と説明。直後に元のフォームに戻すが、「数字を残さないと、すぐ引退と書かれるからな」なんて不敵に言い放つ41歳の四番打者に対して、長嶋監督は「久しぶりに出て来て2本ですか。あれがプロなんですね。こういう生き様を、みんなわかってくれるのかな?」と変わらぬ信頼を口にした。
まさかの最下位転落…そして「名球会拒否」事件
4月7日の開幕戦、東京ドームは約2週間前に起きた地下鉄サリン事件の余波で、爆発物処理班など約700名の警察官が配置される厳戒態勢下での試合開催となった。因縁の野村ヤクルトを本拠地に迎え、空前の33億円補強を敢行した巨人の開幕スタメン野手に生え抜きは、岡崎郁、川相昌弘、松井秀喜の3名のみ。注目の4番には、新戦力組のマックや広沢らではなく、通算2000安打にあと8本の落合が座った。
だが、優勝候補の大本命・長嶋巨人は開幕からつまずく。3連戦の初戦こそエース斎藤雅樹の開幕2年連続完封勝利で先勝するも、2戦目は完封ペースで飛ばしていた桑田真澄が、9回表の先頭打者・飯田哲也に頭部死球を与え危険球退場。急きょマウンドへ送られたリリーフ陣が5失点と踏ん張り切れず、野村克也監督は「ルールがヒーローや」と試合後に笑い、のちに落合も「ヤクルト独走のきっかけの試合」と振り返る痛恨の逆転負けとなった。早くもハウエルが左足カカトを打撲して、代わりに原辰徳が「七番三塁」でスタメン出場も機能せず。負の連鎖は続き、3戦目は最終回にマックの痛恨の送りバント失敗もあり、開幕カード負け越し。自慢の“5点打線”も看板倒れに終わり、スタートダッシュに失敗した巨人は、4月15日の阪神戦で4連敗を喫すると、1037日ぶりの最下位に転落してしまう。
その渦中にあの事件が起きるのだ。「落合博満、名球会入会拒否騒動」である。
<続く>
文=中溝康隆
photograph by KYODO






























![[U-23日本代表のマリ戦スタメン予想]勝てば決勝T進出。中2日も初戦からの入れ替えは2名のみと予測。平河悠が負傷の右ウイングは...【パリ五輪】](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/soccerdigestweb/s_soccerdigestweb-158184.jpg)