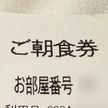いつも笑顔を絶やさない、あのピーター・アーツが泣いた――亡き友への思いを胸にリングに立ち続けた“20世紀最強の暴君”は、なぜ全盛期を過ぎても絶対王者に勝利することができたのか。アーツと30年来の交流があるフォトグラファーの長尾迪氏が、日本を愛し、日本のファンに愛された「ミスターK-1」の実像に迫った。(全2回の2回目/前編へ)
アーツが感情をあらわにした“ふたつの激闘”
「彼はとても近しい親友だった。試合だけでなく、テレビ番組やコマーシャルの仕事も沢山したよ。プライベートでも多くの時間を一緒に過ごした。わざわざ結婚式にも来てくれたんだ」
ピーター・アーツが振り返る“彼”とは、2000年8月24日に急性前骨髄球性白血病で他界したアンディ・フグのことだ。そのときのことはよく覚えている。フグの入院先だった病院で、緊急の記者会見が開かれた。会見場には見たこともないくらいの数の報道陣が来ていたが、アーツはメディアなど目に入らないかのように号泣し、ただただ悲嘆に暮れていた。
そんな関係性を聞いて、あらためて思い出した。普段はスマートで冷静な試合をするアーツが、感情をあらわにし、どうしても勝ちたいという気持ちを見せた試合があったことを。
ひとつは後で触れる2010年のセミー・シュルト戦。そしてもうひとつは、2000年12月のシリル・アビディとの戦いだ。アーツは2000年7月にアビディと初対決してKO負けを喫している。翌月にグランプリの開幕戦でアビディとのダイレクトリマッチが組まれたが、怪我によるTKOで連敗。フグが亡くなったのは、この敗戦の4日後だった。
本来であれば出場資格のないアーツだが、主催者推薦枠として急遽12月のトーナメントに出場することになった。1回戦の相手は因縁のアビディ。序盤にアーツがダウンを奪ったが、バッティングで眉の上をカット。2度目のバッティングを受け、傷口が広がり血が止まらない。
感情をむき出しにして戦うアーツだが、激しい流血と傷の深さからドクターチェックが入る。左目の上がざっくりと大きく切れている。通常なら試合を止められる状態だ。アーツはドクターに何やら強硬にアピールしているが、私の位置からでは聞こえない。おそらくは「試合を止めるな、やらせろ」と言っていたに違いない。
彼は是が非でもこのトーナメントで優勝したかった。若くして天国へ旅立った戦友への供養として、なんとしてもベルトを届けたかったのだ。
だからこそボロボロになりながらも、あれほど激しく、気持ちを前面に出して闘ったのだろう。思いが通じたのか、試合は続行され、アーツは判定で勝利した。
しかし、勝利の代償は大きく、準決勝への出場は不可能に。リングドクターの代表である中山健児医師がわざわざリングへ上がり、アーツの負傷の詳細を説明した。傷口の幅は5cm、深さは1cm。下手をすれば、骨が目視できるほどの重傷だったのではないか。
「タイミングにズレが…」撮影者が感じたアーツの衰え
2000年以降、アーツはK-1の第二世代ともいわれるアビディ、ステファン・レコ、アレクセイ・イグナショフなど、格下と見られていた選手にも敗北するようになる。
私は彼の初来日から、ほとんどすべての試合を撮影してきた。パンチ、キックを出す距離とタイミングは完璧に分かっていたつもりだ。しかしある時期から、「ここだ」と確信してシャッターを押しても微妙にズレが生じるようなった。こちらの予想よりもワンテンポ遅いのだ。酷な言い方をさせてもらうと、アーツの打撃には往年のスピードがなくなった。得意のハイキックも一撃必殺とはならなくなった。
無論、対戦相手に研究されたこともあっただろう。ただ、それ以上に深刻だったのは怪我が多くなったことだ。歴戦のダメージなのか、右足のすねが毎回のように割れ、激しく流血することが多くなった。ここは皮が非常に薄く、骨に近い部位だ。蹴りを得意とするアーツにとっては致命的なことだった。
2006年5月、長年のライバルで、デビュー3戦目に初黒星を付けられたアーネスト・ホーストが、ボブ・サップを相手に母国オランダでの引退試合をすることになった。同郷のアーツは地元テレビ局の解説として来場していたが、サップが試合開始1時間前に対戦を拒否。すると、ホーストの窮地を救うべくアーツがスクランブル出場を果たす。試合用のトランクスはシュルトから借りたという。
「僕はとにかくK-1やRIZINを助けたい気持ちが大きい。格闘家として全く迷いはなかったね」
アーツは2015年の大晦日に行われたRIZINの旗揚げ興行でも、怪我をしたジェロム・レ・バンナの代役として把瑠都とMMAルールで対戦した。試合のオファーがあったのは、六本木でのクリスマスのパーティー中だったそうだ。
アーツはもう終わってしまったのか?
同世代の選手たちがトップ戦線から遠ざかっていくなか、アーツはその後もK-1で試合を続けていた。2006年、2007年ともにグランプリでは準優勝を果たす。
彼の優勝を阻んだのがシュルトだった。シュルトは空手がベースの格闘家で、212cm、130kgの巨体ながらも器用で俊敏な動きを見せ、UFCやPRIDEなどのMMAで活躍しながらK-1でも戦った。2005年からK-1に本格的に参戦すると、年末のグランプリで初優勝。さらに2006年、2007年と3連覇した。2008年は不運な判定負けがあり、グランプリ本戦出場を逃すが、翌2009年には王者に返り咲いた。“難攻不落の最凶王者”とも呼ばれ、圧倒的な体格差で勝利する試合内容に対して、一部の関係者からは「シュルトの試合はつまらない、このままではK-1の人気が下がる」といった厳しい声も寄せられた。
事実、K-1の人気は下降気味だった。2003年9月からK-1の運営が創設者の石井和義からFEGに変わり、東京ドームでの開催は2006年が最後に。翌年からは横浜アリーナへと規模を縮小していった。
それはアーツとて同じだった。“20世紀最強の暴君”も、加齢による身体の衰えからは逃れられない。2007年のグランプリで準優勝したとき、アーツはすでに37歳。K-1の絶頂期だったころ四天王と呼ばれたフグは他界し、マイク・ベルナルド(2012年に死去)とホーストはリングを去った。2010年4月の京太郎戦では、日本人選手に初めてKO負けを喫した。
アーツはもう終わってしまった――そう感じたのは私だけではなかったと思う。不惑を迎え、リングでのステップワーク、スピード、反射神経など、あらゆる面で衰えが見られる。絶頂期を知っている者にとって、そんなアーツを見るのが何よりも辛かった。あるいは、アーツ自身も「終わり」を予感していたのかもしれない。
絶対王者シュルトに挑んだ“K-1最後の戦い”
2010年12月11日有明コロシアム。40歳のアーツがK-1で最後の試合をした日だ。トーナメント1回戦をKO勝ち。しかし準決勝の相手は、絶対王者のシュルトだった。
序盤から積極的にアーツがインファイトを仕掛ける。シュルトは冷静にカウンターを狙い打ちながら、アーツの突進を防ぐ。だが、アーツはお構いなしに前に出続ける。足元はおぼつかないが、気持ちだけで戦っている。勝ち上がって決勝へ進むことなど考えていない。そんな考えで勝てる相手ではないことは分かっている。「この試合で終わってもいい」という彼の強い覚悟が見えた。
アーツの闘志は最後まで衰えることなく、3ラウンド試合終了のゴングが鳴らされた。僅差だがアーツが有利に見えた。延長戦もあり得るが、その場合アーツに勝ち目がないことは明らかだ。彼にはもうスタミナは残っていない。判定が読み上げられる。1人目のジャッジは29-29のドロー、2人目は30-29でアーツ、3人目も30-29でアーツを支持した。
シュルトには気の毒だが、場内にいたほとんどの人が「アーツに勝ってほしい」と願っていたのではないだろうか。こんな魂を揺さぶるファイトを見せられたら、誰もが応援したくなる。そんな試合だった。アーツのセコンド陣もまるで優勝したかのような喜びようだった。
アーツはシュルトとの激闘をこう振り返る。
「体格差があり、有り得ないほどタフな状況だったが何とか勝った。セミーはとても激しい選手だよ。彼との試合の後には、血尿が出たほどだったから」
シュルトとの戦いですべてを使い果たしたアーツに、アリスター・オーフレイムとの決勝を戦う余力は残されていなかった。1ラウンドでのKO負け。だが、40歳という年齢で史上最多となる6度目のファイナル進出を果たしたレジェンドに、ファンは惜しみない拍手を贈った。
「ダウンのコール後もアリスターがフルパワーで顔をパンチしてきたんだ。それで長年、首のヘルニアで苦労したよ」
現在は日本に在住「この国が大好きだし…」
アーツはK-1での試合から1年後にリングへ復帰するも、以降の戦績は12戦5勝6敗1引き分けと往年の強さを発揮することはできなかった。
最後の試合から4年以上が過ぎた。53歳のアーツに引退のことを聞くと、彼はこんなふうに答えてくれた。
「確定ではないけど、もう試合はしないと思う。今は新団体『LEGEND』を立ち上げたので、そちらに集中したい。3月24日の次は7月に第2回大会を予定している。セミーも来日して弟子が参戦するんだ。いまから凄く楽しみにしているよ」
『LEGEND』とは3月24日に横浜・大さん橋ホールでアーツが主催するイベントのことで、彼の息子と娘も試合をすることになっている。
最近は日本の試合会場でアーツを見かけることが多い。本人に尋ねてみたところ、現在は基本的に日本で暮らしているようだ。
「この国が大好きだし、日本に住むのは自然な流れだったよ。自分を大きく、有名にしてくれた場所だから、その恩返しをしたいんだ。僕の経験や知識を伝授して、日本の格闘技を強くしていきたい。日本中でセミナーをするのもすごく楽しいね」
SNSなどでの対戦相手への挑発が話題を集める現在の格闘技界については、このように考えている。
「対戦相手をリスペクトするのはとても大事だと思っている。昔はそれがいちばん大切なことだった。でも、いまはそれが大事にされていないと思う。そのような風潮も変えていきたい。それが『LEGEND』を立ち上げた理由のひとつでもあるんだ」
では、あなたにとってキックボクシングとは? 最後にそう質問すると、いかにもアーツらしい、いや、「アーツだからこそ言える言葉」が返ってきた。
「キックボクシングは僕の人生だ。自分が世界で一番キックボクシングのことを知っている。そんな自信がある」
<前編から続く>
文=長尾迪
photograph by Susumu Nagao