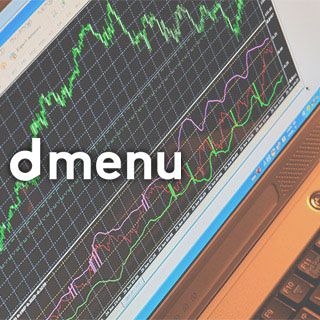NumberWebで特集が始まった「アスリート親子論」。これまで公開されてきた記事の中から、特に人気の高かった「アスリートの親子関係」にまつわる記事を再公開します。今回は、瀬古利彦さんと息子・昴さんの物語です。《初公開:2021年7月3日/肩書などはすべて当時》
都内の桜が若葉に生えかわった4月13日、瀬古利彦さんの長男である昴さんが34歳の若さでこの世を去った。
25歳の頃、ホジキンリンパ腫という血液のがんの一種を患ってから、およそ9年にわたって彼が駆け抜けたのが“がん”のマラソンだった。難治性の病で、何度も入退院を繰り返す中、彼はこの分野の“トップランナー”を自認する(亡くなる約ひと月前、『がんマラソンのトップランナー 伴走ぶっとび瀬古ファミリー!』(文藝春秋企画出版部)という初めての著作であり、遺作を世に送り出している)。
過酷ながんマラソンにパイオニアの精神で挑んだ昴さんの生き様とはどのようなものだったのか。
瀬古さんが幼少期からの歩みを振り返る。
歯ブラシを捨てるときでも「ありがとう」って
「子どもの頃から昴は優しかったです。困った人がいたらその人のためになりたいとか、そういうことはよく言っていました。たとえば歯ブラシを捨てるときでも、『今まで僕の歯を守ってくれてありがとう』って、手を合わせてから捨てていた。私が教えたわけじゃないから、それが昴の性格だったんだろうね」
感受性の豊かな少年は、中高と野球に打ち込み、勉強もよくできた。陸上競技をやらなかったのは、マラソンのトップランナーである父と比べられるのがいやだったのかもしれない。やがて慶応大学へ進むと、環境問題に熱心に取り組むようになる。
「マイ箸、マイコップなんてずっと前から実践していましたね。私はサッカーの岡ちゃん(岡田武史氏)と早稲田の同級生なんだけど、昴が岡ちゃんの講演会を聴きに行ったことがあって。その日は『お父さんと岡ちゃんは全然違う。もっと見習わなきゃ』ってずいぶん怒られました(笑)」
大学生の時にはエコ文化について学ぶため環境先進国のドイツへ短期留学をした。交友関係は広がり、前途には無数の選択肢があった。就職先には食品販売会社を選ぶが、入社2年目の春にあの震災が起きる。東日本大震災で原発の危険性や問題点が明るみに。昴さんはこれに怒りを覚えた。
「感受性が強いんだろうね。悪いことが許せないんです。原発ももともと昴は反対していて、皇居前のデモなんかにも参加していた。それで会社を辞めて、見聞を広めるためにピースボートに乗って旅をするんだけど、帰りの船の中ではすでに体調が悪かったんだね……」
船を下りるときには背中に謎の発疹が
地球一周の船旅から船を下りるときには、背中に謎の発疹ができはじめていた。後に判明することになる、ホジキンリンパ腫(悪性のがん)による症状だった。そこから「ジェットコースターのような日々」と表現するように、昴さんの人生はがんに翻弄されていく。激しい痛み、治療、そして入院。症状が治まり退院しても、またがんが再発してしまう。闘病の様子は前述の本に詳しいが、昴さんの真骨頂はどんなに辛い状況でも前向きさとユーモアを忘れないことだった。
昴さんは本の中でチャップリンの『人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見ると喜劇だ』という言葉を引用し、こんな風に私見を述べている。
「辛い経験を笑いにできるということは、『その経験を乗り越えた』と言い換えられたとも思うのです。(中略)僕たちの世代(AYA世代、15歳から39歳くらいまでの人)には、学業、仕事、恋愛、結婚などで、高齢になってからのがんとは違った特有の悩みがありますから。そんな、僕と同世代のみなさまに、この本が届いて、経験をシェアできたら嬉しいです」
「よっぽど伝えたいことがあったんだと思う」
だからこそ、闘病中の悩みについても包み隠さず記した。もしかすると、強い怒りの感情が免疫力を下げさせ、自分や周りを傷つけたのではなかったか――。体調を崩した初期の段階で手術を勧められていたのに、なぜ病院に行くことを拒んでしまったのか――。自らの経験を学びの参考書にしてほしいという、彼の一途な思いが伝わってくる。
「この本を昴が書き始めたのは1年半ほど前かな。一番体調が良くないときですからね。よく書けたなと思います。普通は病気でウンウン唸っているときに文章を書こうなんて思わないよね。だからよっぽど伝えたいことがあったんだと思う。でも、書いている間は楽しそうで、痛みや苦しみを忘れられる時間でもあったんだろうね」
自ら新薬の治験対象者になることを選んだ
本の価値をさらに高めているのが、自ら新薬の治験対象者になることを選び、その効果や副作用についての経験談を率直に綴っていることだろう。新薬とはがん免疫療法薬であるオプジーボのことで、投与を始めた2015年時点では未承認の薬だった。それまでにも様々な化学療法や放射線治療、弟をドナーにした幹細胞移植などで命をつないできた昴さんは、一縷の望みをかけてこの新薬を試すことにした。安心や安全が保証されていない中での勇気ある決断。まさにトップランナーとしての使命を果たそうとしたのだ。
「今日ちょうど、主治医の鬼塚(真仁・東海大学准教授)先生のところに最後の挨拶に行ってきたんだけど、ホジキンリンパ腫の患者に移植後にオプジーボを投与してからの長期生存者は当時はフランスの女性と昴のふたりだけだったんだって。もちろん日本では初めてだから、先生たちが論文を書いてくれて、今それが世界中で読まれている。昴の決断が医療を進化させていると思うと嬉しいよね」
オプジーボの投与で症状は以前に比べてずっとやわらいだ。今までの抗がん剤と違って吐き気をもよおすことがなく、これは「精神衛生的にもとても良いこと」と昴さんは書いている。本の後半部分は主に認知症を患っている祖母(愛称はちばちゃん)との微笑ましい会話のやりとりが描かれているのだが、辛い経験を乗り越えるたび、昴さんは人間的に大きく成長していったように思える。
「こんなに苦しかったんだ、痛かったんだ」
だが、オプジーボも決して万能薬ではない。副作用としてドライアイの症状が進み、左目はアイパッチが欠かせないようになった。副作用は肺にも及び、「鼻のチューブから常に酸素を供給する必要がある」状態になってしまう。移動に車いすが欠かせなくなった長男の姿を見て、瀬古さんもさぞ心を痛めたことだろう。
「改めて本を読むと、全身の痛みにもんどり打って、台所の包丁が光って見えたとか書いてあるじゃない。その時は何も言わなかったけど、こんなに苦しかったんだ、痛かったんだって思うと、泣けてくる。
私たちの時代は昴と同じで、弱みを他人に見せちゃいけなかった。ぜんぶ自分で抱えて、それがストレスになってしまう。私もロサンゼルスオリンピックの直前に心も身体もおかしくなっちゃったんだけど、中村(清)監督にも言えなかったもんな。昴も一人で抱え込んで我慢して……そこは親子で共通しているようですね」
病気をきっかけにして、スキンシップが生まれた
一つ違いがあるとすれば、昴さんにはいつでも手をさしのべ、言葉にせずとも気遣ってくれる家族がいたことだろう。昴さんは本の中で「僕の病気をきっかけにして、家族の気持ちをひとつにする機会が増えたように思います。(中略)もし僕が健康に、外で働いて、一人暮らしをして、という生活をしていたら得られなかったもの、過ごせなかった時間がたくさんあるように思います」と書いている。
瀬古さんも同感のようだ。
「私が足をマッサージしてやると昴が喜んでくれるんです。ちょうどコロナ禍で家にいる機会が増えて、そこで初めて父と息子のスキンシップが生まれた気がする。長いときで1時間、短くても30分、ほとんど毎日続けていました。いま思えば、ああいう時間をいただいて本当に良かったと思うし、やりきったと思えるからね。この8年余りでどれだけ東海大の付属病院に通ったか。自宅から往復120km、車のメーターの8割はそれですから。もう目をつぶってたって行けるよ(笑)。最後に昴と心を通わせることができたのは、神様の計らいだったのかなって思うね」
「悲劇ではなくて、喜劇の方へ」
昴さんは生前、生まれてきたことの意味を問い続けた。なぜ病気になったのか、なぜ自分なのか。もしそれが「自分を成長させるために神様が与えてくれた試練」であるならば、「辛くて返品・リコールしたくなるときもありますけどね!」と冗談ぽく言いながらも、懸命に考え続けた。
辛い経験を乗り越えようとする過程で、その答えにたどり着けたのだろうか?
「すごく苦しい中でも笑いを忘れない。悲劇ではなくて、喜劇の方へ持っていく。それは最期まで貫きましたよね。痛いとか苦しいとか、家の中ではほとんど言いませんでしたから。泣き言を一切言わずに走り抜けた。それは父親の私から見ても本当にすごいことだと思います」
瀬古さんの携帯には、この本が出版されたとき、車いすで本が並ぶ書店に駆けつけた昴さんの写真が収められている。昴さんは何よりもこの本の出版を楽しみにし、読者に自分の声が届くことを喜んでいたようだ。
享年34。早すぎる死は本当に残念だが、活字として遺した、みずみずしい感性は決して色褪せない。
がんマラソンを先駆的に駆け抜けた昴さんの足跡は、いま現在、そしてこれからがんに悩むであろう患者たちの、行く先を照らす良き道しるべとなるだろう。
文=小堀隆司
photograph by 瀬古利彦提供