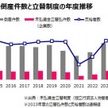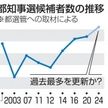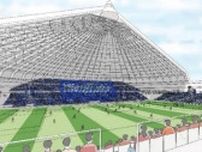1999年5月3日、IWGPヘビー級チャンピオンの武藤敬司(36歳)と天龍源一郎(49歳)による初のタイトルマッチが実現した。この年のプロレス年間大賞ベストバウトに選ばれた激闘は、両者にとってプロレス人生のターニングポイントになったという。あれから25年ーーふたりはお互いをどう思っているのか。NumberWeb連続インタビューの後編では、昨年、60歳で現役を引退した武藤敬司が“あの一戦”と天龍源一郎について語った。<全2回の後編/前編「天龍源一郎インタビュー」も配信中>
武藤に天龍からの言葉をぶつけると…
61歳の武藤敬司は今なおトレーニングを日課としている。
東京ドームで引退試合を行なってから1年を過ぎても、盛り上がった筋肉は現役時代とそう変わらない。
「どうしても(トレーニングを)やりすぎるところもあって。痛めている股関節に負荷をかけすぎると、主治医の先生に怒られちゃうよ」
いい汗を流してうまいワインと食事を嗜むためだという。
近況から本題となる1999年5月3日、福岡でのIWGPヘビー級タイトルマッチへ。「“どうしてあんなジジィとやんなきゃいけないんだ”という武藤の声が風に乗って聞こえてきた」という天龍源一郎の話をぶつけると、「覚えていない」と首をかしげる。なるほど正面からぶつかってくる相手に対して、スッとかわすファイトスタイルに似ている。
「そんなこと言ってねえと思うよ。ムタが1996年に天龍さんとWARの大阪で絡んで、これでもかっていうくらい集客できたんだよ。その流れもあってそろそろってことで(対戦が)決まったんじゃないかな。むしろ俺は逆に盛り上げたよ。ミスタープロレスってお互いに呼ばれていたから、その座を懸けようって言ったくらいだから。試合に勝ったけど、確か天龍さんに“譲る”ってコメントもしたんじゃないかな」
確かに天龍はミスタープロレスと呼ばれていたが、武藤はむしろナチュラルボーンマスターと称された時代。そんなツッコミはさておき、ベストバウトを宣言した天龍に対して武藤なりに表現のインパクトで上回ろうとしたことは何となくうかがえる。相手の土俵にまともに乗っからないのもまた武藤らしい。
リング上で天龍と対峙して、真っ先に感じたのが「間」だった。
「天龍さんと同世代になる新日本の先輩方で言えば、長州(力)さん、藤波(辰爾)さんは間を嫌うせっかちなプロレス。でも天龍さんは間を大切にするし、おおらかなプロレスをする。間ってお客さんに想像させるんだよ。次の技が来るとか、効いたとか効いてないとか、痛そうだとか。俺と天龍さんのプロレスが合うかどうかってまでは分からないけど、間というものを俺自身も大切にしていたっていうところはあるよね」
「天龍さんの打撃は痛いんだよな」
間は、言うなれば駆け引きでもある。天龍との読み合いは、武藤の探求心をくすぐる。ドロップキックも胸と思わせておいて低空で右ひざに打ち込み、苦悶の表情を浮かべさせている。技一つひとつの応酬にある間が緊張感と期待感を醸し出していた。
「俺だって若いころは間なんて大切にしてなかった。運動能力には自信があって、アメリカでもそういうところを求められてどんどん出していって。でも膝を痛めたり年齢を重ねたりして、どんどん技がなくなっていった。それなのにどんどん試合が長くなる。足4の字ができたときから必然的に長くなる新しい俺流の戦い方が始まったわけだけど、技術、経験、それに才能だってあると思うよ。ただあの試合は25分だっけ。振り返ってみるとあの天龍さんとの戦いがあって、もっと試合時間が長くても表現できるって思えたのかもしれないな」
間と言っても、間延びではない。ゆったりのリズムもあれば、一気呵成のリズムもあって、それは組曲のごとく。武藤にしては珍しかったのが“張り合い”だ。天龍が繰り出す逆水平チョップに対して胸へのエルボーを繰り返している。
「一発食らっても俺はお返ししないから。みんなやるし、いかにも日本のプロレスっぽいじゃん。そういうバトルになるのは嫌だし、そもそも意地を張ることが俺は嫌なんだよ(笑)。ただ天龍さんの打撃は痛いんだよな。逆水平も、(グー)パンチも、キックも」
無意識に出たお返しのエルボー。自分のペースを崩していないと思いきや、知らず知らずのうちに天龍の土俵にも引きずり込まれていた。
足4の字、低空ドロップキック、ドラゴンスクリューと足に狙いを定めたプロセスを経て、最後は再び低空ドロップキックをひざに見舞ってからムーンサルトプレスで自分のひざを天龍の顔面に浴びせて3カウントを奪った。
意外にも、プロレス大賞の年間ベストバウトは初めての受賞だった。この年は2度目のMVPにも輝き、2冠を達成している。
「プロレス団体っていっぱいあって、きょうだってどこかで興行をやっているわけでしょ。当時はもっと団体があったし、毎日、それも1団体7〜10試合くらいはやっていたと考えると1年で凄い数の試合になる。ベストバウトはそのなかで1番なんだから、光栄に決まってるよ。1995年に東京ドームでやった高田延彦戦ですら選ばれていないんだから。あれは納得いってないけどさ(笑)。まあまあ、ファンが期待する以上のものを超えていかないとベストバウトっていうのは取れないんだよ」
「武骨極まりないあの人は、不格好なんだよ」
天龍との邂逅は、じっくり、たっぷりの“武藤ワールド”が確立された実感を得ることになった。そして以降も緊張感ある2人の関係性が続いていくことになる。大量退団で危機にあった全日本に天龍が復帰すると、武藤も主軸を全日本に移してのちに社長に就任。2002年までに3冠ヘビー級タイトルを懸けて2度対戦している(グレート・ムタでも1度)。
「福岡で雪崩式フランケンシュタイナーをやられて、全日本のときはシャイニングウィザードも。武骨極まりないあの人は、はっきり言っちゃえば不格好なんだよ。でも、それがお客さんの心をくすぐるんだよな。全日本では巡業にも一緒に行った。面白いへそ曲がりというか、興行的にお客さんの入りが悪いときのほうが燃えてプランチャやったりする。それにやっぱりプロレス頭があるっていうか。天龍さんが引退する前にムタと後楽園で戦ったけど、毒霧を吸い取られているからね。このときのキスも武骨でさ(笑)。俺も引退する前にムタがSHINSUKE NAKAMURAと戦って、同じようにやられたんだけど、天龍さんが先にやってんだよな」
「ジジィだけど、そう感じさせない」
面白いへそ曲がり、一歩先に行く感覚。武藤なりにリスペクトを持って、その背中を眺めていた。武藤は言葉に間を置かず、矢継ぎ早に語る。
「天龍さんが53歳のときに『53歳』という新しい技をつくった。正直、そのころは何とも思わなかったよ。でも自分もその年齢になったときに。あの頃の天龍さんと同じかって思うと何とも感慨深かった気がする。体はボロボロなんだけど、ジジィなんだけど、そう感じさせないんだから。
天龍さんは全日本を飛び出してSWSに行って、WARつくって。もしかしたら俺もそういう背中を見ていたから全日本に行って、WRESTLE-1旗揚げしてっていうところはなきにしもあらずかもしれない。やっぱ天龍さんもそういう意味でパイオニアだよ。
結局レスラーって、最後は人間力だから。人間そのものが戦いに出るわけよ。クソ真面目なヤツはプロセスもクソ真面目、あまりにいい加減なヤツはプロセスもいい加減。それじゃファンには刺さらないわけだよ。プロレスも面白くない。武骨で、面白いへそ曲がりな部分が天龍さんの人間力。それはファンからしても魅力だったってこと」
今のプロレスに足りないものとは?
華麗と武骨、タイプは違えど、ポリシーは違えど、プロレスラー天龍の生き方にどこか刺激を受け、どこか参考にする武藤がいた。
65歳の天龍がオカダ・カズチカと戦った引退試合は年間ベストバウトに選ばれている。一方の武藤も2021年の潮崎豪戦に続き、ムタのラストマッチとなった2023年のSHINSUKE NAKAMURA戦で受賞している。還暦となってもトップを張り、間を大事にするプロレスを究め、お互いに現役を締めくくる試合がベストバウトになるというのは何とも不思議な縁だ。
「ああいう引退の仕方も天龍さんっぽいよ。だから俺の引退試合では(対戦相手の)ラインからオカダは外させてもらった」
刺激、参考のみならず、最後まで意識させられた人とも言えるのかもしれない。
引退した武藤は解説など一歩引いた形で今のプロレスを眺めている。全体の活気という意味では危機感も覚えている。
足りないものは何か?
そう尋ねると、即答だった。
「一つはやっぱり天龍源一郎みたいなレスラーがいないよね。大きながたいで、武骨で、へそ曲がりで、何よりプロレス頭があって。別にあの人、持ち前のパワーみたいなところで勝負していないから。みんな結構似たような体型じゃん。今はああいうタイプのレスラーがいないし、いればいいのになって単純に思うよ」
武藤の言葉に実感がこもる。
タイプもマインドも違えど、意地を張るのが嫌いな天才は意地を張る武骨との戦いを通じて、背中を通じて、己の戦い方に、そして生き方に味つけをしていった感がある。影響をまったく受けていないようで、その影響をサラリと自分のものにしてしまうのも武藤敬司の天才たるゆえんなのかもしれない。
<天龍源一郎編から続く>
文=二宮寿朗
photograph by Shigeki Yamamoto