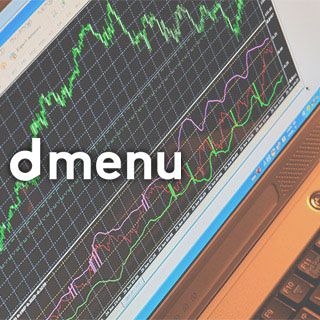W杯ベスト8以上の高みを見据えて戦うサッカー日本代表。これまでの歴史の中には代表に定着できなかった“消えた天才”がいた。雑誌「Sports Graphic Number」「NumberWeb」掲載記事から彼らの才能と今を知る。(全2回/第2回も)
<名言1>
これまでもそうでしたが、東京と大阪を行ったり来たりしながら、ぷらっとしていますよ(笑)。
(礒貝洋光/NumberWeb 2020年10月10日配信)
https://number.bunshun.jp/articles/-/845365
◇解説◇
1990年代から2020年代にかけて描いた日本代表の成長曲線には、数々の名選手がブルーのユニフォームを身にまとって激闘を制してきた歴史がある。しかしその中には類稀な能力を持つと期待されながらも輝くことなく、代表メンバーからフェードアウトしていった選手も数多い。その1人が礒貝である。
天才テクニックと“変わり者”なパーソナリティ
テクニカルなプレーとパスセンスは小学校時代からサッカー関係者には知られた存在で、中学生にしてU-17日本代表のエース格となり、名門・帝京高校入学後には1年生にして背番号10を着用。東海大学時代の1991年に日本代表に初選出され、Jリーグ開幕前年の92年に大学を中退してガンバ大阪に入団。クラブ創成期の中核を担うなど、間違いなく日本を背負う存在としての期待は高かった。
その一方で礒貝がサッカーファンに知られていったパーソナリティには“変わり者”という一面もある。例えば2020年、インタビューに応じた際にこんなエピソードを明かしていている。
「若い頃は、奇抜な髪形にしたくて美容院に行くんだけど、長い時間じっとしていられなくて。パーマをかけてロッドがまだ巻かれているのに『あとは自分でやるから』と帰っちゃったり。ときには頭にロッドを巻いたまま祇園の舞妓さんのところに遊びに行ったこともあった(笑)」
礒貝は94年夏の親善試合、95年初頭のインターコンチネンタル選手権で招集を受けたものの、さしたる結果を残せず。そのまま日本代表から遠ざかるとJリーグでの個人成績も落ち、98年に29歳の若さで引退した。
ゴルファー、大工、焼き鳥屋…流浪の人生
礒貝が独特なのは、引退後のキャリアもである。
サッカーから離れるとまず目指したのはプロゴルファーで、何度かテストを受験したものの合格には至らず。その後は大工や塗装業、焼き鳥屋を転々とし、2023年10月には民放テレビ番組にヒゲを蓄えた姿で出演した姿も話題になった。
言わば“流浪の自由人”のような人生を送っている礒貝だが……実はその親戚である礒貝飛那大(ひなた)が、2023年末にフットサル日本代表で初招集を受けている。飛那大が、フットサル日本代表という舞台で結果を残せば……埋もれた天才・礒貝洋光の存在が再びピックアップされるかもしれない。
“ラモス後の10番”を背負った岩本の本音
<名言2>
日本代表は、僕にとって「雲の上のような存在」でした。
(岩本輝雄/NumberWeb 2018年6月8日配信)
https://number.bunshun.jp/articles/-/830942
◇解説◇
いわゆる「ドーハの悲劇」後、ファルカン監督体制になった日本代表には1つの注目点があった。ラモス瑠偉が背負った「10番」を誰が背負うか、である。そのエースナンバーを預けられたのは岩本だった。
岩本はJリーグ参入したベルマーレ平塚(当時)にあって、左足での創造性を武器にチームの躍進に貢献していた。それをファルカン監督は見逃さず、94年5月の親善試合で代表デビューを果たした。当初のポジションは左サイドバックだったが、同年9月の親善試合と10月のアジア大会では本来のポジションである攻撃的MF、さらにはナンバー10を背負うことになった。
「自分の番号ではないっていう感覚でしたね。それでも期待してもらっている以上、つけるしかなかった」
岩本はこのように当時を本音で述懐している。
「振り返れば、日本代表のこともすべて…」
そんな彼が日本代表として臨んだ唯一の公式戦が、アジア大会だった。
しかし当時、Jリーグは「超」がつくほどの過密日程だったこともあり、岩本のコンディションは低下していた。目立った活躍はできず、チームは準々決勝で敗れてファルカン監督も解任された。
そして岩本の代表キャリアも、結果的にこの韓国戦でラストとなった。わずか半年間の代表生活だった岩本。それでも日本代表での日々をこのようにも振り返っている。
「呼んでくれたファルカンさんには今でも感謝しかありません。振り返ってみると、日本代表のこともすべて良い思い出です」
若き日の前園は“トガっていた”
<名言3>
岡田さん、とりあえずゾノを呼んで下さい。
(中田英寿/Number440号 1998年3月12日発売)
https://number.bunshun.jp/articles/-/848930
◇解説◇
サッカー男子にとって28年ぶりとなる五輪出場を果たした、1996年アトランタ五輪。川口能活や中田英寿といったメンバーの中でキャプテンを任されたのは前園真聖だった。アジア最終予選準決勝サウジアラビア戦では2ゴールを挙げる大活躍で五輪切符を手繰り寄せる原動力になった。
今ではバラエティー番組で“いじられキャラ”になるなど、前園はすっかり丸くなった。しかし20代前半の若き日には、殺到するメディアに自身の意図することとは違う報道がされることもあった。
「馴れ馴れしさを少しでも見せれば自分が崩れていってしまうような気がしていたんです」
自身でも当時は“トガっていた”ことを認めている。
そんな前園だが、サッカー選手につきものの移籍によって、キャリアが大きく変わることになった。横浜フリューゲルスからスペイン移籍を狙ったものの、結局はヴェルディ川崎でプレーすることに。その後はブラジルやポルトガルやギリシャのチームでプレーするも本契約には至らず、2000年にはJ2に降格した湘南ベルマーレでプレーすることを決めた。
「オレは日本へ戻る時、J1に復帰できないようなら後がないと思ったから。この先、サッカーできなくなることまで覚悟しましたから」
と語るなど、プロサッカー選手の人生の厳しさを肌で感じた代表格と言える。
中田英寿も前園の突破力には一目置いていた
選手としてのピークは短かったとはいえ、「ドリブルはどこで使えば相手の脅威になるかの選択が大事」と語るなど、そのドリブルの切れ味は日本サッカー屈指だった。
冒頭の言葉はフランスW杯出場権を獲得したのち、中田が前園との対談で「Number」誌面上で語ったものだ。前園と中田はテレビCMで共演するなど“仲良し”で知られた。日本代表の中核になりつつあった3学年下の後輩も、その突破力に一目置いていたのだ。
苦難のキャリアを送った前園だが、アトランタ五輪本戦では金メダル候補と見られていたブラジル代表を撃破する「マイアミの奇跡」を成し遂げたのは事実だ。一方で、その舞台に立つはずだった「レフティーモンスター」小倉隆史は、嘱望されたサッカー人生に暗雲がかかっていた。
<つづく>
文=NumberWeb編集部
photograph by Kazuaki Nishiyama





























![[U-23日本代表のマリ戦スタメン予想]勝てば決勝T進出。中2日も初戦からの入れ替えは2名のみと予測。平河悠が負傷の右ウイングは...【パリ五輪】](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/soccerdigestweb/s_soccerdigestweb-158184.jpg)