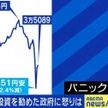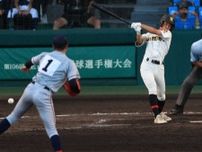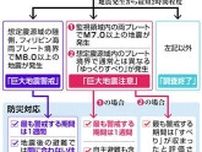2023年夏の甲子園を制した慶応義塾高校は、森林貴彦監督のもとで「エンジョイベースボール」を掲げる。ただこの校風は一朝一夕でできたものではない――前監督の上田誠氏が知る“消えた古豪”からの脱却までのプロセスとは。(初出以外敬称略。全3回の第1回/第2回、第3回も配信中)
「慶応高校が優勝してから、ずっと電話で追いかけまわされているんです。スポーツ紙とか、テレビとか。もう大変ですよ。〈森林、やってくれたな〉って思っています」
昨秋、話を聞いた慶応義塾高校前監督の上田誠氏は嘆いてみせた。もちろん、顔は喜びにあふれている。
2023年夏の甲子園を制した慶応義塾高校の森林貴彦監督は、上田の教え子である。「エンジョイベースボール」を掲げて今の慶応義塾高校野球部の礎を築いたのは上田に他ならない。メディアが追いかけまわすのも無理はない。
かつての慶応大はスパルタ式だった
筆者は少年野球の現場や野球指導者の会合など、様々な場所で上田にお目にかかった。上田は少年野球の現状に危機感を抱き、指導者や野球界に耳の痛い直言を続けてきた。つまり反骨の野球指導者なのだ。そんな上田は、どのような経歴を歩み、その野球哲学を育んだのか。じっくりと聞いてみた。
「小学4年くらいから野球を始めて、中学は学校の部活です。高校は公立の神奈川県立湘南高校で、一浪して慶応義塾大学に入りました。投手でしたが、大したことなくて、そのうえ股関節を悪くして、新人選手の面倒を見る役回りになって『教える面白さ』が分かってきました」
しかし当時、慶応義塾大学の雰囲気は、いわゆるスパルタ式だったという。上田は「大学の4年間、これは違うのではと感じていた」そうで、このように続ける。
「卒業後は教職免許を取るために大学に引き続き通って、桐蔭学園に就職し、野球部の副部長になりました。ここは慶応よりも、もっとすごかった。僕が通った湘南高校は、監督も『自分で考えてやれ』という方でしたから、練習時間もそれほど長くはなかったのですが、桐蔭は朝3時半から練習です。こうなったら、授業中は寝るしかない。
僕は、いかに短い時間で効率よく練習をして実力をつけるかが大事だと思っていたので、これは違うと思った。県立の厚木東高校に移って指導しているうちに、慶応高校の監督のなり手がなく、地区予選も勝てない状態だということだったので、監督をお引き受けすることにしました」
高校野球のやり方に染まって、すごく怒られた日
慶応の監督を紹介したのは、当時の慶応義塾大学野球部監督である前田祐吉監督だった。
「前田先生は『エンジョイベースボール』を提唱した指導者です。それから25年ほど監督を務めました」
しかし当時の上田は、本当の意味で「エンジョイベースボール」を理解していたわけではなかった。
「僕自身も日本の高校野球のやり方に染まっていたんですね。前田監督が見ておられる試合で、点差が開いていたのにスクイズをやらせたら、ものすごく怒られたんです」
上田は「早くコールド勝ちに持ち込んで投手を休ませよう」という意図だったそうだが、前田は、このように怒ったのだという。
「なんてことやってるんだ、それは野球じゃない。お前は高校野球に毒されている。野球とは点の取り合いだ。そして選手ファーストで考えるべきなんだ」
価値観が変わったUCLA留学
エンジョイベースボールの理念を知っていく中で、前田からある提案を受けた。
「前田監督はアメリカの野球に精通されている方で、『お前、高校野球にいるとどんどん毒されるぞ、アメリカに留学してこい』ということで、1998年にUCLAに2年間、コーチとして留学することになりました」
実は、1990年代に指導を受けた慶応高校OBの中には「上田先生はおっかなかった」という人もいる。上田の野球観が180度変わったのはこのUCLA留学だった。
「その頃まで僕は神奈川大会を勝ち抜くために、肘が痛い投手を無理してマウンドに上げることもあったんです。そうして無理をさせた挙句にエースが投げられなくなって、準々決勝で敗退したこともありました。
でもUCLAでは全然違った。UCLAはPac-10(Pacific-10 Conference、現在はPac-12 )と言われる大学グループのリーグ戦が中心で、それ以外も含めて年間50試合くらいやります。プレーオフがあって、最後にオマハで全米の決勝シリーズがあるのですが、そこまで行くのは8チームだけなんです」
エースが「冗談言わないでくれ、俺を潰す気か」
その中で上田のチームは、あと少しで決勝シリーズに行けそうな状況になった。そこで前日の試合で投げたジョシュ・カープ(Josh Karp)というエースに、「明日も頼むぞ」と声をかけた。前の日は100球前後を投げていたものの、日本の感覚では、いけないことはないという発想だった。しかし、カープの返事はこうだった。
「冗談言わないでくれ、俺を潰す気か」
上田は当時を、こう振り返る。
「『オマハに行けたら最高じゃないか』、と言ってもそんなことは、これっぽっちも考えていないんです。大学だから投手も複数そろえることができる。先発、救援も準備できるということはありますが、日本とアメリカの意識の差を実感しました。
それにアメリカでは練習から球数を数えていた。遠投もカウントしていました。こういう意識は全く違いました。カープは2001年にドラフト1位でモントリオール・エクスポズに指名されました。残念ながらメジャーに昇格できませんでしたが、良い教訓になりました」
以前の野球部は“合コン”をやったりする雰囲気で
慶応高校は、夏の甲子園大会の前身である「全国中等学校野球優勝大会」第2回大会(1916年)で優勝している古豪である。しかし1962年を最後に、甲子園に出場しない期間が40年も続いた。1990年に監督に就任した上田には「何とか古豪復活を」という気持ちもあり、当初はある程度のスパルタ野球もやっていた。しかしUCLA留学を機に、上田の指導方針は大きく変わった。
「当時の慶応高校はとても甲子園なんて雰囲気じゃなかった。野球部で合コンをやったり、楽しい雰囲気で、それもあって僕は厳しくやっていた部分もある。前田監督には『慶応高校でいい選手を育てて大学に送ってくれ』と言われました。実は当時、息子さんが慶応高校にいて『あんなのは野球部じゃない』と言っていたようです。そこで、僕は選手に『甲子園、本気で行こうよ』といって野球部を変えていったんです」
しかし内部進学組と受験で入ってきた選手が中心だったため、甲子園は遠かった。西武ライオンズで外野手として活躍した佐藤友亮がいた年に、神奈川県大会で準優勝したのが最高だった。
慶応=ピアスして茶髪の印象を変えるために
転機となったのは2003年に「推薦制度」ができてからだ。
「ロサンゼルスオリンピックでボート競技の監督をしたスポーツ指導者が、慶応高校の校長になったんです。その先生が〈慶応高校の生徒と言えばピアスして茶髪という印象で、アスリート的な生徒がいない。何かカンフル剤が必要じゃないか〉と言った。
そこで、他部活の顧問の先生と『推薦制度を作りましょう』と行ったんです。〈誰でもいいというわけでなく、しっかり審査しましょう〉と言ったら設立委員会ができて、僕もそれに加わって、1学年40人の推薦枠ができた。その上で、内申点が45点満点で38点以上です」
上田は「何しろ推薦入学組は、入ったときからキャッチボールがしっかりできるんですから」と笑いながら「野球部もガラッと変わったんです」と証言する。実際、2005年春の甲子園に出場。1962年の夏以来、43年ぶりだった。さらに、2008年春夏と甲子園に連続出場した。
こうして慶応高校は「エンジョイベースボール」の旗を掲げて、復活した。
<つづく>
文=広尾晃
photograph by JIJI PRESS