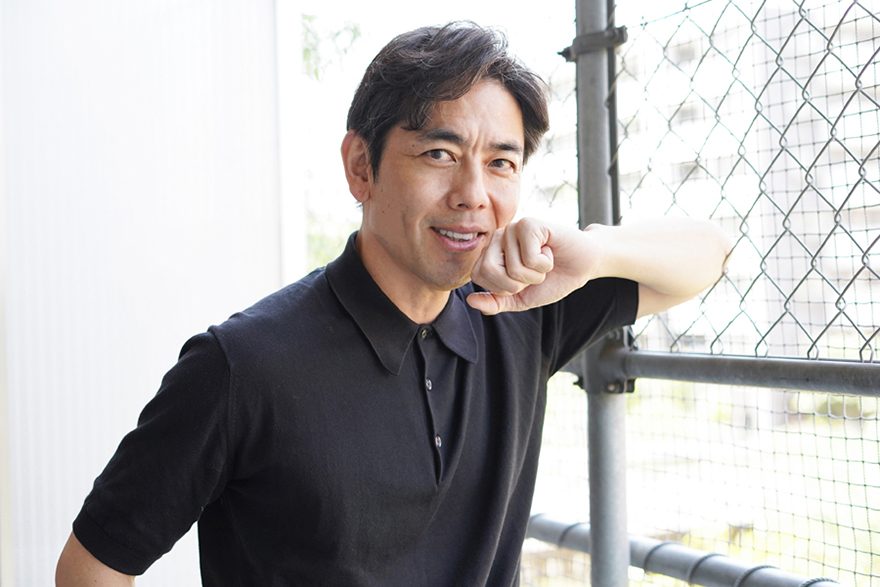
2003年からドラマ『相棒』(テレビ朝日系)に出演し、芹沢刑事役として広く知られている山中崇史さん。
『時代劇スペシャル 無用庵隠居修行』シリーズ(BS朝日)、『花咲舞が黙ってない』(日本テレビ系)、映画『TAP THE LAST SHOW』(水谷豊監督)、映画『太陽とボレロ』(水谷豊監督)などに出演。劇団扉座の看板俳優としても活躍。
2024年6月6日(木)から16日(日)まで座・高円寺1で劇団扉座第77回公演『ハロウィンの夜に咲いた桜の樹の下で』(作・演出・横内謙介)に主演する山中崇史さんにインタビュー。

◆学芸会の拍手が気持ち良くて
埼玉県で生まれた山中さんは、小さい頃から目立ちたがり屋で明るい子どもだったという。
「僕は長男坊で年子の弟と妹がいて、家の中はとても賑やかで、兄弟仲良くて、家族も仲良くて。お兄ちゃんなので、弟と妹よりも目立ちたいって、家の中でもそんなふうに思っていたし、学校でも目立ちたいみたいなことを思っている子でしたね。
僕が小学校2年生ぐらいのときに鉄棒のグライダー(飛行機飛び)というのがあって、それがみんなはできなかったけど、僕はできたんです。それで、僕がそれをやったら、みんなに『ヒューッ、ヒューッ』って言われて(笑)。そういう人気者とかになるのが気持ち良かったりしていましたね」
――ひとりだけできたら、クラスではスターですよね。
「そう。そういう感じだったので、気持ちがいいなと思って。僕は小学校3年生のときに茨城に引っ越したのですが、すぐに学芸会があって、お芝居をやることになったんです。僕はいい役をやりたかったんだけれど、何せ引っ越してすぐだったので、あまりみんなも僕のことを知らない状態で配役をされてしまって。
僕は目が悪くて黒縁の眼鏡をかけていたからワンシーンだけ出てくるお医者さんの役になって、短いセリフが一言だけなんですよ。自分的にはあまりうれしくはなかったんだけど、当日体育館でそのお芝居をみんなでやって。
僕は釣り針が引っかかってしまった鯛の喉から釣り針を取ってあげるお医者さん。『その釣り針を取ってください、お医者さん』って言われて、舞台の袖から黒縁の眼鏡をかけて長い白衣を着た僕が、後ろに黒い大きな革のバックを持たせた看護婦さんをひとり連れて、2人でズルズル、ズルズル出てきたらお客さんがすごくザワザワしはじめて。
僕もそのザワザワが新鮮で『何だろう?どうしたんだ?』みたいな感じで(笑)。鯛の喉から釣り針を取って、そこで客席に向かって一言、『おーっ、あった、あった』って言ったら大爆笑で、ものすごい拍手を受けた記憶があるんですよ。
それでもう完全に気持ち良くなってしまって(笑)。これいつも思うんですけれど、振り返るとそれが『役者さんをやりたいな』と思ったきっかけだったかもしれないなって」
――一言しかセリフを言ってないのにすごいですね。
「ウケてやろうと思ってないのにね。よっぽど可愛かったんだと思うんですよ、僕(笑)。ちっちゃかったし、長い白衣を着て黒縁の眼鏡で。本当に気持ち良かったです」
――小学校3年生で、拍手をもらう快感を覚えてしまったわけですね。
「そう。何か人前でやって拍手されたりするのは気持ちいいって思いました。それは今、舞台上で芝居をして拍手をいただいても同じ感覚。今でもそれと一緒ですもん。気持ちいいなあって。癖になりますよね(笑)」
※山中崇史プロフィル
1971年2月5日生まれ。埼玉県出身。1995年、劇団扉座に入る。1997年、『内藤忠と山中崇志のミリオンナイツ』(TOKYO FM)のパーソナリティー。1998年、『小田靜枝と山中崇志のミリオンナイツ』(TOKYO FM)のパーソナリティー。2003年、『相棒 season2』の第4話から捜査一課の芹沢慶二刑事役でレギュラー出演。『だましゑ歌麿』シリーズ(テレビ朝日系)、映画『HOME 愛しの座敷わらし』(和泉聖治監督)、映画『轢き逃げ 最高の最悪な日』(水谷豊監督)などに出演。2024年6月6日(木)から上演される劇団扉座第77回公演『ハロウィンの夜に咲いた桜の樹の下で』に主演。

◆高校卒業後、養成所に通うことに
小学校3年生のときに舞台上で拍手される快感を覚えた山中さんだが、中学・高校で演劇部には入らなかったという。
「演劇をやろうというような土地柄ではなかったですよね。演劇部には男の子がひとりいるぐらいで、そこで一緒にやろうなんていうことは全然思わなかったです」
――高校を卒業すると同時に養成所に?
「はい。僕がその当時知っていた劇団はふたつしかなくて。ちょうどそのうちのひとつが募集していたので受けたら受かって。ちょっとやってみようと思って養成所に行くことにしました。
そこで、『お前、演劇向いているよ』って言ってくださる講師の方がいらっしゃって。僕はその人のことを信用していたので、舞台をちょっとやってみようかなって思って。でも、ここ(養成所)はちょっと違うところだという感じがしていて、演劇をやるところじゃないなあと思ったんですよね。
高校を卒業するときはふたつしか知らなかったけど、世の中に劇団ってこんなにあるんだって、それからどんどん知っていくわけですよ。それで、『これはしまったな、失敗したな』って(笑)。
ただ、僕が信頼していたその講師の方が横内謙介さんの戯曲を使ってレッスンしていたんですね。その当時、横内さんは30ちょいぐらいだったと思うんですけど、その講師の方に『この作家は若いのにすごくおもしろい。お前がもし演劇をこれからやっていくなら、こういう人とやらなきゃダメだ』って言われたことがあるんですよ。
実際に僕たちは、横内さんが若いときに書かれた『夜曲』とか、『ジプシー』とかをレッスンでやっていたんですけどおもしろかったんです。稽古、レッスンが楽しくて。僕は信頼している人(講師)が『この人はすごい!』と言う人と一緒に仕事ができたらいいなって思っていたんですね。
その頃はまだ扉座ではなく、善人会議という劇団名でした。それでもすぐに善人会議を受けようとは思わなかったんですけど、養成所はやめまして。
『ここじゃねえや、俺がやりたいのはもっと違う。つかこうへいだ!』みたいなやつらがいっぱいいたんですよ。そいつらが結局『自分たちで劇団作ろうぜ』ってやるんですね。それで、そこに入れてもらったというか。『来いよ』って呼んでもらって、劇団員の真似事をやりはじめるんです。
そこで、3年ぐらいやったかな? 何人か知り合って、演劇、劇団ってこういうものなんだということがなんとなくわかってきて、自分が舞台俳優みたいな気分になっていくんだけれど、いつまで経ってもお客さんが増えない。結局自分の親戚と高校のときの友人が2、3人来るぐらいで、ずっと一緒なんですよ(笑)。
それで何か手っ取り早くもっと自分のことを全然知らない人に知ってもらいたいって思うようになったんですね。その頃も目立ちたいというか、結構僕は生意気だったんですよ。『俺が一番だ!』みたいな感じで常にいたので。もう少し上に行きたいという思いと、横内謙介さんのところでという思いはずっとあったので、これはそろそろ行くべきかなって。
そのときには扉座に劇団の名称も変わっちゃっていて、別物になってしまったかもって思ったんですけど、とりあえず受けに行こうって決めたとき、扉座が『アインシュタインの子供たち』という作品をやるんですよ。
それを見に行ったら、その作品は横内さんが書いたのではないと。役者たちがエチュードとか自分たちでシーンやセリフを作り上げて、それを横内さんがまとめるというか、形にしての作品だということが書いてあったんですね。
僕はまたそれにすごく興味を持ってというか、『本が書ける人がいるのに、それをやらないで役者が作っちゃうの?じゃあ、もう最強じゃねえかよ。これはおもしろいぞ』って思って。でも、見ておもしろかったかと言ったら、別にさほどおもしろいとは思わなかったんだけど(笑)。
でも、『これは俺イケるぞ。俺この中でやっていけるな』って、そのときに確信というか、何て言うんですかね。根拠なき自信があって。ちょうどオーディションがあったので受けました。オーディションには80人ぐらいいたかな。『これ、俺イケるかもしれないな』って、そのときも思って(笑)。
結局、三次試験で8人ぐらいになるんですよね。その中から4人ぐらい残るかもみたいな感じで。その4人の中に、同期で結局残った犬飼(淳治)というやつがいて。そいつがやったときに、『こいつおもしろれえな、こいつ残るかもしんねえな』とか思ったら、本当に犬飼も残っていて。
僕も結局残れたので、『よし!もう受かったらこっちのもんだ』って。それでちょっと目立ってやろうと思って、その日の夜か次の日の夜に髪の毛をバリカンで刈って特殊な髪型にしたんですよ。
それで、次の日稽古場に行ったら、みんながすっげえあ然とした顔で僕のことを見ていて。そのとき茅野イサムという先輩が僕の顔を見て、『お前は何でそんなふうにしたんだ?クビにするぞ!』って、入ったばかりなのにいきなり脅かされて」
――扉座に入ってみていかがでした?
「もっと『俺が、俺が』ってすごい競争なのかと思っていたら、そんなことはなくて、皆さん優しい先輩方でしたよ。そうでもない先輩もいましたけれどね(笑)。みんな自分の役割をちゃんと持っているんですよね。だから出過ぎないし、やっぱりちょっと出来上がっている感じがありますよね」
――イヤな思いをすることもなく?
「僕はわりと可愛がられたほうですね。たとえば稽古が終わって、『じゃあ飲みに行くぞ』ってなったときに『崇史来い』って僕は飲みに連れて行ってもらえるんですけど、犬飼くんは誘われず、ずっと小道具作りをしているという感じだったから、犬飼くん的には、『何で崇史さんだけ?』ってずっと思っていた。
毎回毎回僕ばかりというのも何だから、『僕もちょっと小道具を作ってから』みたいなことを言っても『いいんだ。お前は来い』っていう感じで。僕が行かないと、たとえば注文を取るとか、酒を注ぐとか作るとか、そういうやつがいないんで、それはそれで必要なんですよ。だから、飲み会の席の小道具係みたいな感じですよね(笑)。
そういう感じでかなり差別的な感じでした。悪いなって思いながらも僕の中では、同期のやつとか、もしくはそのあと後輩ができていくけれど後輩のこととか、あまり気にかけてられなかった。『俺は上に行かなきゃいけない。早く売れたい』って思っていたから。
扉座に入ったのが24で、早く仕事をしたかった。犬飼くんなんかは本当に面倒見がいいんですよ。後輩ができても『大丈夫。いいよ、僕がやっておくよ』ってね。『お茶はこうやって作るんだよ、コーヒーはこれでね』とか丁寧に教えてあげていましたね」
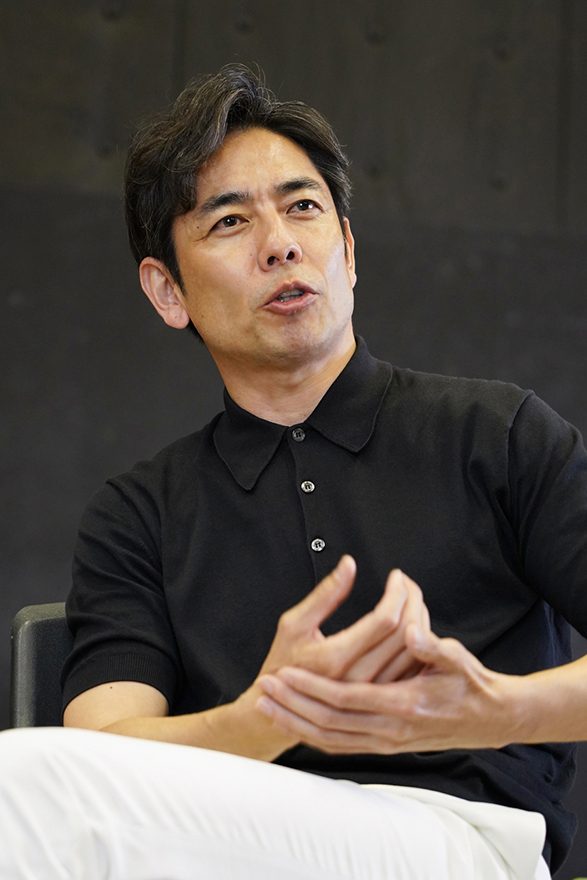
◆強烈なダメ出しに灰皿が…
1995年、劇団扉座に入った山中さんは、その年に『曲がり角の悲劇』で初舞台を迎えることに。
「24、5で扉座に入って、わりとすぐです。僕が初めてやったのが本多劇場で横内さんの『曲がり角の悲劇』という舞台なんですけど、劇団M.O.Pのマキノノゾミさんが演出。劇団がマキノさんに演出してほしいとお願いしたんです。それをマキノさんが引き受けてくださった。
僕は最初は多分、群衆の中のひとりをやることになっていたんだと思うんですよ。それが突然、準主役の役者さんが出られなくなっちゃって。『山中、お前この役やれ』ってことになったんです。『俺、持っているなあ!』って(笑)。
だって、入ってすぐで本多劇場ですよ。僕はずっと本多劇場に立ってみたかったから。それまでは新宿のモリエールとか、築地のブディストホールとかでやったりしていたんだけど本多劇場。僕は『それ見たことか』と。で、稽古に参加して好き勝手やったんですよ。
そうしたら演出席に座っているマキノノゾミさんが『違う!もう1回、違う、違う、もう1回。違う!違う!』って言って、テーブルをバンバン、バンバン叩いて、灰皿を投げて『違う!違う!違う!』って…。ボロボロ泣くんです、マキノさんが。
泣きながら『違うんだよ、違うんだよ。扉座の芝居はこんなもんじゃねえ!』って言われて。それで、僕はもう完全に伸びた鼻をヘシ折られて…。
誰も助けてくれなかったそのとき、僕だけじゃなくて、当時俳優さんだった先輩の赤星(明光)さんが主演だったんですけど、赤星さんもやっぱり『赤星、違う!違う!違う!』って言われていて。
慰めてくれるのは赤星さんぐらいだった。先輩だから、僕が赤星さんを慰めるということはなかったけれど、1カ月間の稽古は本当にもう初っ端から体がおかしくなっちゃって、下痢が止まらなくて、幕が開いてもしばらく止まらなかったですね。
とにかくかなり追い込まれました。別に殴られたりするわけじゃないですけどね。劇団で主役を張ろうとか、そういう役回りって、こんなに責任重いのか…みたいなことをちょっと思いましたかね。
『俺、ここ(劇団)でトップとってやるぜ!』なんていう、ハッタリな感じでいたけれど、そんなんじゃないかもって思って…色々教えてもらいましたね、マキノさんに。
だから、僕が最初に演出を受けたのは、横内さんじゃないんですよ。マキノさんなんです。そんなある日、横内さんが稽古場に見に来て、それでまた『それ違う!違う!違う!』ってなるでしょう。それを横内さんが見ているんですよ。
ダメをもらっているときに、チラッと横内さんを見たら横内さんが、ものすごく集中した顔で僕のことをジッと見ているのが見えたので、『この人今どう思っているんだろうな?』って思ったりしていましたね」
――ずっと「違う!違う!」と言われ続けたのですか?
「ほぼほぼそんな感じでしたね。どんどん稽古が重なっていくと、僕は入ったばかりだし生意気だったけど、先輩たちが見るに見かねて『お前、マキノさんが言っているのは、こういうことだよ』とか、色々言ってくれましたよ。ただね、そんなことを言われてもできなかった。
だから結局、言われたことをやろうと思っていたけれど、『本当に初日、僕は(舞台に)立っていられるだろうか?』っていう不安のほうが大きかった。怖くて。
舞台上で違うと感じたら、もうとてもじゃないけど、役じゃなくて自分に戻っちゃうでしょう? 初めての本多劇場だし…そういう不安とかのほうが大きかったんですけど、初日上演後、すごい拍手だったんですよ。
初日の幕が開いて、2日、3日、4日って続いて千秋楽なんて、もうお客さんが入りきれないんです。本多劇場にお客さんが立ち見でブワーッといて超満員。僕はいい役だったから、それこそカーテンコールなんて、先輩たちより後に出て行って拍手を受けるみたいな感じだったし。いやあ、すごかった。あの経験は本当にすごかったですね」
――昔は通路までお客さんがいっぱいで人の頭越しに舞台を見たりしていましたけど、熱気がものすごかった。懐かしいですね。
「本当にね。僕は若いときにそれを経験できて良かった。また、その作品がある国の戦国時代の若者たちの話で、生きるか死ぬかとか、殺す生かすとか…そういう話だったんです。
その中で一瞬だけの短い恋愛をしたり、失明して目が見えなくなったり…という結構難しい役で。だから、追い込まれたんですけど、若いときじゃなきゃできなかったですね。今あれをやれと言われたら、『できません』って言ってやめちゃうと思う(笑)」
初舞台を成功させた山中さんは、舞台に加え、ラジオのパーソナリティー、そして『相棒』など映像作品にも出演することに。次回はそのエピソードなども紹介。(津島令子)











































































































































