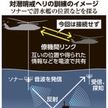デペッシュ・モード(Depeche Mode)といえば全世界でレコード総売上1億枚を突破、海外ではスタジアム規模の人気を誇るのに対し、日本での人気は今ひとつとされてきた。しかし最近では、往年のファンのみならず、若いネットユーザーの間でもデペッシュ・モードを待望する声が年々大きくなっている。1980年の結成以来、このバンドが熱狂的に愛されてきた理由とは?
デペッシュ・モードとは?
1980年から40年以上の歴史を持つイングランド出身のエレクトロニック・ロック・バンド。ヴィンス・クラーク(key)やアラン・ワイルダー(key, dr)の脱退/加入を経て、1995年以降はデイヴ・ガーン(vo)、マーティン・ゴア(key, g, vo)、アンディ・フレッチャー(key)のトリオ編成で活動。2022年5月にアンディ・フレッチャーが急逝し、残された二人はジェイムス・フォード(アークティック・モンキーズ)をプロデューサーに、マルタ・サローニ(ビョーク、ブラック・ミディ)をエンジニアに迎えて、15作目のスタジオ・アルバム『Memento Mori』を完成させた。
Depeche Mode discography 80's
『Speak & Spell』(1981年):「Just Can't Get Enough」「New Life」収録、最初期の明るくポップな作品
『A Broken Frame』(1982年):「See You」「The Meaning of Love」収録、ナイーヴで叙情的な作風に転向
『Construction Time Again』(1983年):「Everything Counts」収録、サンプリングやメタル・パーカッションを導入
『Some Great Reward』(1984年):「People Are People」「Master and Servant」収録、インダストリアルとポップ路線が融合
『Black Celebration』(1986年):「Stripped」「A Question Of Time」収録、耽美でゴシックなダークウェイヴを確立
『Music for the Masses』(1987年):「Never Let Me Down Again」「Behind the Wheel」収録、シアトリカルな音響を獲得
2020年にデペッシュ・モードがロックンロール・ホール・オブ・フェイムへの殿堂入りを果たした際、女優のシャーリーズ・セロンが披露したスピーチが強く印象に残っている。
「デペッシュ・モードは、私の青春時代のサウンドトラックです。冗談ではなく──文字通り私の人生のあらゆる場面で、彼らの曲がそこにあった。初めてのデート、初めて南アフリカを離れたとき、そしてもちろん初めて失恋したときも」
シャーリーズ・セロンは1975年生まれで、10代の多感な時期にデペッシュ・モードの音楽に触れ、彼らの音楽と寄り添って歩んできた世代。『Some Great Reward』(1984年)のヒットで世界的なポップスターの仲間入りを果たしたデペッシュ・モードが、むしろポップ性に背を向けてストイックに深化を進めた『Black Celebration』(1986年)以降、『Music For The Masses』(1987年)、『Violator』(1990年)と傑作を連発していた時期の名曲群に、当時の多感なティーンエイジャーたちと同じく、ほぼリアルタイムでセロンも触れていたはずだ。
3度ノミネートされてようやく叶ったデペッシュ・モードの殿堂入りに対して、“彼らはロック・バンドなのか?“という狭量な議論が起きるであろうことも見越したのか、セロンはスピーチの中で「彼らがロックの殿堂入りを果たしたことは驚きではありません。私に決められるなら、20年前に殿堂入りしていたはず」と言い切った。セロンの主演映画『アトミック・ブロンド』(2017年)に「Behind The Wheel」が使用されたのも、もちろん彼女自身が推したからだ。
カンヌ映画祭で『たかが世界の終わり』(2016年)がグランプリに輝いたグザヴィエ・ドラン監督は、『わたしはロランス』(2012年)でデペッシュ・モードの「Enjoy The Silence」を挿入曲として使用した。主人公のカップルがクラブでダンスに興じる場面で流れるが、この曲の歌詞を踏まえて考えると、性同一性障害に悩んでいることをパートナーに告白できずにいる男性の苦悩を暗示した選曲のようにも思える。
ここ10年ぐらいの劇映画を振り返ってみても、デペッシュ・モードの影響力はよくわかる。『アクアマン』で「It‘s No Good」、『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』で「New Life」、『ラストデイズ・オブ・アメリカン・クライム』で「Personal Jesus」が使用されたし、最近では『コカイン・ベアー』の熊から必死に逃げるシーンで「Just Can‘t Get Enough」がコミカルに使われていたのも記憶に新しいところだ。
TVドラマ・シリーズでの楽曲使用頻度も近年非常に高い。今年1月にも同題のビデオゲームから派生したドラマ『THE LAST OF US』(HBO)エピソード1のエンディングで、物語の展開を不吉に示唆する曲として「Never Let Me Down Again」が使われ、これがきっかけでこの曲はビルボードの歌詞検索チャート「LyricFind U.S.」「LyricFind Global」の2部門でNo.1を獲得。米国内で1週間に552,000ストリームを稼ぎ、Shazamのチャートでも上位に食い込んで話題になった。
『ストレンジャー・シングス』に使われて空前のリバイバル・ヒットを記録したケイト・ブッシュの「Running Up That Hill」もそうだが、80‘sの空気をわかりやすく伝えるニュー・ウェイヴ/エレクトロ・ポップ的なサウンドは2020年代前半の“旬“。テイラー・スウィフト「The Man」の下敷きにデペッシュ・モードの「Just Can‘t Get Enough」があるのは一目瞭然だし、ザ・ウィークエンド「Take My Breath」のアレンジを注意深く聴けば「Enjoy The Silence」が聞こえてくるはずだ。The 1975のマシュー・ヒーリーは昨年アメリカのラジオ局WFPKのインタビューで、デペッシュ・モードから音楽的に影響を受けた部分はそう多くないが、美学的な部分では大いに影響された、と認めている。
音楽性やファッションに見られる「美学」
そのサウンドのみならず、長年一貫性を保っているデペッシュ・モードの個性的なコスチュームやヴィジュアル・イメージも、彼らが多種多様なクリエイターたちから支持される大きなポイント。彼らの“ノワール“なイメージに80年代から貢献してきたキーパーソンが写真家/映像作家のアントン・コービンで、2020年に限定発売された写真集『Depeche Mode by Anton Corbijn』は約10万円という高額にもかかわらず完売、翌年に廉価の普及版が発売された。最新作『Memento Mori』のアート・ディレクション、シングル「Ghosts Again」の監督もコービンが手がけている。
ファッション界に与えた影響も小さくない。2019年には原宿にも店舗があるニューヨークに拠点を置くブランド、NOAHがデペッシュ・モードとのコラボでカプセルコレクションを発売。『Violator』に収められた4曲、「World In My Eyes」「Personal Jesus」「Enjoy The Silence」「Policy Of Truth」をテーマにしたジャケット、ニットウェア、フーディー、Tシャツ、アクセサリーなどを含む計13ピースは、ジャケットやMVから引用したイメージも配され、細部までこだわり抜いたコレクションになっていた。
NOAHの公式サイトに掲載されている文章(署名がないが、恐らく同ブランドのファウンダー、ブレンドン・バベンジンによるものだろう)を読むと、『Violator』というアルバムがリリース当時どれほど斬新に響いたか、具体的に思い出させてくれる。
「デペッシュ・モードは、私たちがすでに愛してやまなかったエレクトロニック・ミュージックに、有機的で新鮮に感じられる方法で、生楽器を織り交ぜる方法を発見したのです。作為的に見えない、テクスチャーのレイヤーを加えて真の経験を構築する新しい方法は、とても受け入れやすく、豊かな想像の世界に没頭することができました」
やはり大きな転機は1990年の『Violator』(全英2位/全米7位)で、ここでジャンルを越えて幅広い影響力を誇るグループへと大きく躍進した。これまでにカバーされた曲を見てみると、「Enjoy The Silence」が圧倒的に多く、パンク・バンドのノー・ユース・フォー・ア・ネイムから、ゴシック・メタル・バンドのラクーナ・コイル、オルタナのナダ・サーフ、果てはR&B/ジャズ・シンガーのパティ・オースティンまでと、数限りないカバー・バージョンが世に出ている。サウンド云々以前に、楽曲の質の高さを認められたがゆえの現象だろう。同じく「Personal Jesus」も凄まじい人気で、ジョニー・キャッシュにニナ・ハーゲン、マリリン・マンソン、デフ・レパードと、まったく異なるジャンルの人々がこぞってカバーしている。
Depeche Mode discography 90's〜10's
『Violator』(1990年):「Personal Jesus」「Enjoy the Silence」収録、バンド史上最大のヒット作
『Songs of Faith and Devotion』(1993年):「I Feel You」「Walking in My Shoes」収録、オルタナの影響を反映
『Ultra』(1997年):「It‘s No Good」「Barrel of a Gun」収録、暗くヘヴィな歌詞とサウンド
『Exciter』(2001年):「Dream On」「I Feel Loved」収録、マーク・ベル(LFO)を迎えてエレクトロニック回帰
『Playing the Angel』(2005年):「Precious」「Suffer Well」収録、新たな黄金期の始まり
『Sounds of the Universe』(2009年):「Wrong」収録、レーベル移籍でより強固になったサウンド
『Delta Machine』(2013年):「Heaven」「Soothe My Soul」収録、ブルージーでオーガニックな円熟の境地
『Spirit』(2017年):「Where's the Revolution」収録、デカダンスな雰囲気を漂わせる貫禄のアルバム
デペッシュ・モードが他のアーティストへ与えた影響について改めて考えるときに、トリビュート・アルバム『For The Masses』(1998年)はやはり外せない。一見遠そうだがダーク・ウェイヴ的な文脈で見ると重なる部分もあるザ・キュアーは、「World In My Eyes」をデペッシュ側に寄せたアレンジでカバー。打ち込みを多用するようになった時期のスマッシング・パンプキンズが「Never Let Me Down Again」を取り上げているのも、英米の国境を越えたファミリー・ツリーが見えてきて面白い。そうしたロック・バンドやテクノ勢などと並んで、デフトーンズやラムシュタインもこのアルバムに参加したことに、影響の広がり具合が如実に表れていると思う。
最新作『Memento Mori』、アウトサイダーを祝福する福音
アンディ・フレッチャーの死後、マーティン・ゴアとデイヴ・ガーンが完成させた最新作『Memento Mori』は、サイケデリック・ファーズのリチャード・バトラーを4曲で共作相手に迎えるという意外な動きはあったが、彼らが培ってきた世界に大きなブレはない。近作で聞かせてきた重量感があるテクノ・サウンドを基調にしながら、彼らにしてはポップな部類の「Ghosts Again」や、80年代の楽曲を思わせる曲調にギターが乗る「Never Let Me Go」も違和感なく収まっている。「My Favourite Stranger」や「Speak To Me」の質感の荒らし方、「Always You」のシンセの処理などは、恐らく前作『Spirit』(2017年)に続いて制作に当たったジェームス・フォード(ゴリラズ、アークティック・モンキーズ他をプロデュース)の存在が効いているのではないか。
左からマーティン・ゴア、デイヴ・ガーン(Photo by Anton Corbijn)
メンバーがインタビューで語っている通り、タイトルの『Memento Mori』は「自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」というラテン語の警句。しかし“死“のトーンがことさら強調された感じでもなく、マーティン・ゴアの「このmemento moriという言葉を『悔いが残らないよう、毎日を精一杯生きる』っていう、より前向きな意味で捉えているんだ」という発言も踏まえて本作を聴きたい。決して明るいアルバムではないが、ジェームス・フォードがソングライティングにも貢献した終曲「Speak To Me」にしても、ほのかに希望をにじませる柔和さが窺える。
歌詞を見ると、脚韻を踏みながら詩的にイメージをまとめている「Ghosts Again」などは、リチャード・バトラーの色が強めに感じられて新鮮。それはそれで味わい深いが、むしろマーティン・ゴアが単独で書いた曲の、抽象性を帯びながらも即効性がある歌詞に目が行く。冒頭から反戦を訴える「My Cosmos Is Mine」は、実は本作の一番最後、ロシアがウクライナへ侵攻した直後に書き上げたそう。しかし言葉を突きつける対象を名指しするような伝統的メッセージ・ソングの形を取らず、普遍的な想いの強さが浮き彫りになるような作りになっている点がいかにもデペッシュ・モードらしい。人間性善説を俎上に乗せた「People Are Good」も言葉数が絞られている分、まるでブルースの詞のように切っ先が鋭く単刀直入。言葉がビートに乗って、スコンと頭に入ってくる。
「Always You」の歌詞にはパンデミックの影を感じるが、ここでのデイヴ・ガーンのボーカルは本作の白眉では。そうした時代背景を切り離しても長く聴けそうな、エモーショナルな名曲に仕上がった。リズムやアレンジでかなり遊んでいるが、メロディメイカーとしてのマーティンの魅力が堪能できる1曲だと思う。
さて、先述のNOAHのコメントでもうひとつ印象的だったのは、デペッシュ・モードと聴き手との間に生まれる特別な“関係“を言語化していたこと。このグループが根強く支持され続ける秘密を、簡潔な言葉遣いで的確に言い表していて感心させられた。
「彼らの音楽には、より深いつながりを促す何かがあったのです。彼らは普遍的な感情を、共感しやすい形で語っていました。(中略)彼らの曲には、人生よりも大きなものに感じられるものがありましたが、その根底には、疎外感や孤独感、真実を伝えるタイミング、至福の追求など、私たちが共感する日常の葛藤が語られていました」
それはそのまま、『Memento Mori』に収められた12曲にも当てはまるのでは、と筆者は思っている。
型通りなポップ・ソングでは埋められない空虚さを抱えてきた人々にとって、心の暗部に語りかけ浸透してくるデペッシュ・モードの詞・曲は“福音“だった。冒頭で触れたスピーチで、シャーリーズ・セロンが彼らの魅力を説明した言葉も忘れられない。
「彼らはアウトサイダーを祝福しているのです。彼らの音楽は、さまざまな人生を歩んできた人たちをひとつにまとめ、〈人と違っていてもいいんだ〉という気持ちにさせてくれます」
セロンは常人では考えられないほどハードな10代を過ごしたことで知られているが、そうした特殊なライフストーリーを持っていない彼らのファンでも、きっと頷ける言葉ではないだろうか。多様性が重視されるようになる遥か以前から、拠り所のない魂を何十年も受け入れ続けてきたデペッシュ・モードが、「限りある人生の残りの日々を寄り添って歩いて行こうぜ」と促してくれる……『Memento Mori』の包容力をそんな風に読み取って、繰り返し聴いている。
デペッシュ・モード
『Memento Mori』
配信リンク:https://depechemjp.lnk.to/MementoMori
デラックス・エディション(完全生産限定盤)
直輸入豪華ケースメイドブック/28ページエクスパンデッド・ブックレット輸入盤仕様
日本語ブックレット・帯付き
2023年5月3日発売予定
デペッシュ・モードが今も愛され続ける秘密 後世のカルチャーに与えた影響を再検証

関連記事
あわせて読む
-

宮脇咲良に「プロではない」「レベルを下げている」と厳しい声も…なぜLE SSERAFIMは韓国でこれほど批判されているのか〈現地記者が解説〉
文春オンライン4/25(木)6:00
-

川平慈英『あさイチ』登場にネット爆笑 博多華丸の代打MC「似すぎw」「朝ドラ受けどころじゃないw」
ORICON NEWS4/25(木)8:23
-

「虎に翼」花岡告白?→急展開ラスト1分にネット衝撃「浮気の方がマシ…」父・直言が贈賄の容疑で勾留
スポニチアネックス4/25(木)8:15
-

「めーっちゃ痩せた」大物芸人の近影にネット騒然…18歳年下女性と4度目の結婚→沖縄プチ移住
スポーツ報知4/25(木)6:38
-

気象予報士の森田正光さん、初期肺腺がん手術からの退院報告「体調も良い」26日から社会復帰へ
日刊スポーツ4/25(木)9:50
-

テレ朝・島本真衣アナ、再婚 40歳、お相手は年上の一般男性 テレ朝「事実です」
スポニチアネックス4/25(木)4:00
-

仲本工事さんの妻・三代純歌が2日連続で週刊誌との裁判に出廷「悪妻に仕向けて書かれた」
日刊スポーツ4/25(木)5:30
-

DAIGO、高校時代の元カノと再会2ショ!「どちらも夢叶えて28年経って再会なんて最高」と反響
スポーツ報知4/25(木)6:30
-

「一番恐れていた反応ばかりだった」長谷部真奈見 娘がダウン症だと周りに伝えるまで3年、友達とのご飯の帰り道も「早く電車を降りたかった」
CHANTO WEB4/25(木)6:30
-
-

フジ元アナ・秋元優里氏、竹林騒動から6年を経て再婚 現在はビジネス推進局で海外担当、お相手は総合商社の幹部クラス
NEWSポストセブン4/25(木)7:15
-

平野紫耀 ヘアケアライン広告キャラクターに就任「是非一緒に試してみてください」
デイリースポーツ4/25(木)8:00
-

広瀬アリスと破局で心配される大倉忠義の〝豆腐メンタル〟 Aぇ!groupのデビューに影響も
東スポWEB4/25(木)5:00
-

朝ドラ「虎に翼」4月26日第20話あらすじ 直言(岡部たかし)の無実を信じて帰りを待つ寅子(伊藤沙莉)ら、しかし逮捕はほんの皮切りに過ぎず…
iza!4/25(木)8:15
-

実力派の局アナがゴールイン続きのワケ TBS安住紳一郎アナ、テレ朝下村彩里アナ、島本真衣アナ…
スポニチアネックス4/25(木)7:15
-

羽生結弦に「時代遅れ感」女優、アイドル教室、ブランド展開…“アスリート妻”の活躍
週刊女性PRIME4/25(木)7:30
-

「虎に翼」漢・轟が愛の鉄拳&W立ち聞き!花岡“涙の改心”ネット反響「轟株天井知らず 梅子さんの度量」
スポニチアネックス4/25(木)8:15
-

本田朋子、昨年出産の“フジ出身ママアナ”3ショットに反響
クランクイン!4/25(木)6:00
-
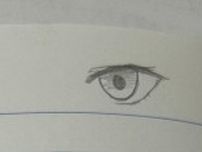
「授業中に片目を描く」落書き癖、小学生→19歳になっても直らなかった結果 ネット唖然「画力上がりすぎ」
よろず~ニュース4/25(木)7:10
-
エンタメ アクセスランキング
-
1

宮脇咲良に「プロではない」「レベルを下げている」と厳しい声も…なぜLE SSERAFIMは韓国でこれほど批判されているのか〈現地記者が解説〉
文春オンライン4/25(木)6:00
-
2

川平慈英『あさイチ』登場にネット爆笑 博多華丸の代打MC「似すぎw」「朝ドラ受けどころじゃないw」
ORICON NEWS4/25(木)8:23
-
3

「虎に翼」花岡告白?→急展開ラスト1分にネット衝撃「浮気の方がマシ…」父・直言が贈賄の容疑で勾留
スポニチアネックス4/25(木)8:15
-
4

「めーっちゃ痩せた」大物芸人の近影にネット騒然…18歳年下女性と4度目の結婚→沖縄プチ移住
スポーツ報知4/25(木)6:38
-
5

気象予報士の森田正光さん、初期肺腺がん手術からの退院報告「体調も良い」26日から社会復帰へ
日刊スポーツ4/25(木)9:50
-
6

テレ朝・島本真衣アナ、再婚 40歳、お相手は年上の一般男性 テレ朝「事実です」
スポニチアネックス4/25(木)4:00
-
7

仲本工事さんの妻・三代純歌が2日連続で週刊誌との裁判に出廷「悪妻に仕向けて書かれた」
日刊スポーツ4/25(木)5:30
-
8

DAIGO、高校時代の元カノと再会2ショ!「どちらも夢叶えて28年経って再会なんて最高」と反響
スポーツ報知4/25(木)6:30
-
9

「一番恐れていた反応ばかりだった」長谷部真奈見 娘がダウン症だと周りに伝えるまで3年、友達とのご飯の帰り道も「早く電車を降りたかった」
CHANTO WEB4/25(木)6:30
-
10

フジ元アナ・秋元優里氏、竹林騒動から6年を経て再婚 現在はビジネス推進局で海外担当、お相手は総合商社の幹部クラス
NEWSポストセブン4/25(木)7:15
エンタメ 新着ニュース
-

山下智久『ブルーモーメント』初回視聴率、フジ水10ドラマ復活以降“歴代トップ”を記録
ORICON NEWS4/25(木)12:51
-

井桁弘恵、絶対領域のぞく“ミニスカ×ニーハイ”スタイル「超かわいい!」「まさに……姫様!」
ORICON NEWS4/25(木)12:48
-

「犯罪都市4」、公開2日目の午前で100万観客突破…驚異的なスピード
WoW!Korea4/25(木)12:45
-

みなみかわ「ちょっと居づらくなったので円満退所です!」生番組で説明「文句言っていたら…」
日刊スポーツ4/25(木)12:44
-

SMILE-UP. 東山紀之社長のインタビューの編集などに対しBBCへ抗議文送付
スポニチアネックス4/25(木)12:41
-

≪韓国ドラマNOW≫「ソンジェ背負って走れ」6話、ピョン・ウソクが嫉妬する=視聴率3.4%、あらすじ・ネタバレ
WoW!Korea4/25(木)12:40
-

キム兄 木村祐一61歳、激やせ? 姿に反響 「ダンディやなぁ」「一瞬、リチャード・ギアかと」
中日スポーツ4/25(木)12:39
-

肺腺がん疑いで手術の気象予報士・森田正光氏が退院報告 10%肺機能失うも「体調も良いです。現代医学はすごい」
サンケイスポーツ4/25(木)12:38
-

NHK朝ドラ「虎に翼」 花岡役・岩田剛典&轟役・戸塚純貴、ビンタ場面から一転、おちゃめにオフショット SNSでは「ほっぺた赤くなってない?!」の声も
サンケイスポーツ4/25(木)12:38
-

ド軍公式X 大谷の「フュージョン・ポーズ」動画公開 ファンから反響「このダンス魔法」「kawaii」
スポニチアネックス4/25(木)12:38
総合 アクセスランキング
-
1

大谷翔平、3戦連発ならずもフェンス直撃の適時二塁打 3二塁打で今季4度目の猛打賞と大暴れ
スポーツ報知4/25(木)10:20
-
2

大谷翔平、赤裸々告白!? 遠征中は真美子夫人に「寂しいと言わせたい」普段は自宅近くを散歩も
スポニチアネックス4/25(木)6:18
-
3

宮脇咲良に「プロではない」「レベルを下げている」と厳しい声も…なぜLE SSERAFIMは韓国でこれほど批判されているのか〈現地記者が解説〉
文春オンライン4/25(木)6:00
-
4

和んだ空気急変も− 大谷翔平の親友喪失への「回答」に称賛の嵐「こんなこと言える人間になりたい」「世界一の人格者ですね」
デイリースポーツ4/25(木)9:07
-
5

川平慈英『あさイチ』登場にネット爆笑 博多華丸の代打MC「似すぎw」「朝ドラ受けどころじゃないw」
ORICON NEWS4/25(木)8:23
-
6

「虎に翼」花岡告白?→急展開ラスト1分にネット衝撃「浮気の方がマシ…」父・直言が贈賄の容疑で勾留
スポニチアネックス4/25(木)8:15
-
7

「めーっちゃ痩せた」大物芸人の近影にネット騒然…18歳年下女性と4度目の結婚→沖縄プチ移住
スポーツ報知4/25(木)6:38
-
8

大谷翔平また全国の子どもたちにプレゼント 今度はマットレス約2500本「一緒に大きな夢を」
日刊スポーツ4/25(木)4:00
-
9

「せっかく褒めたのに」逆効果の言い方にご用心 一流の上司はどんな「褒め方」をしているのか
東洋経済オンライン4/25(木)7:00
-
10

気象予報士の森田正光さん、初期肺腺がん手術からの退院報告「体調も良い」26日から社会復帰へ
日刊スポーツ4/25(木)9:50
いまトピランキング

東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

インド人の彼女に「そのカレー美味しそう」と言うと…? →インドと日本のカレーの認識に驚きの声!
ほ・とせなNEWS4/25(木)12:30
-

トッテナム、「Jリーグワールドチャレンジ」で来日が決定!7月にJ1王者神戸と国立で対戦 さらに“続報”も?
Qoly4/25(木)12:25
-

40歳のテベス、胸の痛みで検査入院…高血圧の影響か
Qoly4/25(木)12:05
-

【AKB48・岩立沙穂、駅弁極めます。】さっほーが「駅弁屋 祭」を直撃!気になる人気No.1駅弁とは?
Walkerplus4/25(木)12:00
-

「5時に夢中!」志麻子&中瀬の下ネタ全開トーク!ゴジムステークスにおかざきなな登場!
TOKYO MX+(プラス)4/25(木)11:55
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
(C) 2024 CCC Music Lab