
第二章「突然の生放送」(9)
短いイントロに続いて切ないボーカルが流れ出し、鋼鉄製のドアが開いた。小さく拍手をしながら、スタジオに陽一が入ってくる。
「いやあ、いいよいいよ。昇太くん、いやサケ茶漬けくん、イイ感じだ。思った通り、ラジオ向きの優しい声をしてるね」
「は、はい、ありがとうございます」
そんなことを思ってたのかと意外に感じながら、昇太は礼を言った。
「それから」
陽一は拍手を止め、穏やかな微笑(ほほえ)みを浮かべて言った。
「恋人さんの想い出。よく話してくれたね」
「あ、いえ。それは……アンジェリカさん相手だと話しやすいし、つい口に出た感じで、夢中で……」
また涙が滲んでくるのを感じながら、昇太は話した。
「うん」
陽一は頷いた。
「昇太くん。それが、真夜中の魔法なんだ」
「魔法?」
どういう意味だろう。
「真夜中というのはね、人々が心の奥底に隠し持っているいろんな想いが、知らず知らず、人知れず、思いがけず溢(あふ)れ出してしまう、そんな時間帯なんだよ」
陽一はアンジェリカを一瞥(いちべつ)し、視線を昇太に戻した。
「深夜ラジオには、あちこちから、様々(さまざま)な想いが集まって来る。嬉しさ、悲しさ、寂しさ、苦しさ、怒り……それら雑多な想いが、今度は逆にマイクからラジオの電波を通して、人々に広がっていく。夜のしじまを通り抜けて、雲間から星々の下を走り、時には時間さえも越えて、世界中に拡散していくんだ」
昇太はこれまで、ラジオのことを陽一が語るようには考えたことがなかった。『手軽で身近なメディア』くらいの印象だったのだ。
――ラジオって、意外と奥が深いものなんだな。
ありきたりな感想しか浮かばない。こんなとき、ボキャブラリー豊富な花音だったらどんなコメントをするだろうか。
「だから僕らラジオマンは、一言一言、心を込めて言葉を紡ぐ。一曲一曲、想いを込めて、音楽をお送りする。これほどやりがいのある仕事はないよ。そうは思わないか?」
彼の熱い思いに賛同するほどに、昇太は自分が恥ずかしくなった。
一言一言想いを込めてどころか、さっきはアンジェリカにリードされつつ、感情にまかせて話しただけだ。

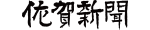











































![[連載・片目のサラブレッド福ちゃんのPERFECT DAYS]ノミと曲芸師(シーズン1-12)](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33747.jpg)



