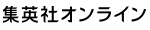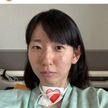101年続いた「週刊朝日」が5月30日発売号でその長い歴史の幕を閉じる。いまやコンビニでも見かけることが少なくなった雑誌だが、元・経済誌「プレジデント」編集長の小倉健一氏は4年後に週刊誌が全滅する可能性を示唆する。今一体何が起こっているのか。『週刊誌がなくなる日 - 「紙」が消える時代のダマされない情報術 - 』(ワニブックスPLUS新書)から一部抜粋、再構成してお届けする。
#1はこちら
#3はこちら
雑誌コーナーが消えたコンビニ…「雑誌売り上げ1%」
2022年初夏、東京・墨田区の両国1丁目に新しいローソンがオープンした。だが、その広い店内に「雑誌コーナー」はない。小さい店舗ならば、それも理解できるが「大きな店舗なのに?」という経験が珍しくない時代に入っているのだ。
インターネット上でも、コンビニオーナーと思われる人による「雑誌コーナーをつくるより、AmazonやNetflixのプリペイドカードを置いた方が儲かる。雑誌はいらない、というより、邪魔だ」というような投稿も、ネット上で見られるようになった。
コンビニの売上に「雑誌コーナー」が占める割合は、日販のデータによれば2002年の7%をピークに年々下がり続けている。今では1%程度で「低位安定」している状態だ。ちなみに、タバコは25・8%。余談だが、コンビニは、あまり知られていないものの、今もタバコに経営を依存する業態ともいえる。

「雑誌売上1%」といっても、近年、宝島社の出版物に見られるように「おまけ付き」の雑誌が増えている。実態は、立派なステンレスボトルやブランドのカバンなどに「雑誌がおまけ」として付いているようなものが目立つ。これでは、もはや雑誌というよりも「雑貨」だろう。コンビニにとって雑誌コーナーは、場所を取る割に売上が低い。さっさと撤去してもいいとみられているのかもしれない。
むしろ、わずか1%の売り上げにもかかわらず、雑誌コーナーを残しているコンビニはなぜそうしているのか、不思議に思えてくる。
それは、どのような経営判断からきているのか。
コンビニの特徴といえば、「目的なく、立ち寄る人」の割合が多いことだ。「2、3日分の食事の材料を買いに行く」などの目的意識が明確なスーパーと比べ、コンビニは1日のうちに何度も来店するリピーターも多い。「朝食を買いに」「ATMでお金をおろしに」「新しいカップ麺はないかなと探しに」などと様々なタイミングや目的で訪れている。無目的でスーパーやドラッグストアに入る人は少ないだろうが、「ヒマ潰しに」などコンビニに足を運ぶ動機は他の店とはちょっと違うのだ。
また、単身者の割合も多い。家族のために買い物に来るのではなく、コンビニは自分のために買い物に来る場所なのだ。そのために「実用性が高い」「コスパがいい」ということよりも、「驚き」「好奇心」などが品揃えの中で重視されていく。
雑誌の「衝動買い」への期待感
「セブン-イレブン」の最年少取締役にもなった本田利範氏は「私は『コンビニは新商品を置く店である』とよく言っています。実際、コンビニには毎週何かしらの新商品が登場しています。すでに好評な商品も常にリニューアルしているため、年間で約7割の商品が入れ替わっていることがあります」(『売れる化』本田利範著/プレジデント社)と指摘している。
スーパーでは日本で一番のシェアを誇る「スーパードライ」が最も売れているが、コンビニでは「スーパーでは手に入らない、サントリーが○○(コンビニ名)のためだけに独自開発したビール」とうたった商品が爆発的に売れているのだ。コンビニに求められているのは「何か変わった商品が出ていないかな」という期待感でもある。実は、毎号話題が変わる雑誌は「常に新商品」という性質を持つ。新聞とは違い、定期購読の割合が極端に低いからだ。つまり、読者はその号の特集によって、買ったり買わなかったりする商品に位置している。毎号、出版社が話題のトレンドを捉えて、読者の「衝動買い」を誘うという狙いに満ちた商品だ。
このコンビニへの「期待感」と「話題が変わる雑誌」は、非常にマッチした。単身世代がフラっとコンビニに立ち寄り、「面白い雑誌ないかな」と探す限り、雑誌の売上は低くとも、雑誌コーナーは販売上の意味を持っていると考えるコンビニオーナーはまだ残っているのだ。

雑誌に求められていた衝動読みがネットニュースに代替
セブン-イレブンが2017年に店舗の新レイアウトに着手した。1日1店舗あたり3万円から5万円の売上アップになった大改革だった。2017年というと、2006年と比較して雑誌の売上が58%減となり、コンビニの売上に占める雑誌の割合が(今とほぼ変わらない)1%程度しかなくなっている状態の時である。
その時でも「雑誌コーナー」は残っていた。セブン-イレブンにとって売上の高いタバコと、雑誌は客を呼び込むと考えられているのだろう。
コンビニの雑誌コーナーが続いているとはいえ、危機が去ったわけではもちろんない。雑誌売上の低迷ぶりは、その雑誌に求められていた「衝動読み」がネットニュースに変わりつつあることを意味する。何か面白い話題はないか、と人が考える時にコンビニよりも身近なスマホを手に取るのだ。
かつて雑誌はコンビニの「主力商品」であった
ある大手流通関係者は今後の「雑誌コーナー」について、次のように予測する。「スマホで得られるネットニュースの方が情報は速く、深く、バラエティに富んでいる。紙の雑誌の役割が終わりつつあるのは間違いない。実際、雑誌コーナーは年々縮小を続けている。当然、コンビニチェーンは『廃止すべき』という議論を毎度のようにしている。ただ、一気になくなるのかというとそうではないだろう。
象徴的なのが、アダルト向けの成人誌、成人コミック誌だ。これだけオンラインで同等の情報が得られる時代でも、細々と存続している。しかも『関連買い・ついで買い』と呼ばれるものが見込める。たとえ雑誌自体の売り上げは1%しかなくても、成人誌やコミック誌を買う人は、飲み物やお惣菜、たばこなどの『ついで買い』が見込める。
高齢者がメイン顧客であるコンビニにとって、雑誌コーナーでの立ち読みは一つの習慣になっている可能性が高い。また、地方では書店がどんどんなくなっており、本が置いてあるのはコンビニだけという実態もある」

かつて雑誌はコンビニの「主力商品」であった。集客力もあった。だが、スマホの時代に突入し、雑誌は低迷している。休刊やネットへの転換が相次ぐ。販売の大半をコンビニに頼っている大手週刊誌にとって、コンビニの雑誌コーナーが減っているという現状は悪夢としかいいようがない。週刊誌は減り続ける売り場に対して、どこまで耐えることができるのだろうか。
恐怖の予測「週刊誌は4年以内に全滅」
2021年の「出版物販売額の実態」(PDF版・日販)によれば、「雑誌(紙)」の販売額は、2006年比で58・6%減と壊滅的な減少を示している。また、2015年に5960億円あった販売額は毎年500億円程度の売上減で、最新データの2020年では3582億円となっている。このまま500億円ずつ減少していけば、「2027年には雑誌の売上はゼロ」になる計算だ。
こうした状況を予測し、2017年に経済誌『ダイヤモンド』を発行するダイヤモンド社内で議論された内容は、驚くべきものであった。「最悪のシナリオでは、2027年に〈紙の週刊誌〉はなくなる」。実際、ダイヤモンドの社内では「最悪シナリオよりも速いペースで〈週刊誌〉の売上が減っている」ことが確認されているという。

特に心配なのが、コンビニに売上を頼っている雑誌である。書店数8789店舗(2020年度)に対し、コンビニは5万6948店(2021年1月現在)もある。コンビニに搬入されるのは限られた雑誌だが、大手経済誌の一つは「実売率が低く、コンビニの売上で利益が出るような水準にはない」としながらも、部数維持・ブランド維持・販売体制維持のためにコンビニ搬入をダラダラと続けているという。
ある大手流通関係者は「コロナ禍にあっては、外国人客が激減し、『巣ごもり消費』が起きたことで雑誌コーナーは生きながらえた部分があった。しかし、年10%程度の売上減が今後も続くことを前提にして、雑誌コーナーはコンビニ各社が始める新サービスに置き換わっていくだろう。地方では『本屋不足』が起きており、本の棚を拡充して雑誌コーナーは維持されるが、全体で見れば限定的だ。最近では、Amazonの『コンビニ受け取り』とメルカリの『荷受け』を始めたことがスペースの減少につながった。コロナが収束すれば何が起きるかわからない」と指摘する。
「オンライン編集長」は「紙雑誌の編集長」より職位が低い
4年後には全滅するかもしれない「紙の雑誌」。著名媒体の編集部員たちにこの事実を突きつけてみると、危機感を口にはするものの新たな行動を起こす気まではないように見える。オンライン編集部に「紙の雑誌」編集部の主力が投入されないのも、そうしたことの表れかもしれない。
その理由を聞くと、「社内での職位が『紙の雑誌の編集長』よりも、『オンライン編集長』の方が低い。『紙の編集部』の副編集長クラスが、『オンライン編集長』だ」「『紙の雑誌』には歴史がある。経営陣は『紙の時代』しか経験していない」という。ただ、確かに仮にデジタルに軸足を移し「主力」とみなすにしても、広告収入に頼りきる無料ニュースの「一本足」だけでいいのかというのは甚だ疑問だ。
有料デジタル化の強みは、優良な読者からの「ロイヤリティ(忠誠心)」だ。無料ニュース編集部を悩ませるのは、記事ごとに起きる読者の大変動にある。アフリカ・サバンナの「グレイトマイグレーション(動物の大移動)」のごとく、今日の読者が明日いるとは限らない。さらには、Googleから得られる広告単価もコロナ禍で激減したというトラウマもある。安定的な収入を得るのは難しく、危機が起きてもいいようなコストでしか記事をつくることができていないのだ。無料ニュースの編集部には、全くといっていいほど余裕はない。

有料デジタル化によって、課金する読者に「メディアを使い倒そう」という意識が強くなり、PVは安定していく。そもそも、PV獲得のみを目指した記事をつくる必要性が低くなり、ヤフーニュースやスマートニュースなどといったプラットフォーマーからの要望に対して余裕を持って対応できる。それは、無料ニュースよりも広告価値が高い読者を抱えることを意味する。有料デジタルは「紙の雑誌」と親和性が高く、事業が軌道に乗るまでの初期コストを回収できれば、たとえ中小出版社であっても、存在感のある雑誌は高い収益率をもって存続していくことが可能になる。成功すれば、いいことずくめなのが有料デジタルといえる。
結局本当のバカは誰だったのか
しかし、初期コストは高く、中小・零細出版社にはデジタル人材が決定的に不足しており、「いろんな人が来て、いろんなことを提案したものの、経営者にはどれが正しいのか最後までわからなかった。紆余曲折を経て、誌面のPDFをそのまま売ることになったが、特集で最も力を入れた誌面が200円でたった3部しか売れなかった」(有名雑誌を発行する中堅出版社)というのは笑えない話だ。
紙の雑誌と並行して有料デジタル化をいち早く決めたのは経済誌『週刊ダイヤモンド』編集部だった。先の「2027年、紙の雑誌消滅」を予測してのことだったが、ダイヤモンドが有料デジタルを始めた時、ライバル社は「何億円もかけて、全然会員を獲得できていないではないか。バカなことをやっているな」などと悠長に眺めていたものだ。週刊誌編集部も同様で、ダイヤモンドに追随しようとする「バカ」は現れなかった。
しかし、ダイヤモンドはその後、順調に有料会員を獲得し、独走状態に入っていった。紙の週刊誌が消えてなくなっても、独り立ちできる状態にまでなっている。ダイヤモンドが「バカ」だったのではない。他社こそ本当の「バカ」だったのだ。
#1「『馬鹿が俺らの嘘を本気にしている』潜入!フェイクニュース製造村の実態…」はこちら
#3「ヤフコメで「いいね!」を集める40代劇団員の手法とやりがい…」はこちら
『週刊誌がなくなる日 - 「紙」が消える時代のダマされない情報術 - 』
(ワニブックスPLUS新書)
小倉 健一
¥990
216ページ
ISBN: 978-4847061974
コンビニから雑誌コーナーがなくなり、都内の書店も減少傾向にある現在。スマホで誰もがニュースや新聞を読める中、紙の週刊誌は消滅の危機にある。電子書籍化、ウェブサイト化も進んでいるが、勝ち組・負け組の格差は広がるばかり。メディア戦国時代をどう生き抜くか。読者はどう効率的に情報を収集すべきか。元『プレジデント』最年少編集長が解説するメディアの現在と未来。
○内容より
第一章:メディアの最前線で何が起きているか
第二章:紙のメディアは5年で消える
第三章:儲かるメディア、死ぬメディア
第四章:デジタル化で起きる大問題
第五章:メディアを使い倒せば情報強者になれる
発行:ワニ・プラス
発売:ワニブックス