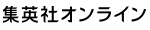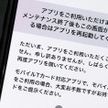コロナ禍のせいで、それまで外国からの労働力を頼っていた農業現場は深刻な人手不足に陥っている。さらには生産問題だけではなく、農作物を消費者に届ける流通システムにも危機が迫っているという。こうした日本の農業の危機を『人口減少時代の農業と食』(ちくま新書)より、一部抜粋・再構成してお届けする。
食卓をおびやかすのは「2024年問題」
われわれ日本人が、四季や土地を問わずに、さまざまな種類の農産物を味わえるのは、物流の発達が大きく寄与している。自分の地域では作っていない、あるいは作れない農産物であっても、物流業者が遠隔地の産地から野菜や果物を安定して届けてくれる。食卓に彩りがもたらされるのは、全国にくまなく物流インフラが整ったおかげであるといえる。
ところが、当たり前と思われてきたこの日常に、いま、陰りがさしている。食卓をおびやかすのは「2024年問題」だ。
労働基準法の改正により、物流業界では2024年4月1日以降、年間の時間外労働時間の上限が960時間に規制される。すなわち、残業時間は月平均して80時間が上限となる。これは、もちろんドライバーも対象である。
物流業者は違反すれば、「6カ月以下の懲役」、または「30万円以下の罰金」が課せられる。
これによって発生する諸々の問題の総称が「2024年問題」なのだ。
もちろん、その影響は農業界にとっても深刻だ。
とくに頭を抱えているのが、北海道や九州、沖縄といった遠隔の産地である。現状の物流体制では2024年から、質と量の両面で従来のように農畜産物を大消費地に送り届けられなくなるからだ。

関東で「あまおう」が食べられなくなる
たとえば、福岡県にとって戦略的な品目のひとつにイチゴがある。そのブランドといえば、イチゴ界の「西の横綱」と称される「あまおう」。
県内の産地は鮮度を維持するため、集荷してから3日目までに関東地方の卸売市場で販売を済ませてきた。それができるのは、物流業界に残業規制がなかったことが大きい。これまでは、ドライバーに多少の無理を強いてきたわけである。言ってみれば、「ブラック」といえるような働き方も通ってきたわけだ。
ところが、先述のとおり、2024年4月1日以降はそれが許されなくなる。
その結果、3日目までの販売がかなわない。今よりも1日や2日遅れるとなれば、鮮度を中心とした総合点において、関東地方の競合産地に勝てる見込みが一気に薄らぐ。
種が持つ力は偉大である。ただ、全国流通が当たり前になった現代において、それを生かすも殺すも物流に負うところはあまりに大きい(図表1–2)。

止まらないドライバー不足
もとより、ドライバー不足には歯止めがかからない。鉄道貨物協会によると、全産業におけるトラックドライバー数をみると、2017年度は10.3万人の不足だった。これが2025年度には20.8万人、2030年度には27.8万人と増えると予測している。一方で、EC(電子商取引)市場が急成長したことにより、宅配便の取り扱い個数は急増しているのだ。ドライバーは減っているのに、需要は増している。このままでは、物流環境は悪化するばかりである。
「2024年問題」が、これに拍車をかけるのは必至だ。九州トラック協会によると、費用対効果が悪い農畜産物は、すでに輸送するのを真っ先に断られる対象になっているという。
迫りくる困難への対処は一通りではない。
たとえば、農産物を生産してから在庫管理して、配送や販売、消費に至るまでの一連の流れを適切な低温度帯に保つ「コールドチェーン」の構築だ。現状、少なくない産地が予冷せずに輸送している。予冷庫を備えた物流拠点を整備すれば、今まで以上に鮮度を保持できるので、輸送にかかる日数を延ばせる。

「2024年問題」に対して、一つで解決できる方法などない
コールドチェーンについては、卸売市場も取り組むべき課題だ。産地で予冷して、冷蔵車で輸送されてきたのに、卸売市場で保冷する施設が整っていないことが目立つ。
段ボールなどを載せる荷役台「パレット」や、一トン程度の穀物を収容できる袋材「フレキシブルコンテナ(フレコン)」といった、効率的に輸送できる資材の活用も無視できない。現状は、段ボールを一つずつトラックに載せたり、コメについては30キログラムという小袋を使ったりしているから手間がかかる。
加えて、流通業者が身近な産地と提携することで、輸送にかける時間や燃料代を抑えるという決断もありうる。
「2024年問題」に対して、一つで解決できる方法などない。一方で、サプライチェーンを見渡せば、取り組むべき課題は数多い。関係者を挙げて、できることを積み重ねることが欠かせない。
集出荷施設の老朽化で青果流通に不安
JAが所有している青果物の集荷と出荷の機能を持つ施設(以下、青果物集出荷施設)が老朽化し、各地ではその再編が課題になっている。青果物の流通の要である施設の更新なくして、これからの産地はありえない。
とはいえ多額の投資をして青果物集出荷施設を新しくしたところで、受益者である農家が減る中では採算性を確保できるのか不透明だ。すでに北海道を除く都府県のJAの9割ほどは、農畜産物や農業資材、食品や日用雑貨品の売買といった農業に関係の深い経済事業は赤字である。それを信用(銀行)事業と共済(保険)事業(併せて金融事業)で穴埋めをしている。
ただ、これまた人口減に伴う顧客数の減少や超低金利などのあおりを受けて信用事業の先行きも危うい。おまけに共済事業も、JA離れで契約数は減ることが懸念されている。だからなおさら青果物集出荷施設への投資には慎重にならざるをえない。

まずは、青果物集出荷施設とは何かについてあらためて説明しよう。これは文字通り、農家が作った野菜や果物などの荷物を受けて、規格に沿って選別して荷造りし、ときに予冷や貯蔵をしながら、卸売市場や量販店などに出荷する機能を持った施設である。JAが一連の作業を一括して請け負うことで、農家は個別にそれらの作業を負担させられることがなくなり、営農に集中できるようになっている。
その青果物集出荷施設は、全国にどれくらいあるのだろうか。農水省がまとめている「農協についての統計」によると、施設の数は2015年に4410だったのが2020年には4179にまで減っている(図表1–3)。

無責任な農水省。老朽化の実態を調査していなかった
では、このうち更新の時期を迎えている施設はどれだけあるのだろうか。農水省に尋ねたところ、「調査はしていない」とのこと。物流危機が国家的な課題になる中、青果物集出荷施設の再整備もまたそこに位置づけられてしかるべきである。それなのに実態を把握していないのは、無責任な話ではないか。
代わりに頼りになるのが、農林中金総合研究所の尾高恵美主任研究員による論文「農協における青果物共同選果場の再編に向けた合意形成」(「農林金融」二〇一八年一二月号)だ。尾高主任研究員はこの論文で、JAの有形固定資産の老朽化の度合いを示す「資産老朽化比率」を試算している。この比率が高いほど、耐用年数が迫っていることを意味する。
その試算によると、1990年度は54.3%だったのが、2000年度には62.2%、2015年度には71.6%にまで上がっている。2016年度には設備投資の回復で71.4%とごくわずかに下がったというのものの、依然として高い水準であることに変わりはない。

集出荷施設の稼働率の方が下がっている
さらに尾高主任研究員は、青果物集出荷施設の減少以上に稼働率のほうが下がっている事態を懸念している。
具体的には、青果物集出荷施設の数は、2007年度に4706だったのが、2016年度には4388と、9年間で6.8%減少した。
一方、青果物集出荷施設の需要量については、果物の二大主力であるリンゴとカンキツ類の栽培面積と出荷量でみている。すなわち2007年から2016年の栽培面積は、リンゴで4万2100ヘクタールから3万8300ヘクタールへと9.0%減、カンキツ類で8万2000ヘクタールから7万1000ヘクタールへと14.5%減となった。
加えて、リンゴの同期間の出荷量は74万8700トンから68万4900トンへと8.5%減となった。カンキツ類については、論文発表時に16年の統計が出ていなかったためか、2007年から15年の期間で比較している。つまり、127万622トンから95万7719トンへと24.6%減となった。尾高主任研究員も説明するように、出荷量については天候の影響や着花や着果の年次変動があるので一概に比較はできない。ただし、右肩下がりで来ているのは確かである。
以上を踏まえると、青果物集出荷施設の稼働率が低下する傾向にあることがうかがえる。
もちろんそれは、青果物集出荷施設の採算性の悪化のほか、施設の利用料が上がるという点で農家に悪い形ではねかえってくる。
青果物集出荷施設をどう再整備するのか。人手が必要な作業をロボットに任せたり、複数のJAが地域の壁を越えて共同で施設を運用するなど、やれることはたくさんあるはずだ。JAには、従来の枠にとらわれない柔軟な発想と実行力が求められている。
『人口減少時代の農業と食 』(ちくま新書)
窪田 新之助 (著), 山口 亮子 (著)
¥1,012
新書 : 304ページ
ISBN: 978-4480075543
人口減少で日本の農業はどうなるか。農家はもちろん出荷や流通、販売や商品開発など危機と課題、また新たな潮流やアイデアを現場取材、農業のいまを報告する。
日本農業にとって人口減少は諸刃の剣といえる。これまでのあり方を一部で壊してしまう一方で、変革の推進力にもなる。農産物の生産や流通は、総じて人手不足で、生産者と流通、販売、消費の間の溝やズレも明らかになっている。ピンチをチャンスに変えるべく、こうした課題に立ち向かう現場がある。生産から出荷までの合理化、消費者と直接つながる商品の開発、物流のルール変更への対応……。世間で思われているほど暗くない、日本農業の未来を報告しよう。