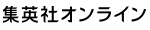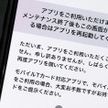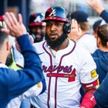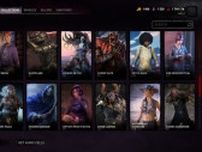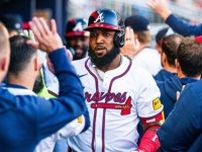事務次官は、官邸主導人事のため省庁の幹部が政治家に「忖度」しているとの批判も絶えない。『事務次官という謎-霞が関の出世と人事 』(中公新書ラクレ)から、今回は幹部人事の歴史や、各国の公務員制度と比較検証して、内閣人事局に内在する危険性に迫った章を一部抜粋・再編集してお届けする。
#1
#2
#3
戦前からのキャリア官僚である彼らのプライドをひどく傷つけた
内閣人事局の発足から9年、キャリア官僚にとって命の次に大事な人事をこの一組織に握られた結果、霞が関からは不平や不満の声が後を絶たない。内閣人事局については、これまで本書でたびたび触れてきた。本章では幹部人事の歴史や、各国の公務員制度と比較検証して、さらにその功罪についての考察を深めていきたい。
まずは戦後のキャリア人事の推移を駆け足で辿ってみる。
戦前のエリート官僚の代名詞である高等文官試験(高文)合格者の伝統は、戦後もほとんど改革されることなく引き継がれた。GHQによる公職追放や農地改革などは厳しく断行されたが、官僚制度改革は米ソ冷戦構造が深刻化するにつれ、抜本的な改革をためらわせる空気が支配的になったからだ。
そのため、キャリア制度は何ら法律に規定されることなく、慣例として戦後もしぶとく生き残った。国家公務員法では、資格任用を官僚人事に適用するため、採用試験だけでなく昇進の時にも競争試験を課すことを原則としていた。同法第三十七条(昇任の方法)は「職員の昇任は、その官職より下位の官職の在職者の間における競争試験によるものとする」(第一項)と規定、競争試験が選考の前提になっていたのだ。
実際、公務員法施行二年後の1950(昭和25)年に局長・審議官などの幹部を対象に実施されたが、戦前からのキャリア官僚である彼らのプライドをひどく傷つけたようで、「多忙な仕事の合い間に、こんな試験などやっていられるか」と不満が噴出し、一年実施しただけであとは沙汰止みとなってしまった。

一度国家公務員試験に合格してしまえば、ほぼ永久就職
その結果、一度国家公務員試験に合格してしまえば、ほぼ永久就職の形で身分が保証された。しかも、試験の成績が入省後も一種の背番号のようについて回り、出世を左右する目安として使われた。といっても、成績に応じてその後の出世が明確に決まった旧海軍の「ハンモックナンバー」ほどではなかったが、各省庁の幹部の序列は試験によってほぼ決まっていたと言っても過言ではない。
国家公務員法上、人事権は大臣にありとされたが、実際はキャリアの仲間うちで人事が決められてきた。各省の中核機能である秘書課長―官房長―事務次官のラインが策定する人事構想を、時に大臣が一部の差し換えを命じたとしても、大方は構想通りに認められてきたのが実態であった。
戦後高まった民主化の掛け声とは裏腹に、キャリア制度はかつての高文官僚の伝統を後生大事に死守してきた歴史といえる。極論すれば、1886(明治19)年の各省官制創設以来、キャリア制度の根幹は何ら揺らぐことなく引き継がれてきたのが、日本という国のかたちでもあるのだ。
橋本内閣が設置した閣議人事検討会議
そうした大河のような流れを、百数十年ぶりに変えようと試みたのが内閣人事局だが、そこに至る以前に制度改革に手を着けた時期があった。橋本龍太郎内閣の1997年、官房長官と三人の副長官からなる閣議人事検討会議を設け、そこで局長以上の幹部人事を審査した後、閣議で承認する方法が導入された。
この時期は、大蔵省不祥事が燎原の火の如く燃え広がり、過剰接待を受けて批判を浴びた幹部公務員が次々と槍玉に挙がった。閣議人事検討会議はそんな人物を事前に厳しくチェックし、ふるいにかけた上で閣議承認により内閣の任命責任をより明確化することに狙いがあった。
対象になったのは局長級以上の約200人で、幹部公務員人事に多少のメスを入れることにはなったが、根本的な改革にはほど遠かった。なぜなら、正副官房長官が参加する閣議人事検討会議に諮って正式決定するタテマエにはなっていたが、府省案がひっくり返ることはほとんどなく、原案を追認するだけの通過儀礼に過ぎなかったからだ。
この背景には、政治家から人事に手を突っ込まれることを極端に嫌う官僚特有の防衛本能が強く作用し、閣議人事検討会議という器はつくっても骨抜きになる状態が続いた。このマイナーチェンジから17年後の2014年、政治主導を前面に掲げる安倍晋三首相の強い意向により満を持して内閣人事局が設置され、閣議人事検討会議の骨格を法制化するとともに、対象人員を大幅に拡大して政治任用化への道へ突き進むことになる。

触らぬ神に祟りなし
新たな制度では、各府省の人事評価をたたき台に、官房長官が適格性評価を行い、内閣人事局が幹部候補者名簿を作成する。これを受けて、各大臣は名簿をもとに事務次官や局長、審議官など幹部の人事案をつくる。この人事案を首相、官房長官、大臣の3者が協議して、最終的に幹部の昇進や異動を決定する。
三者が判定する幹部人事の範囲は、当初は局長級以上の約200人を対象としていたが、内閣人事局発足の直前になって審議官級以上の600人へ3倍に拡大した。人事権を官邸に集中することにより、自らの省益を優先する動きを抑え、縦割りの弊害を排除しながら政治主導の政策決定を進める点に主眼が置かれた。
ここまでは制度の説明だが、問題はこれをどう活用するか、運用面の課題が早くから指摘されていた。官僚から見て、その最大の懸念は幹部候補者の名簿づくりにあり、大臣の思惑を超えて官邸が登用したい人物を無理矢理入れたり、逆に評価しない人物を外したり、恣意に流れるのではないかという危惧があった。
「官邸の意向」―内閣人事局の発足と歩調を合わせるように、この言葉がしばしばマスコミに登場するようになる。人事権の最後のグリップを握る官邸(この場合は首相と官房長官)が強大な権限を持ち、彼らに逆らうと人事で報復されるかもしれないと、幹部公務員たちは身構えるようになったのだ。
その結果、反射的に官僚たちの口から出たのは、「忖度」という言葉である。「官邸の意向だから何を言っても仕方がない」と諦めの心境がはびこり、触らぬ神に祟たたりなしという風潮が、霞が関全体に蔓延していったのである。
内閣人事局は過去何十年と積み上げられてきた評価を
知らぬままに人事権を行使
内閣人事局に内在する危険性を、発足前から指摘していた財務省の次官経験者がいた。その中核に位置するのが「人事評価」であり、この扱いが人事にどう反映されるかがポイントになるとして、こう語った。
「その人物を、誰が評価するのかという問題がある。各府省は20年、30年と一緒にやってきた上司がいて―もちろんそれでも人物評価にはバイアスはかかるが―すべてを知った上で人事評価する。それに対して、内閣人事局は過去何十年と積み上げられてきた評価を知らぬままに人事権を行使する。まして、最後の与奪の権を握るのが政治家となれば、評価の対象が「あいつは愛奴じゃ」といった極めて表面的な好き嫌いの感情が判断材料になるのは人の世の常だろう」
そういう構図が予想されるのであれば、当然、官僚は忖度に走る。これもまた必然の道理であると、次官経験者は続けた。
「たまたまある事案を担当し、官邸にしばしば通って人事権者の覚えがめでたくなる。その結果として、府省内のコンセンサスとは違った抜擢人事が行われると、自分もしばしば通ってゴマを擂すったほうが得、盾突いたら損と自己規制を始める。あまり好きな言葉ではないが、猟官運動に走る輩やからが出てくるのは不思議ではないし、官僚とて人間集団だからいろいろな人がいて、ぎらついた思惑で動くのは避けられない」

「抜擢」か「左遷」か…当然、官僚は忖度に走る
内閣人事局創設の前後から霞が関で交わされ始めた微妙なささやきの声は、いざ制度がスタートするにつれ具体的な輪郭を伴って現実化していった。事務次官、あるいはそれを目前にした局長人事で、「抜擢か」「左遷か」―それらをあえて一言で片づければ恣意的人事と言えるのかもしれないが―判断を迷わせる異例な人事が目につくようになった。
ここに取り上げる事例は、霞が関で話題を集めただけではなく、マスコミなどに取り上げられたケースであり、概して「過去の慣例を破った」人事の数々である。今更筆者がしたり顔で解説するまでもなく、人事は「ひとごと」とも読めるように、人が人を評価して任免を決める行為だけに、決定までには好き嫌いを含めたさまざまな感情が入り交じりながら一つの結論に収斂していく。
内閣人事局の中でどのような会話が交わされたのか、中でも首相、官房長官、各府省大臣による三者協議で、最後の決定打となるどんなやり取りが交わされたのか。そのすべてとは言わないまでも、人事を決定づける三者の片言隻句でも耳にしない限り、公表された人事をあれこれ詮索するのは、本来、的外れの批判を免れないかもしれない。
異例の人事の数々…年功序列、順送りの慣例を崩した人事
何やら自己弁護に似た言い訳を書いたが、要するに、これから取り上げる事例は日本のキャリア官僚制度の代名詞ともいえる年功序列、順送りの慣例を崩した人事といっていい。それが、内閣人事局発足に伴って起きた事例なのかどうかは証明のしようがなく、霞が関での話題やマスコミの記事を参考にするしかないので、登場人物は実名は避けてイニシャルで書くのをご容赦願いたいと思う。

[2015年7月]
◯金融庁の人事で、M監督局長が大方の予想より一年前倒しで長官に就いた。Mは金融行政の見直しを積極的に進め、早くから将来の長官と目された本命ではあったが、年功序列の色彩が強い財務省系列の役所では前例や慣習を破った人事と受け止められた。その結果、前任のHは二年間務めるであろうという金融業界の予想を覆し、一年での退任を余儀なくされた。その要因に、官邸が求めた農協改革に絡む協力依頼に対し、消極的だったことが不興を買ったと見られた。
◯総務省自治税務局長だったHが、自治大学校長への異例の人事を発令された。自治税務局長は同財政局長と並ぶ出世コースであり、次期次官就任が確実というわけではないが、いきなり自治大学校長への転出は誰の目にも「左遷」と映った。ふるさと納税で限度額の引き上げを主張する菅義偉官房長官に、Hは高所得者の寄付額を制限する案を進言し、即座に却下された。その後、上司からは「予定していた昇格人事が官房長官の意向で覆された」と聞かされたという。
[2016年6月]
◯農林水産省の次官に、O経営局長が就任した。Oは農協を監督する経営局長を約五年間務めて、全国農業協同組合中央会(JA全中)を一般社団法人に転換するとともに、JAグループの反発をかわして農協法を改正した実績を買われた。特にこの分野の改革には、菅官房長官がご執心といわれ、その要請に応える形で異例の次官就任となった。
農水省の場合、次官の最短コースは水産庁長官や林野庁長官とされ、農協改革一筋に実績を上げたとはいえ、経営局長からの昇格には意外感が強かった。また、前任の次官はOと同期だが、定年を前にしてわずか10ヶ月で退任を余儀なくされた。
[2017年7月]
◯学校法人「森友学園」への国有地売却問題が国会で厳しい追及を受ける中、財務省の担当局長であったS理財局長が国税庁長官に昇格した。国会答弁で事実確認や記録の提出を拒み続け、「真相解明に消極的」と批判を浴びたSだったが、麻生太郎財務相は「国税庁次長や大阪国税局長といった税の関係をいろいろやっているので適材」と人事を正当化した。野党からは「森友問題の功労者として出世させた」との厳しい指摘も出た。
◯この人事とは対照的に、国有地の売却価格算定問題を追及され、国会答弁がしどろもどろになった国土交通省のS航空局長は退任に追い込まれた。航空局長は国交省の局長の中でも次官への最短コースと見られており、答弁のまずさが官邸の怒りを買い、結果として次官への道が絶たれたと受け止められた。
渦巻く怨嗟の声…人事は
安倍首相や菅官房長官の独断で決まったのか
巷間に伝わるように、一連の人事が安倍首相や菅官房長官の独断で決まったと結論づけるのは難しい。繰り返しになるが、最後は三者協議に委ねられるとはいえ、そこに至るまでの過程で秘書官を長く務めたとか、政策論で擦れ違いが起きたとか、関係者の間でさまざまな思惑が絡み合うからだ。
ただ、ここに取り上げた人事の数々は、霞が関の話題を大いに集めただけではない。人事の度に官房長官から発せられる次の一言が、官僚たちのさらなる疑心暗鬼を増幅する効果をもたらした。
「適材適所」―人事権を握る政治の側が、すべての人事をこの一言で片づけてしまえば、官僚の側はただ現実を黙って受け入れるしかない。人事権者にとって極めて都合のいい言葉だが、発令される身にとっては「そう決定した評価基準を明確に示してほしい」と、文句のひとつも言いたくなるのが人情というものだろう。次官、局長級の幹部はすでに三〇年前後のキャリア経験があり、それまで蓄積されてきた人事評価が顧みられることもなく、最終段階にまで辿り着きながら官邸の一存で黒白をつけられるのは耐えられない、と不満を抱いたとしても不思議ではない。

官邸に好かれると偉くなれる、嫌われると外される
霞が関に充満する怨嗟の声を拾うと、
「恐怖心で人事を操るのはやめてもらいたい」
「政策は本来大臣が責任を持って決めるのであり、官邸が人事権を盾に政策議論を都合良く誘導するのは弊害が大きい」
「官邸に好かれると偉くなれる、嫌われると外されるといった傾向が強まり、各府省ともエース級の人物で辞める人が増えている」
こうした声が渦巻く背景には、安倍首相の長期政権が続き、安倍―菅の政府首脳が長らく幹部公務員の人事を掌握していた現実があった。とりわけ、菅官房長官は著書『政治家の覚悟』(文春新書)の中で、「私は、人事を重視する官僚の習性に着目し、慣例をあえて破り、周囲から認められる人物を抜擢しました」と明言しており、抜擢された人物は満足するだろうが、その背後に傷つく人物が何人もいるはずで、人事の一面だけを見ていると内閣人事局の本質を見誤ることになる。
#1『「胸、触っていい?」のハレンチ「福田淳一元財務次官」はテレ朝記者にセクハラ…1.7年に1人辞職!「次官の地位は堕ちるところまで堕ちた」』はこちらから
#2『なぜ最強官庁・財務省では非常識な不祥事が相次ぐのか…若手官僚によるパワハラ上司ランク「恐竜番付」の中身とは』はこちらから
#3『ハレンチ辞職のあの次官も…癒着を指摘される危険もあるなか、なぜSBIは財務省からキャリア天下りを6人も受け入れたのか』はこちらから
『事務次官という謎-霞が関の出世と人事 』
(中公新書ラクレ)
岸 宣仁 
1012円
280ページ
ISBN: 978-4121507945
「事務次官という謎」を徹底検証!
事務次官、それは同期入省の中から三十数年をかけて選び抜かれたエリート中のエリート、誰もが一目置く「社長」の椅子だ。
ところが近年、セクハラ等の不祥事で短命化が進み、その権威に影が差している。官邸主導人事のため省庁の幹部が政治家に「忖度」しているとの批判も絶えない。官界の異変は“頂点”だけに止まらない。“裾野”も「ブラック」な労働環境や志望者減、若手の退職者増など厳しさを増す。
いま日本型組織の象徴と言うべき霞が関は、大きな曲がり角を迎えているのだ。事務次官はどうあるべきか? 経験者や学識者に証言を求め、歴史や法をひもとき、民間企業や海外事例と比較するなど徹底検証する。長年、大蔵省・財務省をはじめ霞が関を取材し尽くした生涯一記者ならではの、極上ネタが満載。
■本書の目次■
プロローグ――霞が関の「聖域」
1章 その椅子のあまりに軽き――相次ぐ次官辞任劇の深層
2章 「名誉職」に過ぎないのか――事務方トップの役割を探る
3章 社長と次官――「組織の長」を比較する
4章 冬の時代――先細る天下り先、激減する志望者
5章 内閣人事局の功罪――幹部人事はどうあるべきか
6章 民間と女性の力――改革なるか人事院
エピローグ――「失敗の本質」