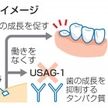◇セ・リーグ 阪神7−0中日(2024年4月19日 甲子園)
バットが発する快音には不思議な力が宿っているのかもしれない。
村上春樹が小説家になったきっかけは神宮球場の外野芝生席(当時)で観戦中に耳にした快音だった。1978(昭和53)年4月1日、開幕のヤクルト―広島戦。1回裏先頭のデーブ・ヒルトンが左翼線二塁打を放った時である。エッセー『走ることについて語るときに僕の語ること』(文春文庫)で明かしている。
<僕が「そうだ、小説を書いてみよう」と思い立ったのはその瞬間のことだ。晴れ渡った空と、緑色を取り戻したばかりの新しい芝生の感触と、バットの快音をまだ覚えている。そのとき空から何かが静かに舞い降りてきて、僕はそれを確かに受け取ったのだ>。翌年『風の歌を聴け』で群像新人文学賞を受け、デビューしたのだった。
この夜、阪神打線の活気を呼んだのは大山悠輔の快音である。2回裏先頭、中日先発ウンベルト・メヒアの速球を引っ張りライナーで左前に運んだ。不調だった大山が久々に放った快打である。
スコアをつける際、打球の種類を記号で記録している。ゴロ、フライ、ライナーの3種だ。大山の安打でライナーをつけたのは9日広島戦(甲子園)の右前打以来だった。引っ張った安打では3日DeNA戦(京セラドーム)以来、14試合ぶりだった。
4番の快音で打線は目を覚ました。この回、木浪聖也先制打に投手・青柳晃洋犠飛で2点。3回裏に森下翔太ソロ、4回裏に近本光司適時打、5回裏には大山自身に待望の今季1号が出た。3点以上奪うのは6日ヤクルト戦(神宮)以来、実に11試合ぶりだった。
監督・岡田彰布が大山を4番に据える理由を「誰もが認める」からだという。成績だけでなく、その姿勢や存在感、4番の風格を備えている。
昨季も苦しい時期を乗りこえた。優勝を決めた後に流した涙と岡田との抱擁を忘れてはいない。
今季は開幕から相当に打撃不振で苦しんでいたが、それでも懸命に守って投手を救い、凡打疾走の姿勢を崩さなかった。チーム内の誰もが復調を待ち望んでいた。だからあの快音快打に、チームは奮いたったのである。
ラグビーで言う「ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン」か。「チームのために」と「大山のために」が交わった、久々の快勝だった。=敬称略= (編集委員)
【内田雅也の追球】活気呼んだ4番の快音

スゴ得でもっと読む
スゴ得とは?関連記事
おすすめ情報
スポニチアネックスの他の記事もみるあわせて読む
-

【阪神】大山悠輔、5月攻勢のろし打!初回先制打、9回全力疾走でマルチ
日刊スポーツ5/2(木)9:16
-

【阪神】近本光司チーム救う好捕、12回2死一、二塁サヨナラピンチに
日刊スポーツ5/2(木)9:11
-

【阪神】岡田彰布監督ドローで延長戦不敗、10回以降6試合全て0封、セ・リーグ貯金独占
日刊スポーツ5/2(木)9:11
-

マツダスタジアムCーT速報まとめ!塹江らブルペン陣7継投で総力戦の末延長12回またまた引き分け、頼みの大瀬良自ら失点モードへ
ひろスポ!5/2(木)7:10
-

好きなプロ野球選手「“大谷翔平と並んだ”人気1位は誰?」甲子園球児が選ぶベスト25発表…山本由伸と吉田正尚が4位タイ、ではトップ3は?―2024上半期読まれた記事
Number Web5/2(木)6:00
-

阪神が4時間36分死闘の末に引き分けセ・リーグの貯金を独占 打点を挙げれば8戦不敗「大山神話」も継続
スポニチアネックス5/2(木)5:15
-

阪神・大山 初回鮮やか先制大瀬良撃ち 主砲打点挙げれば不敗、2戦ぶりマルチ
デイリースポーツ5/2(木)5:00
-

阪神・近本 速攻二盗で先制劇お膳立て、セ単独トップ5盗塁 ドロー決めたスライディングキャッチ
デイリースポーツ5/2(木)5:00
-

チャンスは大山!! 直近得点圏で3打数3安打…「とにかく先制点がほしいと思っていた」
サンケイスポーツ5/2(木)5:00
-
-

阪神・近本、自らも驚く超絶美技「ああいう変化になると思ってなかったんで…」
サンケイスポーツ5/2(木)5:00
-

△阪神選手コメント集 8人の継投で執念の延長十二回ドロー リードした梅野隆太郎 「ほんとにピッチャー陣、お疲れさまっていう感じです」
サンケイスポーツ5/1(水)23:46
-

阪神、延長十二回ドロー 4時間30分超えの戦いでも負けない虎
サンケイスポーツ5/1(水)22:41
-

【阪神】延長12回の末ドロー 今季延長戦は負けなしの2勝4分け 白星ならずもセの貯金独占
日刊スポーツ5/1(水)22:39
-

阪神・大山悠輔、5月初戦で先制タイムリー 大瀬良の立ち上がりを攻め立てた
サンケイスポーツ5/1(水)20:33
-

「月間JERAセ・リーグAWARD」3・4月度大賞候補発表 DeNAドラ1度会、中日37歳涌井ら
Full-Count5/1(水)19:19
-

阪神・大山悠輔が一回に適時打で先制! 今季広島から初打点で4連勝へ好発進
サンケイスポーツ5/1(水)18:23
-

スタメン発表 広島先発・大瀬良大地から前回対戦で2安打 阪神の5月は近本光司の打席からスタート
サンケイスポーツ5/1(水)17:38
-

大阪桐蔭春夏連覇と金足農ブームの「2018甲子園ドラフト組」最多勝は根尾昂でも吉田輝星でもなく…最多HRは万波中正〈プロ6年目24歳の明暗〉
Number Web5/1(水)17:04
-
スポーツ アクセスランキング
-
1

〝連休〟の大谷翔平 今季初欠場はハチの影響? 米メディア駆除遅延による「休息減」を指摘
東スポWEB5/2(木)20:44
-
2

腐敗した牛肉を「焼き肉のタレに漬け込めば臭いは消える」と食べさせ…大相撲・佐渡ヶ嶽部屋が元力士に訴えられた“ドケチいじめ”
文春オンライン5/2(木)17:00
-
3

大谷翔平が「なんで?」 新契約で“発覚”…背景に広がる違和感「絶対そうだよね」
Full-Count5/2(木)17:33
-
4

右腕の切断報告の佐野慈紀氏、一部の声に怒りをにじませて反論「勝手な発言は腹が立ちます」
サンケイスポーツ5/2(木)19:42
-
5

巨人・阿部監督 秋広には「あまり期待しないほうがいいです」 元木大介も苦言「監督は真剣に…」
スポニチアネックス5/2(木)19:06
-
6

《痛恨の青学卒業失敗》広島ドラ1・常広羽也斗「あと1単位で留年」今後シーズンは“野球専念”も単位修得は「秋以降に」
NEWSポストセブン5/2(木)17:10
-
7

快進撃・今永昇太が女性レポーターを爆笑させた一言 「本当にそんなこと言った?」と米ファン虜
THE ANSWER5/2(木)21:03
-
8

【新体操】フェアリーJ、パリ切符逃す 会心「ソーラン節」も2位で5大会連続五輪ならず
スポニチアネックス5/2(木)21:19
-
9

U23アジア杯決勝直前、大会最強のウズベキスタンを日本は破れるか?二人の天才を揃えた強敵に迫る
Qoly5/2(木)20:00
-
10

「胴元たちはミズハラを売ろうとした」 ESPNの新報道…大谷口座からの流れを知った米司会者指摘
THE ANSWER5/2(木)16:33
スポーツ 新着ニュース
-

望月慎太郎 第3シードに善戦も敗退
tennis365.net5/3(金)2:30
-

開幕戦でスーパーキャッチ&2ランの梶谷隆幸が1軍昇格 得点力不足に苦しむ巨人打線の起爆剤に…増田大輝も
スポーツ報知5/3(金)2:00
-

西岡良仁 激闘の末敗れ8強ならず
tennis365.net5/3(金)1:37
-

カブス今永 “スパイダー”快投で無傷5連勝&防御率の2冠「うまく狙いを外せた」昇太マニアも大満足
スポニチアネックス5/3(金)1:30
-

カブス今永の快進撃支える“浮き上がる”直球 被打率.137は2番目の低さ フライボール革命には効果的
スポニチアネックス5/3(金)1:30
-

タイガース前田 待望の今季初勝利で歴代8位の日米通算163勝目 球団もダジャレ交えて祝福
スポニチアネックス5/3(金)1:30
-

レッドソックス吉田 左手親指痛め自身初の負傷者リスト入り「トレーナーさんと次に向けて話し合っている」
スポニチアネックス5/3(金)1:30
-

ドジャース由伸 15回連続無失点 日本投手1日3勝の“大トリ”「ファンの方にはハッピーなこと」
スポニチアネックス5/3(金)1:30
-

大谷翔平 序盤の大量点で出番なし ドジャースでは初の欠場 ベンチでヒマワリの種頬張るなどリラックス
スポニチアネックス5/3(金)1:30
-

日本投手の初勝利から2万1764日目 史上初の快挙!先発3投手の同日勝利 背番号18は295勝目
スポニチアネックス5/3(金)1:30
総合 アクセスランキング
-
1

千原せいじ「和尚さんになりました」 天台宗の得度式で「千原靖賢(せいけん)和尚」に
スポニチアネックス5/2(木)17:06
-
2

これで71歳!?小柳ルミ子 衝撃“すっぴん”姿に称賛の声「なんて奇麗な肌なんでしょう」
スポニチアネックス5/2(木)16:41
-
3

《那須焼損遺体夫婦》「自分は2000万円もらって…」黒幕の1次下請け“指示役”佐々木光容疑者28歳が地元福岡に残した「悪評」と「長髪写真」
文春オンライン5/2(木)21:00
-
4

【叡王戦】藤井聡太叡王「間違えてしまった」 タイトル戦で初のかど番、初連敗 次戦は31日
日刊スポーツ5/2(木)19:19
-
5

『Believe−君にかける橋−』まさかの急展開に視聴者ざわつく「橋作りドラマかと思ってたのに…」「予想外すぎる」
ORICON NEWS5/2(木)22:15
-
6

マシュマロ喉に詰まり重体 沖縄・石垣の学童クラブ
共同通信5/2(木)20:35
-
7

アン ミカ、ロケ途中でお疲れさまも言わず無言で帰宅…現場は騒然、高そうな私物バックにも注目集まる
ABEMA TIMES5/2(木)20:00
-
8

〝連休〟の大谷翔平 今季初欠場はハチの影響? 米メディア駆除遅延による「休息減」を指摘
東スポWEB5/2(木)20:44
-
9

RIEHATA出演のサッポロビールCM放送を見送り「様々なご意見を頂戴…総合的に判断」
日刊スポーツ5/2(木)18:28
-
10

「やめないで」卒業&LDH退社発表の関口メンディー、最新投稿に「やっぱり理解できない」と賛否両論
All About NEWS5/2(木)18:30
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
(C) 2024 SPORTS NIPPON NEWSPAPERS.