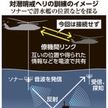今季からDeNAに加わったメジャー通算83勝のトレバー・バウアーは、かつてこう言ったことがある。
「僕は生まれついてのアスリートじゃなかった」
2020年にサイ・ヤング賞に輝いた男にしては弱気な発言だが、裏付けがないわけではない。バウアーは身長185cm、体重92kg。UCLAの同期で、現在はヤンキースのエースとして活躍するゲリット・コールは193cm、99kgであることを思えば、確かにやや小柄だ。そんなバウアーがなぜ、MLBで最高の投手に贈られる賞を受賞するほどの一流投手に上り詰めることができたのか?
2019年に刊行された『The MVP Machine』(邦題『アメリカン・ベースボール革命』/科学同人刊)において、バウアーは「僕は作られたんだ」と述べている。もちろん、右腕が機械でできているとか、ドーピングで実力を上げたということではない。天性の才能ではなく、自分で考え、試行錯誤しながらトレーニングを積んで研鑽し続けてきた、という意味だ。
高校時代、バウアーはコーチから炎天下のブルペンで投球動作中に右足だけで静止してバランスを取るという練習を命じられた。アメリカの高校野球では伝統的な練習方法なのだが、バウアーは少し取り組んだだけで拒否。「別に人の話を一切聞かないわけじゃない。悪いアドバイスは拒絶しているだけだ」と平然と言ってのけた。
その代わり、バウアーは自ら開発したロングトスの練習を当時からずっと続けている。登板前の30分ほどの時間を、外野に出て遠投に費やす。大学時代には、この独自スタイルの練習を「投手として結果が出ている限り放任する」と監督に認めさせた。2011年ドラフト全体3位指名でプロ入りしてからも、ロングトスに苦言を呈するコーチや先輩捕手が後を絶たなかったがか、それでもバウアーはやめようとはしなかった。
『The MVP Machine』で、バウアーは実質的な主人公として扱われている。何しろ、プロローグの書き出しからしてバウアーの名前から始まるのだ。プロ入り後も、独自の研鑽に取り組んできた彼にとって飛躍の転機となったのが、最先端トレーニング施設『ドライブライン・ベースボール』との出会いだった。
ドライブラインでは、重さの異なる6種類のボールを用いたピッチング練習や、モーションキャプチャーによる動作解析などを行っていた。そうした独自の科学トレーニング法に、バウアーは夢中になった。12年の創設当初から毎年通い詰め、1秒で最大5000コマ以上の撮影が可能なエッジャートロニックカメラを自ら持ち込んでさらにトレーニングの幅を広げた。
ドライブラインでの取り組みを通して、バウアーはボールの球速だけでなく、回転軸や回転数、回転方向や変化量などを詳細にデータ化し、どのような指のかかり方や腕の角度であれば、より効果的な球種が投げられるのかを探求した。この過程を、バウアーは「ピッチデザイン」と名付けた。
これによってバウアーの投球は大きく進化し、ついにはサイ・ヤング賞を獲得するまでに至った。そして、この「ピッチデザイン」の考え方は、他の投手にも大きな影響を与えた。2000年代前半のマネー・ボール革命以降、データ分析をチーム作りに活用することは当たり前になっていたが、選手育成における有効なデータの活用法はそれまで見出されていなかった。
バウアーの成功によって、単に「ファストボールのスピードを上げる」「変化球の曲がり幅を大きくする」といった曖昧な目標ではなく、自分の感覚とデータの具体的な数値を組み合わせてピッチングを向上させる道が他の投手にも開けたと言っても過言ではない。
今や、プロ・アマ問わず年間500人以上の選手がドライブラインを訪れ、データ分析によって自身の才能を開花させようとしている。その中には、日本プロ野球で活躍する多くの投手も含まれる。20年オフには、大谷翔平(エンジェルス)も受講して飛躍につなげている。バウアーは、道なき道を切り拓いたパイオニアと言ってもいい存在なのだ。
ここまで4試合に先発して防御率6.86とNPBへの適応に苦しんでいるバウアー。だが、自分の課題を分析し、成績向上のための目標を具体的に設定してクリアする能力にかけては折り紙付きだ。今後どのようにピッチングを修正してくるのか楽しみだ。
構成●SLUGGER編集部
道なき道を切り開いてサイ・ヤング賞投手へ――トレバー・バウアーが最先端理論「ピッチデザイン」を作るまで<SLUGGER>

関連記事
あわせて読む
-

大谷翔平、赤裸々告白!? 遠征中は真美子夫人に「寂しいと言わせたい」普段は自宅近くを散歩も
スポニチアネックス4/25(木)6:18
-

和んだ空気急変も− 大谷翔平の親友喪失への「回答」に称賛の嵐「こんなこと言える人間になりたい」「世界一の人格者ですね」
デイリースポーツ4/25(木)9:07
-

大谷翔平、3戦連発ならずもフェンス直撃の適時二塁打 3二塁打で今季4度目の猛打賞と大暴れ
スポーツ報知4/25(木)10:20
-

福島牝馬Sで落馬した吉田隼人騎手は命に別状なし 兄の吉田豊騎手「意識障害がある状態」
スポーツ報知4/25(木)7:51
-

大谷翔平また全国の子どもたちにプレゼント 今度はマットレス約2500本「一緒に大きな夢を」
日刊スポーツ4/25(木)4:00
-

阪神・岡田監督 取材拒否をついに解除も…番記者たちへ突きつけた「まさかの交換条件」
女性自身4/25(木)11:00
-

「エンジェルスに対して失礼」大谷翔平がみせた無礼な質問への“切り返し”に称賛止まず!「気遣い半端ない」「格が違いすぎる」
THE DIGEST4/25(木)5:00
-

ドジャース指揮官 大谷翔平とボンズの打球速度を比較「バリーは最高の打者。文句なしだ」
スポニチアネックス4/25(木)9:30
-

ベッツ 大谷翔平に「彼のやることのうち90%は私にはできない。できるのは最高のベッツになること」
スポニチアネックス4/25(木)12:10
-
-

天皇賞・春は今年好調なキズナ産駒は外せない 好走実績豊富なハーツクライ産駒にも注目
webスポルティーバ4/25(木)7:20
-

ベッツ、6打数4安打で3連勝に貢献 二塁打3本の大谷に「これ以上言葉が見当たらないよ」
日刊スポーツ4/25(木)11:45
-

大谷翔平に指揮官“おねだり”「新しい車が必要」 ド軍日本生まれ最多HRへ残り1本
Full-Count4/25(木)7:12
-

大谷翔平と「ラブラブかよ」「いつも一緒」 敵地で撮られた「ベストフレンド」との1枚に大反響
THE ANSWER4/25(木)5:43
-

【巨人】ついに9試合連続2得点以下… チーム内でささやかれる貧打の「原因」とは
東スポWEB4/25(木)5:00
-

大谷翔平「新しい通訳が素晴らしいからじゃないですか」と笑いを取る…水原一平容疑者がいなくなってオープンになったとの声も
中日スポーツ4/25(木)9:52
-

中日、連敗止めるも「ベンチは切羽詰まっている」 専門家が分析…拭えぬ得点力不足
Full-Count4/25(木)7:43
-

大谷また弾丸186km打、呆れるしかない米メディアが本音「常軌を逸してます…」「野球界を破壊」
THE ANSWER4/25(木)8:08
-

“絶望の打率.068”元MVPほど「酷い打者いない」 年俸30億円も…戦力外を躊躇するワケ
Full-Count4/25(木)7:20
-
スポーツ アクセスランキング
-
1

大谷翔平、赤裸々告白!? 遠征中は真美子夫人に「寂しいと言わせたい」普段は自宅近くを散歩も
スポニチアネックス4/25(木)6:18
-
2

和んだ空気急変も− 大谷翔平の親友喪失への「回答」に称賛の嵐「こんなこと言える人間になりたい」「世界一の人格者ですね」
デイリースポーツ4/25(木)9:07
-
3

大谷翔平、3戦連発ならずもフェンス直撃の適時二塁打 3二塁打で今季4度目の猛打賞と大暴れ
スポーツ報知4/25(木)10:20
-
4

福島牝馬Sで落馬した吉田隼人騎手は命に別状なし 兄の吉田豊騎手「意識障害がある状態」
スポーツ報知4/25(木)7:51
-
5

大谷翔平また全国の子どもたちにプレゼント 今度はマットレス約2500本「一緒に大きな夢を」
日刊スポーツ4/25(木)4:00
-
6

阪神・岡田監督 取材拒否をついに解除も…番記者たちへ突きつけた「まさかの交換条件」
女性自身4/25(木)11:00
-
7

「エンジェルスに対して失礼」大谷翔平がみせた無礼な質問への“切り返し”に称賛止まず!「気遣い半端ない」「格が違いすぎる」
THE DIGEST4/25(木)5:00
-
8

ドジャース指揮官 大谷翔平とボンズの打球速度を比較「バリーは最高の打者。文句なしだ」
スポニチアネックス4/25(木)9:30
-
9

ベッツ 大谷翔平に「彼のやることのうち90%は私にはできない。できるのは最高のベッツになること」
スポニチアネックス4/25(木)12:10
-
10

天皇賞・春は今年好調なキズナ産駒は外せない 好走実績豊富なハーツクライ産駒にも注目
webスポルティーバ4/25(木)7:20
スポーツ 新着ニュース
-

【一問一答】阪神・高橋が1回3安打1失点 2度目の登板「むしろ今日の方がいいかなという感じ」
スポニチアネックス4/25(木)13:26
-

阪神・青柳晃洋、26日先発予定のヤクルト戦に向け調整「しっかり投げることができたら」
サンケイスポーツ4/25(木)13:25
-

青森知事、国スポ大会の改革要求 「3巡目は廃止やむなし」
共同通信4/25(木)13:24
-

ドジャースのムーキー・ベッツ「大谷ができることの90%は俺にはできない」打率で大谷に6厘差2位浮上
スポーツ報知4/25(木)13:24
-

ロッテ、4選手ゆかりの4市とスポンサー契約 種市「地元とつながってうれしい」
スポニチアネックス4/25(木)13:23
-

マスターズから2週連続優勝で直近5試合で4勝、まさに世界最強のスコッティ・シェフラー
ゴルフネットワーク4/25(木)13:21
-

MLB最高球団フロントに大谷所属のドジャース「あらゆる面でエリート」米メディアが格付け発表
日刊スポーツ4/25(木)13:20
-

【阪神】高橋遥人 2軍で実戦復帰後2度目の登板で1回3安打1失点 最速は147キロ
日刊スポーツ4/25(木)13:18
-

「『打ってください』っていうメッセージかなと思って」。相手を突き放す3点目。ボランチで先発した戸嶋祥郎が攻守に躍動【ルヴァン杯】
SOCCER DIGEST Web4/25(木)13:18
-

中日連敗ストップ、立浪監督戻らぬ「声」 「喉がガラガラ」で試合後インタビュー行えず ナインを鼓舞できない毎日にやきもき!?
夕刊フジ4/25(木)13:17
総合 アクセスランキング
-
1

宮脇咲良に「プロではない」「レベルを下げている」と厳しい声も…なぜLE SSERAFIMは韓国でこれほど批判されているのか〈現地記者が解説〉
文春オンライン4/25(木)6:00
-
2

大谷翔平、赤裸々告白!? 遠征中は真美子夫人に「寂しいと言わせたい」普段は自宅近くを散歩も
スポニチアネックス4/25(木)6:18
-
3

和んだ空気急変も− 大谷翔平の親友喪失への「回答」に称賛の嵐「こんなこと言える人間になりたい」「世界一の人格者ですね」
デイリースポーツ4/25(木)9:07
-
4

「めーっちゃ痩せた」大物芸人の近影にネット騒然…18歳年下女性と4度目の結婚→沖縄プチ移住
スポーツ報知4/25(木)6:38
-
5

大谷翔平、3戦連発ならずもフェンス直撃の適時二塁打 3二塁打で今季4度目の猛打賞と大暴れ
スポーツ報知4/25(木)10:20
-
6

川平慈英『あさイチ』登場にネット爆笑 博多華丸の代打MC「似すぎw」「朝ドラ受けどころじゃないw」
ORICON NEWS4/25(木)8:23
-
7

福島牝馬Sで落馬した吉田隼人騎手は命に別状なし 兄の吉田豊騎手「意識障害がある状態」
スポーツ報知4/25(木)7:51
-
8

大谷翔平また全国の子どもたちにプレゼント 今度はマットレス約2500本「一緒に大きな夢を」
日刊スポーツ4/25(木)4:00
-
9

松本人志に文春と和解の噂も、振り上げた拳は下ろせるか? 告発女性の素性がSNSで暴露され…
日刊ゲンダイDIGITAL4/25(木)9:26
-
10

2人組と品川で接触、その後殺害か 現場の住宅に血痕 栃木2遺体
朝日新聞4/25(木)5:00
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

元アルゼンチン代表FWイグアイン、人気上昇中の競技「パデル」の大会で優勝!賞金を勝ち取る
Qoly4/25(木)13:00
-

インド人の彼女に「そのカレー美味しそう」と言うと…? →インドと日本のカレーの認識に驚きの声!
ほ・とせなNEWS4/25(木)12:30
-

トッテナム、「Jリーグワールドチャレンジ」で来日が決定!7月にJ1王者神戸と国立で対戦 さらに“続報”も?
Qoly4/25(木)12:25
-

40歳のテベス、胸の痛みで検査入院…高血圧の影響か
Qoly4/25(木)12:05
-

【AKB48・岩立沙穂、駅弁極めます。】さっほーが「駅弁屋 祭」を直撃!気になる人気No.1駅弁とは?
Walkerplus4/25(木)12:00
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright(c)Nippon Sports Kikaku Publishing inc. All rights reserved.