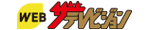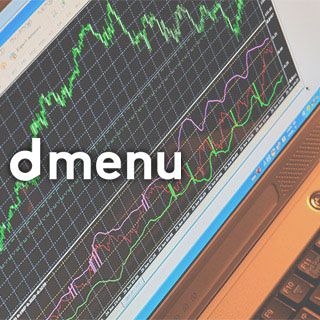コミックの映像化や、ドラマのコミカライズなどが多い今、エンタメ好きとしてチェックしておきたいホットなマンガ情報をお届けする「ザテレビジョン マンガ部」。今回は、プランタン出版より発売中の書籍「紙の舟で眠る」をピックアップ。
作者の八田てきさんが12月25日にX(旧Twitter)で同作の第1話を投稿。そのツイートには合わせて5000以上のいいねと共に、多くの反響コメントが寄せられた。この記事では八田てきさんにインタビューを行い、創作のきっかけやこだわりについてを語ってもらった。
■“死神”に取り憑かれた天才脚本家…
天才脚本家の北原憬は、“死神”に取り憑かれている。彼が手掛けた主人公のモデルたちは次々と亡くなってしまうのだ…。
度重なる不幸によって、憬は闇酒場で飲んだくれる日々を送っていた。そんなある日、憬が酔って路上に倒れていると、あるアマチュアカメラマンが介抱してくれた。
その後、憬は彼の家に泊まらせてもらうことに。彼の部屋には、彼の撮った写真がそこら中に飾られていた。彼の写真を見た憬は、涙が止まらなくなる。
憬が名前を尋ねると、彼は笑顔で「三上燿一といいます」と答えてくれた。するとその瞬間、何故かあの“死神”が目の前に現れた気がした…。
“死神”に取り憑かれた天才脚本家がアマチュアカメラマンと出会う物語に、読者からは「映画のような作品」「圧倒された」「のめり込んでしまった」など多くの反響の声が寄せられている。
■「長年温めてきた昭和への思いを…」作者・八田てきさんが語る創作秘話
――「紙の舟で眠る」を創作したきっかけや理由があればお教えください。
物心つく頃からこの国の「昭和」という激動の時代に大変惹かれるものがあり、いつかテーマに描いてみたいという気持ちがありました。漫画家として初めて単行本で出させていただいた前作がアメリカを舞台とする物語だったこともあり、この機会に自分の中に長年温めてきた「昭和」への思いを今作にすべて込めてみようと思ったのです。
構想段階から、この物語が本体表紙のカラクリも含めて北原憬という脚本家が書いたという形にしたいと考えていたのですが、日本の戦前から戦後にかけての銀幕世界に憧れる気持ちも強くあり、今作を通じて当時の映画作りに携わる方々の情熱に私自身が繋がってみたかったという想いもありました。
戦争によって生命の尊厳と文化が破壊され、人格にまで影響を与えるようなトラウマティックな体験をされた方々の創作には、地べたを這うような生命と魂の慟哭が泥臭くむせ返っているように私には感じられます。それは破壊と再生に流転するひとつの生命現象のようにも思われるのですが、当時の創作者の心象に戦後の時代がどのように影響を与えたのか、未熟ながらも拙い私なりに表現してみたいと思いました。
当時の映画や小説に触れると、人々の情念が創作という「いきもの」の血肉によって蠢いている、また、戦後という時代の様々な不条理に翻弄されることで、本来眠っていたはずの魂の叫びが剥き出しになり、「創る」というより何かに「創らされる」ことでようやく今日1日を生き延びようとした人たちがいたことがわかります。現代に生まれ生活する私には到底想像や理解が及ぶものではありませんが、そんな姿を主人公に込めてみたかったのです。
ですから北原憬と三上燿一は、そのような時代に対する私の印象を2人の人間に分けて擬人化したようなキャラクターです。その意味においては、2人が素肌で愛し合いひとつになる場面は特に大切なものがあります。宿命を抱えたこの2人に私の思い描く「昭和」という時代を託してみようと思ったのですが、結果的にはむしろ、私自身が2人の思考や選択に押し流されるような感覚で描き上げることになりました。
――本作を描くうえでこだわった点があればお教えください。
主人公2人のキャラクターに関しては、こだわりというより彼らに導かれたという方がいいかもしれません。北原憬は幼少期のトラウマ体験と、自分が書く脚本のモデルが立て続けに死んでしまうという「呪い」に長年苛まれ苦しんでいる人間です。幼少期に小説家であっためったに会えない父親と初めて会った母親が本懐を遂げるために2人で身投げをするという心的外傷を負った青年が見る世界は、およそ現実感のないものなのではないか......果たして自分は生きているのか死んでいるのか、それは現実なのか彼岸の出来事なのか、それとも自分が書いている言葉が紡ぐ夢想の世界なのか、そんな迷妄に囚われることに自ら依存してしまっているキャラクターです。
それでも生きるために書かずにはいられない、生きるために狂ってしまうことを無意識に選び、どこかでそんな自分に酔っている。根源的な生への欲求に翻弄されながら、北原憬にとっての創作の源が三上燿一という人間の形をして目の前に現れたらどんな風に振る舞うだろう、両親の身投げという暗い過去に蓋をして、どのように彼を愛そうとするだろう、そして燿一も市電事故で母親が自分を庇って死んでしまい、チャブ屋という愛欲と情念の吹き溜まりで育った経緯がありますから、お互いに共鳴し依存し合いながらも、空虚な心をどのように埋め合おうとするだろうという私自身にとっての思考実験でもありました。
また、冒頭の市電事故は憬と燿一にとっての戦争のメタファーとして描きましたので、そのように物語を読み進めてくださるとまた違った見方ができるかもしれません。
■作者・八田てきさんから読者へメッセージ
――本作の中で特に気に入っているシーンやセリフがあれば、理由と共にお教えください。
上巻で言えば、後半、燿一のすべての仮面がそぎ落とされて「一緒に地獄へ堕ちてくれって言ってみろよ」「僕はそんなにも愛しがいのない人間なのかなあ?」と、憬に本心をぶつけるシーンです。燿一も幼少期の辛い過去ゆえにアイデンティティと主体性を無くすことで生き延びてきました。幼いなりにもあらゆる顔を使い分ける空虚な人でしたから、愛するがゆえに憬の抱える闇を自分の鏡に映せば映すほど憬の世界に引き摺り込まれてしまったのです。
あのシーンを描くにあたっては、こんな本音が燿一から出てくるのか、これはやはり相手が憬だからこそ、生まれて初めて吐露できたものに違いないという驚きが私自身にありました。憬が自身のインナーチャイルドである死神を燿一に見出したのは、燿一もまた母親が死んだ時のまま時間が止まってしまっていたからです。
下巻では、ふとしたきっかけで2人が熱海に行くことで憬の記憶が甦り、岬から脚本を手放し両親に対して鎮魂するシーンが好きです。憬の魂に焼き付けられた父と母の情念が成仏し、日昭の東社長に操られて同じ轍を踏みかけていた彼らがその寸前で「生きる」という選択と悟りに至った瞬間でもあります。
また、東社長に引導を渡して壽子さんから手紙が届くシーンは、憬のすべての苦悩が救われたカタルシスの象徴として描きました。両親と抑圧されていた幼い自分の鎮魂を経たからこそ、憬が書く「言葉という呪い」が今度は燿一の台詞通り、生きるための味方になったのです。あのシーンは、私自身描きながらとても感慨深いものがありました。
――作品の世界観にすっかり惹きこまれてしまいました。普段作品のストーリーはどのようなところから着想を得ているのでしょうか?
普段から映画作品に触れることがとても好きなので、スランプに打ちのめされながら映画からインスピレーションをいただくことはよくあります。自分の中にあるイメージが頭の中で映画作品として上映され、それを漫画に描き起こしていくような感覚です。今回はだから北原憬を脚本家にしたのかもしれません。また、物語の重要なシーンに取り組むにあたっては敬愛する方々の音楽は欠かせません。音楽が醸し出す空気感や風景に力を貸してもらいながら導き出されるシーンや台詞もあります。音楽の力は本当に偉大だと思います。
――今後の展望や目標をお教えください。
私の場合、展望や目標を持つというよりは、その都度自分に何ごとかを訴えてくる世界を描きたいと思う方です。もしかすると、次作は近未来的な世界への挑戦になるかもしれません。描きたいものは沢山あるのですが、表現力が足りなくてもどかしい気持ちがあり、ひとつ形になるたびに己の力量不足を痛感して歯痒く悔しい思いがあります。
今作で勉強になった糧を活かしつつ、またどんな生命の物語を形にできるのか楽しみでもありますが、それによって私が少しでも創作という生きものの毛細血管の一脈として還元できることを願うばかりです。
――最後に、作品を楽しみにしている読者へメッセージをお願いいたします。
いつも応援してくださり、本当にありがとうございます。皆様から頂く励ましの言葉やお手紙、声援のひとつひとつに大きな力をいただいています。また、感想や考察を拝読するのが大変楽しく、そのように作品を読み込んで頂けることが本当にありがたく嬉しく思います。
今作の解釈にただひとつの正解というのはありません。私は私の思いを持って描きあげましたが、もし、読者の皆様が持つ心の鏡にこの作品が映し出されることがあれば、それは皆様1人1人の物語として考えて頂ければと思います。今後も皆様に楽しんで頂けたり、少しでも何かを考えるきっかけになったり、そんなよすがのひとつとなる作品を提供できるよう誠心誠意励んでいきたいと思っておりますので、あたたかく見守っていただけますと幸いです。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
【漫画】“死神”に取り憑かれた天才脚本家…彼の身に起こる衝撃的な出来事に「映画のような作品」「圧倒された」と反響

関連記事
おすすめ情報
WEBザテレビジョンの他の記事もみるあわせて読む
-

NHK開会式中継 中川安奈アナの服にネット騒然「びっくりした」「一瞬服着てないのかとw」「アナの服が」
デイリースポーツ7/27(土)1:25
-

GACKT、歌が下手な人をバッサリ「すっごいキツイ言い方をすると、音痴な人は家庭環境が悪かったですね」
スポーツ報知7/27(土)1:31
-

神田正輝「旅サラダ」休止で「X」トレンド入り…SNSは寂しさがあふれる事態に…「旅サラダがないので土曜日じゃないのかも」
スポーツ報知7/27(土)8:22
-

レディー・ガガ パリ五輪開会式出演「一生忘れられない」ポンポンは実在のキャバレーから借りたと明かす
スポニチアネックス7/27(土)4:01
-

空手形銀の清水希容さん「逃亡したいくらい」だったけど「五輪には結果以上のもの」選手にエール
日刊スポーツ7/27(土)6:00
-

「女優さんみたい」石川佳純さん パリから中継レポートにネット驚き「まるでガッキー」「う、美しい」フジ美人アナと並んでも
デイリースポーツ7/27(土)1:03
-

『あさイチ』生出演した元女優にネット衝撃 68歳の現在が「お若い」「変わらずキレイ」
ENCOUNT7/27(土)7:20
-

GACKT、熱く持論展開「世の中で売れているミュージシャンで音程が外れている人もいっぱいいる」
スポーツ報知7/27(土)7:34
-

フランス在住の杏、白ジャケット姿の凜々しい姿…NHKの開会式直前中継に登場
スポーツ報知7/27(土)1:36
-
-

「外でこういうの無理」水原希子、彼氏との際どすぎる“イチャイチャ”写真にツッコミ殺到
週刊女性PRIME7/27(土)7:30
-

NHK開会式実況 中山果奈アナとは…報道のエース「ポスト和久田のトップランナー」
スポニチアネックス7/27(土)1:00
-

【笑うマトリョーシカ】禁断の男女関係!ネット衝撃「手ェ出したん!?」「それはアカン」「すごい展開に」
スポーツ報知7/26(金)23:03
-

相武紗季、芸能界の“お父さん”と再会明かす「20年以上前、芸能界入るきっかけ作ってくれた」
日刊スポーツ7/27(土)6:00
-

パリ五輪開会式でネットが戦慄…セーヌ川に浮かぶ“巨顔”に「怖すぎ」「トラウマに」「夢に出てきそう」
スポニチアネックス7/27(土)3:46
-

“とにかく明るい仏村”現る!パリ五輪開会式でネット衝撃「色違い出てきて吹いた」「フランス版安村」
スポニチアネックス7/27(土)5:23
-

第一子出産の日テレ・徳島えりかアナ、局の垣根を越えた“ママアナウンサー”らとの写真が「素敵すぎる」と話題
スポーツ報知7/27(土)5:37
-

大谷翔平の“珍しい出勤姿”にファンもん絶「萌え袖ーーーーー」「萌え袖の大谷サン!」「NBのスニーカー気になる〜」
ORICON NEWS7/27(土)9:03
-

木梨憲武、ラジオ生放送で「旅サラダ」休止余波…勝俣州和が生出演し「神田正輝」トーク
スポーツ報知7/27(土)8:36
-
エンタメ アクセスランキング
-
1

NHK開会式中継 中川安奈アナの服にネット騒然「びっくりした」「一瞬服着てないのかとw」「アナの服が」
デイリースポーツ7/27(土)1:25
-
2

GACKT、歌が下手な人をバッサリ「すっごいキツイ言い方をすると、音痴な人は家庭環境が悪かったですね」
スポーツ報知7/27(土)1:31
-
3

神田正輝「旅サラダ」休止で「X」トレンド入り…SNSは寂しさがあふれる事態に…「旅サラダがないので土曜日じゃないのかも」
スポーツ報知7/27(土)8:22
-
4

レディー・ガガ パリ五輪開会式出演「一生忘れられない」ポンポンは実在のキャバレーから借りたと明かす
スポニチアネックス7/27(土)4:01
-
5

空手形銀の清水希容さん「逃亡したいくらい」だったけど「五輪には結果以上のもの」選手にエール
日刊スポーツ7/27(土)6:00
-
6

「女優さんみたい」石川佳純さん パリから中継レポートにネット驚き「まるでガッキー」「う、美しい」フジ美人アナと並んでも
デイリースポーツ7/27(土)1:03
-
7

『あさイチ』生出演した元女優にネット衝撃 68歳の現在が「お若い」「変わらずキレイ」
ENCOUNT7/27(土)7:20
-
8

GACKT、熱く持論展開「世の中で売れているミュージシャンで音程が外れている人もいっぱいいる」
スポーツ報知7/27(土)7:34
-
9

フランス在住の杏、白ジャケット姿の凜々しい姿…NHKの開会式直前中継に登場
スポーツ報知7/27(土)1:36
-
10

「外でこういうの無理」水原希子、彼氏との際どすぎる“イチャイチャ”写真にツッコミ殺到
週刊女性PRIME7/27(土)7:30
エンタメ 新着ニュース
-

山口祥行×崔哲浩×福士誠治トリプル主演、3兄弟ヒューマンバイオレンス映画『ぴっぱらん!!』公開決定
ORICON NEWS7/27(土)10:12
-

大河でも注目の玉置玲央、映像と舞台の演技に垣根はない 演劇ブームの熱狂をもう一度取り戻せたら
WEBザテレビジョン7/27(土)10:00
-

16年ぶりに梅田スカイビルも会場に!関西圏で最大規模を誇る“踊る祭り”「第25回こいや祭り」が9月7日・8日に開催
Walkerplus7/27(土)10:00
-

“令和の白ギャル”ゆうちゃみ「まだまだマジ下っ端のぺーぺー」 コンプレックスだった高身長も武器に次なる野望に挑戦
スポーツ報知7/27(土)10:00
-

活躍続く若手バイオリニスト、金川真弓「計算できないものの価値を忘れないでいきたい」
産経新聞7/27(土)10:00
-

志らべのユー、次なに見る 1987年型の古びた自動車…恋愛ほぼなしがイイ!おばさん絡むカーコメディー 韓国映画「ステラ SEOUL MISSION」
夕刊フジ7/27(土)10:00
-

あのちゃんvsゆうちゃみ〝写真集バトル〟セクシー作か芸術志向か 「アンゴラ村長」に続くヒットは!? 9月4日同日発売で注目
夕刊フジ7/27(土)10:00
-

ゆたぼん 活動休止を発表 高卒認定試験に集中
デイリースポーツ7/27(土)9:59
-

山崎育三郎、公演当日に中止を発表「体調不良により、やむなく中止」
ORICON NEWS7/27(土)9:58
-

成田悠輔氏「小学生の頃に戻りたい」と告白“その理由”に反響「共感します」
日刊スポーツ7/27(土)9:55
総合 アクセスランキング
-
1

NHK開会式中継 中川安奈アナの服にネット騒然「びっくりした」「一瞬服着てないのかとw」「アナの服が」
デイリースポーツ7/27(土)1:25
-
2

開会式、バレー男子は全員不参加 西田有志「そっちよりも勝ち」
毎日新聞7/27(土)2:36
-
3

GACKT、歌が下手な人をバッサリ「すっごいキツイ言い方をすると、音痴な人は家庭環境が悪かったですね」
スポーツ報知7/27(土)1:31
-
4

2度目の大関陥落・貴景勝、師匠の常盤山親方は「本人の意志を尊重」進退も含め話し合う方針【名古屋場所】
中日スポーツ7/27(土)5:00
-
5

「日本見逃した」続出 開会式紹介が一瞬すぎて午前4時の視聴者悲鳴「トイレ行ってて…」「1時間半起きてあの一瞬」
THE ANSWER7/27(土)4:15
-
6

ウクライナ軍の無人機、ロシア軍の大規模武器庫をほぼ壊滅…南部ボロネジ州
読売新聞7/27(土)5:00
-
7

メッツ・藤浪晋太郎が事実上の戦力外通告、今季メジャー登板なし…千賀滉大復帰戦前に非情通告
スポーツ報知7/27(土)1:30
-
8

トランプ氏に聴取要請 FBI、事件被害者として
共同通信7/27(土)4:48
-
9

五輪開会式に登場のアヤ・ナカムラとは、日本とのかかわりは…YouTubeは9・7億回再生
読売新聞7/27(土)3:24
-
10

ド軍、“戦力外”の8勝左腕をRソックスへトレード 17歳内野手を獲得…球団発表
Full-Count7/27(土)4:18
いまトピランキング

東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

シティGKエデルソン、控えGKオルテガへの不満説を完全否定 妻も「完全なフェイクニュース」と斬り捨てる
Qoly7/27(土)9:15
-

上田綺世のフェイエ、FW3人体制に…TDが説明 「上田への関心がより具体的な形に…」
Qoly7/27(土)8:55
-

隅田川花火大会主催者が本日の開催決定を発表!公式Xでリアルタイムの情報を確認しよう
Walkerplus7/27(土)8:34
-

日本の“三笘マニア”にBBCも注目!「ブライトンは消滅危機の暗黒時代からどれほど成長したか」
Qoly7/27(土)8:25
-

【目黒区】権之助坂商店街振興組合主催の「第38回目黒駅前 地域のふれあい盆踊り大会」が7月28日(日)に開催されます
号外NET7/27(土)8:00
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) 2024 KADOKAWA. All Rights Reserved.