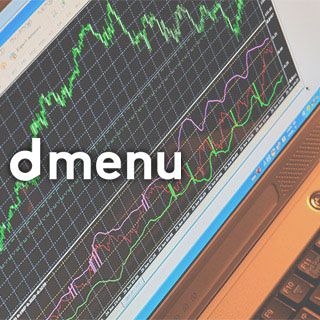前回:「彼の子どもがほしい」妻の職場に届いた一通の手紙。夫のストーカーかと思い、家で尋ねると…
◆
この日の京子の講義テーマは『物語における複数人の視点』だった。講義までに読んでくるように、と京子が学生たちに指示を出していたのは、芥川龍之介の『藪の中』だった。
文庫本に収められると、わずか20ページほどという短編で、有名な作品でもあり、黒澤明監督も羅生門という映画で描いているので、もともと知っていたという学生もいたかもしれない。
『藪の中』という小説は、平安時代、昼でも薄暗い藪の中で26歳の男が殺された、という殺人事件にまつわる7人の証言だけで構成されている。
登場人物は、遺体の第一発見者、目撃者、容疑者の男、容疑者を捉えた役人、死んだ男の妻、その妻の姑、さらに死んだ男の霊を憑依させた巫女、の7人。
ところが、それぞれの証言は大きく食い違い、真実がわからないまま物語が終わる。《真相は藪の中》という言葉の語源にもなった小説だ。芥川龍之介は、この小説で一体何を伝えたかったのかと評論家や専門家たちの間で今だに議論が続いている、謎の多い作品でもある。
実は、京子にとってこの『藪の中』は、脚本を書く前に儀式のように読み直す大切な作品で、そのことを知っているのは夫の崇だけだった。
「皆さんは、誰の証言を真実だと思いましたか?」
京子の問いに、学生たちが順番に答えていく。
通常、真実は1つとされるのが世の常で、ある出来事に対して何人かの証言が食い違った場合、《誰かの言葉を信じるなら、誰かの言葉は嘘》となる。だが、京子がこの藪の中から学び、仕事の指針としている考え方は、その世の常とは少し違っていた。
「僕は、誰の証言も正しくない…完全な真実とは言えない、のだと思います」
そう答えたのは、友坂大輝だった。京子が、どうして?と先を促す。
「ある事柄に複数人が関わった場合、誰かひとりの人の意見だけで真実は語れない、ということをこの作品は伝えたかったんじゃないかな、って。
例えば、自分なりの真実を話しているつもりでも、無意識のうちに、自分に都合よく解釈するから真実が少し捻じ曲がる、とか…中には、保身のためにウソを言った人もいる。それがバラバラの意見になって…というか…先生、伝わります?」
「伝わりましたよ、ありがとう」
京子の言葉に、大輝は嬉しそうに、その笑顔を加速させた。きゃぁ♡と小さな声を上げたのは、いつもわかりやすい好意を大輝に向けている女子学生で、京子に向けられた笑顔にさえ撃ち抜かれてしまったようだ。
「では、皆さんにはこれから、この7人の証言を今文庫本に書かれている順番と違う順番で読むと、どうなるのか。構成の変化が、読後の印象に与える影響を試してもらいます」
『藪の中』の構成を入れ換えたPDFを、学生全員に送付する。全員が読み始めたことを確認してから、京子は大きな桜の木が見える、窓際に歩いた。窓は開け放たれ、優しい風が入ってくる。学生たちを見守りながら、PCに集中している大輝に目を留める。
― やっぱり…彼とは、感覚が近いというか…物語へのアプローチ方法が近いのかもしれない。
1人の学生の意見に肩入れするつもりはないが、京子が『藪の中』から学んだことはまさに、先ほど大輝が言った要素、《真実は人の数だけある》という考え方で、常にその視点を忘れぬように脚本を書くときには強く意識しているのだ。
そして、実は大輝と自分の感覚が近いと思ったのはこれが初めてではなかった。
これまでの授業や、大輝の脚本を添削した時にも、そう感じたことが何度かあった。大輝が京子の作品のファン故に、その作品群から京子の感性を吸収することで、京子に近づいてきているのかもしれないが。
構成の変化により作品の印象は変わったか?をそれぞれが発表し、さらに、自分が際立たせたい登場人物の意見を強調するために構成を変えるなら、どういう順番にするか?というディスカッションが終わったところで、京子は授業を終えた。
部屋を出ようとする京子に、大輝が近づいてくる気配があったが、京子は気づかぬふりをして、大輝が女子学生に捕まっている間に教室を出た。
授業中は、努めて考えないようにしていたし、少し忘れられていたけれど、教室を出た瞬間、夫が2日も家に帰ってきていない、という事実が、疲労感と共に、蘇ってくる。
― まずは、カドくんを捕まえなきゃ。
未だ現実味を帯びない、夫の浮気。どう決着をつけるにしても、まずはきちんと話さないと、と自分を奮い立たせながら廊下を歩き、校舎の外に出た時だった。
「門倉先生」
声をかけられ、京子は立ち止まった。
若い女性。知らない顔で、自分が教えている学生ではないはず…と思っていると、その女性が言った。
「長坂美里です」
綺麗なお辞儀をした後、この後お時間いただけますか?と微笑んだ長坂美里の視線に絡めとられ、京子は言葉を出せず、動けなくなった。
女子学生から解放された大輝は、京子を追いかけた。京子は、授業が終わればいつもすぐに帰ってしまう。次の授業は、京子の都合で、2ヶ月先になると聞いていた。だから今日、どうしてももう少しだけ、京子と話しておきたかった。
大輝は今、半年後が締め切りのシナリオコンテストに応募するつもりで作品のプロットを作っていた。京子は相談すれば、律儀な指摘を返してくれる。京子との時間を作りたいためだけに書いているわけではないが、京子に自分の作品を認めてもらいたいという想いが、創作意欲を掻き立てることにもつながっていた。
校舎を出て構内を抜け、京子がいつも使っているバス停へ向かう道を急ぐと、髪を一つに束ねた京子のすらりとした後ろ姿が見えた。ホッとして、さらに駆け寄ろうと思った時、隣に並んで歩く、同じく髪を一つに束ねた女性に気がついた。
― 先生の講義を受けてる子じゃなさそうだけど。
京子に嬉しそうに話しかけるその女性の横顔は、大輝と同世代に見えた。
彼女も京子に相談しているのだろうかと思い、声をかけることを遠慮し、大輝はしばらく2人の後を歩いた。京子のいつものバス停を通り過ぎても、2人は歩き続けていく。
オレ、ストーカーみたいで気持ち悪いかな、先約があるなら今日は諦めようか、などと思いながらも、京子を追う足を止めることができずにいた大輝は、あることに気がついた。
隣の女性がはしゃぐように京子に話しかけ続けているのに対して、京子は、1度も彼女の方に顔を向けていない。
京子は、口数が多くなく、愛想がよいタイプでもないが、話す相手の目をしっかりと見て受け答えをする。それは大輝に対してだけではなく、他の人とのやり取りを見ていてもわかる。そんな彼女があれだけ話しかけられているのに、一度も顔を向けないなんて。
違和感を覚えた大輝をよそに、2人はカフェに入り、窓際の席に向かい合わせて座った。
注文を取りに来た店員と言葉を交わす京子の顔に笑みはなく、店員が立ち去った後に対面の女性に戻された視線は、まるで何かを恐れるように、こわばって見えた。
― やっぱり、先生の様子が変だ。
大輝は心配になり、かといって正面に居座ることもできず、少し離れた所にあったガードレールに座りながら、京子の様子を見守った。対面の女性の顔は大輝の方からは見えなかったが、身振り手振りで話し続ける対面の女性に対し、京子は時々、短い言葉を発するだけだった。
15分程たっただろうか。京子は、その女性を置いたまま席を立ち、店を出てきた。その足もとがふらついた気がして、気づけば大輝は京子に駆け寄っていた。
「先生、大丈夫ですか?」
大輝を見た京子の瞳が、驚いた後、揺らいだ気がした。どうしてここに?と言われると思ったのに、京子が口にした言葉は意外なものだった。
「…どこかに…どこかに連れて行って」
「…え?」
「彼女から離れたいの…すぐに」
京子の唇は震えていた。今にも倒れてしまいそうな程顔色が悪く、大輝は思わずその肩を支えた。店内に目をやると、京子の対面に座っていた女性が振り返り、こちらを見ている。
大輝と目が合うと、その女性はほほ笑んで、ぺこりと頭を下げた。改めて見るとその顔に見覚えがある気がしたが…今は京子のケアが最優先だった。京子を支えながら女性に背を向けて、自宅へ帰すためにタクシーを止めた。
タクシーに乗ると、京子は背もたれに体をあずけて、目を閉じた。先生、運転手さんにご自宅の住所を…と大輝が言っても、京子は目を開けず、反応しない。
あの…どこに行けば…と、困った顔の運転手に頼られ、ぐったりと動かない京子への心配も増し、大輝は自分も乗り込むことにした。
「とりあえず、千駄ヶ谷の方に向かってください」
以前の雑談で、京子が夫と住むマンションは、千駄ヶ谷にあると大輝は知っていた。好意を向けてくる男に自宅の住所がばれるのは気持ちが悪いかも、と気を使い、1人で帰そうと思ったのだが、結局乗り込んでしまった。
顔色を失くし、苦しそうに眉間にシワを寄せる京子を見つめていると、大輝の胸が痛んだ。抱きしめて慰めたい欲をぐっとこらえるため、大輝は京子から視線を外した。
しばらく沈黙が続いた後、ごめんなさい、迷惑かけて、と小さな声が聞こえた。大輝が京子に視線を戻すと、京子は窓の外を見ていた。気にしないでください、と言った大輝に、窓の外を見たままで続けた。
「大輝くんは、お酒を飲む人?」
「…え…?」
京子に初めて大輝と呼ばれた衝撃で、すぐには答えられなかった。うれしいけれど、その弱った声に素直には喜べない。大輝の返事がないことで、伝わらなかったと思ったのか、お酒、飲む人?と、今度は京子に見つめられたので、大輝は慌てて答える。
「はい、そんなに強くはないかもしれませんけど」
「じゃあ飲みに行かない?今から」
「…2人でですか?」
「…家に帰りたくないの。付き合ってよ」
弱ったままの笑顔でそう言われて、もう、大輝が断れるはずはなかった。
どこでもいい、と言われたので、大輝が店を選んだ。千駄ヶ谷に住む京子が帰宅しやすいように、外苑前の店を選んだ。このまま向かえば、丁度オープンの18時頃に到着できるはずだ。
店に着き、4人席のテーブルに案内されると、京子は赤ワインを頼んだ。
どんな赤ワインが好きですか、などのたわいもない会話をしながら、お互い2杯目になるころには、京子の顔に表情が戻ってきたことにホッとし、大輝は、2人きりの時間を過ごせていることに、喜びを感じ始めていた。
「先生、さっき、僕のこと大輝くん、って呼んでくれましたよね」
「…そうだった?」
「あ、ひどい。なかったことにしようとしてます?これからはずっとそう呼んで欲しいです」
大輝は自分の笑顔を、グイっと対面の京子に近づける。大輝は自分の容姿が武器になることを知っている。京子が少しでもドキッとしてくれたらいい。少しでも異性として意識してほしい。でも京子の反応は、またも意外なものだった。
「…似てるの。あなたの名字が」
「似てる?」
「さっきの女の子。夫の不倫相手なんですって」
「…不倫…?ちょっと待ってください。先生の旦那さんって…」
京子の夫は有名な演出家で、門倉夫婦はお互いの能力を高め合う最高のパートナーであるという話を、同じ業界を目指す大輝は知っていた。京子の言葉が信じられず、大輝は思わず反論した。
「もしかして、さっきの子が言いに来たんですか?あなたの夫と不倫してます、って」
「うん」
「それ、彼女がウソをついてる可能性もありますよ」
実は大輝には、ウソでかき乱された経験があった。
大輝に恋をしてストーカー化した女性が、大輝の当時の恋人に、大輝と自分は関係をもった、大輝があなたと別れたがっているので別れてくれ、としつこくつきまとった。不安になってしまった恋人の誤解を解くために、ずいぶん苦労したのだ。
その例を説明した大輝に、京子がそれは大変だったね、と言い、私も、ウソだよって言われたかったんだけどね、と笑った。
「私の場合は、夫も自白済みなので」
「…え?」
「あの子と体の関係を持ったのは事実、ごめん、って謝られてるの。夫はそれきり家に帰ってきてない。さっきの彼女の話だと、今、彼女と一緒にいるらしいわ」
黙った大輝に、笑顔のままの京子が続けた。
「彼女は長坂美里さん」
「…」
「あなたは友坂大輝くん」
「…」
「…あれ?発音してみると、あんまり似てないか。坂、だけだね、一緒なの。でもあの瞬間、なぜか、あなたの名字が口にできなかったんだよね。なんでだろ。…バカみたいだね、私」
京子の瞳に、涙が浮かんだ。
「え。私、泣いてる?いやだ、なんで?」
ゴメン、生徒の前で泣くとか最悪だね、と京子はおどけようとしたけれど、涙は頬を伝いこぼれてしまった。うわぁ、ほんとゴメン、酔っぱらってるのかも私、とハンカチをカバンから取り出し、笑いながら涙をぬぐう京子に、大輝の胸が締め付けられる。
大輝は席を立ち、京子の隣に座ると京子を抱きしめた。え?ちょっと、何?と驚き、離して、と乞う声が、大輝の胸に直接響く。大輝はその腕に力を込めて言った。
「笑わず、思い切り泣いてください。作り笑いで、自分の痛みをごまかしたらダメです」
大輝の言葉に、京子の抵抗が止んだ。そして、声を押し殺した小さなすすり泣きが始まり、それが止まるまで、大輝はずっと京子を抱きしめていた。
◆
― 頭が痛い。
明らかな二日酔いで目を覚ました京子は、ぼんやりとした意識の中で、そこが自宅ではないことに気がつき、慌ててあたりを見渡した。
掛けられた衣服やインテリアが、男性の部屋であることを主張している。京子が今いる場所はキングサイズかな、という大きなベッド。自分の着衣を確認すると上下共にスウェット。男性のもののようで、かなり大きい。
部屋の隅に置かれているハンガーラックに、京子が昨日着ていた衣服が掛けてあった。起き上がり、その服を手に取りながら、なんとか昨夜の記憶を手繰り寄せようとしてみるものの、どうやってこの部屋にきて、ベッドに入ったのか全く思い出せない。
羞恥と情けなさがこみ上げたが、ここはおそらく大輝の部屋なのだろう。ベッドサイドのテーブルには、のどが乾いたら飲んでください、というメモと、水のペットボトルが置かれていた。
時計を見ると朝6時。京子は、自分の衣服に着替えると、部屋を出て、物音がする…人の気配がする方へ向かった。そこはリビングで、京子と目が合った大輝がパアっと輝くような笑顔になった。
「京子さん、おはようございます。コーヒー飲みます?」
「…京子、さん?」
昨日まで、先生と呼ばれていたはずなのに、という疑問に、大輝が答えた。
「あれ?もしかして覚えてない?昨日、京子さんが、京子さんって呼んでいいって言ってくれたんですよ」
講義の時はちゃんと先生って呼びますから、という大輝に、京子はそんな約束をした記憶がないと伝えたが、もう取り消せませんよ、と笑われてしまった。
「…なんで、私はここに?」
「うわ、全く覚えてないんですね。ひどい」
どこまで覚えてます?手つないで帰ったのは?オレが抱きかかえてベッドに連れて行ったのは?などの一言一言に、焦り、赤面し、とまどう京子を、大輝は上機嫌にからかい続ける。
「オレのスウェット着て寝ちゃった京子さん、めちゃくちゃかわいかったなぁ。オレ、もう遠慮しませんよ」
絶対、オレを好きになってもらいます!とウィンクをしながら、コーヒーを手渡してきた大輝に、京子は、未だに何が起こっているのか飲み込めないまま呆然とし。ウィンクが様になる日本人男性もいるのだな、と、今は絶対にそこじゃない、どうでもいいところで思考が止まり、パニックに陥っていた。
▶前回:「彼の子どもがほしい」妻の職場に届いた一通の手紙。夫のストーカーかと思い、家で尋ねると…
▶1話目はこちら:24歳の美男子が溺れた、34歳の人妻。ベッドで腕の中に彼女を入れるだけで幸せで…
次回は、3月2日 土曜更新予定!
酔っぱらった34歳の人妻。目を覚ましたら、知らない男物のスウェットを着てベッドで寝ていて…

関連記事
あわせて読む
-

「お水もらっていい?」デート4回目で初めて男性の家を訪れた33歳女が、水だけ飲んで急に帰ったワケ
東京カレンダー7/27(土)5:01
-

ダイソーさん…専用ポーチまでついて300円?太っ腹な本格アウトドアグッズ
michill byGMO7/27(土)11:00
-

40代の垢抜けはテク次第♡簡単にできる「垢抜けメイクのポイント」4つ
michill byGMO7/27(土)11:00
-

夫のモラハラが酷く離婚宣言 → 夫「俺もせいせいした!」と応じるも、離婚後【ストーカー化】して!?
ftn-fashion trend news-7/27(土)8:01
-

<強欲な女友だち>人の男を奪いまくる【寝取り女】がついに入籍 → 『地獄の結婚式』に、、、
ftn-fashion trend news-7/27(土)11:01
-

『脇汗染みてる、、』はもう卒業!【グローバルワーク】もっと早く出会いたかった!「機能性トップス」
ftn-fashion trend news-7/27(土)8:05
-

30年以上ひきこもる兄を“恥”だと思っていた57歳の弟、兄の存在が原因でフラれ続けEDにも…「もう背負うのは嫌だな」兄の死を願ってしまったワケとは
集英社オンライン7/27(土)11:00
-

65店舗出禁のパチプロが「過去に出禁になった事例」を暴露。店員に“パチプロだとバレずに打つ方法”とは
日刊SPA!7/27(土)8:25
-

ダイソーさん…どれか1つなんて選べないよ!悩んだ末に2つも購入してしまったキャラグッズ
michill byGMO7/27(土)11:00
-
-

「イケメンすぎる」「お名前は?」オペラ歌手兼ブレイキン選手にネット騒然 五輪開会式でパフォーマンス披露
まいどなニュース7/27(土)11:35
-

5匹の赤ちゃんシュナウザーの寝かしつけに失敗 「たすけて……」と言いつつ至福の時間
おたくま経済新聞7/27(土)7:00
-

ひきこもりの兄を持つ57歳男性「不妊治療をやめたら、1つ道が閉ざされた感じがした」家族にぶつけた怒りの矛先…突然の父親の死から向き合った初めての人間関係
集英社オンライン7/27(土)11:00
-

青春ドラマかよ!中学野球部の先輩後輩カップル、出会って10年の今もキュンキュン 新婚さんが眩しすぎて直視できない…
まいどなニュース7/27(土)11:55
-

銀行員「投資してみませんか?」50代の母が【1000万円を預けた】3年後 → 「何かおかしい」実は?
ftn-fashion trend news-7/27(土)7:31
-

「絶ッッ対に捕まえてやる!!」【野菜泥棒の隣人】を懲らしめるため → 『野菜に細工』をすると!?
ftn-fashion trend news-7/27(土)12:01
-

「ダブルクリックがわからん!」コールセンターに“高圧的な態度”を取り続けた50代男性の末路
日刊SPA!7/27(土)8:54
-

「オリンピック」みたいなクルマ!? “輪っか”の並ぶ「謎エンブレム」のクルマは何者? 気になるマークの意味と「似ている理由」とは
くるまのニュース7/27(土)12:10
-

どこ行くか迷う…!「KITTE大阪」のグルメスポット一挙紹介
Lmaga.jp 関西のニュース7/27(土)12:00
-
トレンド アクセスランキング
-
1

「お水もらっていい?」デート4回目で初めて男性の家を訪れた33歳女が、水だけ飲んで急に帰ったワケ
東京カレンダー7/27(土)5:01
-
2

ダイソーさん…専用ポーチまでついて300円?太っ腹な本格アウトドアグッズ
michill byGMO7/27(土)11:00
-
3

40代の垢抜けはテク次第♡簡単にできる「垢抜けメイクのポイント」4つ
michill byGMO7/27(土)11:00
-
4

夫のモラハラが酷く離婚宣言 → 夫「俺もせいせいした!」と応じるも、離婚後【ストーカー化】して!?
ftn-fashion trend news-7/27(土)8:01
-
5

<強欲な女友だち>人の男を奪いまくる【寝取り女】がついに入籍 → 『地獄の結婚式』に、、、
ftn-fashion trend news-7/27(土)11:01
-
6

『脇汗染みてる、、』はもう卒業!【グローバルワーク】もっと早く出会いたかった!「機能性トップス」
ftn-fashion trend news-7/27(土)8:05
-
7

30年以上ひきこもる兄を“恥”だと思っていた57歳の弟、兄の存在が原因でフラれ続けEDにも…「もう背負うのは嫌だな」兄の死を願ってしまったワケとは
集英社オンライン7/27(土)11:00
-
8

65店舗出禁のパチプロが「過去に出禁になった事例」を暴露。店員に“パチプロだとバレずに打つ方法”とは
日刊SPA!7/27(土)8:25
-
9

ダイソーさん…どれか1つなんて選べないよ!悩んだ末に2つも購入してしまったキャラグッズ
michill byGMO7/27(土)11:00
-
10

「イケメンすぎる」「お名前は?」オペラ歌手兼ブレイキン選手にネット騒然 五輪開会式でパフォーマンス披露
まいどなニュース7/27(土)11:35
トレンド 新着ニュース
-

ヨドバシcom、7/28までのFLASH SALE。SIMフリーiPhoneやテレビなどが安い!
PHILE WEB7/27(土)13:32
-

野外イベントにも! 「軽くて持ち運びやすいアウトドアチェア」おすすめ3選
Fav-Log by ITmedia7/27(土)13:30
-

今売れている「かき氷メーカー」おすすめ3選&ランキング とろふわ食感が楽しめる&ジュースやプリンの氷で作れるドウシシャ製品など【2024年7月版】
Fav-Log by ITmedia7/27(土)13:19
-

Motulレーシングオイルの性能を証明! 鈴鹿8耐上位10チームの半数が採用する実力
バイクのニュース7/27(土)13:10
-

トヨタ新型「スポーツカー」登場!“TE27風”グリーン色×タン内装がカッコいい! まもなく締め切り!? 「特別なGR86」反響は?
くるまのニュース7/27(土)13:10
-

「適応障害は甘え!」【無理解な姑と夫】に苦しんでいると → 「甘えてるんじゃなくて──」娘に感謝!
ftn-fashion trend news-7/27(土)13:01
-

【InRed付録使ってみた!】リトルミイ&ミムラねえさんの可愛いバッグ&ポーチ3点セットで、夏のお出かけ準備♪
InRed web7/27(土)13:00
-

【Her lip to】六本木ヒルズにてアイスクリームショップを期間限定でオープン♡
cocotte7/27(土)13:00
-

【uka】仕上がりによって選べるヘアオイルミスト3種を限定発売
美容最新ニュース7/27(土)12:45
-

アルプスの峠の名を冠した「アドベンチャーバイク」は日常の移動も快適! モト・グッツィの新モデルは“スポーティなライディング”も楽しめます
VAGUE7/27(土)12:40
総合 アクセスランキング
-
1

「日本見逃した」続出 開会式紹介が一瞬すぎて午前4時の視聴者悲鳴「トイレ行ってて…」「1時間半起きてあの一瞬」
THE ANSWER7/27(土)4:15
-
2

神田正輝「旅サラダ」休止で「X」トレンド入り…SNSは寂しさがあふれる事態に…「旅サラダがないので土曜日じゃないのかも」
スポーツ報知7/27(土)8:22
-
3

緊急降板の千賀滉大は「左足ふくらはぎの痛み」 球団発表…復帰戦で痛めて場内騒然
Full-Count7/27(土)10:16
-
4

開会式、バレー男子は全員不参加 西田有志「そっちよりも勝ち」
毎日新聞7/27(土)2:36
-
5

「トランプもハリスも無理」若いアメリカ人の本音 若者の2大政党に対する「不満」と「悲観」
東洋経済オンライン7/27(土)9:00
-
6

「格差エグくない?」「悪趣味としか思えない」パリ五輪の開会式で世界を騒然とさせた珍演出!“血しぶきの中で生首が歌唱”は 日本ではコンプラ的に絶対NG
集英社オンライン7/27(土)8:00
-
7

パリ五輪開会式、「韓国」を誤って「北朝鮮」と紹介 まさかのミスに韓国メディア激怒「お話にならない」「でたらめ」
THE ANSWER7/27(土)7:58
-
8

【パリ五輪】「がっかり」200億円かけた開会式で起きた“衝撃のトラブル”に観客は不満爆発!「台無しになった」
THE DIGEST7/27(土)8:39
-
9

山田涼介は尻に火が付いたか…目黒蓮にブッちぎられ《賞味期限切れ》のレッテルも?
日刊ゲンダイDIGITAL7/27(土)9:26
-
10

なぜ藤浪晋太郎は“事実上の戦力外”に? 指揮官説明…復帰の「センガのために」
Full-Count7/27(土)7:43
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

日本のミスして謝る文化を変えろ!欧米を知る吉田麻也が提言 「日本のスポーツ全体でなくしていくべき悪しき習慣」
Qoly7/27(土)13:00
-

U-23日本代表、パリ五輪マリ戦で「避けるべきこと」を“アフリカ通”トルシエが教える!
Qoly7/27(土)12:30
-

スカイツリーが「隅田川花火大会」の特別ライティング パリ五輪応援も
みんなの経済新聞ネットワーク7/27(土)12:25
-

日本の酷暑に悲鳴…来日のトッテナムFW 「これまでで最悪…クレイジーな暑さ、サウナみたい」
Qoly7/27(土)12:15
-

なでしこジャパンに痛手…主力DF清水梨紗が怪我でパリ五輪離脱「気持ちは一緒に戦い続けたいと思います」
Qoly7/27(土)12:10
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright © 2024 TOKYO CALENDAR INC. All rights reserved.