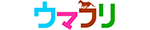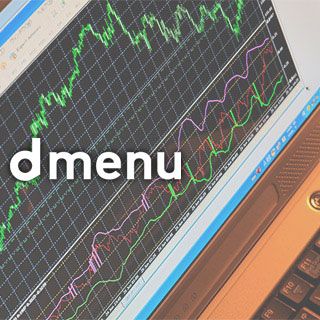淀の直線、最後の一完歩…。
鞍上の巧みな手綱さばきで馬群を縫い上げたレインボーラインは、粘るシュヴァルグランを内から交わし、歓喜のゴールに飛び込んだ。
2018年4月29日。私を競馬に引きずり込んだステイゴールドの、その産駒として3頭目となる春の天皇盾を、レインボーラインと岩田康誠騎手がつかみ取った瞬間だった。

私がいたのは"いつもの"ウインズ札幌。
人いきれの中、私は、レインボーラインの勝利にこぶしを突き上げ、刹那、興奮の絶頂に至っていた。
その、最後の一完歩。
明らかに、レインボーラインの前半身が「ガクン」と落ちた。
「あっ…!」
熱気の汗が一気に引いて悪寒に変わり、歓喜に突き上げた拳が、次に直視することとなるかもしれない冷酷な現実への恐怖に、震えていた。
「脚、やったかもしれないぞ…」
そんな声が、そこかしこから、聞こえてきた。
確か「DISC BOX」という名前だっただろうか。
20世紀末。競馬にのめり込み始めた私の今思えば旺盛だった知識欲が、私を(馬券も買わないのに)ウインズへ向かわせた。お目当ては「DISC BOX」で見ることができる、過去のレース映像だった。
備え付けられていた目次本からお目当てのレースに振られた番号を入力すると、いにしえのジュークボックス宜しく「BOX」の中に搭載されたレーザーディスクのディスクチェンジャーが作動し、ブラウン管の画面にレース映像が流れるというのがその仕組みだ。令和の世では(吉幾三が歌ったのとは逆の意味で)「レーザーディスクはナニモノだ」という声も上がろうが、そこはググっていただきたい(「ググる」ももはや死語かもしれぬが)。
「ブロードバンド」という言葉がようやく聞かれ始め、インターネット上での動画視聴など思いもよらない時代。GⅠレースや限られた名馬の歩みはレンタルビデオでまかなえても、「知る人ぞ知る」レースは、たとえ重賞であっても視聴の手段は限られていた。
競馬ファンの先達や当時隆盛を迎えていた競馬関連のムック本に書かれていた「伝説のレース」を、動画として見る手段は、当時の私には「DISC BOX」しかなかったのだ。
いつもその周りは込み合っていた。皆が互いの間合いを図りながら思い思いの番号を入力し、それぞれの「見たい」を共有し、また次のレース番号入力の機をうかがう。前の人がどのレースを入力したかなんてわからないので、たまに1990年の有馬記念が2回連続で流れたりもした。
シンボリルドルフが「持ったまんま」で馬場を一周してきたら勝っていた1985年の日経賞。
スプリングステークスの豪脚が鮮烈に過ぎたマティリアルの、最後の、そして最期の意地、1989年の京王杯オータムハンデ。
自分の「見たい」をDISC BOXは叶えてくれた。
そしてDISC BOXが私の記憶に強く刻み込んでくれたもう一つのレースが、1989年の弥生賞である。
芝の緑が全く見あたらない泥田のような不良馬場。
馬場を苦にしたか、後方から全く上がっていけない前年の最優秀3歳(現2歳)牡馬サクラホクトオー。
4コーナーで「イヤイヤ」をするように逸走していくロマネコンテイ。
そして他馬がもがく中ただ1頭、中山の直線を、水面を滑るがごとく突き抜け2着に1秒7の大差をつけた、レインボーアンバーの姿は、2分7秒7という勝ち時計とともに今でも脳裏に焼き付いている。
芝1000mのレースでデビューし、ダートで勝ち上がり、不良の弥生賞を制し、裂蹄で春の二冠は棒に振ったものの秋に復帰し、結果的にラストランとなった良馬場の菊花賞でバンブービギンの2着に食い下がったレインボーアンバー。わずか9戦の戦績に「重馬場の鬼」「距離万能」という記憶を残した。
何故こんな思い出話を長々としたかというと、そのレインボーアンバーが種牡馬となり、血統登録されたわずか25頭のうちの1頭、レインボーファストの娘レーゲンボーゲン(ドイツ語で「虹」)にステイゴールドが交配されて生まれたのが、レインボーラインだからである。
「なお1頭、ジョッキーが下馬。おぉっ? 12番レインボーライン、岩田康誠騎手が下馬しています…!」
場内実況も声を裏返らせながらレインボーラインの異変に触れる中、私は恐れに震える手でスマホを操作し、SNSを検索する。
「何かあったか?」
「岩田騎手が下馬した…。レインボーライン、痛そうだ…」
「馬運車が来た…」
「頼む、無事でいてくれ…」
ファンの悲痛な呟きが、私のタイムラインを埋め尽くしていた。
私の脳裏には、あの日DISC BOXで見た「最後の勝利」が「最期の勝利」となったマティリアルのことが、不意に浮かんでしまった(マティリアルは京王杯オータムハンデ1着入線後故障発生。手術の甲斐なく4日後にこの世を去っている)。
笑顔なき勝利騎手インタビュー。
口取りのない表彰式。

いたたまれなくなった私は、ウインズ札幌を後にし、家路についた。
当日にJRAから「右前肢跛行」と発表され、3日後の5月2日に精密検査が行われたのを最後に、レインボーラインの情報は、しばらく途絶した。
2歳、2015年の夏、札幌でデビューしたレインボーラインは芝1800m戦連続2着ののち3戦目で初勝利。一息ついて芝1800mのオープン、重賞に挑むも結果が出ず、距離をマイルに縮めた年末、阪神の千両賞で待望の2勝目を挙げた。
そしてそこから残り16戦、彼は様々な距離、条件の重賞に挑み続けていく。
3歳時にはマイルのGⅢ、アーリントンカップで5着まで同タイムの大激戦をハナ差制して重賞初制覇を遂げると、NHKマイルカップではメジャーエンブレムの3着と好走。ダービーにも出走を果たす(8着)。
そして夏の札幌記念で果敢に古馬に挑戦。のちの香港GⅠ馬ネオリアリズム、前年の年度代表馬モーリスに続き、オークス馬ヌーヴォレコルトを抑えての3着に食い込む健闘を見せると、次走菊花賞で一気の距離延長に挑み、勝ったサトノダイヤモンドにこそ決定的な差をつけられたものの、母母父レインボーアンバーと同じ2着を死守した。
NHKマイルカップと菊花賞でともに馬券内に入着した馬は、NHKマイルカップがはじまった1996年以降、レインボーラインただ1頭である(2024年4月現在)。
3歳、その距離万能性を見せ、充実の8戦を走り切ったレインボーライン。
明けて4歳、2017年シーズンのハイライトはなんといっても秋の天皇賞だろう。
日経賞4着、天皇賞(春)12着、そして宝塚記念5着で春のシーズンを終えたレインボーラインは秋初戦。
ここまでGⅠ5勝のキタサンブラックをはじめとするGⅠ馬8頭の豪華メンバーの中に入っては、出走18頭中単勝13番人気も致し方ないものであった。
しかし彼の血に入った無類の重馬場巧者レインボーアンバーの血が、26年ぶりの不良馬場で、レインボーラインを後押しした。
水煙を上げながら最後の直線を駆ける18頭。出遅れながらも武豊騎手の伝説的な最終コーナーイン突きで一気に先頭に立ったキタサンブラックを、それまでの国内重賞4勝すべてが稍重・重馬場のサトノクラウンが追い詰める。
勝ち時計2分8秒3(上述のレインボーアンバーが勝った弥生賞よりも遅い)、ラスト1ハロンが14秒0という歴史的消耗戦が2頭のデッドヒートで終わろうというゴールの場面、2頭のほかに唯一映っていたのが、2着サトノクラウンから2馬身半にまで食らいつき、4着以下を5馬身ちぎり捨てた、3着のレインボーラインだった。
完敗ではあったが、躍進の3着でもあった。SNSにはレインボーラインの健闘を称えるとともに、レインボーアンバーを懐かしむオールドファンの呟きが、数多く見られた。
そしてキタサンブラック、サトノクラウンとともにジャパンカップ(6着)、有馬記念(8着)と秋の古馬三冠を戦い抜いた(3頭ともなんとタフなことか)レインボーラインは、5歳春初戦の阪神大賞典を4コーナー大外から悠々と差し切り約2年ぶりの勝どきを上げると、勇躍春の天皇賞へと駒を進めてきたのだった。
そして、命を賭けた最後の一完歩で、10度目の挑戦にして初めて、GⅠ馬の栄誉に輝いたのである。
22戦5勝、2着3回、3着4回。
レインボーラインの競走成績は、刹那の歓喜とともに、突然の終わりを迎えた。
あれから6年。2024年になった。
時折私のSNSには、馬房から顔をのぞかせるレインボーラインの姿が流れてくる。その元気な、そしてお茶目にも見えるその姿に、癒される。
レインボーラインの引退が正式に発表されたのは、精密検査から1か月以上たった6月初旬のことだった。右前繋浅部屈腱不全断裂。無念と安堵が入り混じった感情を抱いていたことを思い出す。
彼には種牡馬としての第二の馬生が用意されたが、産駒を残せたのはわずか3世代。
初年度産駒のワイズゴールド(船橋所属)が岩手競馬の留守杯日高賞、金沢所属のダイヤモンドラインが地元のサラブレッド大賞典と、地方重賞2勝を挙げる活躍を見せたのは、彼が種牡馬を引退し、ノーザンホースパークで乗馬として暮らし始めた後のことだった。
一方でレインボーラインはノーザンホースパークに移動後、障害馬術に取り組み、去年(2023年)7月の大会では見事優勝したそうだ。
競走馬としてのレインボーライン。
種牡馬としてのレインボーライン。
そして今、乗馬として活躍するレインボーライン。
サラブレッドの様々な可能性を見せてくれているレインボーライン。
あの天皇賞、「最後の一完歩」を耐え抜いたからこそ、今がある。
産駒の活躍はまだまだ続く。そしてレインボーライン自身の第三の馬生も末永く続く。そう願いながら、ただひたすら応援するのみである。
それが、母母父レインボーアンバーをDISC BOXで知り、父ステイゴールドに脳を焦がされ、そしてレインボーライン自身の活躍と生命力に勇気づけられた一ファンに、唯一できることだから。
写真:Arata
著者:枝林 応一