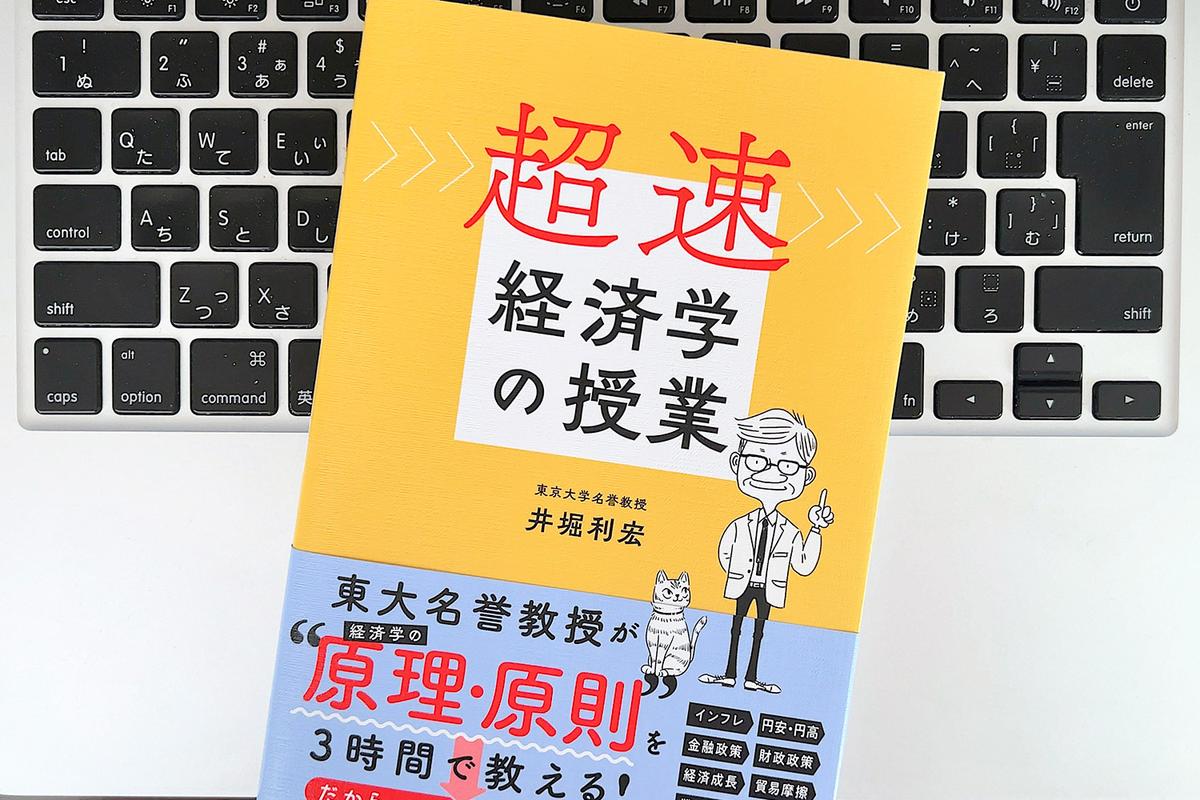「経済学を学びたいとは思うけど、なんだか難しそうな印象がある」
「そもそも毎日忙しく、じっくり学べる時間をとれない」
そんな思いを抱いている方も少なくはないはず。そこでおすすめしたいのが、きょうご紹介する『超速・経済学の授業』(井堀利宏 著、あさ出版)。財政学・公共経済学・経済政策を専門とする東京大学名誉教授が著した、文字どおり経済学を「超速」で学べる書籍です。
ちなみに、超速である理由は大きく2点。
ひとつは、一般の社会人が世の中の動きを知る上で身につけておきたい経済学の知識を取捨選択した点です。(「はじめに」より)
多岐にわたる経済学の範囲のなかから本書が焦点を当てているのは、インフレや円高・円安、国債、金利など私たちの日常生活に影響を与えるトピックス。学術的な理論は最低限に抑え、具体的かつ理解しやすい内容になっているため、忙しいビジネスパーソンでも短時間で理解できるはずだといいます。
もうひとつは、生徒と先生(私)の授業形式で話を展開していく点です。(「はじめに」より)
つまり、これまでの経験を活かしつつも会話形式にすることで、無理なくすらすらと読み進められるように工夫されているわけです。
きょうはスタートラインというべき第0時限「経済学は人類規模で実施する思考実験」のなかから、「経済学はなんの役に立つの?」に注目してみたいと思います。
経済の「しくみ=仕組み」を明らかにする
普段見るニュースのなかでも経済関連の話が理解できなくて困っています。そもそも経済学とは何なのでしょうか?(16ページより)
私たちは毎日働いてモノやサービスを生み出し、その一方では消費しています。
たとえば営業職の人が行っているのは、取引先から注文を取ってくることを通じ、自社がモノを生産するきっかけをつくること。企画職の役割は、会社の製品となるモノを生み出すために中心となる役割を果たすこと。そして販売職は、自社の製品を売り出すため、お客様との接客というサービスをしているわけです。
いいかえれば、どのような職業であってもモノやサービスの生産に関わっているということ。そして私たちが生み出したモノやサービスは、お店やインターネットなどを通じ、お客様の手に渡るのです。
経済学の目的はそれらがどのように分けられて、どのように社会で消費されるのか、またそれらの「しくみ」をより望ましい形にするにはどうすればよいかを明らかにすることです。(17ページより)
経済の「しくみ=仕組み」を明らかにできれば、モノやサービスが生み出されて消費される(経済活動)流れを予測したり、安定した豊かな社会を生み出したりする方策を考えることが可能になります。
つまり経済学は、現実の世界で私たちが豊かになるための方法を考えている学問だということです。(16ページより)
経済学はどうやって実験するのか
でも、経済の「しくみ」は目には見えませんよね。どうすればわかるのでしょうか。(18ページより)
経済学では「しくみ」を明らかにするために、さまざまな思考実験をしているのだそうです。とはいえ、てんびんやフラスコなどを使った実験を通して“さまざまな主張(=仮説)”を明らかにする科学であるならともかく、経済学の実験とはどのようなものなのでしょうか?
著者によれば経済学では、架空の世界を想定して経済社会のしくみを表すミニチュア(=モデル)を組み立て、それを利用して思考実験を行うのだとか。
たとえば、ホットドッグを買いたいと思ったとき、目の前にパン屋Aとパン屋Bがあるとしましょう。はたしてパン屋Aで買うべきなのか、それともパン屋Bで買ったほうがいいのか。基準は味かもしれませんし、値段かもしれません。いずれにしても、こうした架空の世界では、すべての人間が「合理的に動く」と考えるのだそうです。
合理的人間というのは、「(味や包装紙などの他の条件が同じなら)一番安い買い物をしたい」という経済的な動機で動く人たちのことをいいます。(19ページより)
より正確に表現するなら、「限られた条件のなかで、ある目的を達成するために、もっとも望ましい行為を選択する行動」をする人たちのこと。上記の例でいえば、2つのパン屋という限られた条件で満足度の高い買い物をする人たちのことです。
では、合理的人間はどのように満足度の高い行動をとるのでしょうか?
例えば、消費者(=家計)が「駅近くのスーパーで半額セールをやっているから、買い物に行ってみよう!」という行動をするとき、行動を引き起こした原因は「半額セール」という「値段」といえます。
合理的人間の行動を促す原因のことを難しい言葉で「インセンティブ(誘因)」といいます。(20ページより)
ここからもわかるように、経済学では「架空の世界に生きる合理的な人間がどのように行動するのか」をさまざまな想定したモデルを利用しながら思考実験しているわけです。(18ページより)
最初から読み進めれば、それぞれの経済知識がつながり、やがて大きな知識の「幹」となるように構成されているそう。
とはいえ各トピックは独立しているため、興味のある部分から読み始めてもOK。つまりは経済学を学びたい方にとって、非常に使い勝手のよい一冊だといえるでしょう。
>>Kindle unlimited、2万冊以上が楽しめる読み放題を体験!
「毎日書評」をもっと読む「毎日書評」をVoicyで聞くSource: あさ出版