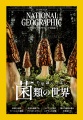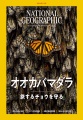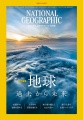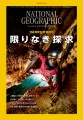仲間と群れながら、互いに餌の取り方、道具の使い方、そして独自の「言葉」を身に着けていく動物たちがいる。シャチ、チンパンジー、鳥類の社会には文化的要素があると言われているが、最新の研究調査でマッコウクジラにも同様の傾向がみられることが明らかになった。
ガラパゴス諸島周辺の海には、数千頭のメスのマッコウクジラとその子どもたちが生息し、それぞれの群れには独自の「方言」がある(成熟したオスは、これとは別に極地に近い冷たい海に集まる)。こうした方言をもつ群れがどのようにして形成されるのかは、これまであまり知られていなかった。(参考記事:「イルカ・クジラの「潜水病」、集団座礁の一因か」)
9月8日付「Nature Communications」誌に発表された研究報告によると、マッコウクジラの群れは、それぞれの「文化」によって一つにまとまっているのではないかという。ここでいう文化とは、メンバーに共通する行動を指す。特に海の奥深くまで潜るこのマッコウクジラの群れは、互いにコミュニケーションをとり、社会的交流を図るのに、特有の連続したクリック音を発している(コーダと呼ばれる)。
同じような行動をとるマッコウクジラが共に過ごすあいだに、互いに音の発し方を学び合う。科学者はこれを社会的学習と呼んでいる。そうして「同じ言語を話す」クジラ同士がくっつきあって、群れを形成していくというのだ。
動物にも文化がある証拠?
論文の筆頭著者で、カナダのハリファックスにあるダルハウジー大学の海洋生物学者マウリシオ・カンター氏は、動物にも文化があるという考え方をさらに裏付ける研究結果であるとしている。
群れはどのように形成されるのか、カンター氏の研究チームがコンピューターシミュレーションを行ったところ、遺伝的つながりや母から子への情報伝達という要因だけでは、自然界で観察したパターンを説明することはできなかった。チームの分析から導き出された最も納得のいく説明は、マッコウクジラが「うまの合う」仲間同士で集まっており、発声の仕方を互いに学習し合っているというものだった。(参考記事:「あえてジグザグに進むアリの賢い行動を解明」)
人間だけではない「社会的行動」
人間に特有のように思える行動を、クジラなど他の動物が見せるのは非常に面白いとカンター氏は言う。実際のところ「私たちは彼らとそれほど変わりません」。
シャチにも、群れによって独自の言葉がある。ザトウクジラは、社会的ネットワークを介して新しく覚えた捕食法を仲間へ伝え、チンパンジーは道具の上手な使い方を互いに教え合う。
カンター氏は、動物についての理解が深まるにつれ、人々が環境に関心を向けるようになり、地球環境保護の動きが高まることを期待している。(参考記事:「海の歌い手 ザトウクジラ」)