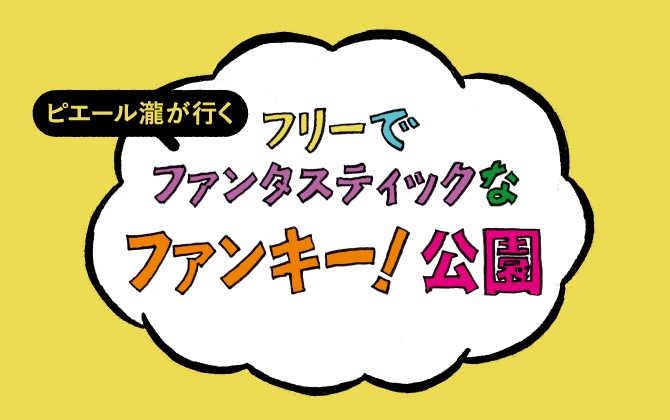自分が怒られることへの耐性が低いと気づいたのは小学生の頃だった。体育の時間に友人とふざけていたら、さっきまで穏やかに微笑んでいた教師がいきなり「ええ加減にせえよ!」と怒鳴り、数分間説教を受けた。その後、一緒に怒られた友人は5分も経てばケロッとした顔で再びふざけ始めていたが、私は30分経っても怒られたことを引き摺(ず)ってうまく笑えなかった。当時多くの男子の間には「怒られ慣れている方がかっこいい」というムードがあり、すぐに元気をなくしクヨクヨしている自分が嫌だった。大人にゲンコツを食らってもペロッと舌を出し走って逃げていく下町の子供のような、そんなタフな子供に自分もなりたかった。
友人に「怒られるのがつらくないのか」と聞くと、「お母さんに怒られるのに比べたら先生なんて全然怖くないわ」と余裕の顔をしていた。自分は家庭で甘やかされていると言われているようで情けなかった。今考えれば私の家庭が特段甘かったわけでもないと思うが、なぜか私には友人のようなヤンチャ坊主感が備わらなかったのだ。
私はちょっと怒られただけでもドロドロとした思考をつい巡らせてしまう。今の怒られ方に正当性はあったのか。ただ怒りにまかせて怒ったのか、それとも教育としてあえて怒ったのか。怒るタイミングを窺(うかが)いながら臨界点を超えるまで様子を見ていたのかと思うと、何も気づかずはしゃいでいた自分が滑稽だ。また怒り終えた後、これでノーサイドだから、といった態度でやけにフレンドリーに接してくるのも素直に受け入れられない。自分には常に上から叱る力があるが、今は出さないでおいてあげるから、と言われているようで屈辱を感じる。相手も自分と同じダメージを受けなければチャラにはならないはずだが、やり返す機会は来ない。
H先生の怒り
教師に怒られるたび、自分もいつかこんな風に瞬間的に怒りをぶちまけられるようになるのかと思っていた。しかし未だに上手く怒ることができない。心の中で怒りが沸騰しても、声を荒げて怒ったことは多分今までに一度もない。
もっとも、私と同じようにうまく怒れないタイプの教師も何人かいた。中学時代のI先生は、いかにも穏やかというかもったりした人で、大きい声で怒ると声が震えたりやたら言葉が詰まったりして、生徒によくモノマネされていた。また中2の途中から非常勤で入ってきたH先生は将棋の村山聖のようなどっしり太っているがいかにも内向的で繊細そうな顔をしていた。H先生は生徒が騒いでいると突然こちらがビクッとするような声量で「黙れって言っとるやろがオラァァ!」と叫ぶ。私は普通にビビっていたが、周りにいたヤンキー中学生は舐(な)めても良い人を選ぶ力に長けているらしく、いくら怒られてもH先生を小馬鹿にして授業中遊んでいた。確かにH先生の怒りにはどこか心がこもってないというか、怒り慣れていない人が無理して怒っているような不自然さがあった。
ある日の掃除時間中、H先生が「俺って舐められとんかなあ」とボソッと心情を吐露してきた。同様に周囲から舐められていそうな私にシンパシーを抱いたのだろうか。だが当時ヤンチャな感性を持っていると思われたかった私は「まあ暗そうだから舐められるんじゃないですかね」と偉そうに返事すると、先生の顔が途端に険しくなり不穏なものを感じた。
一週間後、朝礼で校長が「H 先生は家庭の都合で退職されました」と発表した。聞いた話によると、実際は授業中にビンタをしてきた上級生をボコボコに殴り返して辞めさせられたらしい。私は心の中で「よくやった」とガッツポーズをしつつも、H先生もやはり自分と違ってブチ切れることのできる人だったのかと少し寂しくなった。
怒らないと舐められるなどというのは高校生くらいまでの話かと思っていたが、大人になっても、自分がヘラヘラしているせいで不当に扱われていると感じることが多々ある。怒るタイミングは難しい。100対0で相手が悪いと言える機会はそうそうなく、「確かに自分にも悪いところはある」などと考え出したら一生怒れない。
今でも感情的に声を荒げたりするのは無理だが、それでも最近はできるだけ怒りを表に出すように努めている。怒る基準は自分が「不快に感じたかどうか」だけでいい。自分に悪いところがあったとしても、不快だと感じたらそう伝える。そうすると相手は意外とこちらの思いを尊重してくれるものだとだんだんわかってきた。
先日地元に帰った際、昔ヤンチャだった中学の同級生とすれ違った。そいつは「お前まだあれやっとん? なんやっけ、あのトリプル(笑)ファイヤー(笑)やっけ?」と明らかに馬鹿にした態度で言ってきたが、その時は時間がなく「ああ、やっとるよ別に」と余裕ぶって済ませてしまった。
次に同じことを言われたら「それ、馬鹿にして言っとるよな。めっちゃ腹立つんやけど」と淡々と伝えよう。イメトレはもう数十回も済ませた。「お、おう……」と虚を突かれた同級生の顔を今から想像しワクワクしている。
文=吉田靖直 撮影=オカダタカオ
『散歩の達人』2024年2月号より