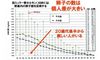不妊治療、努力ではどうにもならない精子の数や運動率。やはり年齢が重要・産科医
子どもを授かるには、どうしても年齢という壁があります。
不妊の記事を配信するたびに「もっと早く知りたかった」という声が届きます。
「選択したつもりではなかった」「学校で教えてほしかった」「男性も知るべきと思った」。いつか子どもを授かりたいお思った時のために、もっと前から知っておきたいことを特集としてお届けします。
特集「授かるチカラ」 連載「産科医・齊藤 英和 授かるチカラとは」第2回
精液の量は年齢とともに減る
今回は第2回目。男性についてもお話ししましょう。最近10年ぐらいの妊活の話題は、「卵子の老化」という言葉に象徴されるように、女性に関わることが多かったように思います。また、私がまだ新米の医者であった40年ぐらい前の教科書では不妊の原因は女性が9割、男性が1割などと言われており、不妊検査といえば、まず女性側の不妊原因検査が最初でした。しかし、ご存知のように、現在では、不妊原因はほぼ半々、不妊原因検査をするのであれば、男女とも、一緒に検査を開始することをお勧めしています。
まず、男性の検査で最初に行われる精液検査の年齢による影響をお話ししましょう。精液検査では、精液量、精子濃度、精子運動率、精子奇形率、などが一般的に検査されています。表1は数ある報告の一つです。
表1 男性年齢階層別の精液所見
40歳未満と比較すると、年齢が高くなると精液量、精子濃度、精子運動率、総運動精子数などが徐々に低下してきます。これらの値は平均ですが、この値ですと低下はしてもそれほど問題が無いように見えます。
確かに、正常な精子一個が卵子と受精すればよいのですが、総精子数のこの程度の低下では、ほとんど影響がないと思われるかもしれません。
しかし、精子も卵子と同様個人差が大きく、わずかではありますが、かなり厳しい精子所見の方が増えてきます。
また、精子にとって、大切なのは「数」だけではなく「質」も大変重要です。「質」の変化はもっと若い頃から起こっていると考えられています。この精子の質を直接測定するのは、なかなか難しいのですが、いろいろな現象でお話ししましょう。
図1 妊娠に至るに要する期間(月)
●妊娠するまでにかかる時間●
図1を見てください。このグラフは男性の年齢を横軸にとり、妊娠を試みてから相手の方が妊娠に至るまでの期間を示したグラフです。男性の年齢が20代までは、約6か月で相手の方が妊娠しますが、30代から40代前半だと、相手の方が妊娠するまでの期間は約10か月かかります。
40代後半だと約18か月(1年半)かかるようになり、50歳以上だと24か月(2年)以上かかるようになります。男性の年齢が高齢化すると、相手の方が妊娠するまでの期間が長くかかることがわかります。
男性の年齢が高くなると、相手の女性の年齢も高くなる傾向はあります。しかし、そのことを補正しても、男性の年齢が高くなると、相手の方が妊娠までにかかる期間が長くなるとされています。
●1年間の累積妊娠率も下がる●
男性の年齢別の1年間の累積妊娠率を見ると、どの年齢でも、児を持つことを希望してからの期間が長くなると累積妊娠率は上昇していきますが、図2にあるように、1年後の累積妊娠率で見ると、男性が20歳未満のグループで90.4%、20歳から39歳のグループで78.4%、40歳から49歳のグループで62.6%、50歳以上で25%と、やはり男性の年齢が高くなるほど、挙児(子どもを授かること)を希望してから1年後の累積妊娠率も低下しています。
図2 男性の年齢別累積妊娠率
相手の女性の妊娠する確率から見ても、男性の妊孕性(にんようせい)が加齢とともに低下してくることがわかります。
図1,2の結果は、男性の加齢に伴い、精子の質が低下し、妊娠至る期間が延長したり、一定期間(1年間)に妊娠する率が低下したりしたものと考えられます。
●流産リスクが高くなる●
では次に、妊娠された相手の方の流産率について、そのパートナーである男性の年齢との関係をグラフで見てみることにしましょう。図3の横軸は男性の年齢です。縦軸は相手の方の相対的流産リスクです。20歳を1としています。
図3 流産リスク
男性の年齢が上がるとともに、妊娠した相手の流産リスクも上昇します。女性の加齢でも流産リスクは上昇しますが、それを補正しても、男性の年齢だけでも上昇するということがわかっているのです。
精子の高齢化と子どもの先天異常のリスク
男性の年齢と出生児の先天異常のリスクについても、実は厳しい現実があります。
出生児の先天異常のリスクも、女性の加齢と深く関わっていますが、その影響を補正して検討したのが、図4になります。男性の年齢25歳から29歳を対照として、各年齢のグループと比較しています。
図4 男性の加齢と先天異常
若いグループ(20歳未満)でも、少しリスクが上がっています。はっきりした原因は不明ですが、未熟性が原因の一つであると考えています。
一方、30歳以上では、年齢が高くなるに従い、出生児の先天異常のリスクが明らかに上昇しています。その原因は、精子の遺伝子が加齢にともない障害を受ける可能性が高くなることだと考えられます。
ここからは、遺伝子に関する少し難しい話になります。精子それ自体に起こる年齢による「質」の低下は、精子遺伝子の断片化とポイントミューテーションが考えられています(表2)。
表2 男性の加齢と精子の質の劣化
遺伝子の断片化は遺伝子配列のいろいろな部位で断裂が起こることですが、この現象によって妊娠率の低下、流産率の上昇、先天異常の率の上昇などが生じます。一方、ポイントミューテーションは、精子の基の細胞(精祖細胞)が増殖するときに起きる、遺伝子のATCGの一つの塩基が、別の塩基に置き換わることで、簡単にいえば、遺伝子に微細な変化が起こることで生じる現象です。
精子は卵子と異なり、高齢まで分裂増殖している細胞です。つまり、分裂回数が多くなるほど、遺伝子配列にミスが起こりやすいのです。1年間に約2個のミスが起こると推計されています。
30歳加齢すると、30年前より、精子の微細な遺伝子異常は、約60個増える、と考えられるわけです。この遺伝子配列のミスが起こる場所はさまざまで、アミノ酸など体を作るのに大切な遺伝子配列の場所に起こる場合もあれば、体を作るのには関与しないところで起こる場合もあります。
具体的な影響として現れるかは、変化した場所によるということになります。しかし、です。やはり遺伝子配列に変化が起こる箇所が多くなると、「数撃てばあたる」というように、影響が出る可能性も高まります。
生まれた数年後にわかる、精子の質
そして、このポイントミューテーションには、もう一つ、大きな問題があります。それは極小な変化と述べたところにあります。
変化が大きい場合には、「妊娠しない」「妊娠しても流産する」「生まれてすぐに先天異常とわかる」というように、はっきりとした影響が、早期に現れます。しかし、ポイントミューテーションは、その変化が微小であるために、生まれる(流産しない)可能性は高いのですが、生まれた直後には異常がわからず、大きく発育してから、「なんとなくおかしい」と、気づかれる可能性があるということです。分裂回数が多い精子、すなわち高齢な父親から生まれた子に、なんらかの変化が現れることが考えられています。
現在、疫学的研究で分かっていることは、高齢の父親から生まれた子に、発達障害や精神疾患を持つ子が多いということです。自閉スペクトラム症、注意欠如/多動性障害、鬱、統合失調症といった疾患です。これらの病気は、「父親の高齢」が理由のすべてではありません。
もちろん父親が高齢でもなんの問題もない子もたくさんいますが、「父親の高齢」によって発症率が高くなっている可能性はあります。
以上をまとめてみますと、年齢が高くなるにつれて精子の数が減少し、質が低下してきます。これらを考慮すると、男性においても、妊娠適齢は20歳代と考えるのがよいと言わざるをえないでしょう。もちろん、人それぞれのライフプランがあると思います。しかし、これらの知識を知ったうえでなのか、知らないままでなのかによって、立てるライフプランは異なってくるのではないでしょうか。
若い時期にいろいろな知識を得て、考えてみてください。
(文/齊藤英和 撮影/古谷利幸 構成/関川香織)
齊藤英和(さいとう・ひでかず)
産婦人科医師。元国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 副センター長。現在梅が丘産婦人科ARTセンター長。長年、不妊治療の現場に携わっていく中で、初診される患者の年齢がどんどん上がってくることに危機感を抱き、大学などで加齢による妊娠力の低下や、高齢出産のリスクについての啓発活動を始める。
著書に「妊活バイブル」(共著・講談社)、「『産む』と『働く』の教科書」(共著・講談社)


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い