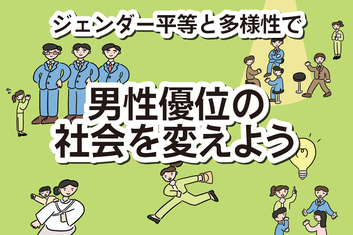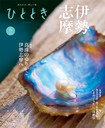戦後の木材需要により多くの木々が植えられ、育てられてきた日本。森林大国の日本における林業は、今後どのように発展していくべきなのだろうか。
木々の健康を守るはずの間伐により起こる問題、花粉症対策から見える政策の穴――。日本の林業の課題を紐解く、必読の記事を集めました。
国内産業について問いかける人気記事の中から、<林業>をテーマにした4本を編集部が厳選してお届けします。
<目次>
1:【日本の林業は奇跡】開発と環境保護を両立してきた山林利活用の歴史と、これから進むべき道とは(2023年6月5日)
2:「信用を裏切る林業界に明日はない」盗伐、放置、鳥獣被害……山積みの課題に林野庁は机上の空論でなく研究を(2023年8月6日)
3:「60年間で1800万本植樹」山林活用による国力増強を唱えた“明治の巨人”から林業再生を学べ(2023年6月2日)
4:【税金の無駄遣い、精神論、反省なし】の林野庁が立てた花粉症対策予算から見えてくる林政の不可思議さ(2023年9月15日)
1:【日本の林業は奇跡】開発と環境保護を両立してきた山林利活用の歴史と、これから進むべき道とは(2023年6月5日)
通常、物事というのは、「あちら立てればこちら立たず」といった二律背反(トレードオフ)のケースが多い。例えば、これまでの「経済・生産」対「環境・公益」などはそのような関係にあったといえる。
それに対して、「予定調和」とはドイツの哲学者・ライプニッツによる哲学用語で、「神があらかじめ定めていた調和によって世界の秩序が整っているという原理」と説明される。宇宙は無数の単子(モナド)からなり、互いに作用し合うことなく独立しているが、それが調和しているのは神の定めたところによるというものだ。
私利私欲に突き動かされる人間たちの無秩序で乱雑な行動も、アダム・スミスによる「市場」という仕組みの発見できれいに説明できた。アダム・スミスはその説明の美しさに感激して、市場には「神の見えざる手」が働いているといったとされているが(真偽のほどは分からない)、ここにも神による予定調和的な考え方を見て取ることができる――。
【続きはこちら】
さらば!林野庁による「林業の成長産業化」
2:「信用を裏切る林業界に明日はない」盗伐、放置、鳥獣被害……山積みの課題に林野庁は机上の空論でなく研究を(2023年8月6日)
これまで3回にわたって、間伐について紹介してきた。説明は長ければいいというものではないが、これまで多くの場合、間伐についてあまりに簡単な説明ばかりがなされていたようで、誰もがすぐに分かった気になっていた。一般市民だけでなく専門家でもそうだったようで、筆者の記事を読んで改めて考えさせられたという声が寄せられている。
最後に間伐に関わる問題点をあげてみたが、改善方法を簡単に示せない難問が多い。
間伐対象木には胸高部に白いビニールテープ等が巻かれ、すぐにそれとわかるようにする。かつての国有林では、白テープの表示のほかに、根もと部分の樹皮を削って、ナンバーテープをホチキスで打ち、さらに極印(こくいん)を打刻した――。
【続きはこちら】
3:「60年間で1800万本植樹」山林活用による国力増強を唱えた“明治の巨人”から林業再生を学べ(2023年6月2日)
「年間10万本から100万本、平均して30万本の苗を植えた」。吉野の林業家、土倉庄三郎が晩年に漏らした言葉である。15歳から約60年間で1800万本の木の苗を植えたというのだ。これがとてつもない本数、面積であるのは言うまでもない。
庄三郎は明治の山林王である。その所有森林面積は、最大時で9000ヘクタールだったという。だが庄三郎が植えたのは吉野だけではない。自ら全国で植林事業を展開するだけでなく、全国を講演して歩いた。また、資産家に山林を所有して経営するよう勧めた。実際に山県有朋など山に投資した政財界人は多い。現在、日本第4位の森林所有者である三井物産(三井家)が山を持つきっかけも、庄三郎の勧めに応じた結果である。そうした山々における植林も含めたら、いったい何千万本の木を植えたことになるだろうか。
なぜ、それほど植林に熱心だったのか。もちろん第一義的には、林業を行うためである。土倉家は植えて育てた木を収穫することを家業としていた――。
【続きはこちら】
4:【税金の無駄遣い、精神論、反省なし】の林野庁が立てた花粉症対策予算から見えてくる林政の不可思議さ(2023年9月15日)
2024年(令和6年)度の林野庁関係予算概算要求には政策目標として、「国産材の供給・利用量の増加(3400万立方メートル(㎥)[21年]→4200万㎥[30年まで])」とされている。供給・利用量とは主に丸太と燃料材の生産量らしく、これを毎年100万㎥ずつ増加させていき、2030年(令和12年)以降は42万㎥を持続させようというのだろうか。どういう根拠に基づいた数値なのか不明であり、花粉発生源対策との関連も闇の中である。
花粉対策と関係ないのなら、なぜ100万㎥増やす必要があるのだろうか。最近はウッドショックでせっかく木材価格も少し上がったところなのに、政府はこれに冷や水を浴びせるつもりなのか。
原料を安く仕入れたい大手の木材加工業や、ウッドショックで燃料材が値上がり・不足して操業停止の相次ぐバイオマス発電所などは大喜びだろうが、一番の被害者はこれまで良質材生産を担ってきた篤林家や良心的な間伐を主体に実行してきた自伐林家であろう。これら営々と日本林業を支え続けてきた林業者を根こそぎ廃業に追い込むのではないか――。
【続きはこちら】
![]()
![]()
![]()
▲「Wedge ONLINE」の新着記事などをお届けしています。