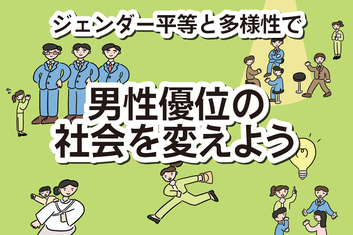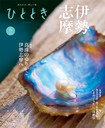日本経済の潮目が変わりつつあります。
2022年春以降、世界的なインフレを背景に、日本でも物価が上昇し、賃金も上がり始めました。厚生労働省によると、23年の春闘での賃上げ率は3.6%で、1994年以来30年ぶりに3%台となりました。さらに、24年の賃上げはそれを上回る見込みで、連合(第4回回答集計結果)によると、賃上げ率は全体で5.2%、中小企業でも4.75%に達しています。
このような動きを受け、日本銀行は3月に、「賃金と物価の好循環」により、2%の物価目標が安定的・持続的に達成できる見通しが立ったとして、17年ぶりに利上げし、金融政策の正常化に踏み出しました。
「賃金も物価も上がらない」ことが常態化していたこれまでの状況から、「賃金も物価も上がる」という前向きな意識を定着させ、経済の活性化につなげることが求められています。
個人消費を拡大し、日本経済を成長軌道に乗せるには、安定した賃上げの継続が不可欠であり、来年以降もその持続力が問われています。
そもそも「春闘」とは?
ここで、春闘について改めて考えてみましょう。
春闘とは、労働組合と企業の経営陣が賃金の引き上げなどを交渉する「春季労使交渉」のことです。一般的に、企業や官庁は、新年度が始まる4月に従業員の給与水準を見直すため、労働組合はその前に賃上げを要求します。本格的な交渉は例年2月から3月にかけて行われるため、「春の闘い」、すなわち春闘と呼ばれます。
日本の労働組合は多くが企業ごとに組織されているため、交渉力が弱くなりがちです。そこで、個々の組合が連携して一斉に行動を起こすことで、この弱点を補おうという意図から春闘は始まりました。高度成長期には毎年賃上げが行われ、春闘は日本の賃金決定に大きな役割を果たしてきました。
本来は労使間で交渉が行われるものですが、14年以降、政府が経済界に賃金の引き上げを要請する「官製春闘」が行われています。