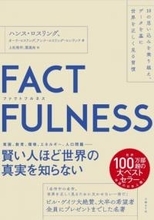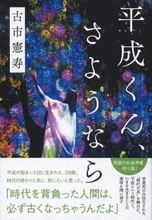写真家・渡部雄吉(1929−1993)のドキュメント写真集『張り込み日記』は、昭和33年にじっさいに起こった、通称「茨城県下バラバラ殺人事件」を捜査する2人の刑事に約20日間同行して撮影されたものだ。神保町でイギリスの古書店バイヤーによってオリジナルプリントが発見されたことをきっかけに、まず、2011年にフランス版が刊行されたのち、2013年にはroshin booksより日本版も出て、ともに話題を集めた。そして、今回紹介するナナロク社版(2014年)は、構成・文に作家の乙一、アート・ディレクターにブックデザイナーの祖父江慎とcozfish(祖父江の事務所)の柴田慧を迎え作られた、いわば再編集版である。
今回この写真集を取り上げたのは、ミステリ小説を読んでいる時のように興奮して、時間を忘れ、どっぷりその世界にハマり込んでしまったから……なのだが、それだけではない。私事で恐縮だが、遺体の遺棄現場である千波湖は、じつは私の実家の近所なのだ。中学のマラソン大会では湖の外周を走ったし、お約束のスワンボートにも乗ったことがある。あるいは、アヒルに餌やりをして噛まれた、公衆トイレで痴漢に出くわしたといったトラウマ系の思い出もたくさんあり、要するに、たいへんなじみ深い場所なのである。周辺には、日本三大庭園の1つである偕楽園や、レストラン、美術館があり、人通りも多い。つまり、現在においては、陰惨な殺人事件の死体遺棄場所としてイメージしづらい、開けた場所なのだ。
スタイリッシュかつ躍動感あふれるモノクローム世界は、どうしても「フィルムノワールを思わせる」とベタな表現をせざるを得ないほどに、まんまその世界である。記録写真と知らなければ、まず映画のスチールと見まがうはずだ。写真の素晴らしさについては、ネット上でも何点か見ることができるし、現物に当たってもらった方が早いだろう(例えば、前述のroshin booksのホームページで見られる)。ここではその代わりに、あとがきに当たる、乙一による巻末の文章「昭和の事件に触れて思うこと」に触れておきたい。もちろん写真集なので、写真がメインではあるのだが、それに負けないくらい興味深い内容なのだ。
その前に、本書の大まかな流れを説明しておこう。死体遺棄場所とおぼしき場所を歩く刑事の姿から始まり、聞き込み捜査や、電話でタレ込みや報告を受けているとおぼしき様子、あるいは捜査が難航して煮詰まっていく様子などを経て、自宅と思われる一室でくつろぐ刑事の姿へと収斂していく。言うなれば、事件発生から解決までを追ったように「見える」のだ。これこそが、先行する写真集があるにもかかわらず、わざわざ新たな『張り込み日記』が企画された目的であり、最大のコンセプトだろう。乙一は書く。
この写真集にはトリックが使用されている。
「茨城県下バラバラ殺人事件」は、解決までに半年以上を要した。しかし、前述したように、渡部が刑事たちに同行したのは20日間程度である。つまり、この写真集に収められた写真は、捜査のごく一部を切り取ったものに過ぎない。事件の全貌を記録したものではないのにもかかわらず、そう見えるというのはどういうことか。
どの写真をどのような順番で配置すれば事件を追いかけているように見えるのか、というディレクションをおこなった。
作家である乙一に求められたのは、限られた素材と事件の顛末を綴ったテキストによって、いわば物語を構築するという役割だったのだ。よって本書は、ドキュメント写真集でありながら、フィクションにおける語りの手法やテクニックが透けて見える、ひじょうにユニークな内容になっている。この、あとがきにおける種明かしによって、ドキュメンタリーとしてはもちろん、ミステリ小説として、フィクションの教科書として……と、読者に多様な楽しみ方を提供してくれるのが、ナナロク社版 『張り込み日記』なのである。
ちなみに、本書の冒頭を飾る写真について「荒涼とした千波湖付近」と書いたが、キャプションなどがあるわけではないので、確証はない。私には「そう見えた」だけである。
(辻本力)