降りしきる雪の中、家屋や船が濁流をさまよう―。東日本大震災の津波被害を伝えるその写真は、宮城県塩釜市の浦戸諸島・野々島で撮影された。一帯は当時、最大8メートル超の津波に襲われた。もともと過疎化が進んでいた地域だが、津波で家や仕事を奪われた住民は次々に島を去っている。震災から13年。塩釜港から市営汽船で浦戸を巡ると、様変わりした景色に戸惑いながらも、かつての文化や記憶をつなぐ人々の交流が見えてきた。(共同通信=小向英孝)
▽「つながりがなくなるのは嫌」
浦戸諸島は日本三景の一つ松島(宮城県)の湾内にあり、有人4島と多くの無人島から構成される。東日本大震災の津波では、全体で家屋の約半数が全壊・流失し、4人が犠牲になった。過去に幾度も津波に見舞われ、寒風沢島には1960年のチリ地震津波の被害が刻まれた石碑が残っている。
浦戸諸島で人口が最も多い桂島。漁業などの就労支援施設で働く内海信吉さん(64)は「(島民は)何をするにも一緒だった」と話す。誰かが家を建てれば本州から船で資材を運ぶ。地区ごとに分かれて競う運動会の後は、酒を囲んで語り合った。狭い島ゆえ、家族のような絆が生活を支えた。
震災発生時も「誰がどこにいるか把握できていた」。約半数が高齢者だったが、消防団員は歩行困難な住民を軽トラックに乗せて優先的に搬送。住民同士でも避難を促し、全員無事だった。土地柄、生活必需品を買いだめしている家庭が多く、避難所では食料や燃料を持ち寄って炊き出しを行った。トイレ掃除などの役割分担も決めた。
ただ、住民の多くはその後、島を去った。浦戸全体の人口は震災直前に589人だったが、今は半分以下。「つながりが深かった。それが無くなるのは嫌なんです」。内海さんの顔が曇った。
▽豊漁に沸いた風景は様変わり
野々島では、消防団員だった遠藤勝さん(60)が震災当時を語ってくれた。
「『ギギギギ』って、家がねじ切られるのを、今も夢で見るんだ」
いつも鏡のようにないでいた海が一変した。長い揺れの後、陸地に波が押し寄せる。「山に逃げろ!」。家々から住民を連れ出し、必死に走った。転びながら高台を駆け上がると雪が降り出し、眼下で家屋が濁流にのまれていた。
写真が撮影された桟橋付近は現在、舗装され無機質な灰色の地面が広がる。びっしりと立ち並んでいた住宅は流され、岩からなる島の地形があらわになっている。あちこちに空き地ができ、日中でも人影はまばらだ。
津波で漁船や加工施設が破壊されたことで、島のなりわいだったアサリ漁やカキ養殖が廃れていった。「漁師を諦めた人がだいぶいた。みな若ければ、今も島で続けていたんだろう。それなりに年をとっていたんだな」。途絶えた伝統行事もあるという。寒空の下、豊漁に沸き活気があったかつての日常風景を想像した。
▽「若者がいないと地域は終わる」
早朝、野々島の桟橋にいると、船を下りた子どもたちから「おはようございます!」と元気な声が響いた。地域で唯一の浦戸小中学校は、38人の全校児童生徒が仙台市などから通う島外出身者だ。
「若者がいないと地域は終わる」
約20年前、少子化に歯止めがかからず、遠藤さんや内海さんら住民は学校存続を求め、行政に掛け合った。協議を重ねた末、学区外からの受け入れが始まった。
豊かな自然や少人数授業が魅力となり、震災後も越境入学希望が絶えない。2023年度は島在住の子どもはゼロだ。
遠藤さんは「学校を残した責任がある」と言う。カキむきやカヌー体験で島民は講師となり、頼みがあれば本土まで給食を取りに行く。「学校で困ったことや協力依頼があったら、とにかく動くようにしている。地域の住民は少しずつ減っているけど、そんな中で子どもたちの声は宝だ」
島の文化を学ぶ生徒児童に加え、近年は地域おこし協力隊として漁業を担おうとする移住者もいる。島民にとって、次の世代は希望だ。「若い世代が俺たちの伝えたことを覚えていてくれたら」
▽故郷への気持ちつづった島の詩
最後に寒風沢島を訪れた。日が暮れる頃、真新しい防潮堤が建つ海岸で、ギターの音色が響き渡る。昨年、地域おこし協力隊として移り住んだ吉田夢さん(30)だ。「島で力強く生き抜いてきた人たちに触れたい」
宮城県多賀城市の出身。震災当時は、合唱やボランティア関係の部活動に所属する高校生だった。海のそばの活動場所に着いたとき、地震が起きたという。塩釜市の学校に避難したが寒さに震えた。津波で家が壊れ、知人宅でしばらく過ごした。
「何が何だかわからず、ただ生きているだけのような感じだった」
卒業後、地域の合唱団に加入。「もっとつらい思いをしている人を元気にしたい」と、復興を願うコンサートなどで歌い続けてきた。その中で、震災により島を離れる住民への思いを描いた曲の存在を知った。
その歌詞は桂島の女性が避難所生活の中でつづった詩から生まれたという。「こういう歌があることで、忘れずにいられる。それもまた復興の一つなのかな」
この詩を書いた女性は3年ほど前に亡くなったが、復興支援の催しなどで今も多くの人たちに親しまれている。歌う一人として、吉田さんが思いを語った。
「浦戸に住んでいるからこそ、(曲に込められた)想いを歌い継いでいかなければいけない」
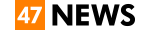




































































































































![[競馬エッセイ]関東の刺客と呼ばれたライスシャワーの歩み](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-31945.jpeg)






