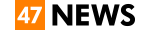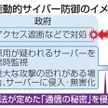北西アフリカ・モーリタニア出身の作家、モハメドゥ・スラヒさん(53)は、かつてキューバのアメリカ海軍基地にある悪名高い収容施設「グアンタナモ」に拘束された。国際テロ組織アルカイダの関係者、つまり「テロの容疑者」と見なされたためだ。収容中に獄中記を執筆。これが世界的ベストセラーとなり、後に「モーリタニアン 黒塗りの記録」(邦題)として映画化された。ようやく容疑が晴れ、釈放されたのはグアンタナモに移送されてから14年たってからだった。
現在オランダに住むスラヒさんは、今年3月に講演するため日本に招かれた。「『自由で民主的で平和を愛する国』に行ける」と楽しみにしていた。
ところが、日本政府が入国査証(ビザ)の発給を1月に拒否していたことが判明した。実は2020年にも政府はビザ発給を拒否していた。テロの嫌疑は晴れているのに、なぜ政府は入国さえ認めないのか。(共同通信編集委員 三井潔)
▽殴打、水攻め…拷問横行
スラヒさんは1990年代初め、アフガニスタンで、当時米国の秘密工作の支援を受けていたとされるアルカイダから戦闘訓練を受けた。ただ、その後は関係を断ったという。それでも米中央情報局(CIA)にアルカイダとの関係を疑われ、米中枢同時テロ2カ月後の2001年11月、モーリタニアで拘束された。ヨルダンや、アフガニスタンにある米軍の秘密施設をへて02年8月にキューバにあるグアンタナモに移送された。
グアンタナモは、拷問の横行が発覚し米軍の対テロ戦争の「負の遺産」と指弾されている。
「(国際テロ組織)アルカイダの勧誘者と認めろ」
アルカイダとの関係を疑われたスラヒさんに、CIAらの取調官が激しく迫った。昼夜を問わない尋問が数十日続いた。殴打されたり、低温の部屋に置き去りにされたりした。スラヒさんが信仰するイスラム教を侮辱するような、女性兵士による性的暴行も受けた。
生きる力を奪われ「指先に血がにじむまで髪を抜いた」。海水を飲ませて殴る拷問や、祖国モーリタニアにいる母を連行するという脅迫に耐えきれず、容疑をいったん認めてしまった時もある。
グアンタナモには、2001年の米中枢同時テロの主犯格とされる収容者は一部いるが、多くは非戦闘員だ。10代の少年から80代の老人までいた。「鎖でつながれ、外部と遮断された日々だった」。ハンストで抵抗する者や自殺した収容者も少なくなかった。
▽母国への送還時も手錠や足かせ
その後、自ら人身保護請求をしたところ、米連邦地裁が「拷問に基づく自白」として釈放を許可した。米政府が最終的に「米国の脅威にならない」と判断して、ようやくモーリタニアに送還されたのは2016年10月だった。故郷に戻る際も手錠や足かせ、目隠しをされた。最後まで「テロリスト」扱いだった。
グアンタナモには最大時約780人が収容されたが、大半はテロと無関係とされてスラヒさんのように母国か第三国に送還された。今年1月末の米ニューヨーク・タイムズ紙によると、今も30人が残る。
心的外傷後ストレス(PTSD)に今も苦しむスラヒさん。それでも虐待に携わった人や米国を「許す」と言う。理由は、「憎しみに支配されるのではなく、許し、和解することで新たな人生を開く」と決意しているから。支えはグアンタナモでの体験だ。
「(解放されるまで)私の側に立ってくれた人も、拷問した人もイスラム教やキリスト教などさまざまな宗教を信じる、多様な人だった」
世界ではロシアによるウクライナ侵攻、パレスチナ自治区ガザでのイスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘など紛争が絶えない。
スラヒさんはオランダを拠点に欧州各地で人権啓発のシンポに参加、交流サイト(SNS)も通じて、自身の思いを伝えている。平和関連の受賞歴もある。日本で自身の体験を基に、紛争が相次ぐ世界の和解について講演する予定だった。
▽理由明かされず
外務省は、なぜスラヒさんのビザ発給を拒否したのか。
取材をすると、外務省外国人課の担当者は「厳正な審査をしてビザ発給事由に当たらないと判断した」とだけ説明した。
ビザ発給が拒否されるのは、一般的に(1)過去に懲役1年以上の犯罪歴がある(2)日本の利益または公益を害する恐れがある―などがあるが、理由は明かされない。
講演を企画した一般社団法人「刑事司法未来」代表理事で龍谷大の石塚伸一名誉教授は、外務省の対応についてこう話す。
「英仏も自由に移動できるのに日本政府はどうしてビザを発給しないのか。テロリストの烙印を押し、米国に忖度しているのではないか」
スラヒさんも無念さを隠さない。「日本は『自由で民主的で平和を愛する』国というイメージがあっただけにビザを得られず、日本に行けなくなって落胆している。日本政府がまだテロリストとして私を疑っているのかもしれない」
さらにこう続けた。「紛争が後を絶たない世界で、宗教や国の立場を超えて平和を築く方法について、日本の次世代の若者たちと語り合うことを楽しみにしていただけに本当に残念だ」