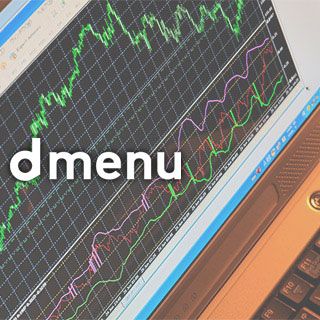最近読んだ本はどのような本だったでしょう。ずいぶん前だから思い出せないという人もいるのではないでしょうか。労働時間が長い日本では、「労働」と「読書」の両立はなかなか難しいとも感じます。一方で、気がついたらインターネットやSNSを見るのに時間を費やしていた、という経験のある人もいるのではないでしょうか。
ではなぜ、インターネットには時間を割くことができて、読書に時間を割くことは難しいのでしょうか。この点について、今回ご紹介する『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆著、集英社新書)では、大正から昭和を経て現代までの教養や読書がどのようなものであったのか、といったことをたどりながら考察が進められます。
著者の三宅香帆氏は1994年高知県生まれ、京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了したのちIT企業に就職します。その数年後、本をじっくり読むために退職し、現在は文芸評論家として活躍しています。三宅氏は本書で「どういう働き方であれば、人間らしく、労働と文化を両立できるのか?」という問いからスタートします。
●本を読むことはいつから「教養」となったのか
日本で「サラリーマン」が誕生したのは大正時代ですが、その後、昭和に入る頃「円本ブーム」が起きます。円本とは1冊1円の本で、現在の貨幣価値で考えると2000円程度になります。これは当時の通常の本が現代の貨幣価値で1冊1万円程度するものだったことからすると、かなり安かったことがわかります。さらに現代でのサブスクのように、毎月おすすめの名作が送られてくる形での全集セット売りでした。
当時、中高等教育を受けたエリート階層=新中間層が、労働者階級との差異化のために「教養としての読書」を重視した流れがありました。ここに向けて円本全集が売り出されたことで、実際に読んだかどうかは別として教養としての本が一気に一般に広がったようです。
つまり読書することは、エリート層(新中間層)が仕事とは直接関係のない「教養」を持つことを求めたことによる行為だったとことがわかります。またこののち、戦後1950年代以降からは全集ブームや文庫ブームが起こり、1960年代になると今度は、『英語に強くなる本』といった仕事でも「役に立つ」新書が出てきます。
●「教養」から「コミュニケーションのためのもの」に
その後、1970年代に入ると、サラリーマンが司馬遼太郎の描く立身出世物語を文庫本で読むようになり、1980年頃には女性にも教養が広く開かれていきます。ここまでの流れを踏まえて三宅氏は、「読書や教養とはつまり、学歴を手にしていない人々が階段を上がろうとする際に身につけるべきものを探す作業」だったのかもしれないといいます。
一方で、1980年代ではより実用的で明日使える知識を伝える雑誌「BIG tomorrow」がサラリーマンに読まれるようになりますが、これは「学歴ではなく、コミュニケーション能力を手にしていないコンプレックスのほうが強くなったからだ」と三宅氏は分析します。さらに、この頃には『ノルウェイの森』などの「自分の物語」がヒットします。ここにも「他人とうまく繋がることができないコミュニケーションの問題」があったと推測します。
●90年代前半は「内面」へ、後半は「行動」へ
1990年代に入ると、さらに「内面」に向かい、ややスピリチュアルな方向から「自己」を探究していきます。しかし、1990年代後半になると、突如「行動」の時代に移行します。出版界ではポジティブ思考で「行動」で自分を変える自己啓発書『脳内革命』が大ヒットして「脳」ブームが起きます。ただし、この多くは脳科学書というよりは「思考法」やビジネス書といった、あくまで「行動」を促すことで成功をもたらすというものでした。
この背景に三宅氏は、バブル崩壊により一億総中流時代が終わったことを挙げます。この頃、仕事を頑張ったところで日本は成長しないし社会は変わらないという感覚が強くなり、経済の波によって社会は動き、この波に乗れたかどうかで成功が決まると考え始めます。そして、人々は「コントロールできない現実社会」と「コントロールできる自分の行動」に分けて考えるようになります。こうして自分の行動をコントロールするための自己啓発書が求められるようになります。
●アンコントローラブルなもの=ノイズ
このような流れで「教養」としての読書だったものは現在、自分をコントロールする方法を得る自己啓発書を読む行為や、インターネットで情報を得ることに取って代わっています。ここで共通する点が、「ノイズが除去されている」点です。自己啓発書のロジックはアンコントローラブルなものを捨て置き、コントローラブルなものに注力することで、自分の人生を変革する、ということです。
コントローラブルなのは自分の私的空間や行動です。たとえば「片づけ本」や「断捨離」といった本が売れ、アンコントローラブルな他人や社会について触れる文芸書や人文書といったものは、ノイズを提示するものとしてあまり注目されない流れにあります。つまり、その昔「教養」とされていたような本は、現在では働く上での「ノイズ」として排除されているのかもしれません。
●ノイズを受け入れる必要性
この状況に対して、三宅氏はノイズ性を完全に除去した情報だけで生きることは無理なのではないか、といいます。他者の文脈をシャットアウトせず、仕事のノイズになるような知識をあえて受け入れることが、自分に余裕を持つことであり、働きながら本を読む一歩になるのではないだろうか、と言います。
このために、まず「全身全霊を止めること」をやめるべきだと主張します。「全身全霊」とは「自分を忘れて、自我を消失させて、没頭すること」です。仕事だけに没頭することは実は楽なことであり、またそうなると、人はついつい働き過ぎてしまいます。しかし、この「働きすぎること」は実際には「自分で自分を搾取してしまうこと」である点を三宅氏は指摘しています。
三宅氏は最後に社会学者・上野千鶴子の言葉を借りて、「半身で生きる」ことを提案します。難しいことだけれども、これができれば、自分や他人を忘れずに生きる社会になるのではないか、と。
ということで、「教養と読書」の歴史をたどりながら、現代社会の違和感を丁寧に噛み砕いて、わかりやすく解説していくのが本書です。ぜひ手に取って、どうか時間を見つけて読んでみてください。自分の内側の奥の方で燻っている現代社会への違和感が、少しずつ正体を現してくる体験となるはずです。
<参考文献>
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』 (三宅香帆著、集英社新書)
https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-721312-6
<参考サイト>
三宅香帆氏のX(旧Twitter)
https://twitter.com/m3_myk
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が問う日本の読書
関連記事
おすすめ情報
テンミニッツTVの他の記事もみるあわせて読む
-

京産大から初「国家一種合格」浪人重ねた彼の覚悟 母校初の快挙を成し遂げた彼の驚きの人生
東洋経済オンライン5/12(日)9:40
-

60歳で定年退職→同業種で起業…出版社の元編集長が“ワンランク上”のキャリアを手に入れられたワケ【人材開発コンサルタントが解説】
THE GOLD ONLINE5/11(土)10:15
-

人にマウントして顰蹙買うバカを尻目に…人にマウントさせてあげて自分有利に導く"言葉の撒き餌"7つの実例
プレジデントオンライン5/10(金)18:45
-

ビッグサンダーマウンテンに乗って尿管結石が出た人続出…実証研究で排石率は先頭席12.5%、最後部席63.9%【2023編集部セレクション】
プレジデントオンライン5/9(木)7:15
-

岸田政権はまだまだ続く可能性が高い…政治的には詰んでいる岸田首相が「続投に自信満々」となっているワケ
プレジデントオンライン5/8(水)9:15
-

なぜ「つばさの党」は逮捕ではなく、警告なのか…「選挙妨害は逮捕しろ」という主張に決定的に欠ける視点
プレジデントオンライン5/1(水)17:15
-

「小学校を3カ月で辞めた」エジソンの驚く勉強法 牧野富太郎や森毅ら偉人たちの学習法を紹介
東洋経済オンライン4/30(火)11:00
-

「1浪早大中退」学歴捨てた彼が歩む"VTuber"の道 予備校の寮生活を通して人生観が変わった
東洋経済オンライン4/28(日)5:00
-

【毎日書評】落ち込みやすい→ポジティブに。変化をもたらす「最適脳」トレーニング
ライフハッカー[日本版]4/27(土)22:27
-
-

「5浪京大」彼女の合格導いた"80歳恩師"との別れ 予備校を転々としていた彼女、恩師の教えとは
東洋経済オンライン4/21(日)5:00
-

「脳が衰える人」が食事中"無意識"にしていること 「休んでもとれない疲れ」を超回復する簡単方法
東洋経済オンライン4/18(木)9:00
-

80年代、東大駒場に流れていた自由な風の正体 異色の教養シリーズ「欲望の資本主義」の原点
東洋経済オンライン4/18(木)8:30
-

2浪早大「街歩くな」親がひた隠しにした彼の失敗 浪人してよかった一方、唯一後悔したことも
東洋経済オンライン4/14(日)5:00
-

自転車事故で始まる「慰謝料地獄のリアル」をご存じか…無保険で歩行者をはねた25歳男性の"末路"
プレジデントオンライン5/12(日)16:15
-

紫式部に好意をもっていたからではない…10年無職だった紫式部の父・為時を藤原道長が大抜擢したワケ
プレジデントオンライン5/12(日)17:15
-

ほかの刑事ドラマとは決定的に違う…「相棒」を名作にした寺脇康文や及川光博ではない"もうひとりの相棒"
プレジデントオンライン5/12(日)16:15
-

「これって教員の仕事?」疲弊する先生のリアル 終わらない業務、保護者からの無理難題に苦慮
東洋経済オンライン5/12(日)16:00
-

ニュートンの「慣性の法則」を仕事に適応。タスク処理が思った以上に進んだ理由
ライフハッカー[日本版]5/12(日)23:17
-
仕事術 アクセスランキング
-
1

自転車事故で始まる「慰謝料地獄のリアル」をご存じか…無保険で歩行者をはねた25歳男性の"末路"
プレジデントオンライン5/12(日)16:15
-
2

紫式部に好意をもっていたからではない…10年無職だった紫式部の父・為時を藤原道長が大抜擢したワケ
プレジデントオンライン5/12(日)17:15
-
3

ほかの刑事ドラマとは決定的に違う…「相棒」を名作にした寺脇康文や及川光博ではない"もうひとりの相棒"
プレジデントオンライン5/12(日)16:15
-
4

「遺産は私がもらう!」母の死後、独身長女の不満が爆発…ドロ沼相続と「遺留分」の存在
THE GOLD ONLINE5/12(日)16:45
-
5

ニュートンの「慣性の法則」を仕事に適応。タスク処理が思った以上に進んだ理由
ライフハッカー[日本版]5/12(日)23:17
-
6

平日は会社員、休日は副業+書籍執筆…無理せず人生が好転する東大式「土曜朝イチの30分勉強法」
プレジデントオンライン5/12(日)15:15
-
7

「これって教員の仕事?」疲弊する先生のリアル 終わらない業務、保護者からの無理難題に苦慮
東洋経済オンライン5/12(日)16:00
-
8

Androidで手軽に解決できた! 不要な通知をオフにする方法
ライフハッカー[日本版]5/12(日)21:37
-
9

平均年収700万円の顧客に対して年収700万円向けのサービスは絶対ダメ…真のターゲットを求める数字の扱い方
プレジデントオンライン5/12(日)15:15
-
10

クリーニング屋が教える「冬物コートの正しい保管方法」。虫食いを見つけたらどうする?
ライフハッカー[日本版]5/12(日)16:17
仕事術 新着ニュース
-

ニュートンの「慣性の法則」を仕事に適応。タスク処理が思った以上に進んだ理由
ライフハッカー[日本版]5/12(日)23:17
-

Androidで手軽に解決できた! 不要な通知をオフにする方法
ライフハッカー[日本版]5/12(日)21:37
-

紫式部に好意をもっていたからではない…10年無職だった紫式部の父・為時を藤原道長が大抜擢したワケ
プレジデントオンライン5/12(日)17:15
-

「遺産は私がもらう!」母の死後、独身長女の不満が爆発…ドロ沼相続と「遺留分」の存在
THE GOLD ONLINE5/12(日)16:45
-

クリーニング屋が教える「冬物コートの正しい保管方法」。虫食いを見つけたらどうする?
ライフハッカー[日本版]5/12(日)16:17
-

ほかの刑事ドラマとは決定的に違う…「相棒」を名作にした寺脇康文や及川光博ではない"もうひとりの相棒"
プレジデントオンライン5/12(日)16:15
-

自転車事故で始まる「慰謝料地獄のリアル」をご存じか…無保険で歩行者をはねた25歳男性の"末路"
プレジデントオンライン5/12(日)16:15
-

「これって教員の仕事?」疲弊する先生のリアル 終わらない業務、保護者からの無理難題に苦慮
東洋経済オンライン5/12(日)16:00
-

平均年収700万円の顧客に対して年収700万円向けのサービスは絶対ダメ…真のターゲットを求める数字の扱い方
プレジデントオンライン5/12(日)15:15
-

平日は会社員、休日は副業+書籍執筆…無理せず人生が好転する東大式「土曜朝イチの30分勉強法」
プレジデントオンライン5/12(日)15:15
総合 アクセスランキング
-
1

【独占取材】宝島さん夫妻が経営する14店舗を買わないかと打診された居酒屋店主の証言「息子さんが事業をやらないみたい」「現金ですぐに」
ABEMA TIMES5/12(日)16:00
-
2

自転車事故で始まる「慰謝料地獄のリアル」をご存じか…無保険で歩行者をはねた25歳男性の"末路"
プレジデントオンライン5/12(日)16:15
-
3

嵐・松本潤 インスタで注意喚起「ワタクシXやってません」
東スポWEB5/12(日)19:21
-
4

紫式部に好意をもっていたからではない…10年無職だった紫式部の父・為時を藤原道長が大抜擢したワケ
プレジデントオンライン5/12(日)17:15
-
5

重盛さと美が自分より稼いでなさそうな事務所の先輩暴露 上沼恵美子一喝「めっちゃ失礼!」
東スポWEB5/12(日)17:36
-
6

『アンチヒーロー』衝撃ラストにネット混乱 “緋山”岩田剛典が再登場「はぁ!?」「どゆこと?」「意味わからん」
ORICON NEWS5/12(日)21:51
-
7

「おじいちゃんになってる」デビュー30周年を迎えるGLAYの近影に衝撃受ける人が続出した理由
週刊女性PRIME5/12(日)20:05
-
8

〈那須殺害・独自〉「女ではなくカネのある女が好きみたい」車と服に浪費、喧嘩もできないほどのビビり、下戸、殿・姫・鶴の全身刺青…主犯・関根容疑者の異常なまでのカネへの執着と独特な人生観
集英社オンライン5/12(日)16:00
-
9

加藤綾菜 実はファンクラブに入っているアイドルグループ告白「旦那にも言わずに隠れて入ってる」
スポニチアネックス5/12(日)18:33
-
10

【あすの天気】朝の通勤通学の時間帯は東〜北日本で雨風強まる 土砂災害や低い土地の浸水に警戒
日テレNEWS NNN5/12(日)20:03
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
© Imagineer Co., Ltd.