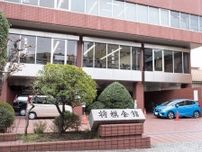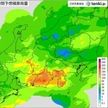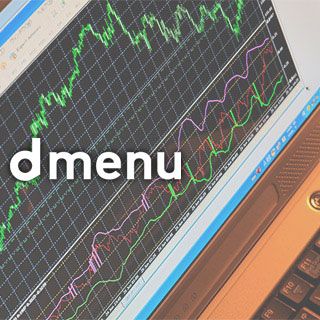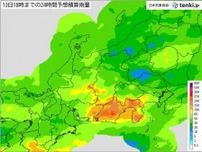◇第28回「パチンコの発祥は名古屋?」
名古屋市、愛知県は全国屈指のパチンコ王国と呼ばれ、時に「発祥の地」と呼ばれることもある。ただし、業界の識者や文献を探ると実際はそうではないといわれている。それではパチンコのルーツはどこにあるのか? 名古屋は業界の歴史をひもとく上では重要な位置付けにあるのは間違いないようだが―。(鶴田真也)
日本で最初にパチンコ店の営業許可を得たのが名古屋市の業者だったというのが通説だ。
1930(昭和5)年2月12日に名古屋市の「平野はまの」という人物が愛知県警保安課に同市中区門前町4丁目(現・同区大須2丁目)での遊技場営業を届け出て「平野パチンコ店」として開業したという。大須観音に近い繁華街で、営業時間は午後8〜12時と決められていた。
ただし、その1年前の29年に大阪府、京都府で「自動球戯機」の出店が許可された事例があり、大阪など関西地方で温泉地や海水浴場など行楽地や、神社・仏閣などの縁日での露店営業の場でパチンコ台が設置されていたという。
千葉県旭市にあるパチンコ博物館の牧野哲也館長は「日本での発祥は関西と考えてまず間違いはない。が、日本にはパチンコの歴史に関する史料が少なく、今後の研究次第では新たな史料が見つかる可能性もある」としている。
パチンコ台の原型は英国で誕生したとされる縦置きの「ウオールマシン」「マシン・ア・スー」とされ、手打ちのハンドルで球を打ち出す形式で共通点が多い。『パチンコ歴史事典』(パチンコ必勝ガイド編)によると、日本には大正末期に大阪の輸入業者が米国から欧州製遊技機5台程度を輸入したとの記録が残っている。
それではなぜ名古屋が「パチンコ王国」といわれるようになったのか。昭和初期は「一銭パチンコ」と呼ばれる台が主流で、投入口に1銭銅貨を入れると玉が出て、打った玉が入賞すると1銭銅貨あるいはメダルが払い出される仕組み。射幸心をあおっていたこともあり、1932年に大阪府警から禁止令が出されたのを皮切りに全国的に取り締まりが厳しくなった。
そこで名古屋市の藤井正一が35(昭和10)年に「鋼球(パチンコ玉)式」のパチンコ台を考案した。入賞すると硬貨やメダルではなく、玉が戻ってくるという現行の景品交換のシステムの先駆けで、牧野館長も「鋼球を使うので賭博ではないと主張し、営業許可を得て翌年にパチンコ店を開業した。現在の景品交換の原型をつくった意味では名古屋も『パチンコ発祥の地』の1つと呼べるかもしれない」という。
旧・一銭パチンコなどとの差別化を図る意味で「スチールボール野球器」の機器名で名古屋市西区の円頓寺(えんどうじ)商店街に130台設置の遊技場を初めて設置。同時期には戦後に「正村ゲージ」と呼ばれる人気パチンコ台を生み出した正村竹一も「スピード野球ボール」の屋号で遊技場を同じ西区にオープンさせた。
その後、太平洋戦争が開戦し、パチンコは全面禁止に。店舗の閉鎖を余儀なくされたが、戦後には復活した。特に名古屋はパチンコ台の製造にはうってつけの地だったという。
牧野館長は「名古屋はベニヤ板が豊富だった。軍需工場で生産されたベアリング玉もパチンコ玉に流用できた。正村が目を付けたのが戦時中に農村部で温室用に保管されていたガラス。盤面のサイズにぴったりで、三河地方(愛知県東部)のほか、静岡県の旧・福田町(現磐田市)まで足を運んで調達したことが分かっている」と解説した。
1948年には独自のくぎ配列と風車からなる「正村ゲージ」のパチンコ台が正村の手で考案され、爆発的なヒットを呼んだ。名古屋にも正村の経営する「正村商会」だけでなく多くのパチンコメーカーが存在していた。今も京楽産業、三洋物産、ニューギンなどが本社を置いている。
当時の週刊誌の記事では全国に約4万軒のパチンコ店があったという。警察庁によると2022年12月時点で計7665軒。実に5倍近い数がひしめいていた。戦後のブームを下支えしてきたのが名古屋。まさに「王国」たるゆえんだ。
○…名古屋のパチンコ産業が隆盛を極めた一因として牧野館長は「正村竹一氏は、メーカーとして大成功した後も、全国の購入ホールを巡り、正村ゲージのパチンコ機の扱い方や営業戦略を指導し、全国のホールを繁栄させた」という。正村は正村ゲージの特許を得ておらず、他社にも正村ゲージのパチンコ機の製造を認めていた。1952年に名古屋市のパチンコ機メーカー「豊国遊機」が玉を高速連射できる「機関銃式」を考案したこともブームに火を付けたという。現在のように玉を上皿に置き、連射する方式も名古屋発祥だ。
◇ ◇ ◇
【参考文献】
『パチンコ百年史』(山田清一、今泉秀夫責任編集、アド・サークル刊)
『パチンコ歴史事典』(パチンコ必勝ガイド編、ガイド・ワークス刊)
『パチンコ博物館』パンフレット
『天の釘』(鈴木笑子著、晩聲社刊)