映画「幸福(しあわせ)の黄色いハンカチ」(1977年)の原作者として広く知られ、アメリカでは反骨を貫くジャーナリストとして、またコラムニスト、小説家として一世を風靡したピート・ピート・ハミルさん。かつてはプレイボーイとまで呼ばれた人だった。
そんなピートさんが結婚相手として選んだのは13歳年下、「ニューズウィーク日本版」創刊時にニューヨーク支局長を務めた青木冨貴子さんだ。ニューヨークで穏やかな結婚生活を送るふたりだったが、ある朝、青木さんはドカーンと響く爆発音とともにベッドから飛び起きた。そう、この日は2001年9月11日だったのだ――。
※本記事は、青木冨貴子氏による最新作『アローン・アゲイン 最愛の夫ピート・ハミルをなくして』より一部を抜粋・再編集し、第10回にわたってお届けします。

ジェット機がツインタワーに衝突した瞬間
2001年9月11日はニューヨーク市長選予備選挙の日だった。前の晩、ピートはそれまで数年かかった長編小説の完成原稿が上がったので、ふたりでお気に入りのレストランへ行って乾杯しようと話していた。新刊のタイトルは『フォーエヴァー』。長い間、ニューヨークの歴史を書きたいと思っていたピートが永遠(フォーエヴァー)に生きてしまう主人公を通して、ジョージ・ワシントンに始まるニューヨークの歴史を描く壮大な歴史小説だった。
当日の朝8時、ピートは「ツインタワー」として知られる世界貿易(ワールド・トレード)センタービルに近いニューヨーク市庁舎隣のツイード・コートハウス(ボス・ツイードの時代の裁判所庁舎)で開かれた歴史協会のミーティングに出かけた。8時46分に大きな騒音がしたが、ニューヨークで大騒音など日常茶飯事、気に留める者はいなかった。9時になるちょっと前、スタッフのひとりが部屋に駆け込んできた。
「アメリカン航空のジェット機がツインタワーの一つに衝突した」
この声を聞いたピートはコートを掴んで表に飛び出て、目抜き通りのチェンバーズ・ストリートへ向かった。サイレンを鳴らしたパトカーや救急車がトレードセンターの方向へ走ると、ツインタワーから出る灰色の煙がスローモーションのように次第に大きくなっていったという。
9時3分、ドカーンという大きな爆発音を聞いたピートはオレンジ色の巨大な炎が噴出するのを目撃した。まさに南タワーにテロリストの操縦するジェット機が衝突した瞬間だった。機体までは見えなかったが、地面を揺るがすほどの轟音だった。
路上に脱ぎ捨てられた革靴、ハイヒール、スニーカー…
その時、わたしはまだベッドの中にいてドカーンと響く衝撃音で飛び起きた。トライベッカのロフトにトラックでもぶつかったかと思うほどの異常を感じた。
「トレードセンターにジェット機がぶつかった! いま南タワーの爆発を見たんだ。テロにちがいない」
現場に駆けつけるため、ニューヨーク市警発行の「ワーキング・プレス」パスを取りに帰ってきたピートはこう叫んだ。
「待って、わたしも一緒に行くから」
急いで着替えてスニーカーを履き、野球帽をかぶって、メモ帳をカバンに入れた。
表に出ると昨晩の雨が上がって、雲一つない見事な快晴だった。ブロードウエイに出ると、たくさんの勤め人がトレードセンターを背に北方向へ向かって歩いていた。歩道にはたくさんの革靴やハイヒール、スニーカーなどが転がっていた。靴を脱ぎ捨てて逃げた人たちのものだろう。
トレードセンターはわたしたちのアパートから13ブロック(1ブロックは約70〜80メートル南に位置する。ピートと一緒に勤め人とは逆に南へ向かって足早に歩き、3ブロック下がったところで、煙を吐くツインタワーをわたしは初めて目にした。
さらに5ブロック下がってチェンバーズ・ストリートに着くと、オレンジ色の巨大な炎を噴出させる両タワーがはっきり見えた。さらに南下すると警官の数が多くなり、ブルーのバリケードをトラックから下ろしたり、急行した緊急車両へ指示を与えている。

タワーから飛び降りる人々の影
トレードセンターの北側に位置するヴェッシー・ストリートへ右折しようとしたところで警官に制止されたが、ピートが市警の「ワーキング・プレス」を見せるとすぐに通してくれた。そのままチャーチ・ストリートに近づくと全貌が見渡せた。
鉛色の猛烈な煙が真っ青な秋空を覆い、東のブルックリン方向へ流れていた。ツインタワーのスチール製外壁が朝日を浴びて銀色に輝き、南タワーでは真中より少し上の階、北タワーではそれより上階近くに大きな黒い穴が空いている。穴の周りは焼けただれ、どす黒い傷口を曝け出している。そこから黒い煙が勢いよく上がっていた。
ヴェッシー・ストリートにはジェット機の車輪の中核部分と思われる丸い鉄が転がっていた。その大きさに改めて息を呑む。歩道には灰をかぶった靴が散らばり、朝食用に買ったパンの入った紙袋、書類の詰まった仕事鞄、その近くにすでに変色した血痕がいくつもあった。
北タワーの、あんぐり空いた燃える窓から小さな人影が飛び降りていった。白いシャツを着た男性と思われる。
「これで14人目だ。なんて気の毒な!」
隣にいた警官が呟いた。
いまこの瞬間にも、あの高いタワー上階から地上を見つめている人たちが何人いるのだろう。彼らの気持ちを思うと神に祈りたいほどだった。わたしの横を上半身裸のビジネスマンが放心したようにブロードウエイ方向へ歩いていった。
このとき、隣にいたふたりの警官のひとりが携帯電話から耳を離すと、相棒に向かってこう呟いた。
「信じられるかい。ペンタゴンにもジェット機が突っ込んだって、母さんがいってるぜ」
もうひとりの警官はこう唸った。
「ハイジャックされた別の航空機がまだどこにいるかわからないって……」
「ここから出してくれ、ワイフがいないんだ」
9時59分、ピートは南タワーからポン、と裂けるような音を聞いた。同時に小さな爆発が起こり、壁が膨らんで破裂し、雪崩のように崩れ落ちてきた。
「走れ!」
隣のフキコに声をかけた瞬間、崩れ落ちたタワーから25階分の高さもあると思われる灰が流れ落ちてきた。ピートは警官に誘導されてヴェッシー・ストリート25番地の建物に駆け込んだ。ところが、ビルに入ってみるとフキコがいない。ロビーから表に出ようとすると灰に包まれたガラスのドアは開かない。
彼は妻の名前を呼び、ここから出してくれ、ワイフがいないんだ、頼むからと叫ぶと、誰かがドアを開けるなと大声で叫んだ。
その建物の管理人が地下に別の出口があるというので地下へ降りていったが、出口などなかった。冷水機があったので灰を飲み込んだ口をゆすぎ、墓穴のような地下室から逃げ出してフキコを探そうと思った。
「こっちへ来い!」
誰かが叫んだので再びロビーへ戻ると、全身白いパウダーに覆われた警備員が唾を吐き、咳き込んでいた。まるでホラー映画のようだった。
警備員がガラスドアを壊して外へ出られるようにしてくれた。なかにいたのはほんの14分くらいだったが、1時間もいたように感じた。
表へ出てみると通りはすっかり白い粉に覆われていた。警官も歩行者も白人も黒人も女性もみんな白い亡霊のようだった。タワーからはまだ白い灰が襲ってきた。ピートは2インチも灰に覆われた通りをブロードウエイに向かって走った。
シティホール公園もすっかり灰に覆われ、白い紙が至るところに散らばっていた。株の購買、ステートメント、請求書、領収書、粉々にされた紙吹雪。灰で髪が白くなった黒人女性が呆然と立ち尽くし、アジア系の女性は顔面がパウダーで真っ白。でも、フキコはいない。
彼は通りを進む大勢と一緒にブロードウエイを北へ向かい、やっとアパートへ着いた。ちょうどわたしがドアから出てきたところだった――。
わたしたちは長い間ハグした。ああ、無事だった。
小説『フォーエヴァー』のラストはこうして生まれた
その日からキャナル・ストリート以南は立入り禁止になったが、わたしたちのアパートは立入り禁止区画のなかにあったので、世紀のテロの取材を続けた。ダウンタウンは全域、電気もガスも水道もなく夜は真っ暗、燃え続けるトレードセンターの煙にむせぶようだったが、ワース・ストリート以北にあるわたしたちのアパートは電気もガスも水道も使えて普通に生活できた。
それでも漂ってくるあの何かが燃えたようなにおい。焼き場のにおいだという人も多かったが、それだけでない、ケミカルも混じった独特のにおいは長い長い間、忘れることができなかった。
ピートは完成したはずの長編歴史小説『フォーエヴァー』の手直しをしなければならなくなった。この本ではニューヨークの歴史を書いているのに、9.11抜きには終わらせられない。それから大幅な書き直しに取りかかり、1年以上かけて完成させた。
刊行された小説の中で、主人公は恋人を探して両タワーが崩れ落ちた跡を探しまわる。最後のシーンはわたしたちふたりの体験から生まれたのだ。
(第9回に続く)
※『アローン・アゲイン 最愛の夫ピート・ハミルをなくして』より一部抜粋・再編集。
青木冨貴子(アオキ・フキコ)
1948(昭和23)年東京生まれ。作家。1984年渡米し、「ニューズウィーク日本版」ニューヨーク支局長を3年間務める。1987年作家のピート・ハミル氏と結婚。著書に『ライカでグッドバイ――カメラマン沢田教一が撃たれた日』『たまらなく日本人』『ニューヨーカーズ』『目撃 アメリカ崩壊』『731―石井四郎と細菌戦部隊の闇を暴く―』『昭和天皇とワシントンを結んだ男――「パケナム日記」が語る日本占領』『GHQと戦った女 沢田美喜』など。ニューヨーク在住。
デイリー新潮編集部



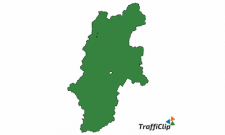






























































































































![[競馬エッセイ]関東の刺客と呼ばれたライスシャワーの歩み](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-31945.jpeg)






