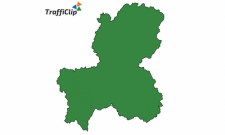「裏金問題」を発端として企業献金に疑念が抱かれる中、わが国最大の経済団体「経団連」にも注目が集まっている。政界との癒着を疑う声も高まる一方だが、その正体は、カネに物を言わす圧力団体でしかないのか。知られざる政治献金の実態に迫る。(以下は「週刊新潮」2024年4月18日号掲載の内容です)
「何が問題なのか」――。昨年12月、加盟企業による自民党への献金の是非を問われた経団連・十倉雅和会長は、記者団を前にこう言い放った。
今なお、岸田政権を大いに揺るがしている派閥の「裏金問題」。この原資となっているパーティー券収入の多くは企業の“まとめ買い”によるもので、実質的な企業献金の体を成している。
さらに、自民党の政治資金団体である「国民政治協会」に対しても、毎年多額の企業献金が行われている。その額、実に24億円。そしてこの大部分は、経団連が主導しているものなのだ。
“政治とカネ”の問題が指摘されて久しい。それでもなお、なぜ企業は政治に対する寄付を行うのか。主導する経団連の目的は何なのか。そして冒頭の会長発言の通り、そこには本当に「何の問題もない」のだろうか。
献金の「廃止」と「再開」の歴史
経団連の事情に通ずるジャーナリストが政治献金の歴史を概説する。
「もともとは『自由主義経済を守るため』という理念のもとで始まったものです。個々の企業が直接的に政治家に何かを要求することがないようにと、経団連が間に入る仕組みが整えられていった。経団連が業界ごとに額を割り当て、各企業の献金をあっせんしていた形です。この規模は拡大し続け、バブル期の頃には、100億を超える額が自民党に寄せられていました」
こうして献金に歯止めが利かなくなった中で転機となったのが、「リクルート事件」や「佐川急便事件」など、いわゆる“政治とカネ”の問題だ。桁違いのカネが政策をゆがめていた事実が相次いで発覚し、政治献金に強い疑念の目が向けられることになったのだ。
その結果、自民党が下野するのと時を同じくして、93年、当時の平岩外四会長(東京電力)の時代に献金のあっせんは全廃された。
さらに政界では、特定の企業や団体に政治がゆがめられることのないようにと、政党交付金制度も導入される。毎年約300億円もの税金が各政党に分配されることで、民間からの寄付に頼らずとも、十分な政治資金を得られるようになったということだ。
だが、経団連の「献金廃止」の意思は、そう固いものではなかった。
「政治への影響力低下を懸念して、04年、一時的に献金は復活されることになりました。『政策評価方式』という、自民党への献金を正当化する仕組みを用意したのです。しかし、09年に民主党政権が発足すると、自民党支持のスタンスを取る経団連としては、野党に献金することになり不都合な状況となってしまった。そこで、ほどなくして献金への関与を取りやめることになりました」(同)
まさに紆余曲折。「廃止」と「再開」の狭間で揺れる経団連だったが、
「やはり献金を廃止していた間、政界における経団連の存在感が低下した感は否めません。米倉弘昌会長時代(10〜14年)には、当時の安倍政権と関係が悪化し、経済財政諮問会議のメンバーから経団連が締め出されたこともあった。このような背景が重なって、ついに14年、榊原定征会長(東レ)時代に、経団連による献金は本格的に再開されることになったわけです。“あっせん”という言葉は使われず、強制力のない“呼びかけ”という表現に変わりはしたものの、『政党交付金がありながらなぜ献金が必要なのか』という批判の声は、今も絶えず上がっています」(元日経新聞証券部記者で、経済ジャーナリストの磯山友幸氏)
有料版では、こうして現在も続く政治献金の本当の目的と知られざるカラクリ、その背景にある自民党側の営業活動の実態、また収支報告書から見えた“横並び献金”などについて詳報している。
デイリー新潮編集部