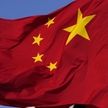前編【ホテル・ニュージャパン火災発生直後、ロビーで目撃した横井社長の意外な行動 警視庁鑑識課長の「呪われた48時間」】からのつづき
昭和57年2月、48時間の間に2つの巨大事故が発生した。死者33人、負傷者34人のホテル・ニュージャパン火災と、死者24人、負傷者149人の羽田沖日航機墜落である。2つの現場で懸命の救助作業が行われる一方、刑事責任の追及という新たなミッションも始まった。この2つの事故で、現場検証や遺体の取り扱いに始まり関係者の捜査、逮捕まで深くかかわった人物の1人は、当時の警視庁鑑識課長・田宮榮一氏だ。田宮氏の証言とともに、横井社長の逮捕やK機長の刑事責任追及を断念した経緯などを振り返る。
(前後編記事の後編・「新潮45」2009年7月号掲載「シリーズ『昭和』の謎に挑む 4・ホテル・ニュージャパン火災と羽田沖日航機墜落 警視庁が呪われた48時間」をもとに再構成しました。文中の年齢、役職、年代表記等は執筆当時のものです。文中敬称略)
***
連日の大惨事で鑑識課は混乱
墜落したのは福岡発羽田行の日本航空350便、DC-8である。午前7時34分に福岡空港を離陸、8時35分に羽田空港の着陸許可を受けて着陸準備に入った。高度200フィート(60メートル強)までは順調に飛行したが、8時44分過ぎ、突如機首を下げ滑走路手前の海上にある誘導灯に車輪をひっかけながら、海面に機首から墜落した。
コックピットの中では、着陸寸前でK機長が操縦桿を前に倒し、エンジンの逆噴射装置を作動させるという異常な事態が起っていた。「キャプテン、やめてください!」という副操縦士の叫びと「逆噴射」という言葉は、その後流行語にもなった。
負傷者が搬出されると、最後に犠牲者の遺体が運び出されてきた。
「空港警察署では、近くのお寺の境内を確保したということでしたが、そんな狭い場所ではダメだ、格納庫を提供してもらえという注文を出したんです。検視が終わった遺体を安置する場所も必要で、これは日航の会議室を使わせてもらうことになった。皮肉なことに、前日のホテル・ニュージャパンにおける遺体検視の経験が活かされたのです」(田宮、以下同)
遺体は当初、どのくらいの数になるか見当もつかなかったが、最終的に24体を数えることになった。現場では監察医による検視が行われたが、その途中、日航側が呼んだ医師が遺体の損傷部分を勝手に縫合し、あわてて田宮が阻止するという騒ぎもあった。日航側が善意でやったことだったが、捜査の妨害になってしまうのである。
前日に続いての大惨事は、鑑識課に混乱をもたらした。田宮は警察犬担当者にまで動員をかけたが、鑑識職員の絶対数が足らず、とりあえずホテル・ニュージャパンの方は現場保持のため数名だけを残し、残りは日航機墜落の現場に集中させることにした。
棺桶、フィルム、弁当が足りない
現実的に問題になったのは、棺桶だった。空港署に棺桶の手配を依頼したが、昨日すでに30個以上かき集めて使用しているので、必要な数を集めるのは困難だった。都下の葬儀屋で棺桶の在庫を豊富に持っている店は少ない。仕方なく板を取り寄せて大至急で組み立ててもらった。
さらに鑑識の写真に使うフィルムも足りなくなった。本部の鑑識課、空港警察署に備蓄されているフィルムが底をついてしまったのだ。仕方なく町の写真屋を回ってフィルムを買い集めた。本部で使用するものは国費、警察署で使用するのは都費と予算上は区別されていたが、そんなことを気にしている暇はなかった。
捜査員たちの弁当の手配にも苦労した。通常は署側で準備するものだが、人手が足りないので頼むわけにはいかない。鑑識課員に弁当の調達を指示したが、数百単位の弁当を急に調達するのは簡単ではない。担当者は弁当屋や今で言うデパ地下を駆け巡って、ようやく数を揃えた。田宮はこれらの騒ぎを通して大惨事における「兵站(へいたん)」の重要さを改めて認識したという。
それにしても機長はどこへ行ったのか。混乱する現場を指揮する田宮の頭の片隅に、その疑問が引っ掛かっていた。千切れて胴体にめり込んだコックピットの様子を見る限り、助かった可能性は少ないようにも思えた。しかし遺体の中には確認できなかったのだ。
横井社長逮捕の決め手はバランスシート
事故発生から1ヵ月後、田宮は刑事部の捜査一課長に昇進した。殺人事件などの捜査を主導、統括する枢要ポストだ。現場で「物」を相手にする鑑識活動から、「人」の捜査への移行である。捜査一課長を担当した期間、田宮はこの2つの巨大事故に関する「人」の捜査に忙殺されることになった。
まずホテル・ニュージャパン火災では、社長の横井英樹の逮捕に全力をあげた。
捜査段階で横井の異様なほどのワンマン経営ぶりが明らかになったが、逮捕の決め手となったのは田宮が作成させたホテルのバランスシートだった。
「横井に防災体制の不備を問い質すと、『ホテルが赤字続きだから金がなかった』という答えしか返ってこない。事務所には、1万円以上の支出には社長の決裁が必要だという通達が貼ってあり、ホテルの収支は大福帳経理で行われているだけだった。つまり横井自身しか収支の実態を把握していない。社員によれば利益は出ているはずだという。そこで本当に赤字続きなのかどうか調べることにしたのです」(田宮)
田宮は経済犯を専門とする捜査二課に応援を頼み、5年前にさかのぼってパランスシートを作成してもらった。段ボール箱に一緒くたに投げ込まれている山のような伝票を整理し、収支を弾き出したのだ。その地道な努力の結果、ホテルは赤字どころか黒字経営で、多額の金が横井の愛人など私的なことに流用されている事実が判明した。
それで横井の弁解は、すべて通用しなくなった。
堂々と連行されることが被害者への償い
捜査の大詰めでは、田宮が弁護人役、捜査員が検事役となって模擬法廷を繰り返し、捜査に不備がないか、証拠固めの検討を何回も行った。焼け残った部屋の建材で出火した部屋を再現した上で燃焼させるという実験も行なった。
逮捕のXデーは11月18日、監視を続けていた愛人宅で横井は逮捕された。
田宮は、「捜査本部の部下を通じ、横井には『一世一代の悪役なんだから、ちゃんと顔を見せろ。堂々と連行されることが被害者への償いだ』と言っておいた」という。その通り、横井英樹はロングコートを襟まで留めた姿で顔を隠すことなく、フラッシュを浴びながら警視庁本部に連行された。
東京地裁は、横井英樹に業務上過失致死傷罪で禁錮3年の実刑を言い渡し、上級審の東京高裁、最高裁でもこれが支持され、刑が確定した。田宮たちの捜査の執念が実ったのである。
焦点はK機長を逮捕できるか否か
一方の日航機墜落事件。こちらで焦点となったのは、果たしてK機長を逮捕できるか否かだった。K機長は事故後、腰椎骨折の治療で西新橋の慈恵医科大病院に入院していた。
事故後の機体の調査では、逆噴射装置が作動したことが証明されていた。さらに副操縦士や機関士の証言で、墜落直前のK機長の異常な行動が明らかになっていた。
彼の異常さについては、さまざまな情報が田宮のもとに集まってきた。事故以前の飛行の中での、急上昇や急旋回、ロンドンなど外国の空港での異常なスピードでのタクシング(空港内の走行)など。また自宅で「天井裏にだれかが潜んでいる」と言い出し、警察に連絡するなどの騒ぎを起していたことも判明した。
とても逮捕状の請求はできない
5月になったある日、田宮は退院が間近いというK機長の様子を見に病院に出かけた。正式な面会ではなく「お忍び」である。病院に張り込んでいる記者たちに気づかれることがないよう、1人で目立たないように病棟に入った。
「K機長は外科病棟に入院していて、リハビリをかねて病院の廊下をゆっくり歩いていたんですが、その表情はうつろで、視線も定まっていない。まる夢遊病者のようだったのです。それを見て私は『ああ、これはあきらかにおかしい!』と思い、とても逮捕状の請求はできないと考えたのです」
世間の注目を集めた大事故である。とりあえず逮捕して身柄を検察官に渡し、そこで精神鑑定等を行えばいいとするのが無難な方策だ。刑事責任能力があるか否かについての鑑定は、被疑者が送検されてから検察官が請求するのが一般的なのだ。
それで世間は納得する筈だが、田宮の考えは違った。自分の目で見てしまった以上、精神が正常でないと思える者を逮捕することはできなかった。
周囲はなぜ見抜けなかったのか
「逮捕前にK機長について鑑定留置の請求をすることはできないか、自分で法令や文献を調べたのです。その結果、司法警察職員は犯罪の捜査において必要があれば、前例がないけれども、鑑定の嘱託をすることが可能だと分かった。そこで担当検察官と協議して、入院中のK機長について“警察が”鑑定留置の請求をして、退院と同時に鑑定留置の場所に収容することにしたのです」(田宮)
鑑定医は筑波大学の小田晋(現・帝塚山学院大学教授)に頼むことにした。K機長は5月22日、待ち構える報道陣のカメラの放列の中を退院、東京警察病院多摩分院(現在の西東京警察病院)に移された。
結論から言えば、K機長の鑑定結果は、妄想型精神分裂病(現在の統合失調症)で、犯行時は心神喪失状態だったというものだった。そのため田宮は、彼を逮捕し刑事責任を追及することを断念した。小田晋氏は、鑑定したK機長の様子を今こう振り返る。
「初めて面接した時から、機長は明らかに妄想型の精神分裂病であると感じました。周囲の人々や日航の乗員健康管理室が、どうしてそれを見抜けなかったのか不思議に思ったくらいです」(小田)
K機長が語った不思議な世界観
小田がなぜそのような事故を起したのかと尋ねると、K機長は全然隠す様子もなく、不思議な世界観を語り始めたという。
彼の説明によれば、世界は「善」と「悪」の二派に分かれて争っていた。事故の当日、福岡から羽田までの飛行中に、善の方の勢力が悪の方の勢力に次々と倒されていき、木更津の上空あたりで勝負がついたような感じになった。そして着陸の直前、頭の中で「イネ、イネ」という声が聞こえた。K機長はこれを「死ね、死ね」という意味だと解釈し、その声に押されるように操縦桿を前に倒したという。
「このときに行った心理テストでも、妄想型の精神分裂病という結論がはっきりと出ました。見た目も、表情が固くて無表情で、典型的な分裂病の表情でした。自分が事故を起したことは自覚していました。ただし統合失調症の患者の場合、感情鈍磨といって自分の犯したことに対して罪悪感をあまり持たなくなります。だから事故のことも淡々と語っていました。K機長の場合、罪の感情がなくなるほど病状が進んでいたのです」(小田)
やるべきことは全てやった
K機長は鑑定留置の期間が満了した後、都立M病院に「措置入院」となった。田宮は、K機長の責任追及断念は仕方がないとしても、彼を管理する立場にあった日航幹部らの責任は問いたかったと言う。精神状態に問題がある者を乗務させていた運航乗員部長や、病気を見抜けなかった嘱託医の責任である。
しかし書類送検された計6名は、いずれも「事故の危険を予見することは困難だった」という理由で不起訴処分になった。こうして精神病の機長の操縦で墜落した旅客機事故の捜査は、刑事上の責任を誰も取ることなく終結してしまったのである。
「遺族の感情を考えると、不起訴処分になったことについては今も忸怩たる思いがあります」と語る田宮。だが、少なくともやるべきことは全てやったという達成感はあった。
巨大事故が立て続けに起きた“呪われた”2日間とそれに続く捜査の日々、田宮は鑑識課長、捜査一課長として捜査の前線に立ち続けた。以後も多くの事故や事件に立ち会ったが、これほどまでに捜査に忙殺された激動の日々は、あとにも先にもこの時だけであったと記憶している。
上條昌史(かみじょうまさし)
ノンフィクション・ライター。1961年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部中退。編集プロダクションを経てフリーに。事件、政治、ビジネスなど幅広い分野で執筆活動を行う。共著に『殺人者はそこにいる』など。
デイリー新潮編集部