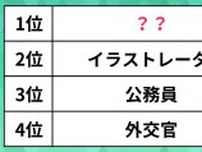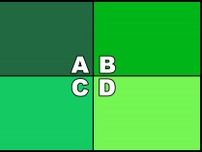TOKYO FMのラジオマン・延江浩さんが音楽や映画、演劇とともに社会を語る連載「RADIO PAPA」。今回は演劇「天才バカボンのパパなのだ」について。

下北沢 本多劇場 2024年2月21日(水)〜3月3日(日)
* * *
2008年夏に赤塚不二夫さんが亡くなった時、追悼番組を作った。芸術祭参加のこの番組のタイトルは「忘れたくても思い出せない」。これは赤塚さんが生み出したキャラクター、バカボンのパパのセリフ「わすれようとしても思い出せない」をもじったもの。作家の村上龍さんが教えてくれた。
赤塚さんのギャグはアナーキーさが心地よく、げらげら笑ったのち水蒸気のように消え、「わすれようとしても思い出せない」。
瞬間的で、だから何度読んでも初めてのように新鮮で心が解放される。
不条理劇の第一人者別役実による戯曲で、市川しんぺーがバカボンのパパを演じる「天才バカボンのパパなのだ」を観た(下北沢本多劇場)。実は2度目だったが劇場もあらすじも「思い出せなかった」。
舞台の昭和の雰囲気の、のどかな街角が懐かしい。署長と巡査が引っ越してきた。ここがいいと派出所に選んだのは電信柱のたもと。そこに現れたのがバカボン。雨が降っていないのに傘をさしている。そこに買い物かごを下げてママが通りかかり、パパが四つん這いで走り回る(今日のパパはネコになったと思い込んでいる)……。レレレのおばさんと謎の女が次々に登場し、全く問題ないのに問題が起こり、揉める必要がないのにどこまでも揉める。
宮藤官九郎風に言えば「“不条理”にもほどがある」。
しかし、なぜこんなに笑えるのだろう。そんなことを思いながら演出した玉田真也に話を聞いた。
「慶應大学の演劇サークルで別役実の戯曲に出会い、めちゃくちゃ魅せられたんです。1ページ読むごとに笑ってしまった。その中で出会ったのが『天才バカボンのパパなのだ』。これだったらいけるって」
そう語る玉田は38歳。別役の孫世代で、もちろん「天才バカボン」も同時代的に読んでいない。
「僕はバブルが崩壊した後の世代です。いってみれば、ものごころがついた時から不条理だった。大企業に入れば何とかなる。そんな右肩上がりの昭和の話はフィクションでしかなかった」
なるほど。つまり時代は巡り、玉田にとって別役の世界(=不条理)はより身近に感じられたわけだ。
「(登場人物が語り合う)セリフ一個一個が微妙にズレている」と玉田は言うが、彼はセリフのやりとりに一つの優しさを感じ取っていた。
「『(そこに)いてもいい』という言葉が登場するんです。巡査が笛を吹いて、『オイ、コラ!』って叱ると、上司の署長が『いてもいいじゃないか。ここはそういう普通の場所なんだ』と言う」
アナーキーな笑いと、「そこにいてもいい」と許す優しさ。だから何度も観たくなるのだ。1978年に発表された別役実のこの戯曲は原作者赤塚不二夫公認だった。
(文・延江 浩)
※AERAオンライン限定記事