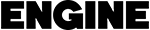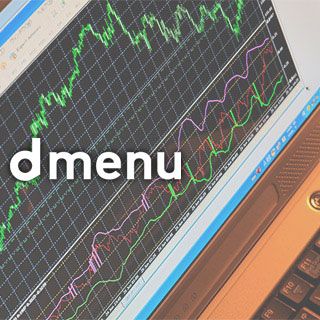ジャガーの専門店(株)ワイズ/ジャガリア代表の後藤将之さん。根っからの旧車好きで、最近新車と見紛うばかりの初代日産シルビアを手に入れた。そのいきさつを聞いた。自身もちょっと古いミニに乗るモータージャーナリストの藤原よしおがリポートする。
忘れられない光景
「1979年かな? 神宮絵画館の前でやっていたTACS(東京自動車クラブ)のミーティングに行ったの。そこで後のジャガー・カークラブの会長の田村行さんがいてね。ちょうどEタイプのレストアが上がったばかりで19歳の僕に丁寧に説明してくれた。フードを開けたら光り輝くカムカバーがドーンとあって、パイプフレームにダブルウィッシュボーンのサスペンションが見えてさ、なんだこれは! ってくらい衝撃的だった。もう一目惚れだったね」
そう話すのは日本屈指のクラシック・ジャガーのスペシャリスト、ジャガリア代表の後藤将之さんだ。
「それで早速知り合いのクルマ屋に探してもらったら、半年後に6万km走った正規輸入車が出てきた。すべてはそこからですよ。でも当時はパーツを扱う店が1軒もなくてね。パーツを頼んでもなかなかこない。そんな時、1歳上の兄貴がイギリスに留学した。それで1982年に初めてイギリスへ行ったんだ。1ポンド500円以上したけれど、日本でワイヤー・ホイールを1本買う金額で4本買えた。そこからお金貯めて毎年行くわけ。その後ジャガーのインポーターだったオースチン・ローバー・ジャパンに入ってセールスやって、1987年に独立した。それで今に至るというわけです」
まさにEタイプとともに人生を歩んできたと言っても過言ではない後藤さんが今年になって手に入れたのが、65年から68年にかけてわずか554台しか作られなかった日産のスペシャリティー・カーの祖というべきCSP311型初代シルビアだ。なぜ今シルビアなのか? その意外な組み合わせの理由を知るためには、もう少し話を遡る必要がある。
「18歳で免許を取って、欲しかったのがSR311型のフェアレディ2000。幼稚園の時に親父がフェアレディ1500に乗っていたから、その刷り込みがあったんだろうね。でも“そんな古いのはダメだ”って中古の240ZGになった。嬉しくて来た日はクルマの中で寝たけど(笑)、やっぱりSRが欲しくて240ZGを売って、SR311の後期を買いました」
当時の後藤さんは北米の安全基準に合わせ、クラッシュパッドを貼ったダッシュボードやハイ・ウィンド・スクリーンを備えた68年以降の後期型の方が斬新に見えたという。
「ところがEタイプを知って、のめり込んでいくうちに気づいちゃったんですよ。オリジナルのデザインの方がいいことに。だから次にSR311を手に入れる時は絶対に67年のロー・ウィンドウにしようって、ずっと思っていたんです」
SRを諦めた理由
そのチャンスは3年ほど前に突然訪れた。それがシルビアの横に写るロー・ウィンドウのSR311だ。
「ジムカーナに出ていたのか、後付けのオーバー・フェンダーとかが付いていたけど、ボディに腐りはないし、機関のオリジナル度も高そうだから、と最初は軽い気持ちだった。でもこれがとんでもないクルマだったの!」
というのも、素性を調べてみたら60年代に95戦中90回の総合優勝を遂げたジムカーナ・キングであり、SR遣いとして名を馳せた中村昌雄さとお兄さんが、新車で購入したクルマであることが判明したからだ。
「しかもメンテナンスを専門家の高島康久君にお願いしたら、塗装、プレスライン、スポット溶接の跡など、あちこちが驚くほどオリジナルの状態を残した、貴重な個体であることがわかったんです」
そこで後藤さんは、新車当時の姿に戻し後世に残すべきだと決意する。しかしその一方で、少しずつSRの存在が重く感じるようになっていったという。
「いざレストアしようと思っても、知識もパーツもないから、一から始めないといけない。僕ももう63歳だからね。完成まで何年かかるんだろう……と思うと、そこまでの熱意がないことに気づいた。一方で高島君はまだ20代で知識も部品も直す技術も熱意もあって、どうしてもこのSRが欲しいという。じゃあ譲りましょうという時に、彼のお父さんが持っていたシルビアと交換することになった、というわけです」
実はこのシルビアも只者ではない。元々素性のいいクルマだったというが、ボディ、機関がイマイチだったので数年前にフルレストアを決意。ただ部品の流通がまったくないので、部品取りを2台手に入れ、その中の一番良いパーツを使い、鈑金職人が“もう古いクルマはやらない”と音をあげるほど徹底してレストアをしたのだという。
その甲斐あってシルビアは内外装、機関ともに世界屈指のコンディションに仕上げられている。
「僕のところに来てから、まずタイヤを換えて、室内のメッキパーツをやり直したくらい。出来上がっているクルマは楽ですよ(笑)。それも自分が散々苦労してきたからわかること。そういう意味でも二十歳の時に自分でEタイプをレストアしたいと思ったのが原点。珍しいからとか、高いからじゃなく、自分が良いと思ったもの、欲しいと思ったものだから、ずっと続けてこられたのだと思います。古いクルマに限らず何事も、何より“思い込みと情熱”が大事なんですよ」
文=藤原よしお 写真=茂呂幸正
(ENGINE2024年5月号)
ジャガーEタイプとともに人生を歩んできたオーナーが、なぜ初代日産シルビアを手にすることになったのか? 素晴らしいクルマには必ず情熱的なストーリーがある!

関連記事
あわせて読む
-

【ジェラート ピケ】ミニーマウスがデザインの主役!ルームウエアなどのコレクションを発売
cocotte5/11(土)0:00
-

人気中古車実車レビュー【PEUGEOT 308】おしゃれ&実用的なフレンチコンパクト
グーネットマガジン5/10(金)10:00
-

新型もいいけれど安定した実力車 先代型も十分イイ感じ
グーネットマガジン5/10(金)9:00
-

最新現行型がよいのはわかっているけど……あえて選びたい! 先代型の美徳
グーネットマガジン5/10(金)9:00
-

V12エンジン×MT搭載! 新型「“2ドア”スポーツカー」初公開! レトロ風デザイン採用の「スーパーキャット」英で発表
くるまのニュース5/9(木)21:10
-

「夫が倒れた…」病院へ駆けつけた妻が見たもの「一体、どういう…?」
CHANTO WEB5/9(木)20:30
-

コミックシーモア4月総合ランキング異色のトップランキング作品 ヤナギナギ『名も知らず』
BCN+R5/9(木)16:00
-
![電気自動車を買って試す本音レポート リアルEVライフ[電費を計測する]の巻](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/goonet/s_goonet-226631.jpg)
電気自動車を買って試す本音レポート リアルEVライフ[電費を計測する]の巻
グーネットマガジン5/9(木)15:39
-

輸入車で旅に出よう【ディーゼル/PHEV/BEV】パワートレイン別おすすめの旅車
グーネットマガジン5/9(木)10:00
-
-

「センスと才能の塊」10歳の長女が作った〝520枚〟コマ撮り動画に20万いいね! 父親も「感動」
withnews5/9(木)7:00
-

楽天モバイルの「最強こどもプログラム」どれだけおトク? 他社の料金プランとの違いもチェック
ケータイ Watch5/9(木)0:00
-

日産チェリー1000GL((昭和45/1970年9月発売・E10H型) 【昭和の名車・完全版ダイジェスト059】
Webモーターマガジン5/8(水)19:00
-
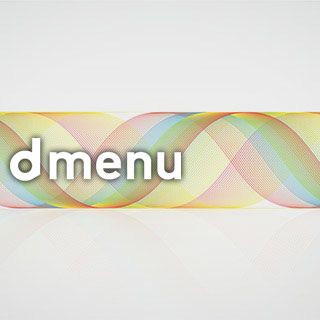
サプライヤーとしてFIAフォーミュラE世界選手権に参戦するヤマハ 今後の活躍に期待
バイクのニュース5/8(水)17:00
-

二輪車の祭典「World Bike Festa -2024 大展示試乗商談会 in アズテックミュージアム-」が仙台で5/25・26に開催!
バイクブロスニュース5/8(水)15:50
-

【毎日書評】それ間違ってます!仕事に悪影響を与える、よくある2つの「認知バイアス」
ライフハッカー[日本版]5/8(水)10:17
-

インディアン「ロードマスターリミテッド」はバイクの域を超えた快適性能! 後部座席はお姫様ダッコ以上!?
バイクのニュース5/7(火)7:10
-

「成長しなきゃ」「頑張っても報われない」ワーママを追い詰める状況 すぐには変わらなくても
withnews5/7(火)7:03
-

埃まみれの日産「マーチR」 なぜ660万円の値が付いた? 綺麗にしたら価値が下がる理由とは
くるまのニュース5/6(月)19:10
-
トレンド アクセスランキング
-
1

「なんで離婚したんだ?」東出昌大、率直な質問に苦笑「2人の娘と1人の息子がいるけど…」
ABEMA TIMES5/10(金)18:00
-
2

36歳男性が4人の“夫人”たちと“勝手に一夫多妻”の共同生活に至るまで「まだまだ夫人を増やしていきたい」
日刊SPA!5/10(金)15:53
-
3

「みんな買ってる!」【しまむら】ハシゴしてでもGETしたい♡ 最旬「華やかジレ」
ftn-fashion trend news-5/10(金)21:05
-
4

スズキが“新”「斬新軽トラ」を実車展示! めちゃ「画期的な荷台」がすごい! 精悍ブラック顔×4WD採用の「軽トラ市」向けモデルとは
くるまのニュース5/10(金)18:10
-
5

「嫁に虐められてるの!」イジワル姑がウソをつき【舅は嫁に激怒】→ しかし、『ある証拠』を見せると?
ftn-fashion trend news-5/10(金)20:11
-
6

姑「三流大学出身なのね」私「それが何か!?」【学歴差別】してくる姑にうんざりしていたら━━!?
ftn-fashion trend news-5/10(金)19:01
-
7

クルマの「サイドブレーキ」なぜ必要?「P」レンジのみで駐車はNGって知ってた? 正しいブレーキのかけ方とは
くるまのニュース5/10(金)20:10
-
8

朝のコーデ選びが楽に!【GU】使いやすさ大優勝♡「シンプルワンピ」
ftn-fashion trend news-5/10(金)22:05
-
9

全部気になる、、!【しまむら】見つけたら即買いして!「人気コラボアイテム」
ftn-fashion trend news-5/10(金)20:30
-
10

保育園が近い我が家に「駐車場貸してくれない?」ママ友のお願いを安請け合いしたら → 後悔する羽目に
ftn-fashion trend news-5/10(金)22:01
トレンド 新着ニュース
-

【ルームツアー】旅、音楽、アート、思い出に包まれる 桃生亜希子さんの暮らし
大人のおしゃれ手帖web5/11(土)0:00
-

【ジェラート ピケ】ミニーマウスがデザインの主役!ルームウエアなどのコレクションを発売
cocotte5/11(土)0:00
-

今月の写真家、今日の一枚。清家 翔世 vol.11
&Premium.jp5/11(土)0:00
-

今日1日を、このイラストと。安里 貴志 vol.11
&Premium.jp5/11(土)0:00
-

パソコンショップアーク、創業25周年記念セールを実施中
AKIBA PC Hotline!5/11(土)0:00
-

【八天堂】ご当地ふるさとくりーむパンに「沖縄」が登場!食べ比べができる詰合せも♪
cocotte5/10(金)23:30
-

『Hades II』突然のリリースで『ザ・ローグ:プリンス オブ ペルシャ』早期アクセス開始日延期―同ジャンルのゲームがまさか1週間前にリリースされるなんて…
Game*Spark5/10(金)23:30
-

ロッテ ZERO meets NewJeans Message Video で5人がめっちゃかわいい日本語でメッセージ! 5/13からTVCMオンエア、かわいい動画&フォトショット公開
tokyochips5/10(金)23:03
-

誕生から40周年を迎えたPORTER「TANKER」シリーズが刷新!全40型がどどーんとラインナップ
GetNavi web5/10(金)23:00
-

『Hi-Fi Rush』ファンが逆レビュー爆撃。Steamに高評価レビュー次々投稿―Tango Gameworks閉鎖を惜しみ
Game*Spark5/10(金)23:00
総合 アクセスランキング
-
1

《再始動》事務所独立の氷川きよしが公式Xアカウントを開設 芸名は継続の裏で手放した「過去」
NEWSポストセブン5/10(金)17:45
-
2

「Believe」大物俳優の体調心配された「かすれ声」理由判明 凄みある怪演 公式が説明
デイリースポーツ5/10(金)20:22
-
3

眞鍋かをり 松本人志裁判で重大提言「性犯罪を告発する場が週刊誌しかない」
東スポWEB5/10(金)18:40
-
4

DeNA敗戦 東力投も九回に森原が決勝点を献上 宮崎負傷交代で球場も騒然
デイリースポーツ5/10(金)21:49
-
5

新宿の女性刺殺、容疑者「消費者金融などに700万円の借金」
読売新聞5/10(金)21:09
-
6

《卒アル入手》AV出演、パパ活、ホスト…“紀州のドン・ファン”殺害容疑の妻が堕ちた“自己承認欲求の沼”《“別の男性”への詐欺罪で初公判》
文春オンライン5/10(金)16:50
-
7

《NHK林田アナの離婚真相》「1泊2980円のネカフェに寝泊まり」元旦那のあだ名は「社長」理想とはかけ離れた夫婦生活「同僚の言葉に涙」
NEWSポストセブン5/10(金)17:50
-
8

宇多田のパクリ扱い、実の父が「倉本麻衣」名義でAV制作、コナン主題歌…倉木麻衣(41)の“波乱万丈すぎた”25年の芸能生活
文春オンライン5/10(金)17:00
-
9

『橋田賞』北川景子、第2子出産後初公の場 大河ドラマで「子どもに誇れる表現を」 お市と茶々の一人二役演じ「私も強くなれた」
ORICON NEWS5/10(金)18:25
-
10

高円宮家の三女守谷絢子さん、第3子の男児出産 母子ともに健康
朝日新聞5/10(金)16:11
東京 新着ニュース
-

帝国劇場、建て替えに合わせてバリアフリー化を 障害者団体が署名2万筆超を東宝に提出
東京新聞5/10(金)23:19
-

那須2遺体事件の「仲介役」を夫婦への殺人容疑で再逮捕へ 品川区のガレージで窒息死させ殺害した疑い
東京新聞5/10(金)23:01
-

小池百合子知事が高校無償化で3知事に反論 埼玉・千葉・神奈川の懸念に「内容に明らかな事実誤認」
東京新聞5/10(金)20:05
-

第五福竜丸被ばく事件から70年、展示館に子どもたちの絵50点、11日は映画鑑賞会
東京新聞5/10(金)20:00
-

東京メトロ東西線 5月11日・12日東陽町〜西葛西で終日運休
TOKYO MX NEWS5/10(金)20:00
東京 コラム・街ネタ
-

CL決勝はレアル・マドリー対ドルトムント!両方でプレーした「最強の5名」
Qoly5/11(土)0:00
-

VARのため「選手が接触しに行く」傾向…U23アジア杯で審判アセッサーを務めた佐藤隆治氏の話が興味深い
Qoly5/10(金)22:00
-

Jリーグで見てみたい実力者!Jリーグ提携国枠の東南アジア人3選手
Qoly5/10(金)21:00
-

池袋にベーグル&スイーツ店「ラヴィーニュアキコ」 ビーガンメニューも
みんなの経済新聞ネットワーク5/10(金)20:14
-

もう「小さじ一杯」は計測不要? エスビー新ブランド「スティックスパイス」が革命的な便利さ...都内でサンプリングも
Jタウンネット5/10(金)20:00
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
(C) 2024 SHINCHOSHA Publishing Co.,Ltd.