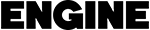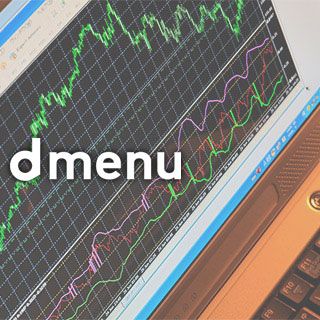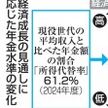2018年の登場以来、ロールス・ロイスの販売台数を押し上げてきたカリナン。そのベストセラーSUVがフェイスリフトを受けてシリーズIIなった。地中海に浮かぶスペインのイビーザ島で開かれた国際試乗会からエンジン編集長のムラカミがリポートする。
90%以上が自ら運転を楽しむ
スペインのイビーザ島といえば、今やクラブ・カルチャーの新たなる聖地として世界中に名を馳せる若者たちの憧れの地なのだそうだ。残念ながら、そういう方面の知識には滅法疎い私はまったく知らなかったが、中には入場料が日本円にして数十万から百万円以上もするようなVIP御用達の超高級クラブもあると聞いて、強烈なカルチャー・ショックを受けた次第である。
とはいえ、ロールス・ロイスがフェイスリフトしたカリナン・シリーズIIの国際試乗会の舞台としてこの島を選んだのは、クラブ・カルチャーの聖地だからではなく、ここにはロールス・ロイスの顧客や将来そうなって欲しい世界中のエスタブリッシュメントが多く別荘を持つなどして訪れているからだ、というのがプレスカンファレンス冒頭の広報担当者の説明だった。しかし、続けて2018年にカリナンがデビューして以来の顧客の変化についての話を聞くに及んで、やっぱり、少しはクラブ・カルチャーのこともアタマの隅にあったのではないか、と勘繰りたくもなったのである。
というのも、6年前の登場時には自らハンドルを握るオーナーは70%以下であったものが、今では90%以上が自ら運転を楽しむためにカリナンを買い求めているというのだ。しかも、昨年のロールス・ロイスの世界販売台数6036台のうち半分近くがカリナンで、もはや大黒柱といっていい存在になっている。結果として、カリナンの登場により、ロールス・ロイスの顧客全体のポートフォリオは大きく変化することになった。すなわち、2010年には平均年齢が56歳だったのが、今では43歳まで下りてきているというのだ。となれば、クラブ・カルチャーに大いに関心を持っているような若き成功者たちがすでにオーナーになっているか、これからなる可能性は大いにあると言っていいだろう。
デザイン・テーマは垂直性
そんな前置きを聞いた後にじっくりとカリナン・シリーズIIを眺めてみると、なるほど、このフェイスリフトの狙いが、若返った顧客層の好みに合わせて、全体をブラッシュアップすることにあったのだというのが良く分かった。
たとえば、その象徴とも言えそうなのが、新たにデザインされたデイタイム・ランニング・ライトだ。ヘッドライトの上部から直角にサイドに回り込んでバンパー・ラインまで長く続くそれは、誰にもひと目みて、これがカリナン・シリーズIIであることを識別させる力強いアイコンとなっている。
この6年間に顧客の動向を調査した結果、高いオフロード性能をも備えるカリナンではあるが、実際にはほとんどが都会で使われていることがわかったのだという。そこでいかに強い個性を発揮するか。考えた結果、大都市にそびえる摩天楼と呼応するように、垂直性を主要なデザイン・テーマにした、というのがプレゼンテーションでのデザイナー氏の説明だった。
ロールス・ロイスの象徴とも言うべきパンテオン・グリルも、今回イルミネイテッド・グリルに進化するとともに、より垂直方向の柱を強調したデザインになっている。全体を取り囲む枠がなくなり、その代わりに左右のデイタイム・ランニング・ライトの間にファントム・シリーズIIとも共通する水平方向に一直線に延びる「ホライズン・ライン」が設けられた。その結果、上下が分離して、まさに垂直の柱が屋根の部分を支えている建築そのもののようなデザインを実現しているのだ。
観音開きのドアを開けて運転席に乗り込むと、真っ先に気づくのは、これまではアナログの針付きだったメーターが、デジタル・パネルに映し出されるヴァーチャル・メーターに取って代わられたことだ。これはロールス・ロイス初のフルEVであるスペクターで導入されたSPIRIT(スピリット)というオペレーティング・システムを引き継いだもので、オーナー専用の会員制アプリとも統合してインターネットを使った様々なデジタル操作を可能にするというが、若返りのためには必須のアイテムと言っていいだろう。
さらに助手席側に視線を移していくと、ボンネットの先端に付いているのと同じスピリット・オブ・エクスタシーのミニチュア・モデルが、アナログ時計とともにはめ込み式のケースに入れて置かれているのが目に入ってくる。これこそがカリナンがドライバーズ・カーになったことの証とも言えるのではないか、と私は思った。光のあたり方によって、様々な色に変化する女神の像を間近で愛でられるのは後席の住人ではないのだ。
そして、助手席の真正面にはガラス製のイルミネイテッド・フェイシア・パネルが新たに設えられた。ガラスの裏側からレーザーを使って7000ものドットがエッチングされており、CULLINANの文字とともに光で摩天楼を思わせる縦の模様が浮き上がるようになっている。ゴーストやスペクターにも使われているこのパネルのおかげで、前期型より一段とラグジュアリー感が増している。
そのほか、220万ものステッチと最長18kmもの長さの糸をつかって織り上げられたデュアリティ・ツイル(二重綾織り)のファブリック・シートを新たに採用するなど、ラグジュアリー感を増すことも、新たなる顧客の要望に応える重要な要素だったことがうかがえた。
スペックは同じだが……
さて、それでは運転してどうだったのか。今回はノーマル・モデルとブラック・バッジの両方に試乗することができたが、各30分ほどの短い時間でしかない。しかし、それでもこのカリナン・シリーズIIの走りの素晴しさは良く分かった。乗ればすぐに分かるくらいに、味の濃いクルマだったからだ。
前提として言っておかなければならないのは、パワートレインに関しては、今回、まったく変更がないということだ。ノーマルが571ps、ブラック・バッジが600psを発揮する6.75リッターのV12気筒ツインターボ・エンジンも、8段ATを介して4輪を駆動するシステムもそのままだ。シャシーについては、今回、新たにノーマルではオプション、ブラック・バッジは標準で23インチのタイヤを採用したことにより、サスペンションのチューニングをそれに合わせて若干変えたというが、それ以外はなにもいじっていないのだとか。
しかし、にもかかわらず、まずはノーマルの方から乗ってすぐに思ったのは、明らかにロールス・ロイスの味がますます濃くなっている、ということだった。ロールス・ロイスに乗っているのだから当り前ではないかと思われるかも知れないが、えも言われぬ柔らかなタッチのステアリング・フィールやマジック・カーペット・ライドといわれる路面の荒れをどこか遠くの出来事のようにしか感じさせない絶妙なチューニングが施された足回りなど、まさにファントムやゴーストが体現しているロールス・ロイスが持つ独特の乗り味の理想の領域に、カリナンもどんどん近づいていると思ったのだ。
たとえスペックが変わらなくても、クルマは生産を続けるうちにどんどん進化するものだ。今回、数字に現れないどんな改良があったのか、残念ながら今回の試乗会にはエンジニアがおらず聞くことができなかったが、間違いなく見た目の変化と同じくらいのブラッシュアップが、走りにももたらされていると思った。
ブラック・バッジも基本的な乗り味はまったく変わらない。ややパワーが勝り、回転数を上げるとエンジンやエグゾーストのサウンドがノーマルより少し大きく聞えるようになる気もしたけれど、だからと言って、急にスポーティな乗り味になるわけではない。
そもそも、ロールス・ロイスの辞書にはスポーティという言葉はないのだ。ただ、十分なパワーがあります、としか彼らは言わない。だから回転計など持たず、持てるパワーを今どれだけ余しているかを示すインジケーターがあるだけだ。しかし、走る曲がる止まるの基本性能の高さは実のところスポーツカーも顔負けで、イビーザ島の山道を走りながら、このカリナンの操縦性の良さにも私は舌を巻いた。
プロのドライバーにショーファーを務めてもらい後席にも乗ってみた。後席の乗り心地も、どうやらずいぶんと進化したと思った。こちらはファントムに近いとまではまだ言えないが、音も振動も確実に前期型より抑えられている。
ロールス・ロイス史上初めて幻影や幽霊ではなく現実に存在するもの、すなわち英王室が所有するという世界最大のダイヤモンドの名前を付けられたカリナンは、確実にこのブランドの血を受け継ぎながら新しい世界を切り開いている。その出来映えに、私は素直に脱帽した。
文=村上 政(ENGINE編集長) 写真=ロールス・ロイス・モーター・カーズ
(ENGIN2024年8月号)
【試乗速報】「ロールス・ロイスの辞書にスポーティという言葉はない」 シリーズIIに進化したカリナンにスペインで試乗! 出来映えに脱帽

関連記事
あわせて読む
-

「中古車」を買ったのですが、外装だけの確認で購入してしまい後悔しています…。一体どこをチェックすれば良かったのでしょうか?
くるまのニュース7/3(水)20:10
-

日産が“奇妙”な「新型コンパクトSUV」初公開へ! 顔は「最新」でボディは「旧車」!? 新型「ミニ・エクストレイル」衝撃の“進化”を中国で披露
くるまのニュース7/3(水)19:10
-

フォルクスワーゲンがニューモデルを一気に4台お披露目。今後の戦略やアプローチは「2本立て」で!
Webモーターマガジン7/3(水)18:02
-

話題の新型フリード、買うならどのモデル?
グーネットマガジン7/3(水)18:00
-

アウディ 京都の町で「Q8 e-tron」を体感!宿泊付き試乗モニターが当たるキャンペーン
グーネットマガジン7/3(水)17:24
-

“知ってる世代は”たまらんガシャポン、SNS2.3万いいね「思わず口ずさんじゃう」「知らない世代はサッパリ」
LASISA7/3(水)16:40
-

新型「ディフェンダー オクタ」ついに発表!シリーズ史上最もタフ&ラグジュアリーなSUV
グーネットマガジン7/3(水)16:25
-

ホンダ新型「ヴェゼル “アーバンS”」初公開! 斬新「黒×メッキ」アクセントが超オシャ! 美麗スタイルが超美しい「コンパクトSUV」とは
くるまのニュース7/3(水)16:10
-

ビーチで小型冷蔵庫やかき氷機に電力供給も! BYDが東京アウトドアショー2024で見せた魅力的なアウトドアライフ
くるまのニュース7/3(水)15:40
-
-

スバル「上質SUV」“STI仕様”がスポーティすぎる! 伝統の「スバルサウンド」も魅力!? 「レイバック」STIパーツ装着車の印象は?
くるまのニュース7/3(水)14:50
-

フォルクスワーゲン 一挙5モデル!新型モデル同時発表!「Tクロス」「ティグアン」など
グーネットマガジン7/3(水)14:08
-

新型モデルを「5台同時」発表! 全面刷新の小型SUV&大型ワゴン登場! VWが攻めの戦略展開へ
くるまのニュース7/3(水)13:30
-

次世代型「CX-5」がウワサされる中「熟成した現行型」に乗って驚いた! マツダで「最も売れたロングセラー」は今も一級品の出来栄えです
VAGUE7/3(水)12:10
-

トヨタ新型「“GR”クラウン」!? 期待高まる「フェラーリ!?なSUV」! 迫力エアロが超カッコイイ「クラウンスポーツ」CGの仕上がりとは
くるまのニュース7/3(水)11:50
-

やりたくない仕事が天職になり、フォロワー数が900万人を超えた寿司職人の話。
はたわらワイド7/3(水)11:15
-

【2024年版】日産 エクストレイルVS三菱 アウトランダーを徹底比較
グーネットマガジン7/3(水)11:00
-

スズキ「新型コンパクト“SUV”」発表へ! クーペスタイルの「小さな高級車」か!? MT設定&「100万円台」の「インドフロンクス」とは
くるまのニュース7/3(水)8:40
-

セリアさんやっぱさすがだわ…「使用後の処理がちょっと…」を解決してくれるボール
michill byGMO7/3(水)8:00
-
トレンド アクセスランキング
-
1

アプリで「最高の彼氏」をゲット♡のはずが → 親友「別れた方がいいよ」って、どうして!?
ftn-fashion trend news-7/3(水)13:01
-
2

在宅ワークの妻に、夫「毎日家にいて暇でしょ?ww」【ならば教えてあげましょう】→ 妻が反撃開始!
ftn-fashion trend news-7/3(水)17:01
-
3

ローソン、7月24日上場廃止 KDDIとポイント経済圏の拡大などを目指す
ITmedia ビジネスオンライン7/3(水)17:46
-
4

【ローソン】「レモネードレモニカ監修」絶品ワッフルコーンに癒される♪
イエモネ7/3(水)13:00
-
5

「あの客スタイル悪いよねww」【失礼すぎるアパレル店員】→ 涙目で試着室を出ると、そこにいたのは?
ftn-fashion trend news-7/3(水)19:01
-
6

しまむらの「新作ワンピ」夏の即戦力になる〜!可愛いのにとにかくラクちんで売り切れが心配…♡
michill byGMO7/3(水)11:00
-
7

「中国海軍の巨大ミサイル艦」北海道沖に出現!日米の主力艦を超えるビッグサイズ 自衛隊が警戒・監視
乗りものニュース7/3(水)15:12
-
8

アンダー200万円から! トヨタ新型「最小ミニバン」登場! 「“新”シエンタ」一体何が変わった?
くるまのニュース7/3(水)18:10
-
9

友人親子と食事に行くも、会計時に「すまん! 実は、、、」→ まさかの告白に「神経が理解できん」
ftn-fashion trend news-7/3(水)10:01
-
10

今年もファミマから “フジロックカラー”のソックスやマフラータオルが登場、普段使いにも役立つアイテムに
ORICON NEWS7/3(水)13:05
トレンド 新着ニュース
-

夏キターーーッ♡ 今すぐ【ダイソー】に走って! 便利 & おしゃれ「夏グッズ」
ftn-fashion trend news-7/3(水)22:03
-

「私が居なかったら共働きなんてできないんだからね!」偉そうにする居候姑に、娘が──?
ftn-fashion trend news-7/3(水)22:01
-

少女たちに夢を、女性たちに人生の道標を。中原淳一、生誕111周年記念展覧会が開催
ananweb7/3(水)22:00
-

レーシングカーのマフラー音をBGMに睡眠!? サーキット内常設キャンプ場「RECAMP 富士スピードウェイ」を一足早く“体験”
くるまのニュース7/3(水)21:40
-
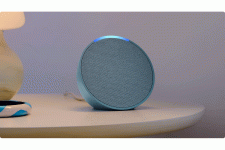
「画面がないほうがいい」こともある。私がEcho Popを求める理由【 #Amazonプライムデーで欲しいもの 】
ライフハッカー[日本版]7/3(水)21:37
-

【ゼスプリ×Afternoon Tea】この夏にピッタリな、新作のコラボメニューが登場♡
cocotte7/3(水)21:30
-

打ちやすいのに美しい! 日本のクラブメーカーが手がける「新作ブレードアイアン」の実力とは?「ゴールド&ブラック仕上げ」が精悍です
VAGUE7/3(水)21:30
-

FC版『ドラクエ3』にあった「使えない呪文」 発売当時は「ガッカリ」ばかりではなかった?
マグミクス7/3(水)21:25
-

Yahoo! JAPANアプリに「アシスト」「フォロー」機能を追加 ユーザーに合わせた情報を提供
ITmedia Mobile7/3(水)21:20
-
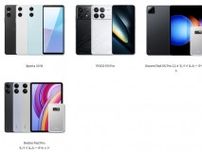
IIJmioで「Xperia 10 VI」「POCO F6 Pro」「motorola edge 50 pro」発売
ITmedia Mobile7/3(水)21:12
総合 アクセスランキング
-
1

「セクシー女優が起用されてるイメージ」桜井日奈子の新CM出演に戸惑いの声
週刊女性PRIME7/3(水)17:30
-
2

自分でドア開け…非常階段から転落したか マンション駐車場で女児死亡 母親は体調悪く寝込んでいた 札幌
HTB北海道ニュース7/3(水)15:57
-
3

ローソンが24日に上場廃止、TOB実施のKDDIと三菱商事が50%ずつ保有
読売新聞7/3(水)18:45
-
4

「2024FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル公開
モデルプレス7/3(水)10:36
-
5

「亡くなった妻が保管していたもの」ふた付きのバケツの中から3人の遺体見つかる 生後まもない赤ちゃんか 神奈川・藤沢市
TBS NEWS DIG7/3(水)16:28
-
6

「5人くらい関係を持った」“西武の新4番”岸潤一郎(27)の“ネットナンパ不倫”が発覚《“嫁が好きなんて一言も…”不倫相手に送った驚愕メッセージ》
文春オンライン7/3(水)16:00
-
7

フジテレビ「イット!」 大谷新居報道を番組内で謝罪 プライベート空間への訪問控えるよう注意喚起も
デイリースポーツ7/3(水)18:59
-
8

「同じ匂いを感じますね」広末涼子のインスタ投稿にツッコミ続出、“チグハグ”コーデに“第二の工藤静香”の声も
週刊女性PRIME7/3(水)18:00
-
9

『あさイチ』学校内での「盗撮」にスタジオ騒然…博多大吉「途中から気持ち悪くなってきた」ゲストも激怒
中日スポーツ7/3(水)10:26
-
10

「あの子の子ども」避妊に失敗した福(桜田ひより)、生理になり安堵で涙するも…ナレーションに不安の声続出「絶対違うでしょ」
iza!7/3(水)10:03
東京 新着ニュース
-

誕生直後の赤ちゃんがごみ箱から見つかる 練馬のアパート 殺人未遂の疑いで出産した女を逮捕
東京新聞7/3(水)21:16
-

第51回現代舞踊展が開幕 めぐろパーシモンホール、4日は午後6時半開演
東京新聞7/3(水)21:09
-

耳が不自由な人にも政見放送を分かりやすく 6日、手話と字幕付き上映会 オンラインでも 東京都知事選
東京新聞7/3(水)19:54
-

「警官が大声で怒鳴っている」と通報され…警部補が交番内で女性を床に押さえつけ、けがさせた疑いで逮捕
東京新聞7/3(水)19:21
-

都知事選の期間中にも「公約」アップデート 「GitHub」使い議論はオープンに…安野貴博氏の手応えは
東京新聞7/3(水)16:54
東京 コラム・街ネタ
-

マツダスタジアム速報まとめ〜九里は佐藤輝に痛恨柵越え2発供給、広島打線は大竹のキャッチボール投法またしても攻略しきれず
ひろスポ!7/3(水)22:01
-

「えほん大賞」に「サンシャインシティ 絵本の森」賞 小学生以下対象に
みんなの経済新聞ネットワーク7/3(水)19:09
-

平和な朝のはずが……隣で寝ていた“ぬいぐるみ”が大慌て!【作者に聞く】
Walkerplus7/3(水)19:00
-

エッフェル塔が復活!PSGが新アウェイユニフォームを発表 パリ五輪イヤーに「パリの象徴」を芸術的に描く
Qoly7/3(水)19:00
-

自由が丘のギャラリーで「がらすとすいさい」 父娘2人展
みんなの経済新聞ネットワーク7/3(水)17:35
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
(C) 2024 SHINCHOSHA Publishing Co.,Ltd.